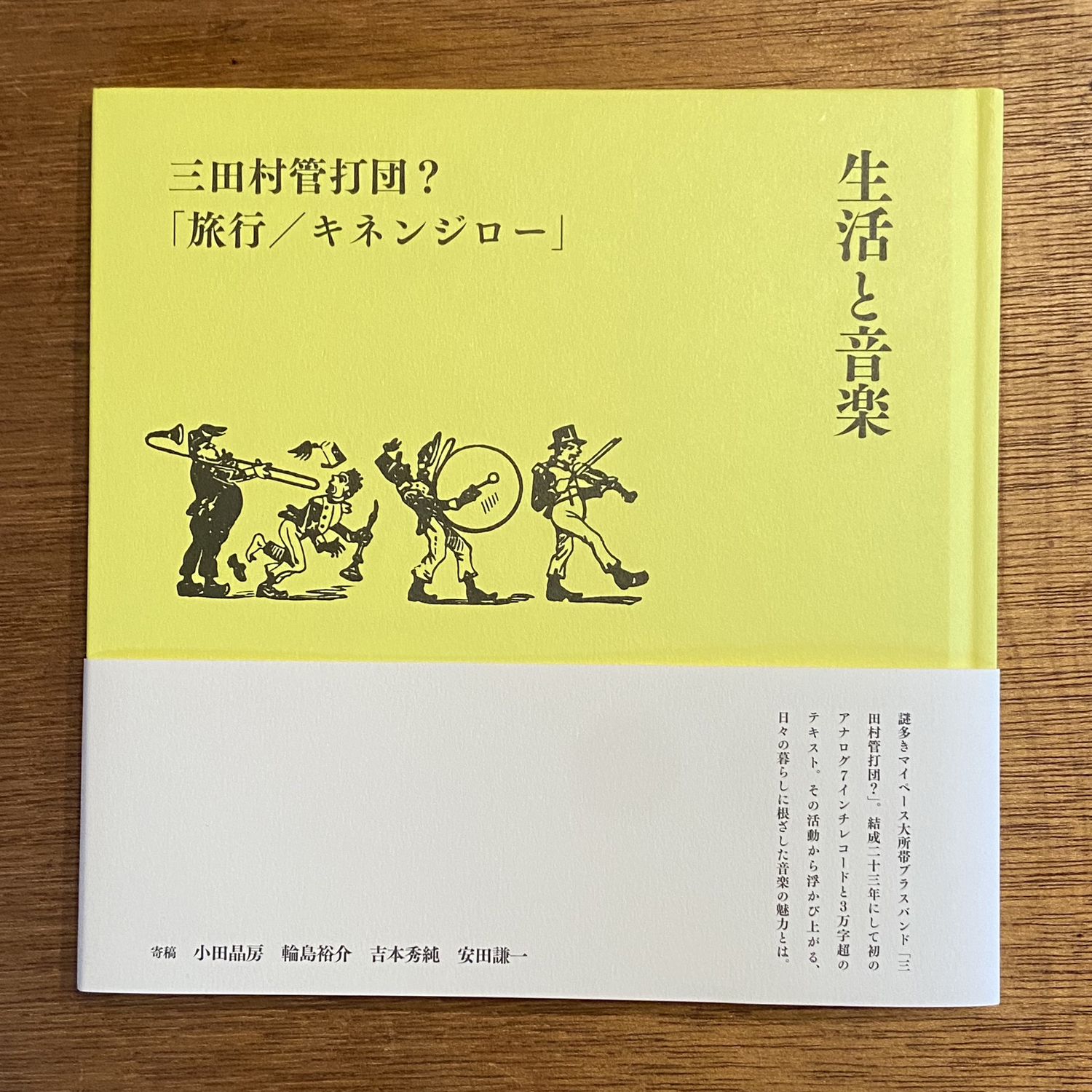『生活と音楽 三田村管打団?「旅行 / キネンジロー」』刊行記念対談
和久田は数年前に大阪から塩屋に移り住み、このほど自身の出版社「和久田書房」を立ち上げた。そして、出版物としての第1作目が、『生活と音楽 三田村管打団?「旅行 / キネンジロー」』。三田村管打団?をめぐるエッセイ、活動中の写真、森本のインタビューなどで構成され、さらにそこに彼らの人気曲「旅行」「キネンジロー」を収録した7”ヴァイナルが付いている。和久田書房の第1作目であり、三田村管打団?にとっては12年ぶりの音源にして、初のレコードのリリース。豪華といえば豪華、謎といえば謎。しかし、この本には、すべてがこれでなくてはならない巡り合わせがあると思えた。その成り立ちと作品への思いを、あらためて和久田(以下和)と森本(以下森)に聞いてみた。
取材・文・写真 | 松永良平 | 2025年8月
――長い付き合いのおふたりだと思いますが。
森 「和久田くんはメディア(関西のカルチャー雑誌『Lmagazine』)で僕を取材してくれた初めての人ですね」
和 「いや、それは僕じゃない(笑)。そのときは『Lmagazine』編集部のデスクではあったけど、取材したのは後輩です。アリさんは当時、口琴のグループ、ビヨビヨ団をやっていましたね。あれはまだ三田村(管打団?)結成前だったから、2000年くらい?」
森 「GAME BOY®のみによる電子音楽のFan Club Orchestra Japanの記事も出してくれた気がする」
和 「だから、最初にアリさんを知った時点では、まだ三田村の人でも、旧グッゲンハイム邸の管理人でもなかった。GAME BOY®とか掃除機とかで演奏している変わった音楽家がいる、という印象でした」
森 「LIVE! LAUGH!(*1)にはいた。三田村の結成は2002年だったかな」
和 「僕はLIVE! LAUGH!は知っていたけど、その時点では森本アリという人がそこにいるとは認識していなかったな。この塩屋の街だって、グッゲンがこういうかたち(ライヴ・スペース)で運営され始めてから初めて来ましたから。大阪在住で神戸の地理感覚も須磨まではわかるけど、その隣駅の塩屋は知らない、みたいな感じ」
森 「僕がLIVE! LAUGH!にいたのは最後の1年未満。結局、最後のほうにいた人たちが、そのまま三田村になったんです。初期の三田村には、神戸(が拠点)という括りも、当時は存在すらしなかったように思うけどね」
和 「三田村のライヴは新世界BRIDGE(*2)でよく観ていた印象ですね。京都でも何度か観ています」
*1: 故・大原 裕が率いたブラスバンド。2001年頃に活動休止。
*2: 大阪の実験的ライヴ・スペース。2002~7年まで存続。
――ふたりが知り合って話すようになったのはいつ頃?
森 「三田村の初めてのCD『!』(2006, compare notes)が出たときに『ミュージック・マガジン』でのレビューは和久田くんが書いてくれたじゃない?あの頃はメディアには和久田くんや吉本(秀純)くんが書いてくれていた印象やけど」
和 「あの原稿をアリさんが読んでくれて、喜んでくれたんですよ。ある日、グッゲンでやっていた三田村ではない別のライヴを観に来たら、アリさんがぐわーっとこっちに来て、“和久田くんやんね!『ミュージック・マガジン』読んだ!ありがとう”って言われた(笑)。それが最初の会話ですね」
森 「え?でもグッゲンの始まりよりも三田村の1stアルバムが出たのは前じゃない?」
和 「そう。だから、レビューを書いてから2、3年は経っていたかな」

――アリさんが旧グッゲンハイム邸の管理人になったのが2007年、ライヴ・イベントを企画するようになったのは2008年と聞いています。とにかく、その会話で関係は始まったと。
和 「でも、いつもしゃべっているのは映画の話ばっかりですね」
森 「ヤスケンさん(ロック漫筆家・安田謙一)と和久田くんの3人で“あれ観た?”とか、そんなんばっかりやね」
和 「それが高じて、神戸の書店・1003で毎年3人で映画のイベント『スター千三夜』をやっているんですけどね。音楽の話はそんなにガッツリしているわけじゃない」
森 「ぜんぜん音楽好きじゃないんでね(笑)」
和 「よう言うわ(笑)」
――僕が初めてグッゲンに来たのは、片想いの1stアルバム『片想インダハウス』のツアーでした(2013年11月2日)。その時点でもうグッゲンは神戸エリアの稀有な場所としてすっかり定着していましたし、アンコールでやった、片想いとアリさんたち三田村のメンバーが合体した「両想い管打団!」も、ファンは楽しみに待っている状態でした。
森 「片想いの存在を知ったのは、大阪でHOPKENというお店をやっていた杉本(喜則)くんが“三田村に似たようなバンドがあるんですよ”と教えてくれたのが最初かな。その後、グッゲンでやった杉本くんのイベント“ホープ軒”(2010年11月6日)で初めて観た。実際にライヴを観て、音楽性というより空気感が三田村に似ているバンドを見つけた!と思って、一緒にやりたくなったんです」
和 「あの日、アリさんが三田村のCDを片想いに渡したんですよね。(片岡)シンさんたちが帰りの車で聴いて、やっぱりめちゃめちゃ盛り上がったそうなんです。sirafuさん(MC.sirafu)もLIVE! LAUGH!が好きやったから“あのバンドにいた人らが今こんなことになっている!”という驚きもあり、一気に急接近みたいな流れでしたね」
森 「あー、そうだった。やっぱり大原 裕という存在がsirafuくんたちのあいだではすごく神格化されていたんですよね。それも大きかった。今回の本に小田(晶房)さんが大原さんについてのすごくいい文章(「小さな社会と移り変わる人生」)を書いてくれているんですよ」
――片想いとの詳しい話は、ふたりの対談がウェブ上に残っているので(ぴあ関西版web「森本アリ(三田村管打団?) × 片岡シン(片想い)“両想い”な2人による初のスペシャル対談!」)、それをぜひチェックいただくとして、和久田さんとアリさんの関係に話を戻します。和久田さんが編集者としてアリさんの著書を作ったのが、2017年の『旧グッゲンハイム邸物語: 未来に生きる建築と、小さな町の豊かな暮らし』(ぴあ)。
森 「和久田くんは、あの本を作っているとき、塩屋に家を探しに来ている最中でしたね」
和 「神戸方面に引っ越すことは決めていて、いろんな街や物件を見歩いていたんですよ。本の取材で塩屋にはしょっちゅう来ていて、いい物件がひとつ見つかって、もしかしたらここにするかもしれへん、みたいなタイミングでしたね」
――引越しの話を聞いたとき、最初から塩屋に決めていたんだと思ってました。
和 「全然そんなことはなくて、それこそ西宮から明石くらいまで広範囲に探していたくらいなんです。でも、やっぱり塩屋は家が安いし、ある程度は街のことも知っていたし、引っ越したとき知り合いがすでにたくさんいるという安心感があった。住むイメージが作りやすかったんです」
――そもそも、この『生活と音楽 三田村管打団?「旅行 / キネンジロー」』を、和久田書房の記念すべき出版物第1号にしようと決めた理由は?
和 「いや、これを1作目にしようと決めていたわけではないんですよ。いくつか企画は同時進行していたので。でもね、そもそもこの本を作る前から、三田村のレコードをちゃんと作ろうという提案はずっとしていたんです」
森 「僕らがレコードを作らへんから、和久田くんが業を煮やした(笑)」
和 「去年、僕が前の会社(ぴあ)を退職するタイミングで、ここでやるしかないやろと思って、まずはレコーディングに向けての準備を始めたんです。その時点では、自分で出版社を立ち上げようとか、第1弾の商品にしようとかまでは考えていなかった。レコードは作るけど、出すのはどこかのレーベルで1枚限りの契約で出せればいいかくらいの考えでした」
――あくまでプロデューサー的な関わりかた。
森 「でも自分で出すことになったのは?いろいろ声かけたけど応えてくれる会社がなかったということ(笑)?」
和 「いや、そもそも声をかけていないです(笑)。それに、会社を辞めた時点では先のことはぜんぜん考えていなかったんですよ。でも、この先どうやって食っていくか考えたときに、自分には編集と出版以外にあまりできることないなと思って」
森 「もともと和久田くんは、ぴあにおった頃から異端というか、作っている本はひとりで出版社を社内に立ち上げていたようなところがあった」
和 「退職が決まって関係先に報告に行ったときも、けっこうみんなに“じゃあ自分で出版社始めるんやね?”と言われて。そんなの考えたことも言ったこともなかったんですけど(笑)。で、それって背中を押されたというよりはむしろ、“お前がやれることはこれ。他に選択肢はないやろ”と言われているような気がしたんです。それで、三田村のことをやるなら、タイトルや装丁、収録する曲も含めて自分でやれないのならあまり意味がないし、だったら自分の出版社としてやろうと決めたんです。まあ、そこからもそれなりに時間はかかりましたけど、結果的にこれが第1弾になりました。でも、これが最初になってよかったとも思う」
森 「最初に変化球を投げるような?」
和 「会社を辞めてわざわざ出版社を立ち上げたんだから、それやったら別に辞めんで良かったんちゃう?、みたいな本じゃなく、自分でやる以外どこも出してくれへんやろ、くらいのものでないと(笑)」
森 「ややこしいのがこの本の題名ですよね。『生活と音楽』だけにしたらレコードではないようだし、“旅行 / キネンジロー”と並べたら何が何だかよくわからなくなる(笑)。実際は、どっちでもいいんですかね?」
和 「まあどっちでもいいというか、全部一緒なんですよ」
森 「『生活と音楽』というレコードであって、そこに入っている曲が“旅行”と“キネンジロー”とも受け取れる?」
和 「そう取ってもらってもかまわないです。“旅行 / キネンジロー”だけだと、やっぱりレコードじゃないですか。あくまで本というのが一番前に来るパッケージにしたかった」
森 「“旅行”と“キネンジロー”が曲名だっていうことは、三田村を知っている人はわかるけどねえ?」
和 「それを言い出すとね、僕が前の会社でやってきた仕事では、そういうわかりやすい売り文句をもっと山ほど付けなあかんかったので……」
森 「会議で“わかりやすくせなあかん”と言われ続けたから、いかにわかりにくくするかを自分の会社では実践してみたというか?」
和 「まあ……言うたらそうですかね(笑)。“?”だらけで別にいいんですよ。“何?この本?”みたいな状態でいいんです」
――三田村管打団?の「?」のように(笑)。でも『生活と音楽』というワードはドーン!と存在感を持っていて。
森 「『生活と音楽』というタイトルで思い出すのは、TARAF DE HAÏDOUKSが出てくる映画(『ラッチョ・ドローム』『ジプシー・キャラバン』)とか、ユアン・マクレガーが出ていたイギリスの炭鉱町楽団の映画『ブラス!』とかの、家から楽器を剥き出しで持ってくる、みたいなシーンがあるやん?」
――やっぱりこの塩屋の街の暮らしがあって、グッゲンのハウスバンドとしての三田村管打団?の存在があって、今回の本 + 7"ヴァイナルのタイトルでもある『生活と音楽』というテーマ性が浮上してきた?
森 「そこは急接近するよね。そういうことは、前の本(『旧グッゲンハイム邸物語』)でも、ゑでぃまぁこんを引き合いに出して僕は書いているんですよ。ゑでぃまぁこんは兵庫・姫路のバンド。姫路というか昔の播磨の側には、仕事しながら音楽を両立できる空気がある。それは塩屋より西の地域が持っている空気なんじゃないかと思っているんですよ。popoの山本信記や江崎將史とか、稲田 誠とか、その全員がクリエイティヴな側面を持ちつつ、音楽を仕事にはしていない。そこの線は引いている気はする」
和 「三田村のみんなも、音楽に対してひとつの目標や高みを目指してやっているという感じがそんなにない」
――でも、単なるアマチュア同好会ではない、不思議な吸引力が音楽にあるんですよ。
和 「三田村管打団?ってある意味では存在自体が批評的なバンドじゃないですか。でも当人たちはクリティカルなことをやろうとはぜんぜん思っていない。そういうところのおもしろさって、今回の本みたいなかたちにしないと伝わらないと思ったんです」
森 「僕も今回のシングルで録った“旅行”と“キネンジロー”を繰り返し聴いていて、三田村ってモデルになるようなバンドが本当にないなと思った。唯一無二というか、まあ世界中が唯一無二だらけだとも思うんですけど、ブラスバンドというジャンルに当てはめても、こういう音楽性のところはない」
――以前、漫画家の山田参助さんが“ブラジルのサンバみたいな歌を日本語でやるのはとても難しいと思うけど、両想い管打団!ヴァージョンの『キネンジロー』(ライヴでのみ披露されていて、歌詞が付いている)はそれができている稀有な例”と話してくれたことがあって、今もすごく印象に残っているんですよね。すごい音楽家たちのすごい演奏じゃなく、市井の人たちから生まれた特別なニュアンスを持つサンバを参助さんはイメージしていたはず。
和 「参助さんが滔々と歌うヴァージョンも聴いてみたい」
森 「わはははは。それは良さそうやね。ニカちゃん(二階堂和美)とやっているヴァージョンもすごくおもしろいですよ」
――タイトルも含めて黄色い正方形の本というフォルムについては?
和 「やっぱりこれだろうという決断はありました。いろいろ考えましたけどね。これまでもいろんな本を作ってきましたけど、タイトルも装丁も正解というものはないんですよ。例えば、中身は同じだけどタイトルやデザインなど5パターンの違いがある本を世に出せたら、どれが一番売れるか、どれがどのように評価されるか、答えがわかるかもしれない。でも、世の中に出るのはひとつなので」
――それでいうと、今回のシングル盤に入っている「キネンジロー」にもその話、当てはまるんじゃないですか?三田村ってやったライヴの数だけヴァージョンがあるバンドだと思っているんですが、今回の「キネンジロー」を聴いたときは驚いたし、これはひとつの結晶として美しいかたちといえるのではと思ったんです。
森 「ですよね!」
和 「いいですよね」
森 「イントロにトライアングルがないんですよ。パーカッション担当の池田(安友子)さんが叩くトライアングルのチキチーチキチーっていう音が、みんなからしたら“キネンジロー”の基本みたいなんですけど、池田さんは録音のスケジュールが合わなくて、今回のヴァージョンには入っていない。だけど、あのスネアのタン!で始まるのも、めっちゃいいですよね」
和 「けっこう意見が割れたんですよ。結局、トライアングルを入れるヴァージョンも作ってはみたんです。カウントだけとか、口でチキチーチキチーって言うのとかもやってみました」
森 「4ヴァージョンくらい作ったかな」
和 「でも、僕とミックス / マスタリング担当の和田(真也)くんは最初から最後まで“絶対トライアングルなしでいこう”と言っていたし、それで押し切りましたね」
森 「三田村なんてほんまに生ものやからね。スピードもいつもと全然違うんですよ。今回採用したのは録った中で一番速いやつ。でも速いだけに全体がダレずにまとまっていて、シングルとしてはすごい正しいヴァージョン。ライヴのドキュメントとしてはもっといっぱい良いテイクもあると思うんですけど、録音版として構成がすごくよかった」
和 「あと、三田村の最後の録音物は12年前だったんですよね。淸造(理英子)さん(トロンボーン、2015年加入)も、“私がクレジットされている作品がひとつもない”とずっと言っていた(笑)」
――今回のレコーディングは、ある意味で現時点のベストメンバー。
和 「いやあ、よく17人も揃いましたね」
森 「17人もいるんやね。あと3人くらい都合が合えば来るかもしれない人がいるから20人は超えるね。グッゲンでPAを長年やってくれている和田くんが自分のスタジオを構えたことも、今回ちゃんとした録音ができた大きい理由だった」

――本にはアリさんのインタビューやバンド活動の写真に加えて、4人の執筆者(小田晶房、輪島裕介、吉本秀純、安田謙一)による三田村管打団?への文章が掲載されてます。これがまたおもしろい。
和 「三田村ってあまり言葉で語られてこなかったじゃないですか。結局、ライヴを体感してもらえればそれが一番なんですけど、どういう人たちなのかということをなかなかきちんと言い表されてこなかったままの23年だったんで、そういうものは必要だと思ったんです」
森 「輪島さんは僕から和久田くんに提案した」
和 「僕は輪島さんとは面識がなかったけど、書いてくれたらうれしいなとは思っていたんです。依頼したら、ふたつ返事で引き受けてくれました。大学ではブラジル、アフリカ音楽を研究されているんですけど、ここ数年は日本の大衆音楽を鋭く考察されているし、笠置シヅ子さんや北島三郎さんについても書かれているんで、三田村に対しても他にないかたちで書いてくれるやろうなと思ったんです。“自分のことばかり書いちゃいました、すみません”と添えてあったけど、かなり素晴らしい原稿でしたね」
――小田さんは、三田村の1stアルバム『!』(2006)から3rdアルバム『!!!』(2013)まで3枚のCDを出した「compare notes」のレーベル主でもあります。
森 「さっきも言いましたけど、今回の原稿で小田さんが大原さんがいたシーンのバックボーンをあんなに詳しく書いてくれたのはよかった。あーそういうことやったんやと僕もいろいろ腑に落ちたんです。岩田 江さんがやっていたXOE XAB(ショイシャブ)なんて僕も大ファンだったけど、音源も残っていないし、20人くらいの前でしかやらなかったバンドだから、その話が出てきて素晴らしかった」
――みなさん、文章が三田村愛にあふれてますよ。
森 「でも直球で褒めない文章ばかりなのがとってもいいよね」
和 「しいて言うなら吉本(秀純)さんの原稿が直球なんですけど、いわゆる正統ライナーノーツみたいな文章も必要だと思って。小田さんには大原 裕から連なるヒストリーを小田さんの目線で書いてほしかったし、輪島さんの原稿はちょっと予想外やったんですけどおもしろかったし、安田さんには、ご自身と三田村や、アリさんとの関係性をテーマにロック漫筆を書いてもらえたらというオファーの仕方でした」
――世にも珍しい本だし、かっこいいレコードも付いている。今後はこういう本がどんどん出てきてほしいと思う。
和 「もともと“レコードを出そう”という話だったとさっき言いましたけど、じゃあレコードって誰が買うねん、って話でもあるじゃないですか。音楽を聴く人は減っていないし、むしろ増えていると思うけど、聴く手段はめちゃくちゃ広がっている。たくさん選択肢があるなかでレコードを買っているのは、息をするように日常的にレコードを買う松永さんみたいなタイプもいるけど、そうじゃなければコレクターズ・アイテムみたいな買いかたになっている。そんな時代に“この人の音楽が聴きたい”と思ってレコードを買ってくれるなら、俯瞰して見ても作品として値打ちがあると思える、そういう物体にしたほうがいいだろうと。だから、これは本なんです。豪華なライナーノーツとかではないです。本にレコードが付いているんです」
――この本を読むことで、三田村管打団?の「?」の部分につかまれるし、すでにその音楽の魅力を知っている人もさらにのめりこめる。最大公約数に合わせてヒットを狙う本じゃなく、最小公倍数をどんどん大きくしていくタイプの本。この本が行き渡るちょうどいい部数はあると思うんですけど、それを超えてもうひとり「欲しい!」という人が現れたら成功だと思うんです。そういう意味では和久田書房がこれから出していく本もそういう線にあってほしいし、これが最初の出版物でよかったと思います。
和 「普通のビジネスはマスを狙うもの。本来ならもっとわかりやすくアピールすべきかもしれないですよね。でも、そもそもこの本で扱うのは、そういう世界の話じゃない。一生懸命アピールすることで逆にだんだん本質から遠ざかっていくみたいなところが物事にはやっぱりあるし。それに、ヒットは自分がやりたくてやっていることの延長線上にあるべきだと思うんですよ。逆にいうと、ヒットするものを考えて作ろうというやりかたはずーっとやってきたんです。でも自分にはそういう才能はないともう十分分かったんで(笑)、そこは無理をせず。でも、お金をかけて記念品を作ったわけじゃないんで売る気は満々だし、少しでも広めていく努力は続けていこうと思っています」
三田村管打団? Instagram | https://www.instagram.com/mitamurakandadan/
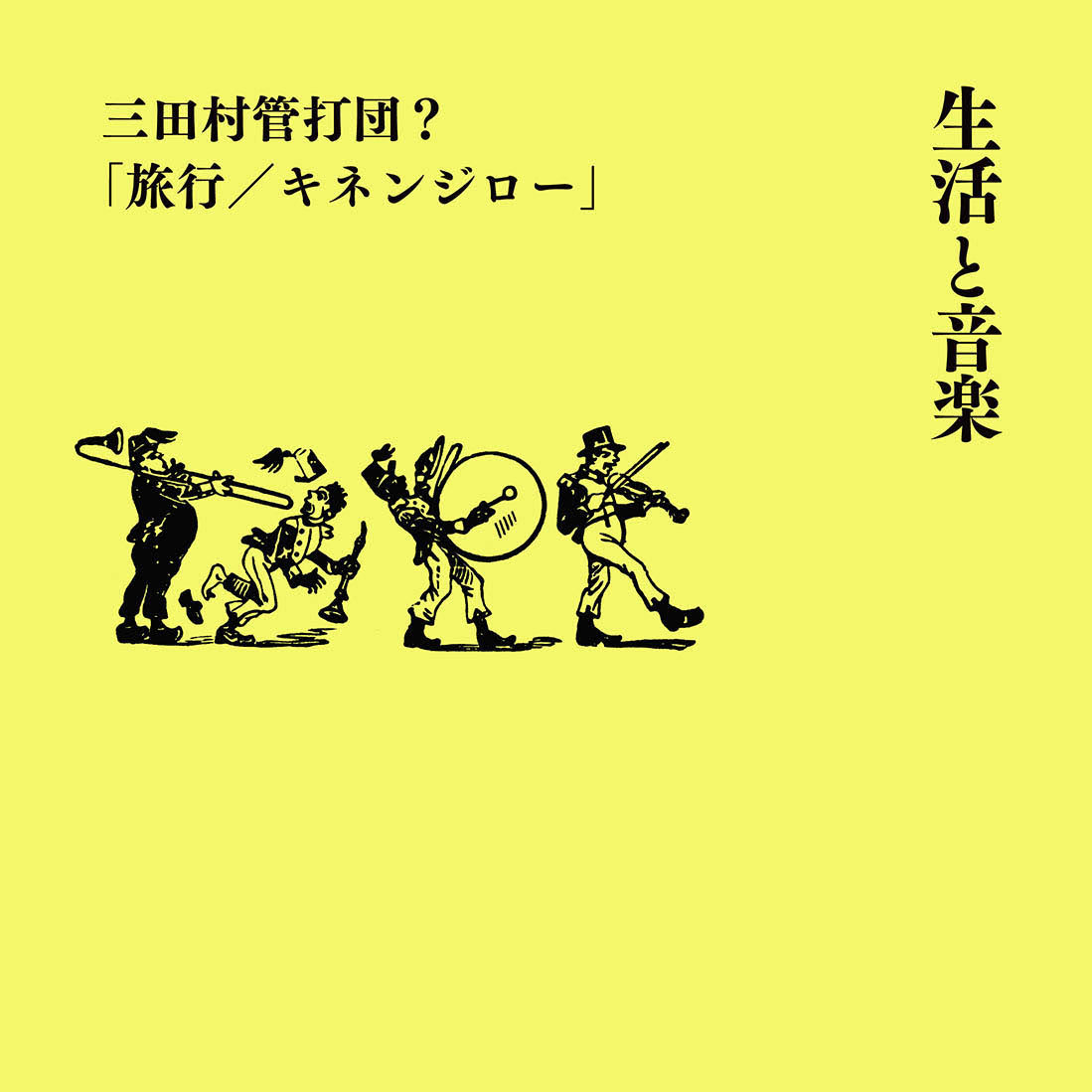 ■ 2025年8月20日(水)発売
■ 2025年8月20日(水)発売
『生活と音楽
三田村管打団?「旅行 / キネンジロー」』
和久田書房 | B5変型判 | 64ページ | 3,300円 + 税
ISBN 978-4-911580-00-4
https://wakudashobo.com/mitamura/
[内容]
レコーディング・データ / 録音メンバー
小田晶房「小さな社会と移り変わる人生」
輪島裕介「仮面ライダー1号型のローカルなブラスバンド」
吉本秀純「他に類を見ない、壮大な音楽地図」
安田謙一「ゲーム・ボーイのアート・スピリット」
MITAMURA KANDADAN? IN PICTURES
森本アリ インタビュー「アバウト・ア・三田村管打団?」
メンバー名鑑