確証なんてどこにもない、でも
活動開始当初はベーシストが在籍していたり、インストゥルメンタル主体という印象も大きかったため、PELICANとかRUSSIAN CIRCLESといったヘヴィ・インスト系のバンドに近いイメージを抱いていたが、ずっとデュオ編成の可能性をストイックに追求するスタイルを極めてきていることもあり、音楽性は違えどIan MacKayeのTHE EVENSとかに通じるものを感じたりもする。歌のパートに関しても、より積極性を増していくことになりそうで、今回カヴァーしたHELMETの「Unsung」では、ジョージ・ボッドマンによる初のリード・ヴォーカルが録音された。以下、そのジョージとのメール・インタビューを掲載しよう。
取材・文 | 鈴木喜之 | 2020年8月
写真 | 松島 幹
――新作EPについて話をする前に、まずはデビュー・アルバム『War Inside You』をリリースして以降の歩みを簡単に振り返っておきたいと思います。ひとつ大きなこととして、ダイロクさんのenvy脱退がありました。今後はSTORM OF VOIDに専念するという意志を感じますが、そのことによって現在のバンドには何か変化がもたらされた部分などはありますか?
「バンドとしての意識や活動が変わったということはないです。ただ、“SOVはライフワークでありたい”という気持ちがお互いに強まった気はします。僕もダイロク君もお互いに10年以上続けたバンドを脱退して気付いたこと、学んだことがあったと思うんです。主に家族との時間や仕事の時間、曲を作ったり演奏する時間とのバランスの取りかたですね。SOVはふたりの意思でしか動かすことができない、その他の誰の意見も受けつけないというスタンスが自分たちにとって一番バランスが取りやすい。みんなの都合を調整するのって本当に労力を伴うし、バンドを続ける上で多少なりともメンバー同士、さらにはその身近な人たちにも我慢してもらってる部分が必ずあると思うんです。それが、ふたりだけなら最小限のストレスで済むし、お互いの事情を尊重することで長く続けられるんじゃないかな、と今は思ってます」
――もうひとつ大きなこととして、1stアルバムをリリースしたレーベルが破綻してしまった件があります。ニューEPのリリースに合わせてアルバム『War Inside You』もBandcampで発売を開始した経緯を含め、STORM OF VOIDに関してはどんな影響があったかを、差し障りのない範囲で教えてください。
「僕らの場合は特にトラブルということはなかったです。強いて言えば、これまであったはずのSpotifyやApple Musicなどでの僕らのアカウントがいつの間にか消滅していたので、それをきっかけにレーベルの責任者に連絡をとって、僕らの音源に関する権利を速やかにバンドに戻してもらったというかたちでスムーズに終わりました。レーベルに対して残念に思うこともありましたが、僕たちの1stアルバムのリリースのために協力してくれたことは事実ですし、感謝してます」
――『War Inside You』のリリース・ツアーをはじめ、2018年から2019年は、いい対バンと組んだライヴを着実に積み重ねてきた印象を受けています。ニューEP収録の2曲もその間に仕上がってきたものだと思いますが、自分たち自身としては、そうしたライヴ活動を通じて、バンドをどのように前進させられてきたと実感していますか? 総合的に見て、この2年半はバンドにとってどんな時期だったでしょうか。
「デュオとしての可能性をずっと探ってきた感がありますし、それは今も続いています。アルバムは3ピース体制を想定した楽曲になっていたので、ライヴでいかに再現するかの試行錯誤がしばらく続きました。その過程で、これまで僕もダイロク君も使うことのなかった機材やアイデアを積極的にチャレンジしてみた時期が、レコ発ツアー前後だったと思います。試みを重ねた上で、結果としてどこか自分に嘘をついている感がいつまでもしていたので、そうしたギミックを全部やめて、すべて削ぎ落としたものを作りたいと思ってまた曲を書き始めました。その手始めが今回の『Kids. EP』です。ふたりとも仕事がかなり忙しいこともあって、スタジオでの限られた時間の中で新曲のアイディアを練りたいけど、次のライヴの練習もしとかなきゃいけないというジレンマに陥る感じがずっと続いてました。ですが、ライヴのオファーはできる限り断りたくないし、PC上でのやりとりで、ある程度新曲のネタは作れるけど、やっぱりスタジオでふたりで音出しながらの作業の方が楽しいし。そんな感じなので、前進するスピードは相当遅いです。年齢のせいか、2年くらいの時間の経過なんてあっという間でした(苦笑)」
――その間に観たライヴの中でも個人的に印象深かったのは、milkcowのツルさんが飛び入りのようにして度々ステージに登場し、嵐のように1曲だけ歌っていく姿で、スタイルこそ違えど、まさにQUEENS OF THE STONE AGEにおけるMark Laneganのようでした。改めて、ツルさんとの関係性について説明してもらえますか?
「まさしく、以前にも話しましたが、僕の中ではツルさんにはMark Laneganのポジションになっていただきたかったので、僕らの無茶ぶりとも言えるリクエストにいつも快く応えてくださるツルさんに大変感謝していますし、今後もチャンスがあれば是非お願いしたいと思ってます。改めてツルさんとの関係性と言われても、“大好きな先輩であり友達”としか言いようがないです(笑)」
――2018年の年末には新宿でAZARAKとのスタジオ・ライヴがあり、アルバムの通りにMark “Barney” Greenwayが参加した貴重な瞬間もありました。共演が実現した経緯と、あの晩の感想を教えてください。
「“やっと人前でやれた”というのが正直なとこでしたね(苦笑)。しかもスタジオ・ライヴで、っていうのがまた良かったです。結局レコーディング以外でBarneyとはあの1回しか演れていないので。長年の友人で、一緒にバンドもやっていた戸川(琢磨)君率いるAZARAKの年末企画にBarneyをゲストに迎えられて、個人的には感慨深い気持ちにもちょっとなりました。2018年辺りはBarneyもNAPALM DEATHの活動がオフになるとよく日本に遊びに来ていた時期で、ネットでも目撃情報がかなり多数出ていたので、東京ではそのありがたみがちょっと薄れていた感がありましたが(笑)、でもBarneyが参加してくれたことは本当に嬉しかったです。Barney本人も“今後も準メンバーのつもりでまた新曲に参加する”と言ってくれているので楽しみですね。コロナのこともあるので、気長に準備出来ればと考えています」
――そもそもSTORM OF VOIDは、ふたりのメンバーがそれまでに所属していた別のバンドに、新しく購入した楽器やアンプを持ち込めなかったことからスタートした“機材ありき”のバンドという話でした。また、ガイド・クリック、サンプラー、ドラム・パッドなども拘りなく試していきたいという意欲も示されていたと記憶しています。アルバム完成後、新たに増えた機材や手法によって導入された新機軸などは、ニューEP収録曲に限らず何かあるでしょうか?
「先程すでに答えてしまいましたが、この2年いろいろやってみた結果、むしろ削ぎ落としたいという方向に現在は向いています。ダイロク君は、自身が所有するヴィンテージ・ドラムセットに対する拘りがすごくあるので、新たな機材に抵抗を示すかと思いきや、僕の想像よりも遥かに新しい機材に対して積極的で、逆に僕はテクノロジーにオープンなつもりでいたのに、蓋を開けたらまったく扱えなくて投げ出してしまうタイプでした(笑)。今回のEPを録ってみて、改めて今はギターとドラム(時々歌も入りますが)だけでどこまで自分たちが楽しめるかを求めたいと思いました」
――インスト・バンドであることには特にアイデンティティとしているわけではなく、メンバー2人とも歌うかも、というようなことも話していましたね。実際、今回HELMET「Unsung」のカヴァーでは、ジョージさんがフルで歌っています。やってみた手応えは?今後はメンバー自身にゲストも加えて、よりヴォーカルの比重は高まっていきそうな予感があったりしますか?
「そうしたいという気持ちは以前からずっとありました。なので、J. Robbins(BURNING AIRLINES, GOVERNMENT ISSUE, JAWBOX)が音源で歌ってくれた“War Inside You”もライヴでは僕が歌ってみたり。さらにチャレンジしようと試みたのが今回のカヴァーでした。自分で歌メロや歌詞を考えるのは相当ハードルが高いので、なかなかできませんが、カヴァーだったら今後も自分でも歌ってみたいと思って。今回のヴォーカルに関してはtoeの美濃(隆章)君に録ってもらえるという安心感も手伝って、楽しみながら歌えました。歌入れに際して、美濃君の所有する様々なマイクの中からしっくりくる1本を選ぶ作業を行なったんですが、これがかなり楽しくて、実際歌入れの時間よりもマイク選びの時間の方が長かったかもしれません(笑)。いずれ作るであろう次回作は、ゲストも迎えつつ自分が歌うことも含めて全曲ヴォーカル入りにしたいと目論んでますが、果たしてどうなることやらです」
――今回「Unsung」をカヴァー曲に選んだ理由は?演奏するにあたっては、どんな点を意識しましたか?
「理由はいろいろです。90年代のハードコア・パンクやオルタナティヴ・ロックと言われていたシーンの中で、ヘヴィなサウンドを打ち出していたバンドは数々いたと思いますが、個人的にはメタル・シーンよりもそうしたバンドから受けた影響が今でも大きい気がするんです。HELMETはMELVINSやTHE JESUS LIZARD等をリリースするAmphetamine Reptile Recordsからもともとデビューしてますし、SOVの音もスタンスもそういうバランス感覚でいたくて。そう思ったときに、“Unsung”のシンプルかつヘヴィなリフ、反復を用いた展開とか、SOVを聴いてくれる人たちや僕ら90年代青春世代なら納得のカヴァーになるんじゃないかと思いました。SOVでカヴァーは初めてだったので、ふたりで“とにかく照れずにちゃんとやろう!”という至極当前のことを肝に命じて取り組みました(苦笑)。過剰なアレンジを加えたカヴァーは好きではないので、ベースレスなのと8弦に合わせるためにキーを下げたこと以外は基本的に原曲に忠実にやったのですが、僕が歌うにはキーが地声に近すぎてしまって逆に自分の首を絞めてしまいました。結果的にハリのない声で録れて、原曲より若干けだるい印象が出せたかな、と思ってます(苦笑)。もうひとつ、この曲を選んだ理由に、歌詞の中に“Die young is far too boring these days”という一文があり、原曲の意味合いや捉えかたはいろいろ解釈の違いがあるかと思いますが、この一言がこの曲の印象を決定づけていると当時から思っていました。自分が子を持つ親であることも理由のひとつですが、今また国内外の様々なシーンで素晴らしい才能の持ち主が若くしてこの世を去ってしまった話を知らされることは、本当に悲しいです」
――ニューEPは、パンデミック下でのレコーディングということになります。この状況で制作を敢行したのには、特に何かきっかけや思いなどがあったのでしょうか?
「今回レコーディングさせてもらった美濃君の自宅にできたMINO STUDIOを建設中に、ダイロク君が大工さんとしてお手伝いしたんですね。それで、美濃君のほうから“完成したらここでSOV録ってみようよ”って言ってくれたんです。当初は僕らがスタジオ完成後最初のテストを兼ねたレコーディングをするはずが、バタバタしているうちに5番目になってしまって(苦笑)。そういう経緯でこのタイミングになりました。もうひとつは、このパンデミックで困っているバンドをサポートしようということでBandcampが始めた“Bandcamp Friday”について知ったこともきっかけになりました。そもそも今後はセルフリリースを考えていたのと、資金的に必然とデジタルだけのリリースになるとは思っていたのですが、サブスクリプションに上げるだけというのがどうにも解せなくて。そのときたまたまDischord RecordsがBandcampに全タイトル上げるという記事を読んで、遅ればせながらBandcampの姿勢や具体的なデータを初めて見て驚きました。日本では“バンドをサポートする”というメンタリティを持ったプラットフォームの浸透はまだまだ広まらないかもしれません。けど、一番システム的に似ているのは所謂“投げ銭”や“おひねり”で、これは日本にも昔からあったシステムだと思います。まだまだ勉強不足なので詳しいことはわかりませんが、たしかにこちらが設定した値段よりも高い金額で音源を購入してくれる方々が全購入者の2割程度いて、大変感激しました。サブスクリプションを悪だとは思いませんが、何千万回~何億回転して成り立つ土俵と、そこを目指しているわけではない音楽と住みわけがあっていいのかなと思います。自らの身を切って音源を製作しているバンドやアーティストは、サブスクにむやみに音源を上げる必要はないと思いますし、リスナーも使い分けて考えられるようになったらいいんじゃないかな、と思います。放っておいても何千万回も聴かれるようなメインストリームのヒットチューンや、過去の名作や定番だの、レア盤化して高値がついてしまった音源とかはサブスクを使って定額で楽しめばよいと思うし、現在進行形のバンドはやはりちゃんとデジタルでも音源を売って、購入者がいることで活動の資金に充てられる。購入する側も、好きなバンドをサポートしてるという意識が強まると思います。誤解を恐れずに言うと、昔は大手レコード販売チェーン店ではローカルのハードコア・バンドの音源は扱いがないけれど、街の個人経営のレコード・ショップに行けば音源を置いてもらえたりしたんです。どの街にもほぼ必ずアンダーグラウンドな音楽を扱う小さなレコード・ショップがあって、そこに掘りに行ったり、オススメのバンドを教えてもらったり。残念ながら今はこうした店舗型のお店は減ってしまいましたが、デジタルの世界での音源の探し方や聴き方の感覚としては、こう考えると構造的に似ているのかな、と思います」
――録音作業は、美濃さんが所有するMINO STUDIOにて行われ、ミックスも担当されたようです。ドラム・チューニングの土田義範さんについても含め、どのようなレコーディングだったか様子を教えてください。
「大変リラックスしたレコーディングでした。まず、先程も述べましたが、MINO STUDIOは美濃君の自宅にありまして、完全に友達の家に遊びに行く感覚です。土田さんも僕たちの親友なので、友達が最新のゲームソフトを手に入れたからみんなでその子の家に遊びに行くような感覚でした(笑)。とはいえ、僕は美濃君と作業をするのが初めてだったので幾らか緊張もしてましたが、実際すごく楽しくて、むしろサクサク作業が進むのが逆にもったいないくらいでした。ドラムもギターもほぼ3テイク以内で録れて、歌もサクッと終わらせて、2日間で録音は終了し、あとは美濃君にミックスをお任せしました。土田さんは数多くのアーティストのドラム・チューニングを手がける素晴らしい腕を持つ職人で、スケジュールを押さえるだけでも大変なので、本当は秘密にしておきたかったのですが(笑)、僕たちのサウンドメイクの土台の要です。おふたりとも、言葉では説明出来ないマジックの持ち主です。今回のレコーディングで、やっと自分たちの納得のいくギターとドラムの音を録れたという実感があって、それは勿論、ふたりのおかげである部分がとても大きいのですが、初めてベースを入れない前提で録れたのも大きな要因のひとつだったかな、と思います。音源を聴くと、当然ベースがいない薄さを感じる部分はあると思うのですが、僕には逆に、ギターとアンプ、ダイロク君のドラムの持つ本来の音のレンジ(音幅)を損なわずにキャッチして、ベースとの音域の干渉を気にせず2つの楽器を目一杯アウトプット出来ているという解釈なんです。この“干渉”という問題は、そもそも僕が8弦ギターを使ってることが原因なのですが……これは話すと長いのでこの辺にします(汗)」
――EPのタイトルが“Kids”で、ジャケットもお子さんの写真が使われていますね。『War Inside You』の時も、ジャケットに絡めて、現在の世界情勢と、子供たちに対する責任感のようなものを意識しているという話が出ましたが、現在STORM OF VOIDの表現活動に、そうした心情はどの程度の影響を及ぼしているでしょうか?
「僕個人は変わらず、子供を持つ親なら当たり前ですが、子供たちが生活の中心なので、子供たちの成長や取り巻く環境が僕の心情に与える影響は大きいと思います。そして、自分の子供たちだけでなく友人の子供たち、地域の子供たち、遠い国の子供たちのことも考える、そういう気持ちが自然と大きくなっている気がします。現在の日本の政治や世界情勢を憂うのも、何より子供たちの未来がどうか今よりも生き易い世界であってほしいと願うからだと思います。ダイロク君とはお互いの子供たちの話も自然とよくしてますし、子供たちが僕らの共通の原動力になっていると思います」
――バンド名に関連して、“虚無”というのが自らにとってのキーワードだというような話もしたと思います。そうした“虚無”とのバランスの取りかたに関しても、変化が生じたりはしていないでしょうか。
「それは終わりない葛藤の連続だと思います。自分の心模様は常に目まぐるしく変わりますし、身の周りや世界もいつも回り続けているので、変化の連続です。自分の子供たちへの愛情だけは死ぬまで変わらないと信じていますが、残念ながらそんな親子関係が死ぬまで続くのか、確証なんてどこにもありません。僕は選挙があれば必ずその権利を行使していますが、自分が投票した候補者が当選したことなど1度もありませんし、自分は常に少数派なのだと思うと、世間を疑った目でしか見られなくなったり、自分の住む国に希望を持てなくなったり。そう思うと生きていることは“無常”で、“虚無”がいつもつきまとう感覚になります。その反動で生きている喜びや証を求めている部分もあるわけですが。でも普段からそんなことばかり考えて行動しているわけではないです(苦笑)。とにかく、いかに楽しく、飢えずに今を家族みんなで生き伸びられるかが僕の思考の中心です。質問からだいぶ外れた回答になってしまいましたが……(汗)」
――Bandcampページのプロフィールに、これまでTシャツなどにもあしらわれてきた“BREAKNECK BUZZCORE”という言葉が載っていることを再確認したので、改めて、この言葉にどういう意味を込めたのか教えてくれますか?
「そもそもはAZARAKの戸川君が僕達の音を“BREAKNECK BUZZ SOUND”みたいに何かで書いてくれたのを見て、ありがたくネタとしていただいた記憶があります(苦笑)。いまだだに、自分のバンドサウンドをジャンルに当てはめるのが得意ではなく、特に音源リリースのタイミングで海外へ向けた文章を書くときなどは悩むんですが、誰にも通じないこの言葉が自分としては一番僕達を言い当てているような気でいます。そもそも、特定のジャンルに当てはまるような音楽をやりたいと思ったことが1度も無く、この言葉に意味があるとすれば、多少なりとも我々のバンドとしての姿勢が伝わればと思うときに使っています」
――今後の活動予定を教えてください。先日、BUSHBASHから初の配信ライヴを行ないましたが、これから先にも同様の企画は予定されているでしょうか。
「いま現在、配信も含めてライヴの予定は1本もありません。大変残念ですし、このままライヴができない状況が続くことも心配ではあります。ちなみに、先日のBUSHBASHのライヴでは、配信ライヴの楽しみかたの一端を見ることができました。あの日はドキュメンタリー映画『MOTHER FUCKER』の監督を務めた大石規湖さんが撮影を担当してくださったんですが、その日の主催者でトリのNoLAのセットで彼女が手持ちのカメラ1台に持ち替えた瞬間に、大石さんらしさが炸裂したんです。それまで4台の定点カメラをスイッチングした映像だったんですが、ワンカメになった瞬間から見事なまでにNoLAの熱量をYouTube越しでも感じました。配信ライヴは、やはり撮る人に依るという部分の大きさを思い知りましたし、そうした楽しみかたがあるな、という発見でした。フロアで体験するライヴがなかなか行えない中で、今だからこそできる遊びかたを、できる人はもっとやったほうがよいと思います。さらにそれが、自分たちの大好きな遊び場を守ることに繋がるならどんどんやるべきだと思うし、僕たちもその一端を担えるなら是非参加したいという気持ちです。ただ、一番大事な音の拘りの部分は、配信と会場でダイレクトに浴びるのとではどんなにがんばっても溝は埋まらないので、別物として考えなければなりません。早くまたこれまでのように誰もがライヴに来られる環境に戻ってほしいとはいえ、無計画で無責任な行動で迷惑をかけるような真似はしたくないし、自分たちが楽しければなんでもいいっていうわけにはいかないので、上手くやれたらいいですね」
――現状どうしても、ライヴより、閉じこもりがちな環境ではあると思いますが、次なるEP、あるいは2ndアルバムの構想を踏まえた作曲活動は進んでいますか?次作については、どんな構想を抱いているのでしょう。
「スローペースですが、少しずつ新たな曲は作っています。僕らは音源や物販の収益を基にレコーディングを行なっているので、なかなか1週間やそれを超えるようなアルバム製作を賄うことが難しく、今後も今回のようにデジタルでEPやシングルのようなリリースを繰り返す傾向になるのではないかと思います。僕らとしても、出来上がった曲からリリースしたほうが長々と寝かせておくよりも気持ちがよいですし、リスナー側の音楽の聴き方も変わってきて、アルバムという形式に拘る必要はあまり感じていません。もしかしたらインスト・ヴァーションとヴォーカル・ヴァージョンでリリースの形態を変えたりするかもしれません。ゲスト・ヴォーカルも実現させたいアイディアはいくつもあります。そして、なにより、また今までのように全国に、そして世界中に演奏しに行ける日が来ることを願ってます」
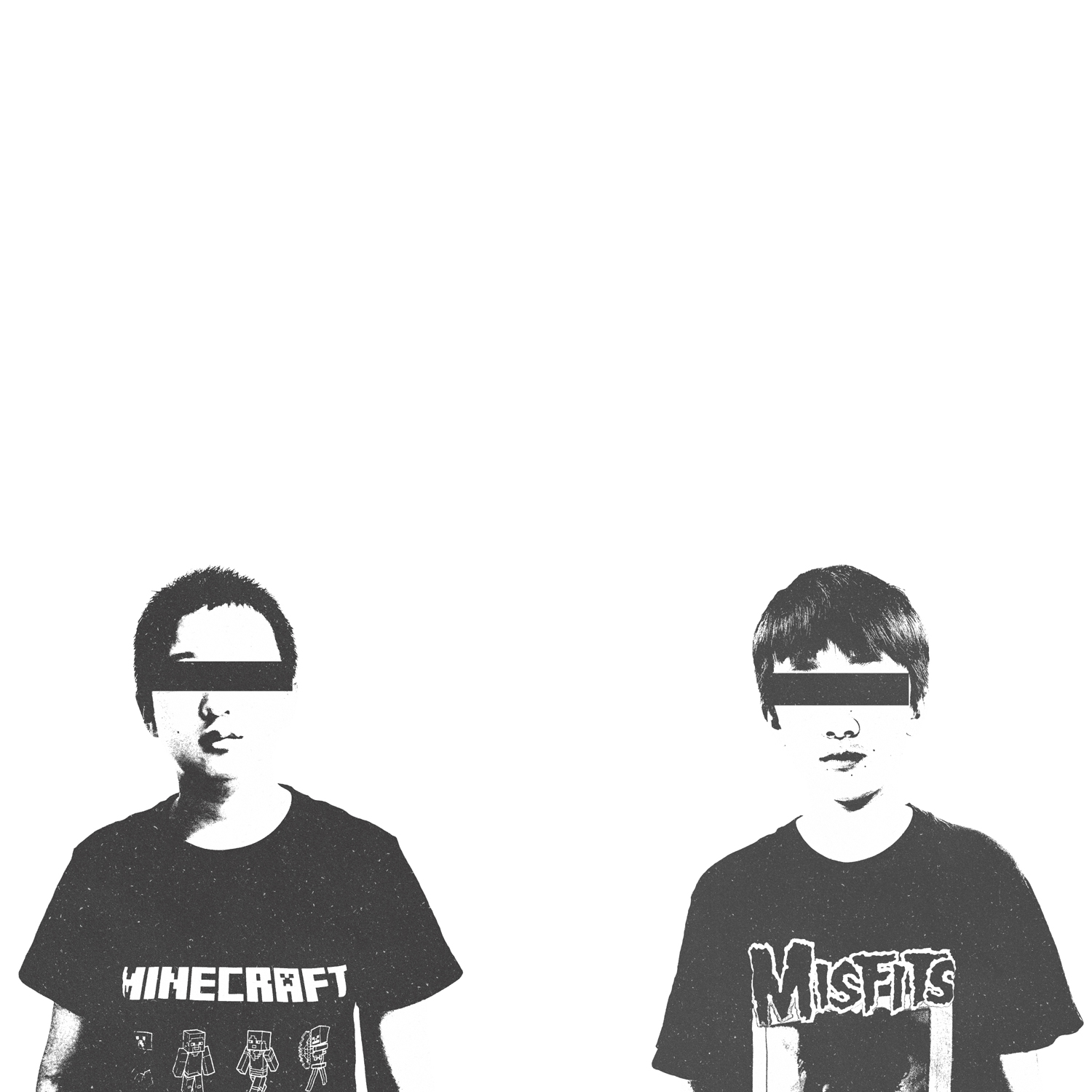 ■ 2020年8月7日(金)発売
■ 2020年8月7日(金)発売
STORM OF VOID
『Kids. EP』
https://stormofvoid.bandcamp.com/
[収録曲]
01. Ripping Every Pages
02. Because You Are Here
03. Unsung







