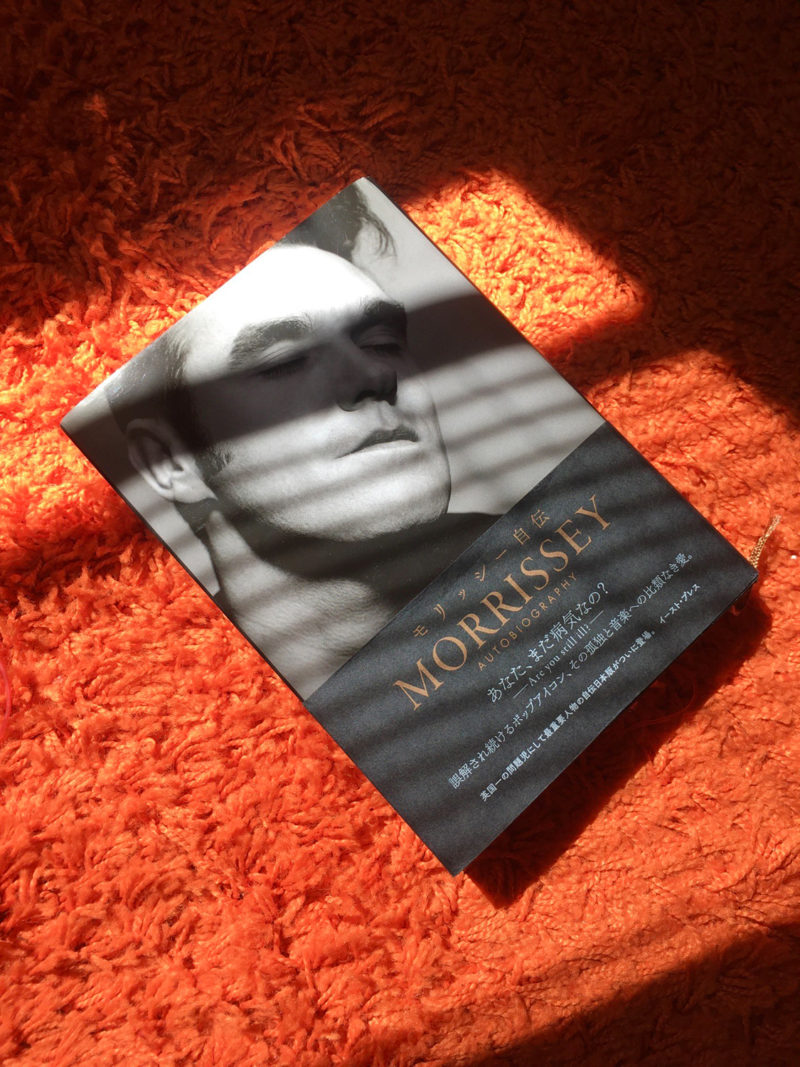文・撮影 | 久保田千史
| 小島秀夫『DEATH STRANDING』
ゲームが好きだ。たくさんのタイトルをプレイするゲーマーではなくて、同じタイトルをリピートするタイプ。“遊具”よりも“作品”として見る傾向があるからなのかもしれないです。それを初めて意識したのは『リンダキューブアゲイン』。ゲームハードのない家庭で幼少期を過ごしたので、けっこういい歳なんだけど、ゲーム観は自分で手に入れたPS®以降のほうが鮮烈なんです。だからPCエンジンで『リンダキューブ』が登場した際の感覚はよくわからなかったけど、荒唐無稽な設定に妙なリアリティを与えるシナリオと、田中達之(CANNABIS)さんのアートワークがとても好きでした。田中さんは『AKIRA』や『ふしぎの海のナディア』、『老人Z』『バブルガムクライシス』とかにも携わっていた人だから、『アニメージュ』『ニュータイプ』を読んでいるだけでいじめられた身(持ち前の容姿と性格に加え、警察庁広域重要指定第117号事件の余波もあってか、オタクへの風当りが非常に強かったのです)としては、好きになるのは当然だったのかも。でも、時間を忘れて同じゲームを繰り返しプレイするようになったのは『サイレントヒル』が発売されてから。現実を何者かに侵される感覚は『サイレントヒル』シリーズでしか味わえないし、今で言う“フォトリアル”なグラフィック、霧の描写、内面にしかフォーカスしていない分析心理学的なシナリオも最高。山岡 晃さんの音楽も素晴らしい。山岡さんが初期Z.O.Aのギタリストだったって森川誠一郎さんから伺ったときには、めちゃくちゃテンション上がりました。OSTはゴス / インダストリアルのファン必聴だと思うな~。しかし『サイレントヒル』シリーズの素晴らしさにより、それ以上にプレイしたいゲームが見つからないという問題が生じました。いくつかのタイトルは気になってプレイしてみたけれど、ファンタジー過ぎるのが嫌だったり、操作が気に入らなかったり、ヴィジュアルやシナリオがグッとこなかったりで、いずれも繰り返しプレイするまでには至ることなく、結局はビッグ・タイトルだからと敬遠していた『メタルギアソリッド』に辿り着いたわけです。もちろんMSX2の『メタルギア』は前述の理由から全く触れていなかったけれど、ゲーム・システムからヴィジュアル、ディストピア過ぎる世界観、決してハッピーではない細部まで寝られたシナリオの虜になり、シリーズ通じて繰り返しプレイしまくりました。伊藤計劃さんによるノベライズしかり、Burialのサンプリングしかり、00年代を象徴する作品であるのは間違いないと思う。少なくとも個人的にはそう思う。だから、小島監督が『サイレントヒル』シリーズに携わると知ったときの喜びはハンパなかった。しかもプレイヤー・キャラクターが、妻の大好きな(『ウォーキング・デッド』じゃなくて『処刑人』で好きになったみたいなので、けっこう筋金入り)ノーマン・リーダス!「まだゲームやってんのかよ……」って白い目で見られる頻度が飛躍的に下がるに違いない!という喜びと共に『P.T.』をプレイし続けたのは言う間でもありません。それだけに、企業体そのものを批判する趣味のない自分でも、KONAMIのやりかたは許せなかったな~。『ファントムペイン』で鏡を叩き割ったヴェノムの姿、それはそれは、なんとも言い難い気持ちになりましたよね……。
そんなわけで、前振り長過ぎたけど、制作発表から約3年間、あまりに楽しみで極力情報を入れずに待った『DEATH STRANDING』。めちゃくちゃ嬉しいよ~!でも、すいません、プレイ後の感想じゃないんです。まだ全然やってる途中。子供がまだ小さいので、何時間もまとめてはプレイできないんですよ……。そのぶん、おなかに赤ちゃんをくっつけてハァハァ歩くノーマン・リーダスさん = サムに感情移入してしまうところはある(笑)。ずっこけてBBが泣き出すと、ごめんごめん!ほんとごめん!って気持ちになる。他の人よりも“BBをあやす”コマンドを使う頻度が高いかも(笑)。子供も、父親がBBをどう扱うか気になるようで、側にいると「あかちゃんないてるよ!」って逐一指摘してきます。とりあえず、弱々しい存在に頼りながら物語を進めるという時点で、なんか新しい。えっ、この赤ちゃん、ずっとくっつけてなきゃいけないの?って思ったもの。エクストリームに言えば荷物を運ぶだけ、っていうゲーム自体の在りかたも新しい。この世界特有の自然現象、現実同様に複雑な地形、荷物を奪おうとする勢力やテロ組織など、けっこう面倒くさい障害はたくさんあるものの、全体的には非常に淡々としているので、“クソゲー”って一蹴している人の気持ちも真っ当だとは思う。でもオープンワールドで、崖に梯子を設置したり、川に橋を架けたり、荒涼とした土地に道路を敷設したりで地味に配送エリアを整えて、荷重と地形、配送形態(徒歩か、バイク便か、トラック配送か)を加味して地味にルートを考えるというのは、めちゃくちゃ楽しい。影響されてUber Eats始めちゃう人とか、実際いるんじゃないか(笑)?事故にはくれぐれも気を付けてね!『メタルギア』シリーズでもすでに“避けるべきもの”だった戦闘や、売買を含むトレードではなく、ロジスティクスにフォーカスするあたり、やっぱり小島監督おもしろい。インターネットのおかげで世の中便利になったねぇ、って中高年はよく言うけれど、それは発注のシステムやインターフェイスに対しての意見でしかないわけよ。その便利を根底で支えているのは、変わらずロジスティックのテクノロジーやテクニークだ。変わらずというか、便利になったねぇ、のおかげでより複雑に高度化していると思う。ひとつのエリアに間違いなく荷物を配送するというだけでも、どれだけの技術が投入されていることか。インターネット以前だって、コンビニ店員の深夜番を2店舗(2社)掛け持ちしてたことがあるんだけど、どっちの店でもPOSで注文した数の通りに毎晩、陽が昇る前までにパンを運んできてくれるの、すごいなあって思ってたもん。だって、それを何店舗もやってるんだよ?ドライバーさんはそれが仕事なのかもしれないけど、大変だよ。技術がないと何軒も回り切れないよ。大した不利益でもないのに、お客さんは神様ですってツラで店員さんにいちゃもんつけてるオッサンは、泥酔した帰り道にその店があって、そこに買うべきものが存在して、その価格で買えるというありがたみを一度は考えてみるべきだと思うね。話が逸れましたけれども、本作は小島監督曰く“つながり”がテーマだそうで、配送という作業を含むいたるところにそのモチーフが現れます。自分は正直、“#~とつながりたい”みたいなやつならめちゃくちゃうんざりするし、「ネットが世界を覆い尽くしても争いは絶えなかった。無理やり世界を繋いでもまた綻びがうまれる」というサムの発言に大いに賛同するけれど、監督のおっしゃる“つながり”がどう帰着するのか、もしくはしないのか、ラストまでがんばって確認したいです。その他感想としては、リーダスさんが脱ぎまくるのいいっすね!雷電はネタ化してしまったけれど、リーダスさんという素晴らしい憑代の力で諸々ジャストに実現させているだけでも、このゲームはほんとすごい(笑)!27週くらい(?)とは言え、谷に陥りがちな胎児というモデルをめっちゃかわいく表現したBBもすごい。スティルよりも動いているほうがずっと素敵なレア・セドゥさんの魅力もばっちり捉えてられてる。ママー(マーガレット・クアリーさん)の日本語吹替を演じる坂本真綾さんの独特な喋り方もすっごくいいです。ママーに「試してみてね!」って言われるとなんか嬉しい(笑)。こないだ玉野先輩とも話したけど、小島監督が帯文を寄せているだけに劉慈欣『三体』のファンもチェックすべき。
| 近藤さくら『場景を愛し、眼差しを共有する』
弐瓶 勉先生の『BLAME!』に登場するドモチェフスキーというキャラクターは、万年筆か何か、ペンのキャップと思しき物体を持ち歩いています。ドモチェフスキー自身は、「前に別の場所で拾った」それを「古い部品か何かだ」と認識しているようです。つまり、拾得した場所を“別の場所”と呼称する程度にしか世界を把握していないし、ましてや物体の出自や用途についての情報など全く持ち合わせていないのだけれど、とても大切に扱っている。ドモチェフスキーが物体をそっと立ててみる場面(8巻)は、大量破壊的なオノマトペが多い劇中においては異色で、最も好きなコマのひとつであります。何だかわからんが、美しいもの、素晴らしいもの(という概念で見ているかは不明だけれど、それに相当するもの)で、自分になくてはならないもの、忘れてはならない感覚に紐付いたものとして、放置されたAI = ドモチェフスキーのアルゴリズムは処理しているわけです。
近藤さくらさんの絵は、何だかよくわからない。岩のように堅くも見えるし、コロイドのように軟らかくも見える。高速で移動する持続のようにも見えるし、違う時間軸で静止する瞬間のようにも見える。轟音が聞こえてくるようでもあるし、耳が痛くなるような静寂に吸収されるようでもある。直線的な意味では、そもそも何が描かれているのかがわからない。ご本人とお話してみると、どうも作家自身ですらわからないらしい。何のヴィジョンもなく描き始め、筆が進み、何かが立ち上がってくるにつれて「なるほど」と感じるそうです。「なるほど」って。まるで他人行儀で、自分では描いていないような言い草だけれど、絵の技術に疎い筆者だって、これだけ大きな絵を完成させるまでに費やされた労力がどれだけのものか、ある程度は想像できる。白波多カミンさんのフライヤー・アートにあしらわれた写実的な美しさを伴うピースを見れば、技術を磨く時間を重ねてきたであろうことだってわかる。少なくとも自分なら、“何か”を描く確固たる“何か”がなければ、わざわざ臨まないであろう行為です。言葉では曖昧な対象および主体である“何か”と“確固たる”は矛盾するように思えるけれど、それは対象と主体が明瞭である様を“確固たる”としているだけであって、過程や行為そのもの、もっと言えばガッシュや筆といった道具、もしくは近藤さんの手などを、“何か”が明瞭化するということだってあるんじゃないでしょうか。だから、こういう言いかたは本来、作家さんに失礼だろうけど、近藤さんは対象たる“何か”に固定された“道具”なのかもしれないって思う。近藤さんが不定期に刊行している「視線の標本」という小さな冊子のタイトルが好きなのだけれど、それも誌面に綴られているような日常を近藤さんが固定しているのではなく、日常に固定された近藤さんの標本なのだという気がしています。移動中に発見した“何か”の数々を携帯電話で撮影し、CARREと白波多カミンさんよる音楽と共に編集した映像作品『眼差しの蓄積』を本展で初めて拝見して、その思いをさらに強くしました。近藤さんは同作のために、“何か”を見つけるや否や、不動の姿勢で撮影を繰り返したそうで、字義通り固定されていたというのは思い切り余談ですが(笑)。標本はたぶん、ドモチェフスキーの“何かの部品”といっしょで、あるときに浮かび上がった定着しない何かを、繋ぎとめる(ストランディング)ためにあるのです。それはもしかしたら、意図や背景を求める“アート”ではないのかもしれませんが、筆者を含む複数の観測者が近藤さんの作品に固定させられているのかと思うと、愉快で、ほっとしたような気持ちになります。世界は、ある種受動的に固定された非連続のレイヤーで成り立っているけれど、どのような力を行使して、どう繋ぎとめるかによって、大きく変化するということを、改めて思い知らされるのです。「Cale / Field Sewing Tokyo」の入口付近にひっそり展示されていた神経系を思わせる立体作品のキョトンとした目も、そう言いたげに見えました。