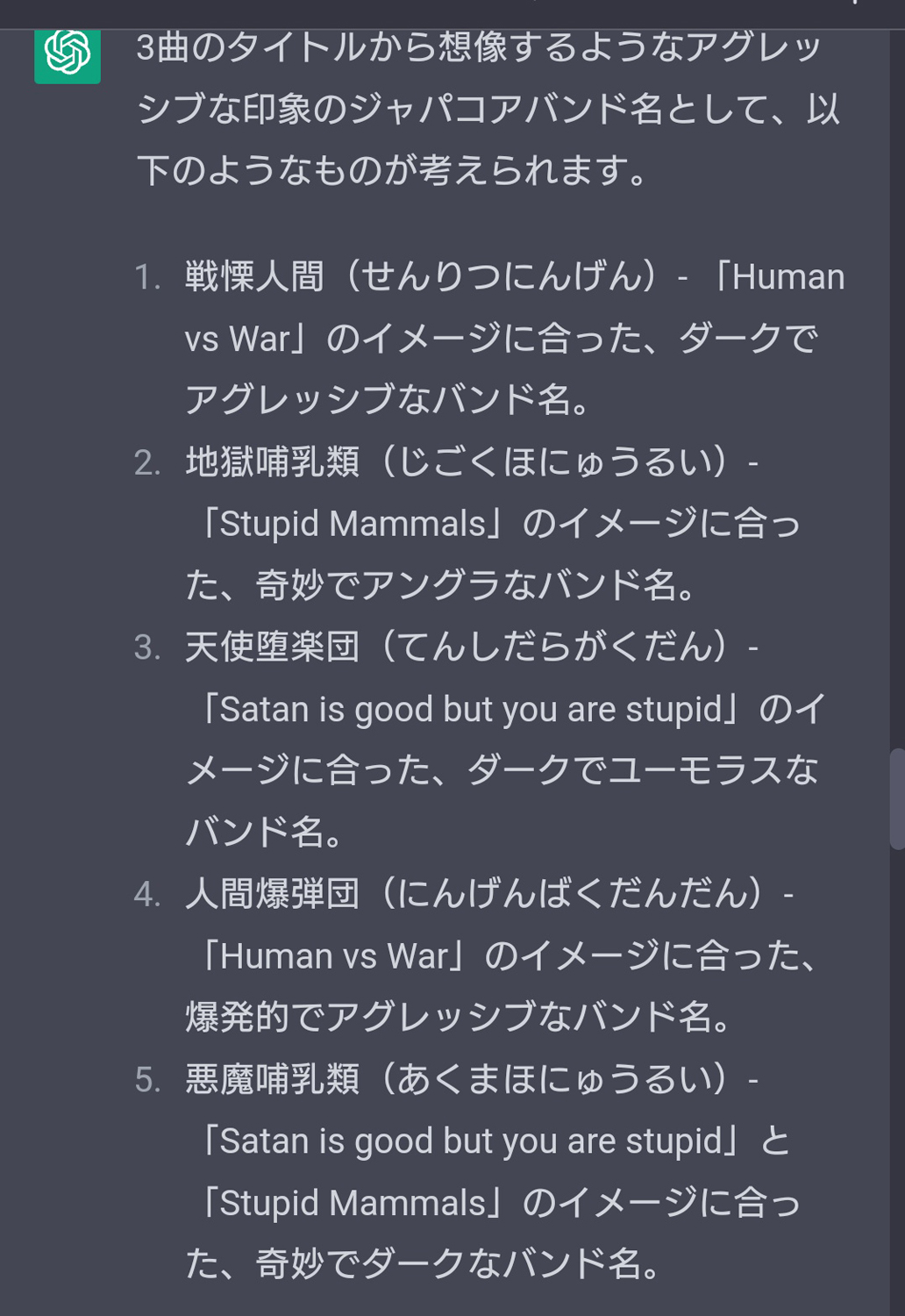たくさんの魂を集める
童子はSOILED HATE(※2024年5月に解散)、Catastrophe Ballet、珠鬼で暗躍するO.Tatakauによる“ひとりロウ・パンク”プロジェクトである。「Japanese Occultic Death Punk」を掲げ、80年代ジャパニーズ・ハードコアと現行のUSロウ・ハードコアのエグいところだけを混交させたかのようなサウンドは危険というほかない。どうしてこんな危ない音楽が生まれてしまったのか、O.Tatakauに直接聞いた。
取材・文 | 須藤 輝 | 2024年11月
Main Photo ©吉河千尋
――童子って、なんなんですか? 2023年の3月に、いきなりBandcampに謎の音源がアップされて震えました。
「当時、たぶんSOILED HATEが解散する感じになっていて、ひとりで何かやりたいと思っていたんです。実際、コロナ禍にひとりでブラックメタルを作っていたんですけど、コロナが明けてから、例えばGAGが来日するという話を聞いたりして、パンクのほうに心が持っていかれたんですよね。あと、YouTubeでCRISIS MANっていうロウ・パンクのバンドを聴いたとき、すごい衝撃を受けて。ものすごく熱いアジテーションから入るのに、次の瞬間、曲が始まったらポンコツで、拍子抜けしちゃう。こういう緊張と緩和の妙がロウ・パンクのいいところだし、ひとりブラックメタルをやるのもひねりがないし……」
――ひとりロウ・パンクをやろうと。
「メンバー全員のグルーヴ感があってこそのロウ・パンクなのに、それを宅録でやったら逆におもしろいかもって思ってしまったんですよね」
――いわゆるロウ・パンクは昔から聴いていたんですか?
「たぶんロウ・パンクをジャンルとして意識したのは、2018年にHANK WOOD AND THE HAMMERHEADSが来日したあたりかな。その頃、ちょうどhate5sixとかで彼らのライヴ動画を観たりしていました」
――unARTigNYC
「そうそう。Iggy Popとかを彷彿とさせるような、ロックかつパンクというか。険しい顔して“うおー!”ってやるんじゃなくて、ウキウキで踊っちゃう感じのハードコア・パンクもあるんだなって。HANK WOOD AND THE HAMMERHEADSとDAWN OF HUMANSとCRAZY SPIRITのメンバーがやっていたMURDERERのアルバム(『I Did It All For You』2018, Toxic State Records)もすごく好きなんですよ。イントロだけエレピできれいな感じだけど、曲が始まったらブラックメタル・パンクみたいな」
――リズムがずっと単調で最高ですよね。
「ドライヴ感がギリギリある、テンションが高いんだか低いんだかわからなくてバグる感じがたまらないですよね。あと、2020年くらいからHarakiri DiatとかNo Dealとか、ハードコア・パンクの音源を上げまくるYouTubeチャンネルにハマって、“アメリカではこういうのが流行ってるんだ?”と。そこでSTUNTED YOUTHという、SIEGEの幽霊みたいなバンドを知って、めちゃめちゃがんばっているのに音は腑抜けているような音源を自分でも作ってみたくなったんです」
――こないだBUSHBASH(東京・小岩)で話したとき、童子を始めるにあたって「フッ、GAGか……俺にもできる」と思ったと、アミバみたいなことを言っていましたよね。
「そうでしたね(笑)。GAGって、生で観るまではある種のギミック・バンドだと捉えていたフシがあって。もっとうまくできるんじゃないかと、勝手に“打倒GAG”みたいな」
――ギミックって?
「もちろん曲がいいのは大前提で、そのうえでパフォーマンスとかでおもしろくしている感じもあるのかなって。生で観てもその印象はあまり変わっていないんですけど、演奏もすごくタイトでブチ上がりましたし、さらに好きになりました」
――GAGをたどっていくとHOAXに行き着きますよね。
「そうなんですけど、僕は2016年のHOAXの来日公演は行っていなくて、後追いなんです。だから童子を生んだ決定的な要因は、USのバンドだとGAGになるのかな。それ以外だと、ちょうどSOILED HATEがKLONNSとか鏡 KAGAMIとよく絡んでいた時期でもあったので、そういう雰囲気を持った若手のバンドがもっと増えれば、シーン的なものができそうだと思ったり。いくつかの目論見が重なってはいるんですが、たぶん一番やりたかったのは、誰も知らなかった80年代のジャパコアの音源が発掘された感じ。“こんなバンドがかつて存在していたなんて!”“いや、今のバンドなんですよ”みたいな」
――童子には「Killed By Death」シリーズ的なオブスキュアさを感じたのですが、あれは狙っていたんですね。
「イメージのひとつとして、当時の音を再現するというのがあって。80年代のジャパコアって、ひとつひとつの音は覇気がなくてキテレツだけど、アンサンブルで鳴るとものすごく粘り気というか、一体感のある音じゃないですか。今ふうのうるさい音楽の、各楽器単品からもうゴージャスで馬力のあるプロダクションがあまり自分の耳に合わないと思い始めた時期でもあったし、ポコポコ、カサカサしているのが好きなんですよね。だから最初に自分でBandcampに上げた3曲入りEPのジャケットは、宮西計三のマンガから拝借していて。ザ・スターリンの『Trash』(1981, Political Records)とか『Stalinism』(1987, Independent Records)のアートワークを手がけたかたなんですが……意外とシーンが近いから怒られたりするのかな?」
――ザ・スターリンといえばじゃないですけど、童子にはアートワークも含めて丸尾末広的な美意識を感じます。
「ちょっと官能的で……そう、僕は肉弾とか、プロト・ハードコアみたいな日本のパンクもけっこう好きで。ちなみに肉弾のメンバーはのちに黒色エレジーを結成するので、自分の中ではポジパンのCatastrophe Balletのほうにも繋がるんですけど。当時の日本のパンクの人たちって、ゴシックホラーとかオカルトとか好きだったんですかね?」
――どうなんでしょう?童子のカセットのレーベル・インフォで、SHVさんがTHE EXECUTEに言及していましたが、THE EXECUTEのLemmyさんはDARKCELLというひとりブラックメタルをやっているんですよね。そこも童子と微妙に重なるし、もしかしたらTHE EXECUTEにはオカルト要素があったのかも。音からは全然わかりませんけど。
「90年代のハードコアとかパンクにはあまりオカルトを感じないけど、80年代はそういう雰囲気があるような。勝手な印象ですけど」
――ブラックメタル的な視点で見ると、童子はリフの刻みかたがCELTIC FROSTじゃなくてVENOMですよね。
「CELTIC FROSTになりたかったけどなれなかった(笑)」
――ジャパニーズ・ハードコアだと、ZOUOとか愚鈍とか、どちらかといえば西の危ない空気を感じました。ものすごく雑にいえば、ZOUOとか愚鈍がGAGをやるみたいな。
「まあ、そうですね。やっぱり80年代のジャパニーズ・ハードコアのウィアードな感じが愛おしくて。おっかなそうなあんちゃんが大真面目にあの音楽をやるというか、大真面目にかっこつけて出てくるのがあの音楽だからいい。ストリート・パンク的な飾らなさよりも、かっこつけているほうが好きです。僕は根がメタル小僧なので。ジャパコアでいうと、童子の曲を作ったときによく聴いていたのはACIDとかA.T. DETとか、もちろんG.I.S.M.もだし、あとはTHE COMESの『No Side』(1983, Dogma Records | City Rocker Records)、80年代じゃないけどACUTE……あ、ACUTEはオカルトというかホラーな感じ、ありますよね」
――童子は「Japanese Occultic Death Punk」を掲げていますが、これは誰が考えたんですか?
「童子です。“Death Punk”は単純に、レギュラー・チューニングでデスメタルをやるという、実験的な裏コンセプトがあって。デスメタルといっても、NIHILIST(pre-ENTOMBED)の影響が一番大きいですね。彼らの音楽は相当ロックンロールなところがあるので」
――童子の録音が元気だったらTHE HELLACOPTERSみたいになったかも。
「あり得るかもしれない。最近、本当にそっち側に行っちゃいそうです。さっきも言ったように、もともとメタルが好きなので」
――だからなのか、童子の音楽にはVENOMとかCELTIC FROSTよりもKing Diamondを感じました。
「おお。ちょうど今、めちゃめちゃKing Diamondを聴き返している時期です(笑)」

――2020年1月の「Discipline」(SHVがBUSHBASHで主催していたパーティ / コレクティヴ)だったかな。僕が初めてSOILED HATEのライヴを観たとき、感動してTatakauさんに話しかけて音楽遍歴的なことを聞いたら「最初はマキシマム ザ ホルモンのマキシマムザ亮君のフェイヴァリットを追っていた」みたいなことを言っていませんでしたっけ?
「中学2年生のときに買ったホルモンの『グレイテスト・ザ・ヒッツ 2011〜2011』(2011, VAP)というシングルに、分厚いブックレットが付いていて。その中で、亮君がいろんなことをやってガンギマリする謎の企画があったんです。例えばハイチュウを1本全部開けて、合体させて噛むとガンギマリするとか、ファミコンのカセットの側面のギザギザを歯でガリガリするとガンギマリするとか」
――YouTuberっぽいですね。
「そこに“前歯でブラストビートを刻め”みたいなことが書いてあったんですけど、ちゃんとブラストビートに注釈が付いていて、例としてNAPALM DEATHの『Scum』(1987, Earache)とSxOxBの『What's The Truth?』(1990, Selfish Records)が載っていたんですよ。当時、本当にホルモンが好きだった僕は、亮君が言うなら間違いないと、NAPALM DEATHのCDを買いに行くわけです。近所でCDを売っている店はBOOKOFFしかなくて、1枚だけ見つけたはいいけれど、1,500円くらいしたんですよね。僕は高校に入るまでお小遣いをもらっていなかったので、お年玉の残りでなんとか買って、家に帰って聴いたらホルモンと全然違う。メロディもないし、うるさいし、好きになれない。でも、1,500円も払っちゃったから“これを好きにならないと……”と思って」
――そのCDは『Scum』だったんですか?
「いや、90年代メタル路線からグラインドコアに戻ってきた一発目の、『Enemy Of The Music Business』(2000, Dream Catcher)です。一応グラインドだけど、正統的なNAPALM DEATHともまた違うラインだから、みんながあまり好きと言わない時期のNAPALM DEATHかも。BOOKOFFあるあるですよね。名盤は誰も売らないから、BOOKOFFには置いていないという」
――初めて自分のお金で買ったCDは、今言ったマキシマム ザ ホルモン?
「そうです。その次がMETALLICAの『St. Anger』(2003, Elektra)で、3枚目がNAPALM DEATHの『Enemy Of The Music Business』でした。僕が買った『Enemy Of The Music Business』は日本盤だったんですけど、ボーナストラックとして前年にリリースされたカヴァーEP『Leaders Not Followers』(1999, Dream Catcher)が収録されていて」
――日本盤あるあるだ。
「このカヴァーEPの1曲目が、イタリアのRAW POWERの“Politicians”なんですよ。ほかにもDEAD KENNEDYSの“Nazi Punks Fuck Off”とか、チリのPENTAGRAMの“Demonic Possession”とか、カナダのSLAUGHTERの“Incinerator”をカヴァーしていて。メロディもNAPALM DEATHのオリジナル曲よりわかりやすいから、当時はカヴァーEPのほうをよく聴いていたし、ここでカヴァーされていた曲が、今思うと童子にとって一番大事な気がします」
――そういえばTatakauさん、RAW POWER好きですよね。
「めっちゃ好きです。なんなら一番好きなハードコア・バンドかも。でも、NAPALM DEATH自体は全然ダメで、高校2年生か3年生になるまで気持ちよく聴けませんでした。そんな中学生当時の、グラインドよりもメタルとかロックのほうがしっくりくる感覚が、今になって蘇っている感じはします。例えばSOILED HATEはパワーヴァイオレンスで、リフを切り替える音楽だったから、繰り返すことで気持ちよくなるスルメ的なリフがあまり使えなかったんですよ。そこにフラストレーションを感じていたところもあって。“メタル小僧なのに、リフで勝負できない……”みたいな」
――リフでいうと、童子の「HUMAN vs WAR」のリフは2023年ベスト・リフ候補に挙げてもいいかもしれない。あれは変なスイッチが入りますね。
「たぶん、“HUMAN vs WAR”が最初にできた曲だと思います。NIHILISTのコンピレーション(『Nihilist (1987-1989)』2005, Threeman Recordings)を聴いていたときにリフの原型を思いついて、“これだ!これを使えば最強のパンクができる!”と、最終兵器の設計図を見つけたような気持ちになりましたね。“HUMAN vs WAR”ができてから、あとは成り行きというか、“HUMAN vs WAR”ありきでバランスを取りながらロウ・パンクに寄せていくような作りかたをしていて。1曲目の“Stupid Mammals”は“ドッタン、ドッタン”みたいな、恐竜が歩いているようなロウな感じを意識的に出そうとしました」

――「Stupid Mammals」のリフも耳に残ります。
「歌えるリフって、けっこう大事かなって。CROSSED OUTの“He-Man”(『Crossed Out』1991, Slap A Ham Records)という曲に、童謡の“こぎつねこんこん”みたいなリフがあるんです。“デデデデ、デデデデ、デデデデ、デデデー”っていう」
――あ、言われてみれば童謡っぽい。
「ごく初期のSOILED HATEはCROSSED OUTのカヴァーをやっていたので、当時スタジオに入っていたときに気付いて“こういうの、いいな”と思ったんですよね。で、そのSOILED HATEがNOISE ROOM(東京・西東京)で『demo』(2019)を録ったとき、僕はまだ大学生で、ちょうどNOISE ROOMの近くに大学の後輩が住んでいて。レコーディングを終えた勢いでヤマモト(ex-SOILED HATE, DEALE, Mortal Incarnation)と一緒に後輩の家に乗り込んで、“最強のパワーヴァイオレンスができた!”って、録ったばかりの音源をかけまくったんですよ。後日、その後輩と“スケボーの練習しようよ”みたいな感じで遊んでいたら、彼がSOILED HATEの“Fight Yourself with Your Fate”のリフを口笛で吹き始めて」
――歌えるリフってことですね。
「“ああ、やっぱりそういうことなんだ”って。いいリフは、つい口ずさんじゃう。そういう意識はメタルなんだと思います。突然ですけど、SANOAにもすごく影響を受けていて」
――それはロウ・パンクとかDビート的な影響?
「いや、アティテュード的な?SANOAって、曲の展開がミニマルだし、ライヴだとこれでもかっていうくらいベースでブレイクするじゃないですか。“ドゥルルルルル……”って。あれで“うおー!これだよこれ!”ってなって、変なスイッチが入るんですよ。予備動作というか前振りがあって、あるいはドラムロールや突撃ラッパを鳴らしてから突進するみたいな、キメの美学を感じます」
――SANOAの曲はフックも強めで、ある種キャッチーですよね。余談ですが、SANOAのカメザワさんもRoachLeg RecordsやToxic State Recordsのロウ・パンクが好きと言っていたので、バックボーン的には童子と重なる部分があるかも。
「だから、童子のカセットの2曲目“Satan Is Good, But You're Asshole”のベースが引っ張る感じとかは、DOOMとかを意識している部分もあるけど、直接的なオマージュとしてはSANOAです」
――一方で、「Dohji's Play」はモッシーですね。
「それはもう、狙っていました。最初は捨て曲というかモッシャーに媚びるつもりで、フロアでサイド・トゥ・サイドをやってもらいたいと思って作ったんですけど、そういうふうに捉えられてはいない気がする(笑)」
――(笑)。
「でも、曲が一本調子で終わるのは嫌なので、何かいい方法はないかと思ったとき……CELTIC FROSTの“Circle Of The Tyrants”(『To Mega Therion』1985, Noise)のリフってヤバいじゃないですか。ああいう感じでトランジションしたくなって、最後のほうにおまけを付けたら自分でも好きな曲になりました。手前味噌ですけど、童子の『Forced Climax Unending』は、これまで自分が携わった音源の中で一番好きかもしれないです。この感じは狙って出せないというか、もう1回同じようなものを作れといわれてもできる気がしない、“技術の自然”の境地に至ったんじゃないかなって」
――技術の自然
?
「自分の中でもまだまとまりきっていないんですが、自然が芸術的な技術のように見える場合の“自然美”に引っかけて、僕が勝手に“技術の自然”と呼んでいて。“技術の自然”の境地においては、芸術作品はその意匠の作為性、人為性を呑み込み、まるでただ自然にそこにあるかのように振る舞います。また、ひとつひとつの意匠もかたちや肌理のように、ある実体が備えていて当然のものとして立ち現れているように感じられるわけです」
――作品である以上、当然、人の手が加えられている。にもかかわらず、そうした技術が自然現象として観測できるみたいな。
「例を挙げると、ENDONの『MAMA』(2014, Daymare Recordings)、SUMACの“Image of Control”(『What One Becomes』2016, Thrill Jockey)、FRIGÖRAのセルフタイトルEP(1995, F.F.T. Label)、NEUROSISの『Through Silver in Blood』(1996, Relapse Records | Release Entertainment)、GODFLESHの『Streetcleaner』(1989, Earache)、CLOAKROOMの『Time Well』(2017, Relapse Records)、SPAZZの『La Revancha』(1997, Sound Pollution Records)、NAPALM DEATHの『Fear, Emptiness, Despair』(1994, Earache)、XMAL DEUTSCHLANDの『Tocsin』(1984, 4AD)、黒色エレジーの『Esoderic Mania』(1993, SSE Communications)、DARKTHRONEの『Under a Funeral Moon』(1993, Peaceville)、Mortal Incarnationの『Lunar Radiant Dawn』(2019, Dead Sky Recordings)、NEGATIVE SUNの『MENTICIDE』(2024)などを勝手にそのカテゴリーに入れていて、『Forced Climax Unending』はその境地に肉薄するものと捉えています」

――ところで、Dビートってプログラミングするの難しくないですか?
「けっこう、ズラしてズラしてみたいな。普通は使わないような、16分音符よりもっと細かいクォンタイズを、ちょっとズラして切り貼りして。ちょっとズレているから、切り貼りした先でまたちょっとズレるんです。それに合わせてギターを弾くと、わりといい雰囲気になりました。実は童子をやる前に、Not Niceという仙台のひとりパワーヴァイオレンス / ノイズグラインドを観て衝撃を受けたんですよ。ベース・ヴォーカル / ノイズ・マニピュレーターで、ドラムがプログラミングなんですけど、ブラストとかフィルがめちゃめちゃロウで。“これ打ち込みですよね?どうやってるんですか?”と聞いたら、MIDIキーボードで1音1音、全部指で打ち込んでいるっていうんです。両手の指で“ドカドカドカドカドカドカ……”って」
――いい話だ。
「“それでああなるの!?”と。ひとりパワーヴァイオレンスのギミック的なおもしろさを超えたアグレッションがあって、本当に感動したんですよ。童子を始めるにあたって、GAGともうひとつ決定的なきっかけがあったはずで、もしかしたらNot Niceかもしれない……あ!もちろんNot Niceも重要なんですけど、自分がロウ・パンクをやるうえで絶対に外せないバンドを忘れていました」
――そのバンドとは?
「デンバーのG.O.O.N.です。ギタリストのJohn MenchacaはCADAVER DOGでもギターを弾いているんですけど、SOILED HATEの初ライヴは、CADAVER DOGとの対バンだったんですよ」
――2019年11月に、CADAVER DOGとREGIONAL JUSTICE CENTERが一緒にジャパン・ツアーをやったときですね。
「CADAVER DOGと対バンしたあとにG.O.O.N.の存在を知ったことで、自分の中でロウ・パンクというジャンルが知覚されていった経緯があったような気がします。特に、彼らの『Natural Evil』(2019, Convulse Records)には、サウンドはもとより作曲思想的にも、CRISIS MANやGAG以上に大きな影響を受けていると思いますね」
――作曲思想的にも?
「ギタリストのJohnとTwitter(現:X)で交わした会話が、自分にとって極めて重要で。僕が“G.O.O.N.のヴォーカルはなぜ、花に覆われているのか?”と尋ねたら、彼から“自然は邪悪だからだ Because nature is evil”という答えが返ってきて、稲妻に打たれたような衝撃が走ったのを覚えています。当時も今も、その言葉の真意はまったくわからないんですが、それ以降、音楽および非音楽が“evil”であることについて、かなり考えるようになりました。童子はもちろん“evil”な音楽にしたいと思って取り組みましたし、そもそも音楽が“evil”であることに言及するというアティテュードの源泉は、G.O.O.N.にあると言っていいでしょう」
――さっきNot Niceの音がロウだという話になりましたが、童子の音も負けず劣らずロウだと思います。この音はどうやって作ったんですか?
「昔から、例えばSOILED HATEのデモを作るときとかも、打ち込みでもなるべくバンドが演奏しているように聞こえるようにしたいと思っていて。自分は楽器のプレイヤーじゃないというか、ギターもベースも一応弾けるけど、演奏技術は高くない。だからなのか、バンド自体を音を鳴らすひとつのデバイスとして捉えていて、それを丸ごとコントロールしたい欲求がずっとあるんです。もちろんバンドは人が集まってできているものであることは承知のうえで、トータルでコントロールするにはどうしたらいいか、バンドをやり始めた頃から研究はしていました。で、童子の音はどうしてこうなったのか。簡単にいうと、最後のマスタートラックにディストーションをかけたら、この音になったんです」
――簡単すぎない?
「僕は打ち込みでドラムの音を作るとき、エアドラムしながら“このフィルをやったら、次の1発目のシンバルはうまく叩けないだろうな”とか“ここのバスドラは弱くなりそうだな”みたいなことを想像して、ベロシティで音の強弱を調整するんですよ。そうやって、ちゃんと人が叩いているようなニュアンスを無理やり作って……」
――ドラムも叩けるんですか?
「いや、Dビートしか叩けないです」
――そっか(笑)。
「でも、人が叩いているように作っても、何かが足りないと感じて。そのとき、普通は絶対にしないことなんだけど、マスタートラックにギター用のディストーション・エフェクトをかけたんです。例えばGAIの曲って、すべての音が歪んでいるじゃないですか。彼らはマイブラ(MY BLOODY VALENTINE)より先にシューゲイザーをやったと思っているんですが、“そうだ、全部歪ませちゃえばいいじゃん。ポチッ!”みたいな。そしたらすべてのピースがハマったんです。そういう実験が好きですね、ずっと」
――「バンド自体を音を鳴らすひとつのデバイスとして捉えて」いるとのことでしたが、SHVさんも「自分の作った曲がバンドという装置を介して具現化されることにもっとも意義を感じる」と言っていました。
「考えかたとしては近いのかな?僕はもともと、バンドを一緒にやれる人が周りにいなくて。軽音部に入るのを禁止されていたんですよ」

――お小遣いをもらえなかったり、けっこう厳しい家庭だった?
「今となってはよくわからないですね。僕が高校生の頃は“バンドなんかやったら絶対に勉強しなくなるんだからやめなさい。せめて大学に入ってからにしなさい”って。だからエレキ楽器を買うのも禁止だったんですけど、“音楽はやりなさい”と言われていたんです。僕はずっとピアノを習っていて、中学も吹奏楽部だったので」
――吹奏楽部では、楽器は何を?
「パーカッションです。高校はオーケストラでコントラバスを弾いていたんですが、いまだにパーカッションの経験が手癖として残っているというか、やたらパーカッシヴにしたくなっちゃうんですよね。あと、ブラスバンドとかオーケストラのパーカッションって、何人もの人が打楽器を分担してビートを作っているので、基本的にひとりがドラムを叩くバンドより、魂の厚みみたいなものがあるんですよ。もっと言うと、バンドって、多くて6、7人くらいの人がひとつの曲にアクセスしているけど、オーケストラともなれば100人前後の人がひとつの曲にアクセスできる。だからみんながひとつの魂になっちゃう。『機動戦士Zガンダム』のカミーユが言った“俺の身体をみんなに貸すぞ!”みたいな……いや、『伝説巨神イデオン』のイデのほうが表現としては近いのかな?」
――いずれにせよ富野由悠季ですね。
「その気持ちよさがすごく好きで。たぶん、魂が合体する感覚は、単純に人が多ければ多いほど強くなる。だから僕は、バンドの気持ちよさは吹奏楽の気持ちよさには勝てないと思いながらバンドをやっているんですけど、バンドには別の楽しさ要因がプラスされているというか。ハードコアだったら、フロアのお客さんも魂の合体に参加できるから、人数的にはイーヴンかもなって」
――我々は合体に参加していたんだ。
「やっぱり、魂が合体した結果できたものが作品であってほしいんですよね。童子の音源は打ち込みなので、入っている魂はよくて自分の魂ひとつ分なんですけど、そこに嘘でも最低5人分の魂を乗せたい。そのためには、5人が演奏しているような空気感とか、5人で入って音を鳴らせる程度の部屋の広さを曲の中に入れ込まないといけないと思っていて。そういう気遣い……いや、気を遣う対象が存在しないから気遣いではないんですが、自己満足として、自分を喜ばせるために、どうやってたくさんの魂を集めるかを常に考えています」
――ひとりロウ・パンクなのにたくさんの魂を集めるって、無理筋な感じが最高ですね。
「たぶん、魂の厚みを含めて音楽を聴いているし、自分が好きな作品は、魂の厚みを感じられるから好きなんですよね。そういう意味で、ひとりブラックメタルとかアンビエントは魂の厚みを考えなくていいジャンルだから、そもそも童子をやるうえで参考にしていなくて。パンクとかデスメタルを含む、広義のロックとしてパッケージしたかったし、そういう音楽には最低でも3つ、できれば5つくらいの魂が入っていてほしい」
――おもしろい発想だなあ。
「例えばチャイを飲むと、シナモンとクローブとカルダモンの味はなんとなくわかるじゃないですか。ああいう感じで、ちゃんと生身のギタリストとベーシストとドラマーの、音じゃなくて魂がそこにあるみたいな」
――擬似魂としてのダミープラグを挿す感じ。
「そういうことです。童子はエヴァかもしれない。もっとブチ上がるのが、魂がいっぱい入っているのに、表現されたものがそれに見合っていない、ガラクタみたいな音楽ですね。だから、よくないAORとか大好きなんですよ。お金も時間もかけて、当代最高のスタジオ・ミュージシャンを集めて、演奏者だけじゃなくてエンジニアとかいろんな人がめっちゃがんばって、たくさんの魂を集結させているのに、“出てきたのがこれかあ……”っていう」
――いっぱいあったはずの魂、どこに消えちゃったんですかね。
「その失われた分量、欠損が、たぶん愛おしくなる。例えばパワーヴァイオレンスは、ストレートに失っているんですよ。必死で、命を削って演奏しているのに、音質がクソすぎてそれがあまり伝わってこないと、“あ、本当はもっとがんばってるんだろうな”ってイマジネーションが働くから、なおさらよい。山が好きで、山のデカさを伝えたくて、山のド真ん中で写真を撮ったら木しか写っていないみたいな。そこに収められなかったけどたしかに存在するはずの風景、山頂、エクスタシーに思いを馳せたい。そういう意味で、ロウ・パンクはパッケージとして優れていますね」

――ちょっと曲の話に戻して、「A Curse」はスキットというか詩の朗読ですよね。「愚かな郵便配達よ」という文言から始まりますが、「郵便配達」は、Tatakauさんにとって何か特別なモチーフだったりするんですか?
「郵便配達って、モダンな感じとアナクロな感じが絶妙に交差しているポイントだと思っていて」
――ジャック・ラカンの「《盗まれた手紙》についてのゼミナール」的なものではなくて?
「あ、たしかにそういうのも念頭にありつつ、勉強不足なのでもっと浅いですね。あるいは直接的な引用としては“何処へでも行ける切手”(筋肉少女帯『断罪!断罪!また断罪!!』1991, TOY'S FACTORY)か。あと、僕は寺山修司が書いた“人力飛行機の為の演説草案”(J・A・シーザーと悪魔の家 / 天井桟敷『国境巡礼歌』1973, Victor)の歌詞が本当に好きなんですよ。“鳥が翼で重量を支えていられるのは ある速度で空気中をすすむ時に まわりの空気が抵抗で揚力をおよぼし それが鳥のさびしさと釣り合うからだ”というやつなんですけど、黒色エレジーの人も好きらしくて」
――おおー。
「科学とメルヘンの融合じゃないけど、郵便ってすごく社会制度的な、システマティックなサービスなのに、そこで運ばれているのは人の気持ちというエモーショナルなものだったりする。そういう不釣り合いな感じがおもしろいなって。その“気持ち”を配達中に盗み見るというタブーを犯してしまったがために、彼は世界中を夜通し配達して回らなくちゃいけなくなってしまったという……いや、別に内容はなんでもいいんですけど、カセットのB面らしく、いい感じのクールダウンが欲しかったんです。曲を作るのも飽きてきたし」
――飽きたんだ(笑)。
「けっこうネタ切れ感もあったので、何かで尺を稼ぎたいなって。ちょうど去年、謎の作曲仕事を請け負ったんですよ。僕は能を習っているんですけど、能の先生から“美術館で能とダンスのコラボイベントをやるから、君は音楽を作ってよ”と頼まれて」
――そういえば作っていましたね。『組曲「飛天 Celestial Maiden」』でしたっけ。「こういうのも作れるんだ!?」と驚きました。
「ニューエイジというか、いかにも和風コンテンポラリー・ダンス的な、喜多郎みたいな曲を作ったんです。そのノウハウはまったく生きていないんですけど、これをやったおかげでシンセっぽい音楽を作りたくなって、童子でやっちゃいました」
――能を習っているというのは、舞を?
「舞と謡(うたい)の両方です。そんなバリバリやっているわけじゃなくて、月1回のお稽古くらいの感じなんですが、けっこうおもしろくて。能の動きって、いらん力の入れかたをするんですよ。僕の先生は“舞台の上に空気のゼリーがみっちり詰まっていると思って動きなさい”とよく言うんですけど」
――空気の抵抗を意識するということ?
「そうです。すべての所作に、空気の重みがかかる。かつ、能は農耕民族の儀礼的な芸能だから大地からの引っ張り力を感じつつ、でも頭は天井から吊るされているように。四方八方から力を受けたり、それに抗ったりしながら立つ、あるいは動く。僕が一番大事だと思うのは、その動きが、いろんな力のベクトルが相互に関係した結果として、ただ動いているように見えるみたいなことで。見かけ上、そういう力の磁場が存在しているように振る舞うことで、あまり現実的でない空間を作っているのかなって。能師の動きって、人間っぽくないじゃないですか」
――郵便の話と同じですね。バレエやダンスを生体力学的に研究する学問があるじゃないですか。あれも、確立されたシステムの上にエモーショナルな動きを乗せていくみたいな話だと思うので。
「大学でパフォーミングアーツの授業があって、その中で暗黒舞踏が扱われたときに土方巽の話とかを聞いて、暗黒舞踏と能は似ていると思ったんですよ。結果として出てくる動きは全然違うけど、どちらも演じる体としてある体じゃなくて、演じる対象そのものになってしまう体、なんにでもなれる体で動いているというか。体を非人格化して、力の動きを伝えるためのメディアにしちゃう感じが、すごく似ている。これは、ある種の“技術の自然”の境地と考えていいかもしれません。あるいは“技術の自然”のための技術……すみません、検討不足です」
――言わんとしていることはわかるような気がします。作為があるのに自然の法則に従っているように見えるということですよね。
「要は、ただぼんやり立っているのと、今にもプルプル震えそうな感じで、なんとかそこにとどまっているように立っているのとでは、立ちかたとしてまったく違うじゃないですか。それに気付いてから、SOILED HATEのライヴでも、力の動きを見せるためのステージングを意識していましたね。観ている人に伝わっているかはわかりませんけど……なんの話でしたっけ?」
――「A Curse」の話かな。曲を作るのに飽きたって。
「そうだ。でも朗読が入っているパンクって、意外とないですね。CRISIS MANみたいに、アジテーションとかはけっこうあるかもしれないけど。LOS CRUDOSの“Tiempos De Miseria”(1993)も内容的にはアジだし。ニュアンスとしては、例えばPOISON RUÏNのアルバムって、ダークウェイヴみたいな曲が挟まったりするじゃないですか。ああいう感じでひと息ついてもらいたい。あとはもう、寺山演劇とか、映画『帝都物語』(1988, 実相寺昭雄監督)っぽい雰囲気を出したくて」
――最後の曲「MASAKADO」も『帝都物語』由来ですよね。「MASAKADO」って、平将門以外にいるのかという話で。
「でも、SHVさんが童子のインフォに“大正浪漫的”って書いてくれましたけど、曲として大正浪漫を感じさせるものがあるとしたら、“A Curse”だけだと思うんですよ(笑)」
――丸尾末広からの高畠華宵で大正浪漫とか?
「意図してはいませんでしたが、結果的に……?あ、そうだ、“A Curse”に関してもうひとつだけ言うと、ちょうどCatastrophe Balletも動き始めるタイミングだったので、Catastrophe Balletの今後の録音に語りとかを入れられたらいいかなって。お試し感覚でやってみたら、いい感じになりました」
――Catastrophe Balletといえば、今日はここまで黒色エレジーとXMAL DEUTSCHLAND以外にポジパン、ゴスへの言及がありませんね。そっち方面もかなり掘っているはずですが。
「そうなんですけど、僕はポジパンが好きすぎて。あえて距離を取らないと童子もそっちに持っていかれて、たぶんDEATHCHARGEとかZYGOTEみたいになっちゃうんですよ。ただ、アナーコな感じのゴスはめちゃめちゃ好きで、最近だとZENOCIDEのアルバム(『Ashes Asylum』2024, Daymare Recordings)がゴス的なラインでも素晴らしすぎました。今、自分で言って思い出しましたけど、ZENOCIDEにはかなり影響を受けています。気持ち的に」
――童子にゴス要素があるとすれば、さっきも言ったKing Diamond的な?
「言っちゃえば、ゴスのふたつの側面が童子とCatastrophe Balletにそれぞれ表れているのかも。童子はアングラ / オカルト的で、Catastrophe Balletは耽美的みたいな。CELTIC FROSTのMartin Eric AinもCHRISTIAN DEATHが大好きで、ひらひらのシャツを着たりしていましたし(笑)」

――童子の歌詞はジャパコアらしく聞き取れませんが、どんなことを歌っているんですか?
「歌詞は、考えるのが面倒くさくて、曲のタイトルと雰囲気を生成AIに入力して……」
――今日イチいい話かもしれない(笑)。
「早くリリースしたすぎて、“歌詞まで書いてらんねえよ”という気持ちに。どうせ“うえー!”って言っているだけだし、歌詞はなくていいかなとも思ったんですけど、体裁上必要ですよね。ちょうどChatGPTが流行り始めた時期だったので、“童子というジャパニーズ・ハードコア・パンクのバンドの歌詞を考えてください”って」
――日清紡と一緒だ。
「“HUMAN vs WAR”だったら、タイトルと共に“これは人間と戦争について風刺的に描いた曲です”みたいな説明を入力すると、ちゃんと歌詞を書いてくれるんです。当然、節回しとかは合っていないので、よさそうなフレーズをピックアップして、ちょっと手を加えているんですけど」
――「HUMAN vs WAR」というのもすごいタイトルですね。
「ちょうど、ロシアがウクライナに侵攻したときに作ったんですよね」
――たぶん「WAR」も、システムとして捉えているのでは?
「たしかにそうかもしれません。“WAR”の前ではあらゆる暴力的な表現が意味をなさなくなってしまうというか。あまりいい言いかたじゃないんですが、戦争にはエンタテインメント的な側面もあって。特にそれが自分の生活に直接関わってこない場合、エンタメとして強すぎる。ジョルジュ・バタイユが言うところの、蕩尽の最悪のかたちが戦争であるみたいな話で、音楽を含む芸術は戦争を回避するための手段でしかないのかもしれない。だから、ウクライナ侵攻が始まってからSOILED HATEというかパワーヴァイオレンスをやるのがキツかったところが正直ありました。ステージで凶暴なパフォーマンスをしているけれど、それよりはるかに凶暴なことが現在進行形で行われていると思うと、“こんなことやってる場合じゃないのに”みたいな。そういう意味では、“HUMAN vs WAR”は自分を落ち着かせるために作った曲でもあります」
――「A Curse」で寺山修司に言及していましたが、それ以外の曲の歌詞では寺山修司の影響は……。
「まったくないです」
――SOILED HATEが解散した直後くらいにTatakauさんとMOONSTEP(東京・中野)かどこかで会ったとき、デマとしての解散理由が「寺山修司ではなかったため」という話になったじゃないですか。だから童子は寺山修司なのかなと思って。
「童子はどちらかといえば寺山修司ですね。“寺山修司である / どちらかといえば寺山修司である / 寺山修司ではない”の三択なら。AIに書いてもらいましたけど、厭世観のある歌詞ではあるんじゃないかな。けっこうAIはおもしろくて、バンド名も最初はAIに決めてもらおうかなと思ったんです。でも、あまりにもセンスがなさすぎて。例えば“侍ロック”とか」
――ひどい(笑)。
「“80年代に活動していた、架空の日本のハードコア・パンク・バンドの名前を教えてください”って聞いたら“人間爆弾団”とか。なぜか殺害塩化ビニール所属っぽいバンド名を付けられてしまう(笑)。でも、最終的に“童子”に落ち着いたのは、けっこうよかったかな」
――いいバンド名です。「子供」という意味でもなんか怖いし。
「“童”って、意味するところに対して漢字として重すぎる。あと、酒呑童子とか茨木童子とか、“○○童子”になると“鬼”を意味するじゃないですか」
――『帝都物語』にも、加藤保憲の使い魔として護法童子が出てきましたね。H・R・ギーガーがデザインした護法童子が。
「そうそうそう」
――森田は?
「もちろん好きです」
――うろつきは?
「好きです。ANISAKISのAndroさんに“『超神伝説うろつき童子』が元ネタですか?”と聞かれて、まあ、そっちを連想するよなと」
――酒呑、森田、うろつきが世界三大童子じゃないですかね。
「あと、ラッパーの童子-T。遊びでChatGPTに“日本のハードコア・パンク・バンド、童子について教えてください”と入れたら、童子-Tをすごい拾ってきて。“童子のメンバーを紹介してください”と入れても“童子-T、童子-F、童子-C……”みたいな感じで、“RAMONESじゃん!”って思いました」
――あるいは藤子不二雄。「童子」というバンド名をひらめいたきっかけとかはあるんですか?
「きっかけとしては、珠鬼 TAMAKIですね。珠鬼のバンド名を決めるとき、自分の中で案はあったんですが、ヴォーカルのセーラーかんな子さん(XIAN)のセンスがすごくいいので、特に何も言わなかったんです。ただ、“鬼”を付けるなら“○○童子”のほうがいいんじゃないかと、ちょっと思ったんですよ。もちろん珠鬼は珠鬼で、音と名前がマッチした最高のバンド名だから異論はなくて。“○○童子”はアイデアとして寝かせていたんですけど、“○○童子”だと、それはそれで高円寺のよくないパンク・バンドみたいな……」
――高円寺に対する偏見だ(笑)。
「なんか、サブカルすぎる感じがあるかなと思って。あと、“○○童子”だと鬼のニュアンスが強く出ちゃうから、いっそ“童子”だけにすれば“子供”という意味もあるし、やっぱり“童”の字がすごすぎる。横棒がいっぱいあって、怖い。たぶんこれが集められた魂なんじゃないですかね」
――宅録ひとりロウ・パンクである童子に、生身のプレイヤーを迎えてバンド化したのが「童子 and The Exorcists」で、2023年12月にCORNER BOOKS(埼玉・戸田公園)で初ライヴを行いましたね。
「もともと宅録とバンドで名義を分けたかったんですよ。童子のコンセプトは架空の80年代ジャパニーズ・ハードコアだから、嘘のバンドだから、“童子”のまま人前に出るわけにはいかない。何かワンクッション置く必要があると思ったとき、僕はHANK WOOD AND THE HAMMERHEADSが好きだし、SIOUXSIE AND THE BANSHEESも好きだし、“人名 and The 〇〇s”への憧れがすごく強くて。それもバンドがシステム化されているのがわかりやすいからなのかもしれませんけど、その憧れを叶えるのに都合のいい名義として、“童子 and The Exorcists”を採用しました」
――童子は霊的な存在で、O.Tatakauは童子を降ろすための依代にすぎないみたいな話もしていましたよね。
「そうです。初ライヴの前に、X
――童子 and The Exorcists(笑)。
「本当にくだらないんですけど、そういう設定を考えるのって楽しいですね」
――エクソシストって、悪霊とかを祓う人ですよね。せっかく童子が降りてきたのに、バンド・メンバーによって祓われかねないという構図になりません?
「いや、童子がこの世の……童子は何者なんですか?」
――(笑)。
「どちらかというと、童子は外に向けてアプローチしていると思うんですよ。東京が大混乱で、その混乱を取り除くために式神部隊を組織したのであって。だからThe Exorcistsは、たぶん童子を祓うんじゃなくて、童子に使役されて、何かよくないものを祓う感じじゃないかな。童子は一応、世の平穏を願っているので」
――『帝都物語』は、式神使いでもある加藤が平将門の怨霊を降ろして東京を破壊しようとするので、それを転倒させた感じだと考えればいいんですかね。
「そう、たぶんそれで合っています。『帝都物語』最高ですよね。加藤を演じる嶋田久作が好きすぎて、僕も早く嶋田久作になりたい」
――『帝都物語』の続編『帝都大戦』(1989, 一瀬隆重監督)で、少女の首から下が虫になっているシーンがあるじゃないですか。子供の頃に観てめちゃくちゃ怖かったのですが、あの特殊メイクはスクリーミング・マッド・ジョージが手がけているんですよね。だから『帝都大戦』はTHE MAD、すなわちロウ・パンク。
「そこで繋がるんだ(笑)」
――今ふと思ったのですが、童子はジャパニーズ・ホラー的なものから何か着想を得ていたりは?
「直接的にはないかもしれないです。“ホラー”というよりは“怪奇”みたいな……例えば土方巽が出演している『江戸川乱歩全集 恐怖奇形人間』(1969, 石井輝男監督)とか。予告編で、筆で書き殴ったような題字がバンバン出てくるような作品が好きですね。テレビ番組だと『ウルトラQ』が好きで、メインテーマは童子の曲を作っているときにめちゃめちゃ聴いていました。劇場版(『ウルトラQ ザ・ムービー 星の伝説』1990)の監督は、『帝都物語』の実相寺昭雄ですよね。もちろん実相寺作品も好きだし、あとは、もう童子というよりは僕個人としてですけど、『鉄男』(1989, 塚本晋也監督)は外せないかな」
――SOILED HATEが、KLONNSとのスプリット『DIFFERENT SENSES』(2021, DISCIPLINE PRODUCTION)に入っている「Change?」で、『鉄男』劇中の、六平直政が演じる医者のセリフをサンプリングしていましたね。
「やっぱり『鉄男』の根底に流れている、“俺たちの愛情で世界中を燃え上がらせてやるぜ!”みたいな熱量は、すごく自分の気持ちにフィットします。愛で世界を滅ぼしたい。TIVEの新曲“あい・あい・あい”もめちゃめちゃいいし、愛は向き合っていきたいテーマですね。たぶん、童子はそんなに向き合っていないから……」
――いや、呪い(「A Curse」)は愛の裏返しですよ。
「たしかに、愛は呪いですね。大学までバンドをやれなかったのも、親の愛という呪いをかけられてしまったから……なんの話でしたっけ?」
――バンドとしての「童子 and The Exorcists」から、映画の話に脱線しました。
「作品のテーマとか内容はまったく童子と関係ないんですが、レオス・カラックスの『汚れた血』(1986)もすごく好きで。劇中で、David Bowieの“Modern Love”が流れるシーンがあるじゃないですか……これも愛ですね。あのシーンが、Dビートのドライヴ感をよく表しているなって。いや、もちろん曲はDビートじゃないんですけど、“ドッタ、ドッタ、ドッタ、ドッタ”に合わせて主人公が夜のストリートを駆けていく映像に、Dビートにあるべき推進力を感じるというか、あれを童子でやりたかったというのはあります」

――The Exorcistsのメンバーは、どうやって決まったんですか?
「あまり深く考えていなくて、単にやってくれそうな人に声をかけた感じです。まずベースは、カセットのジャケットを描いてくれたアッティラ太郎くんなんですけど、彼とは大学のサークルがちょっと被っていたり、もとから交流はあって。今はGensenkanというスクラムズのバンドでベースを弾いていて、GULCHとかGAGも好きだと言っていたので、そういう音楽の楽しさを理解していると思って声をかけました。ドラムのシラサキさんは、大学のサークルで一緒にブルータル・デスメタルをやっていた仲で。ひたすらVOMIT REMNANTSとかDEVOURMENTとかWORMROTのコピバンをしていましたね。自分の知る中で、最高のブラストビートを叩く人間のひとりです」
――童子にはブラストビートの曲、ないですけど。
「童子ではブラストビートは封印しているんですけど、例外的にカヴァーならOKにしていて。だから、ライヴではDEATHの“Back From The Dead”をカヴァーして、思う存分叩いてもらっています」
――シラサキさんは、Mortal Incarnationの元ドラマーなんでしたっけ?
「結成当初のモータルのドラムですね。モータルって、最初は僕も在籍していたんですよ。ヴォーカルが僕で、ギターがMiuraさん(KLONNS)とワダさん、ベースがヤマモト、ドラムがシラサキさんっていうメンバーで始まったんですけど、ヤマモトに“あいつ(O.Tatakau)のヴォーカルはデスメタルじゃないっすよ”と言われ……」
――そっか……。
「別に揉めてはいないんですけど、脱退しました。でも、Miuraさんというヤバいコンポーザーが身近にいたのは自分にとって大きくて。さっき“技術の自然”の例として挙げたモータルの『Lunar Radiant Dawn』って、宅録なんですよ。それを聴いて“これに食い付いていくぞ。俺もひとりで何かをなさねば……”みたいな謎のライバル意識が芽生えてしまい。結果として、勝負するフィールドが全然違う感じになっちゃいましたけど」
――The Exorcistsのメンバーに話を戻すと、ギターはmoreruのコジマアツヲさんですね。
「アツヲくんと知り合ったのは、moreruのライヴを観に行ったときだったかな?Catastrophe Balletのギター / 作曲のTakumiがアツヲくんと仲がよくて、彼の橋渡しもあってアツヲくんと普通に喋るようになり、そのまま誘ったらOKしてくれました。アツヲくんも“ロック”への志向が意外と強くて、いろいろ汲んでくれるので楽しいです」
――僕は、初ライヴは行けなかったのですが、今年の3月と11月にいずれもBUSHBASHで行われたライヴは観ていて。ライヴこそ変なスイッチが入りますね。
「本当ですか?なんか、自分たちのパフォーマンスを気にする余裕がなくて。でも、初ライヴのときにGolpe Mortalさんがめちゃめちゃモッシュしていたのはよく覚えています。特に“Homicidal Radio Broadcast”とかは、自分の嗜好とモッシャーへの媚びをいいバランスで両立できたという、手応えを感じました」
――ライヴでは、ボンデージのマスクとハーネスを装着しているヴィジュアルからすでにヤバかったのですが、ステージ衣装には何かコンセプチュアルな意味があるんですか?
「何もないです。もちろん猥雑な、官能的なニュアンスを出すためのボンデージではあるんですが、単にエンタメ感が欲しくて。メタルの人って、ちゃんとステージ衣装を着るじゃないですか。パンクにはあまり衣装という概念はないけど、メタル小僧としては、ステージ上でしかしない格好をすることは、自分で自分の変なスイッチを入れるためにも大事で。SOILED HATEでもたまにメイクをしていて、それだけで気持ち的に全然違うんですよ。ただ、童子の場合はすごく動きづらくて……」
――あのマスクはめちゃくちゃ歌いにくいと言っていましたね。
「そう、口を開かせないような作りになっていて。だから毎回、“やめりゃよかったな。どうしてこんなことを始めてしまったんだ?”という気持ちになるんですよね」
――童子のヴォーカル・スタイルって、当然かもしれませんが、SOILED HATEともCatastrophe Balletとも違いますね。
「ハードコア・パンクのヴォーカルは、声に色合いがあるほうが絶対いいと思っていて。色合いというのは、地声がわかる感じといえばいいのかな。低いうなり声みたいな声だと、よほど特徴がないと似たり寄ったりになっちゃうじゃないですか。そこがもったいないというか、ヴォーカルは魂を乗せられるポイントなのに、うまく乗せられていないように感じちゃうんです。それとやっぱり、メタルっぽい声?」
――童子の声、メタルっぽいですか?
「言いかたが難しいんですけど、DISCHARGEの『Massacre Divine』(1991, Clay Records)のヴォーカルとか、素っ頓狂で意味がわからない感じが好きなんですよ。DISCHARGEの、『Grave New World』(1986, Clay Records)をリリースしたあとくらいのインタヴューを読むと、“俺たちは今、技術も追いついてきて、ようやくやりたいことをやれるようになった”みたいなことが書いてあって。“それで出てきたのがこれかい!”っていう。あと、VOÏVODとか……」
――VOÏVOD!
「去年、KLONNSの人たちとの間でVOÏVODがブームになった時期があったんです。その頃ずっとVOÏVODを聴いていたら、力が入っているんだかいないんだかわからない声が本当によくて、ああいう違和感が大事だなと。例えばデスヴォイスって、技術として確立されているから、ブルータルな音にデスヴォイスが乗っていても“ああ、デスメタルだな”って聞き流しちゃうと思うんです。逆に、むしろ普通の声に近い声が乗っていたほうが耳を引くんじゃないか。パワーヴァイオレンスをやっていたときに思ったんですけど、INFESTの何がいいかって、ただおっさんが怒っているだけみたいなところがいいんですよ」
――はいはい(笑)。
「音楽然としていない声というか。そういう普通の声っぽい、かつちょっと変な声で歌いつつ、“うっ!”を大事にしています。HANK WOOD AND THE HAMMERHEADSも“うっ!”を多用するじゃないですか。あれってロックの魂なんじゃないかな」
――たしかに「うっ!」があるとないとでは……。
「全然違いますよね。NIHILISTも“うっ!”はよく言うし、クラストとかの、“うっ!”とは言い難い、“イヨッ!”みたいなやつも、すごくいい。これもキメの美学ですよね。だから、童子の音源でもしつこいくらいに“うっ!”を入れてやろうと思って。“Satan Is Good, But You're Asshole”なんかは、入れられそうなところは全部入れているはずです」
――カセットのリリースから1年が経とうとしていますが、新規レコーディングの予定とかはないんですか?
「一応、“童子 and The Exorcists”名義で録ろうかという話をちょっとしています」
――本物の魂が入った音源だ。
「そう、偽の魂じゃない。今、また自分ひとりで作るとメタルに接近しすぎて、G.I.S.M.の2ndアルバム(『Militaly Affairs Neurotic』1987, Beast Arts)みたいになっちゃうかもしれないので(笑)」
 ■ 2023年12月20日(水)発売
■ 2023年12月20日(水)発売
童子
『Forced Climax Unending』
DISCIPLINE PRODUCTION DCP-008
https://disciplineproduction.bandcamp.com/album/forced-climax-unending
[収録曲]
01. Stupid Mammals
02. Satan Is Good, But You're Asshole
03. Homicidal Radio Broadcast
04. Dohji's Play
05. HUMAN vs WAR
06. A Curse
07. MASAKAD