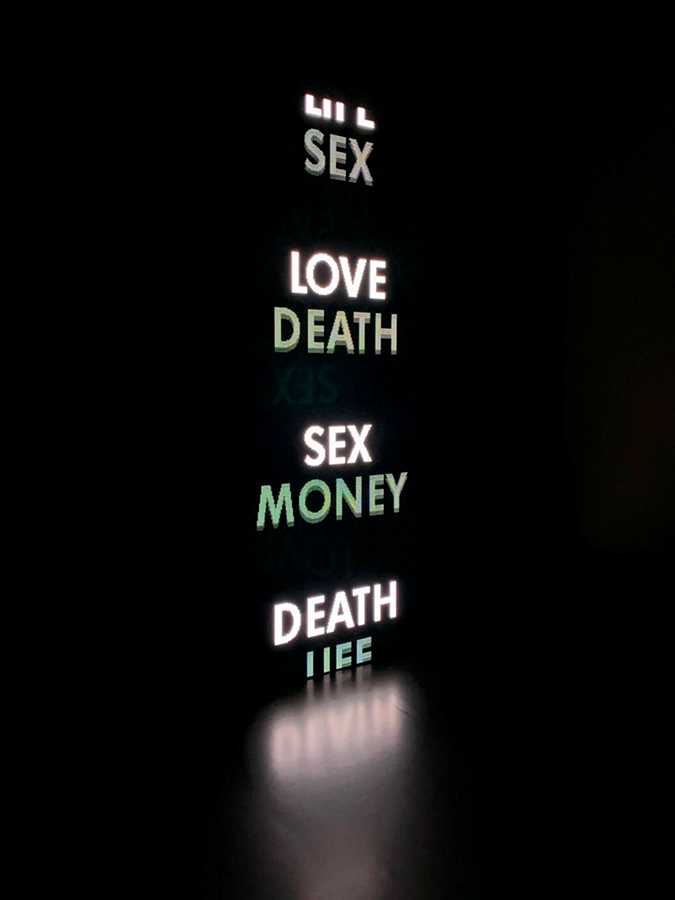文・撮影 | 梶谷いこ
沖縄には一度だけ行ったことがある。大学に入学して最初の夏休みのことだ。入ったばかりのサークルの夏の合宿先が、なぜか毎年沖縄と決まっていた。“合宿”と言ったって、何か大きな目的があって行くわけではない。ほとんど遊びのようなものだった。大学生の夏休みは8、9月のだいたい2ヶ月間ある。しかし超ハイシーズンにあたる8月の沖縄旅行など、高くてとても手が出なかった。必然的に日程は9月に決まった。旅費は、夏休みに地元の百貨店の屋上ビアガーデンでアルバイトをして貯めたお金を充てた。「ほとんど遊びの“合宿”なんておかしな話だ」。そういって両親は半ば呆れていた。
実際の合宿は“ほとんど遊び”というより“全くの遊び”だった。海で泳ぎ、琉球ガラスを吹き、毎晩のように泡盛を飲んだ。吸うタイプの黒くて大きなタピオカを初めて知ったのもこのときだった。今から15年以上前の話だ。ともかく、昨日と今日と明日と、その境目もわからないほど毎日毎夜はしゃぎ通した。ごくありふれた、いかにも学生の沖縄旅行という感じだった。しかしこれは“合宿”のほんの一部分に過ぎなかった。
ついに明日の飛行機に乗って京都に帰るぞ、というときになって、大きな台風がこちらに近づいていることをテレビのニュースで知った。飛行機が飛ばないかもしれない。「まさか」と笑っていたら案の定、次の日のフライトは全便キャンセルになった。欠航になった飛行機がいつ飛ぶのか、それもわからなかった。欠航の知らせを受け、私たちは空港に立ち尽くすより他なかった。お土産をたくさん持って、浮かれた格好で。この旅行に台風保険は付いていなかった。すぐに自力で今夜の宿泊先を探す必要があった。ガイドブックの上のほうに載っているホテルは、当然のように全滅。巻末のリストに載っている宿泊先に片っ端から電話をかけても、「満室です」と断られ続けた。もう空港で野宿するしかないかもしれない。そう思った矢先、ひとつ上の先輩が「大部屋なら泊まれるらしい」と、繁華街にある格安宿の予約をなんとか取り付けてくれた。
空港で野宿は免れた。ただ、そこから宿に向かうのも一苦労だった。窓の外は既に暴風雨が吹き荒れ、「ゆいレール」は運休していた。空港出口には既にタクシーを待つ長い行列ができていた。こんな日に営業しているタクシーは少ない。待ちに待ってやっと空港を出た頃には、那覇の街はもう真っ暗闇になっていた。路地の暗がりに、自販機の「さんぴん茶」の文字だけが赤と黄色に光って、心細かった。
やっとたどり着いたこの宿というのもまた曲者だった。中に一歩足を踏み入れると甘く煙たい香りが強く匂い、漂うような足取りの男が私たちの目の前を横切った。何かの匂いをごまかしているとしか思えなかった。やっとの思いで取れた“大部屋”は、部屋というよりロビーだった。ロビーの真ん中に二段ベッドがいくつか置かれ、その向こうに置かれたソファでは、先程の男がテレビをぼんやり見ていた。この宿には個室もあったが、そちらはもう予約でいっぱいらしかった。
「とりあえずシャワー行ってくるわ」。荷物を置き、誰がどのベッドで眠るかを決めたあと、先輩がシャワーを浴びに行った。空港泊になっていたことを思えば、シャワーがあるだけありがたかった。しかしその十数分後、彼は困惑とも興奮ともつかぬものを顔に浮かべて帰ってきた。「とんでもないシャワーや。がんばれ」。私が行ってみると、シャワーは屋上階にあった。矢印の先にあるドアをおそるおそる開けてみた。外だった。しかも暴風雨がますます強く吹き荒れていた。まさか。激しく降る雨の向こうに目を凝らしてみると、その数メートル先にシャワーボックスらしき縦長の箱がポツンとあった。あれか……。私は怯んだが、意を決してその場で着ているものをすべて脱ぎ、全裸で外へ飛び出した。一瞬で全身が雨に包まれた。もう何もかもどうでもよくなっていた。
走ってシャワーボックスにたどり着いたものの、今度はドアが閉まらない。ドアノブが壊れていた。こんな嵐の夜で、幸か不幸か人の目の心配は全くなかったが、とにかく雨が吹き込んでくる。私は片手でドアノブを抑えながらシャワーを浴びなければならなかった。チョロチョロと温水が流れるだけのお粗末なシャワーを、一滴でも無駄にすまいと必死だった。そして結局、また雨でずぶ濡れになって屋内に戻った。その晩はリュックをお腹にしっかり抱きかかえて眠った。
次の日になってもまだ飛行機が飛ぶ予定は立っていなかった。しかしフライトの目処がつき次第すぐにでも京都に帰りたかった私たちは、ひとまず空港に逗留することにした。先輩たちはそれぞれアルバイト先に電話をかけ、店長に頭を下げていた。他の人がそうしているように、私たちは通路の一角を陣取って、地面にしゃがみこんで時間を潰すことに決めた。食べるものは空港内のコンビニで調達した。しかし品出しのタイミングで人が殺到するので、それを逃すとろくなものは残っていない。それ以前に、手持ちの現金ももう残り少なくなっていた。クレジットカードは今ほど使えるものではなかった。待てど暮らせど飛行機が飛ぶ様子はなく、結局この日は空港で夜を明かすことになってしまった。夜11時頃のことだ。空港の職員が段ボールを満載したカートを押してやってきて、これにも人が殺到した。別の職員は、一人一人に「一般財団法人 沖縄観光コンベンションビューロー」と印刷された水色の薄いタオルを配ってまわった。段ボールと薄いタオルですらありがたく、今や私たちは見事な“被災者”だった。その晩は段ボールの布団で寝た。
フライトの予定が立ったのは、その次の日の午後、全便欠航の知らせから実に50時間以上経ったときだった。手続きを済ませ、やっと安堵のため息をついた私は、空港内のA & Wでひとり食事をとった。コンビニがどれだけ空っぽでも、A & Wだけはすべてのメニューが揃っていた。ただ、それまでは手持ちの残金が心配で、入るのを控えていたのだった。
これで最後だ。私は食べたいものを食べ、ついでにオリジナルのマグカップも買った。私たちを乗せた飛行機はようやく沖縄を発った。ところがその頃、沖縄を離れた台風はちょうど大阪上空にいた。私たちは台風を追いかけるかたちで大阪国際空港へと向かうことになってしまった。「当機はこれから着陸態勢に入ります」。機長からアナウンスがあったあと少しして、機体が大きく揺れ、照明はすべて消えた。乗客たちから悲鳴が上がった。落ち着いてください、という旨のキャビンアテンダントのアナウンスがあったが、舌がもつれてうまく言えないようだった。また大きく揺れた。機体はヒューンと急降下し、無重力になったと思った瞬間、滑走路脇に書かれた「OSAKA ITAMI」の文字が窓の真横に迫っていた。もうだめだ、ぶつかる。しかし直後に機体は急上昇。事なきを得た。その後飛行機は、何度も何度も上下を繰り返し、どうにか着陸を試みている様子だった。もう悲鳴を上げる者はいなかった。その代わり、嘔吐をこらえる呻き声があちこちから聞こえた。薄暗がりの中、めいめいがこの飛行の無事を祈り、自らの三半規管と闘っていた。
「当機は羽田空港へ向かいます」。祈りと闘いは、思わぬかたちで終わりを迎えた。台風はまだ関東方面へは進んでおらず、羽田空港には難なく着陸することができた。できれば始めからそうしてほしかった、と思った。降機後に航空会社から万札が1枚入った封筒が配られ、私たちはそれを足代にして帰路についた。那覇、伊丹、羽田、品川、そして京都へと移動した長い1日が終わった。家に着いて荷を解くと、リュックからマグカップがこぼれ出てきた。空港のA & Wで買ったものだった。あんなに揺れた機内でも、割れても欠けてもいなかった。
親元を離れてからしばらく経ち、水屋にもずいぶん食器が増えたが、このマグカップほど鮮烈な思い出を共にしたものはないと思う。

Instagram | Twitter | Official Site
1985年鳥取県米子市生まれ、京都市在住。文字組みへの興味が高じて、会社勤めの傍ら2015年頃より文筆活動を開始。2020年、誠光社より『恥ずかしい料理』(写真: 平野 愛)を刊行。雑誌『群像』(講談社)、『Meets Regional』(京阪神エルマガジン社)等にエッセイを寄稿。誠光社のオフィシャル・サイト「編集室」にて「和田夏十の言葉」を連載中。