カジュアルな実験性
バンド、スーパーノアでの活動と併行してソロでの音源制作を2011年から続けてきた井戸。出身地である京都のバンドやミュージシャンたちとの交流を続けつつ、現在は東京に拠点を持つ。2年半ぶりとなるこの新作では、非常に興味深いアプローチをとっている。それは宅録ともバンドサウンドとも違う、さまようような音像の中で、歌は夢とうつつ(現実)を行き来するような作りかた。もしかしたら、これは彼だけが見つけ出した発明かもしれない。
そして同作の発表後、井戸は早くもアルバムとはまたアプローチの異なるシングル2作品『OurS』『透過光』を立て続けにリリースしている。まだまだ変化を続けるミュージシャンとしての井戸健人ができてゆくまでの道のりも含めて、このアルバムへたどり着くまでをロング・インタビューで聞いた。
取材・文 | 松永良平 | 2025年2月
撮影 | 池田若菜
撮影協力 | ALDO
――井戸さんは1984年生まれだそうですね。世代としてはceroのメンバーたちと同じくらい。音楽体験の始まりは?
「CHAGE & ASKAかなあ。“太陽と埃の中で”(1990)のサビがいちばん最初の記憶のような気がします。自分で買った最初のCDは、Mr.Childrenのアルバム『深海』(1996)かな。まだ小学生だったと思いますね」
――楽器を始めたのはいつ頃?
「ギターは中学生になってからですね。学校で音楽会のような催しがあって、そこでTHE BEATLESの曲でギターを担当することになり、練習を始めました。そのとき初めて触って、コードとかも弾きました。なんでギターやったんかな?なんとなく興味があって、やりたいと思っていたんだと思います。そのときの体験で、曲に対するとらえかたが変わった気がします。それまではざっくり全体でしかとらえてなかったのが、ドラムやベースがあってギターがあるという構造とか、ジャーンって鳴っているギターは音がコードで積み重なってたんやとか、細部の積み重ねがおもしろいと思ったのは覚えています。コードの連なりによって曲の流れがどんどん変わっていくとわかってきて」
――その時点でもう着眼が宅録的というか、解剖学的。
「たしかに、構造に興味があった。その通りだと思います。そこに気づいてから、音楽を聴くのがおもしろい!と思ったんです」
――その後に、さらに自分を音楽に向かわせる存在となったのは?
「RADIOHEADです。知ったのは90年代半ばですね。その頃、けっこうメロコアやテンポの速いギターが歪んだロックが流行っていたんですが、誰かにZEBRAHEADを勧められたんです。それで何とかヘッドやったな、とうろ覚えの状態でCD屋さんに行ったら、これだ!と間違えて買ってしまったんです。帰ってから、あれ?なんか違うかもしれんと思いながらも聴いていたんですが、だんだん好きになっていって。つまりめちゃめちゃ偶然だったんです。聴いたアルバムは2ndアルバム『Bends』(1995)でした。その後、新譜が出ていることに気が付いて試聴機で聴いてみたら、最初の一音からもうガラッと変わっていて。すごい衝撃を受けて、そのままずっと聴いていました。そのアルバムが『Kid A』(2000)です。試聴機って30分くらい聴いていると止まっちゃうんですよ。それでもう1回再生ボタンを押すという行為を3回くらいやっていたから1時間以上は聴いていました。お店からしたら迷惑だったと思うんですけど(笑)」
――その音像の衝撃は、具体的にいうとどういうものだったんでしょう?
「あまり聴いたことがない音やったというか、電子音で始まったのがまず衝撃だったんです。そこからもう取り憑かれました。自分の音楽にどう影響を与えたかはわからないんですが、ただ、“アーティストは前のアルバムとは違うことをしなくてはならないんだ”と刷り込まれたというか、同じことを繰り返さない美学こそかっこいいと自分の中で規定された気はします」
――自分のオリジナル曲を作り始めたのはいつ頃?
「ギターを始めてからわりとすぐですね。コードの展開で曲になる仕組みがおもしろかったので、いろいろ試しながら歌を上に乗せて作っていたとは思います。大学に入ってからは音楽サークルに入り、その中ではフィッシュマンズやRADIOHEADのコピー・バンドをやっていましたが、それとは別に、自分のオリジナルをやるバンドも併行してやっていて。いわゆる“外バン”でした」
――ソトバン?
「あ、それは、ライヴハウスなど大学の外でやるバンドという意味です。サークルでの活動はそもそも3年くらいで終わっちゃう。卒業後もずっと続けていたのは、外バンのほうです」
――それがスーパーノア?
「そうです。のちのちはメンバー交代もあるんですけど、最初はサークル内から始まったバンドでした。バンドとしての具体的な目標があったというより、できた曲を合わせてやるのがただただ楽しいという感じでした。他のメンバーがどう思っていたかわからないんですが、僕個人としてはくるりやママスタジヲ、越後屋とか、あの頃の京都のバンドの影響下にあった音楽をやっていたと思います。ちょうど、くるりは『THE WORLD IS MINE』(2002)や『アンテナ』(2004)を出した頃で、どんどん違うことをやることのかっこよさを体現してはったバンドやったので、気持ち面ではそういう方向はメンバー間では共有していたと思いますね」
――バンド活動と並行して、ソロ作品も作り始めますよね。
「バンド(スーパーノア)では、ライヴでやっていることを音源に落とし込んで作ってきました。それと併行してソロでの宅録みたいなことは最初からしていました。カセット・レコーダーを使ってピンポン録音とか。宅録での作品は、最初は“イツキライカ”という名義で発表していました。最初は本名でやらないほうがいいと思っていたんです。今もそうなんですけど、あまり自信がないというか、人からなんやかんや言われることで傷付くことを恐れていたのかも。名前が違えばワンクッション置ける。そういう気持ちはあったのかもしれない。でも“イツキさんなんですか?”と聞かれることもあって、そこにあんまり意味があるわけじゃないから、だんだんその名義であることがめんどくさくなってきていたんです。それで“本名にしたら作る音楽も変わるかな”くらいの気持ちで変えてみました」
――実際、音楽は変わりました?
「大袈裟に変わったというほどではないですが、本名にしてからは自分で思っていないことは言っていないと思います。イツキライカ時代の曲を聴き直してみると、めちゃくちゃデカいこと言ってんなあ、と思いました。物語形式で語ろうとしていたというか、“宇宙の誕生から量子の数は変わっていない”みたいな(笑)。それはそれでいいんですけど、今はそんなこと言わんかもな、と思います」
――「井戸健人」の名義で最初にリリースしたアルバムは『Song of the swamp』(2020年)で、これは完全に宅録ですね。コロナ禍でもあったせい?
「あのアルバムの制作はコロナ前から始めていました。宅録用の機材もいいものが出てきたし、これなら自宅でも納得できる作品が作れるかもと思ってやってみたんです。バンドはメンバーの意見を合わせたもので、それが楽しいんですけど、自分のソロは完全に自分だけの意見でバッサリいける。アイディアを考えてきてくれたのに使わんの悪いな、みたいな躊躇が要らない。良くも悪くも独断でいける気持ちよさがありました」
――そんな宅録の快感を推し進めた2022年のアルバム『I’m here, where are you』。そして今年、『All the places (I have ever slept)』に至ったわけですが、今回は厚海義朗(b | GUIRO, cero)、ファンファン(tp)、畠山健嗣(g | THE RATEL, H Mountains, 大森靖子シン・ガイアズ)、池田若菜(fl | THE RATEL)、河嶋大樹(dr)、溝渕匠良(b | THE RATEL)、吉居大輝(g | 幽体コミュニケーションズ)、Yachi(pf | 折坂悠太 重奏, ムーズムズ)らサポートのミュージシャンを迎えての制作です。
「はい。でも、人と作ったとはいっても、かなり変わったやりかたです。ひとりで作った音源って、あんまり覚えていないところがちょこちょこあるんです。これ、ほんまに自分が作ったんかな?みたいな。そして、その作ったことを忘れているような部分が、わりとお気に入りポイントでもある。つまり無意識とまではいかんけど、意識してやろうとしたんじゃないところにフォーカスを当てていったらおもしろいんじゃないかと思ったんです。なので今回は、他の人に頼んで演奏してもらったものを持って帰って、その好きなところをもとにして新しく自分の曲を作っていけば、自分では思いつかへんけど自分だと言える作品になるんじゃないかと思って」
――普通は、デモ音源やプリプロで作ったアレンジがあって、ミュージシャンを呼んだら「ここ弾いて」みたいにしてパーツを集めて曲を組み立てていくのが普通じゃないですか。
「やりたかったことは、いわゆるジャズや即興音楽で行われている“チャンス・オペレーション”ともちょっと違うんですよね。まず、自分の曲をシンプルに作る。それはコードや歌でできている骨組みで、それをミュージシャンにはある程度自由にアドリブや即興をしてもらい、自分のデモは1回消すんです。そして、残った演奏の素材からもう一度自分の曲を組み立てていきます。そうやって作ってみたら、半分くらいの曲は元のデモとは違う曲になりました」
――もともと自分が考えていた曲はどうでもいい?
「元の曲が変化することはむしろ歓迎していました。曲名はなかったですが、歌詞は演奏に影響しそうだったので、日本語で作って歌っていました。でも、歌詞も結果的には、録った演奏がきっかけで変わったものもあります。“沫”はけっこう変わったかな。それも含めて始めたときは、どうなるかはわかってなかったですね」
――現代アートにありそうなハプニング主義ではなく、最終的にはポップスとして構築するわけですもんね。そのアプローチは発明かも。
「あー、そうなんですかね?アイディア自体は、Carlos Niñoのインタビューで読んだのが元なんですよ。彼の場合はライヴで自分の曲を抽象的にやってもらったうちの良い部分をストックしていて、それを再構築したアルバムが出ている。そのアイディアを僕が歌入りで応用してみたらいいんじゃないかと思ったんです」
――Carlos Niñoならありそうな話ですけど、歌ものポップスとしてはなかなかないでしょう。
「ありがとうございます。ひとりでやっていると自分の粗探しみたいな楽しくない作業も多いけど、人が弾いてくれた“いい感じ”の部分を探すのは全然苦じゃない。そういう意味でもやっているときは楽しかったですね。みなさんには最初に“あとで編集します”と伝えていました。ただ、やっているときは“これで大丈夫?”って何度も気にしてくれていましたね(笑)。完成した音源を聴いてもらったら、“自分が何をやってたかわからへんわ。でも、なんかいいね”という感想が戻ってきたりしました」
――全8曲のアルバムですが、そういう意味で、いちばん遠くまで到達できたと思う曲はどれでしょう?
「“¿”と“沫”はかなり変わりましたね。“Into a cave”も基本のリズムは変わっていないけど、上物はわりと変わりました。あとは“Living”。この4曲はけっこう変化したと言えます。ピアノでyatchiさんに参加してもらったんですが、“沫”のためにアドリブで弾いてもらったYatchiさんのソロをたまたま“Into a cave”に当てはめたら、すごくいい感じになったんです。そうか、こういうことも起こるんだとびっくりしました」
――ちなみに、yatchiさんはその編集に気がつきました?
「“わからない”と言ってました(笑)」
――楽しさとは別に、苦労もありました?
「自分の歌ですかね。歌をうまくなりたいと思いました。思ったより歌えなくてけっこう録り直しました。曲やアレンジが変化することで、作ったときに意識していたテンションを感じにくくなるからなんです。どういう歌いかたをすればいいんかな、みたいな。最初のテンションのまま歌えた曲もあるんですけど、ほとんどは曲が変化しているので歌詞やメロディの修正や調整が必要でした」
――しかし、この奇抜な作りかたとシンガー・ソングライターとしての自分の音楽が、なぜ井戸さんの中ですんなり結びついたんでしょう?THE BEATLESで感じた楽曲の構造への興味に始まるものも、レイヤーとしてはあるような気がしますが。
「特に意気込みとかはなかったんですよ。やったことないことをやるべきだ、と自然に思っただけで」
――完成形を決めにくい方法でもあると思うんです。自分の中ではどこが着地点だったんですか?
「1曲ごとに“この曲が完成した!”と思うポイントはあんまりなくて。アルバム全体でこれでいいと思えたときに、前後の曲のアウトロの長さとか、そういう部分も決まっていきました。エンジニアの甲田(徹)さんもいろいろ意見をくださって、ミックスダウンが終わったときに、ようやくよし!と思った感じで。それまではずっと中身はうごめいていましたね」
――でも、このアルバムのおもしろさは、すべてが流動的にゆらゆらしているわけではなく、言葉とかメロディとか、ポップスとしての自覚はしっかりとある。それとチャンス・オペレーション的なプロセスが一緒にあることがおもしろいし、現代的と感じるんです。アルバム・タイトルは、今聞いた話に紐付けて解釈すれば、言ったことやったことはたしかにあるけど、その場所で自分は眠っていた気がする、みたいなことですかね?
「あ、まさにそうです。タイトルはわりとうまく言い表せたと思っていて。寝ているときは意識がない、とはいえ、自分がやったことは確実にあって、それが自分でもある」
――3月26日にシングル『OurS』をリリースされましたが、これはアルバムの延長線上?
「これはまた自分ひとりでやってみようと思って作りました。今回の制作を経て、自分がどう変わったかを確かめるために。変わったところもあるし、シンプルにミックスのコツがつかめるようになった気がします。いい演奏というか、こういうポイントが自分は好きなんやということにある程度自覚的になれたから、そういうプレイを自分でもしよう、と。たとえば、小節の終わりのベースはちょっと遅くなって次に行ったほうが好きなんだ、みたいな細かいポイント(笑)。それを自分でも再現してみる、みたいな曲になっていますね」
――今回のアルバムは、「反AI」のようなアプローチだったと思います?
「あー。でも、AIの力を借りられるんやったら借りたいですけどねえ(笑)。ノイズをとったりとか、めんどくさいところはやってほしい。できた曲に対するアドヴァイスは全然AIに聞きたいし。だけど、楽しいところは基本的には譲りたくないんです。“曲を作ってくれ”はやっぱり自分でやりたい」
――AIって無駄を省くことが大事だから、今回のアルバムの制作方法はAIがやりたくないことだと思います。自分にとってひとつの土台になったんでしょうか?
「いい経験にはなりました。土台になったかどうかは、もうちょっと時間が経てばわかるかもしれない」
――つくづく井戸さんの持つカジュアルな実験性がこのアルバムの支えになっていると感じました。このインタビューを読んで、そんな作りかたがあるのかと気がついて、自分で応用する人も出てくるかもしれません。
「音楽を作っている人がおもしろいと思ってくれたらいいですね」
 ■ 2025年2月19日(水)発売
■ 2025年2月19日(水)発売
井戸健人
『All the places (I have ever slept)』
https://friendship.lnk.to/Alltheplaces_ido
[収録曲]
01. ¿
02. 突堤と海原
03. Living
04. カーニバル・冬
05. 杳
06. 音楽をきいた頃
07. Into a cave
08. 沫
 ■ 2025年3月26日(水)発売
■ 2025年3月26日(水)発売
井戸健人
『OurS』
https://friendship.lnk.to/OurS_kentoido
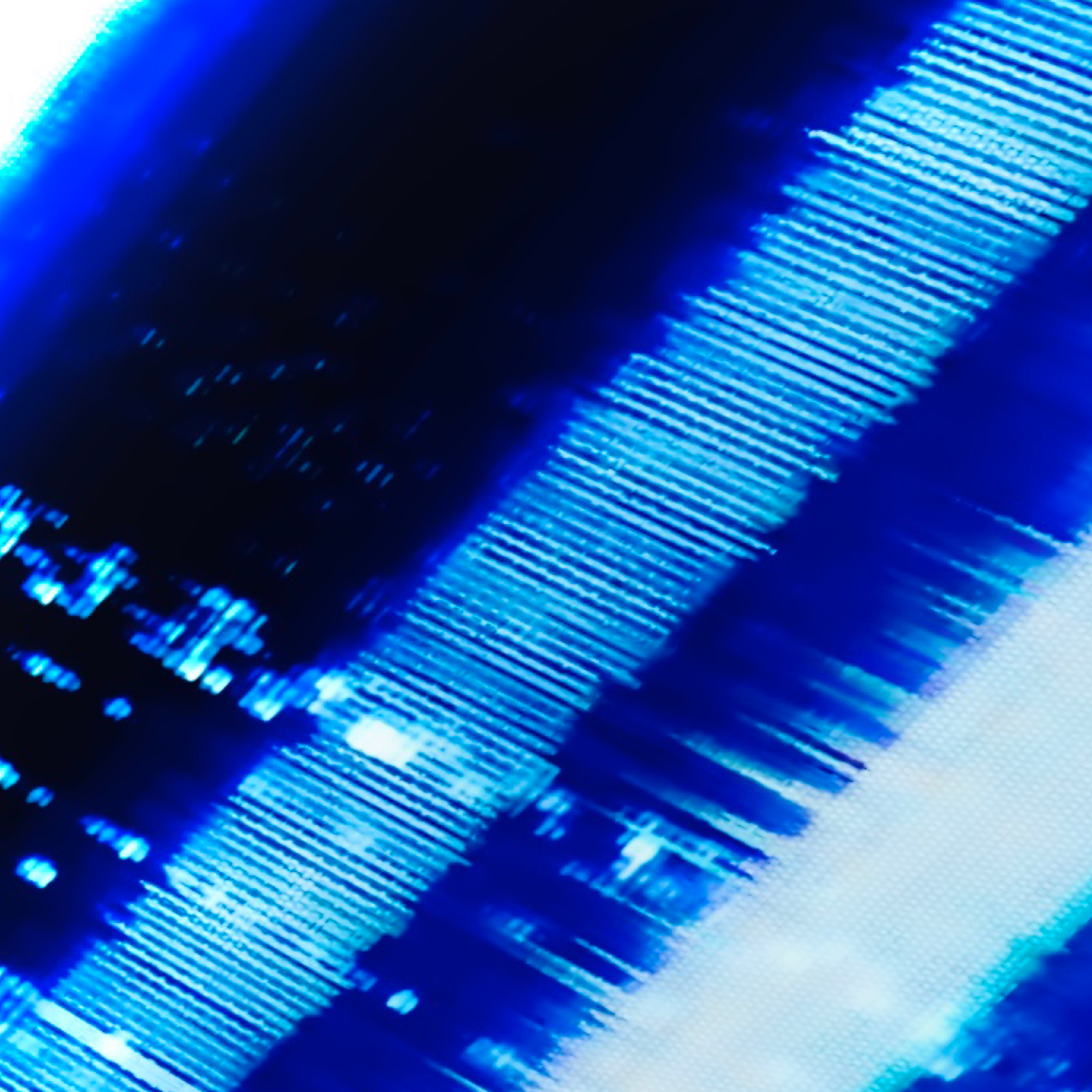 ■ 2025年4月15日(火)発売
■ 2025年4月15日(火)発売
井戸健人
『透過光』
https://friendship.lnk.to/transparent_ido
[収録曲]
01. 透過光
02. 透過光(おるたな)








