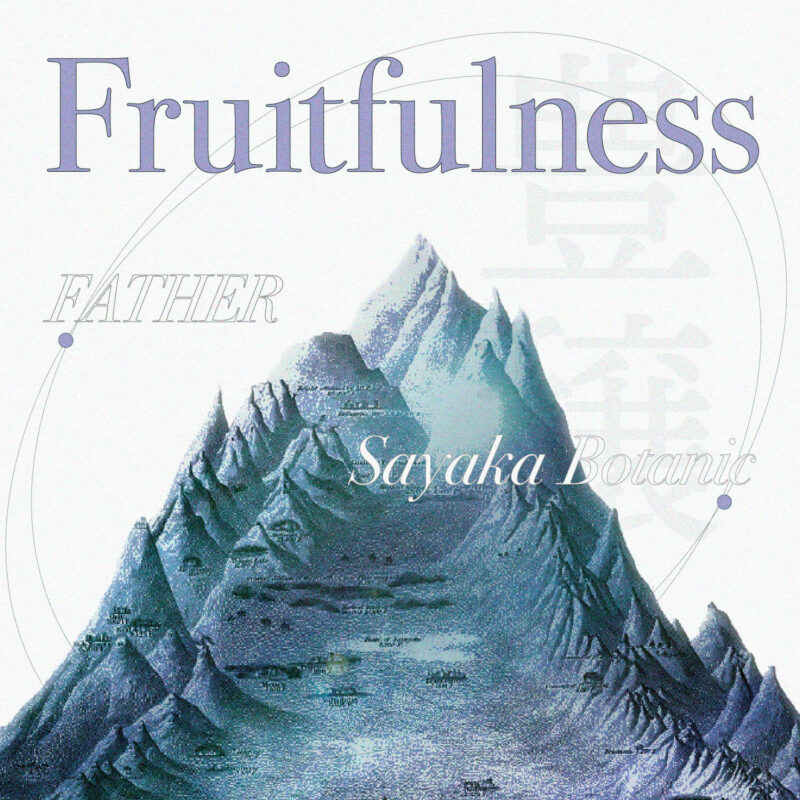いつだって新しい発見がある
このバンドにおいて中心的なメンバーと言えるDuane Denisonは、THE JESUS LIZARDの特異なサウンドで一翼を担い、90年代以降のオルタナティヴ・シーンに絶大な影響を及ぼした偉大なギタリスト。以下のインタビューを読めば、その刺激的なプレイの背景には、真面目な学究肌の性格があると分かるだろう。それにしても、TOMAHAWKでもTHE JESUS LIZARDでもいいから(できれば両方で)いつか日本で彼のプレイを観る機会が実現してほしいものだ。
取材・文 | 鈴木喜之 | 2021年3月
通訳 | 竹澤彩子
――8年ぶりの最新作『Tonic Immobility』は、4年前にはバック・トラックが完成しており、Mike Pattonがヴォーカル・パートにとりかかるまで時間がかかったとのことですが、待たされている間はどんな気持ちでしたか。そうして完成したアルバムを聴いた時には、どんな感想を持ったのでしょう?
「待たされたと言っても、そんなにヒドいもんじゃなかったよ。少なくとも4年ってことはなかったし、せいぜい2~3年ぐらいじゃないか?デモ自体はだいぶ前に作ってあって、ヴォーカルがどんな仕上がりになるかもある程度は予想がついてたんだ。Mikeも1曲録り終えるごとに音源を送ってきてくれたし、その都度確認してたからね。アルバム全体としてかたちになったときにも、大方は予想通りというか、取り立てて意外なこともなく……まあ、これだけ待たされたんで、いい加減うんざりな部分もあったし、ようやく完成したアルバムを聴いたときには、そういう意味でも感無量だったけど(笑)。出来には大満足しているよ」
――Mikeが本作のレコーディングにようやく集中できたのは、ロックダウンでその他の活動が制限されたからだとも聞いていますが、彼のヴォーカル・パートや歌詞に関して、2020年の不穏な社会の状況が多少なりとも反映していると感じたりもしますか?
「まあ、一部そうとも言えなくはないかな。実際に去年1年間は、ほぼロックダウン下にあって、その中でアルバムの作業も進行していたから、そこは少なからず影響を受けてるのかもしれない。大半の曲はその前に完成してたから、昨年のパンデミック云々とはおそらく関係ない内容になってると思うけど、一部、影響は受けてるよね。そりゃそうだろ」
――その他、『Tonic Immobility』の制作に関して、以前のTOMAHAWKの作品と比べ、何か変わったところはありましたか?
「まあ、基本的には一緒だね。俺も含め、各々が作ったデモをもとにして……JohnとTrevorがベースとドラムを録音するために、俺の住んでるナッシュヴィルまでわざわざレコーディングしに来てくれて。Mikeは他のことでずっと忙しくしてたから、とりあえず集まれる連中だけで先に進めとくよ、みたいな感じで始まってね。だから、ヴォーカル以外の部分はナッシュヴィルで録って、一通りミックスした音源をMikeに送ったら、すごく気に入ってくれて、そこからまたスタートした感じだね」
――レコーディングの段階で、JohnとTrevorからはどれくらいインプットがあるのでしょう?
「とりあえず、2人とも名プレイヤーだからね。俺が曲を書いて渡したところで、最終的にはそれぞれ自分なりの色を加えてくれるんだ。そもそも優秀なプレイヤーってことに加えて、2人とも個性的で、自分なりの解釈やアウトプットを通した上で音に還元してくれる……単純に言っちゃうと、元々あるものを活かしてさらに魅力的にしてくれる。俺はドラムに関しては完全に門外漢だけど、ベースなら多少は扱える。それでも、Trevorの足元にも及ばない。2人ともデモに忠実にプレイしてくれているにもかかわらず、やっぱりそこに何かしら独自のカラーを付け加えてくれるよ。音符は変えていないし、基本そのままなんだけど、なぜか俺が提示した音よりはるかにグレードアップした音になるんだ」
――最新アルバムは、これまでに比べ、エクスペリメンタルな部分よりも、ストレートにロックしているところが強調されていて、聴き易い作品に仕上がっていると感じました。今回こういう作風になったことに何か理由はありますか?
「どうだろう?例えば“Eureka”はコラージュ的な曲だし、ある意味エクスペリメンタル寄りとも言える。あるいは“Tattoo Zero”は、ガチャガチャしたインストのパートが中間に入っていたり、それこそプログレッシヴ・ロックに寄っているくらい。だから、そこまでストレートな感じでもないと思う。“Fatback”では、拍子の転換が何度か繰り返されるし。何をもってストレートなロックと定義するかにもよると思うけど……まあ、例えばFANTÔMASなんかに比べたら、確実にストレートなロックだろうけどさ。いずれにせよ、TOMAHAWKが昔からロック・バンドをやってきたことに変わりはないし。あちこちいろんな方向に振れてみたり、メンバーそれぞれいろんなスタイルの音楽をやっているけど、このバンドの一番の目的はロックンロールなんだ。思い切りロックンロールをぶちかましてやろうぜ、っていう」
――今回のアルバムを作ったときによく聴いていた音楽などはありますか?
「俺は一定期間入れ込んで、そればかり集中して聴いたあと、次に行くっていうパターンを繰り返す感じなんだ。例えば去年のロックダウン中は、どういうわけかビバップや古典的なジャズにハマってた。今回のアルバムの何曲かを書いている時期は、MASTODONとかHIGH ON FIREとか、ヘヴィなサウンドを聴いていて、それ以外では、わりとトラディショナルなソングライティングというか、David Bowieにハマっていた頃に書いた曲もある。Bowieは優れたソングライターだし、それこそ何10年にも亘って影響を受けまくってるけどね。あとはサウンドトラック的に耳に入ってくる音だったり、レゲエなりボサノヴァなり、なんでも……ただ、そうは言っても、俺はアメリカのロックンロール・ギタリストだから、何をやったところで最終的には、そこへ帰結していくんだ。自分の中で流行やスタイルがどんなに変わろうが、着地点は常に一緒だって感じてるよ」
――「Sidewinder」というナンバーは、ピアノ主体の静かなパートから激しいパートへと展開する、強弱の対比が印象的ですが、どのようにして出来た曲なのでしょう?
「まさに説明してくれた通りの構造になっているよね。どのようにして出来たかって?まあ、いろいろ試してるうちに……あれは、もともとピアノで遊んでいるときに思いついたんだったかな?いや、ギターだ。ギターを弾いていてアイディアを思いついて、ピアノに切り替えたんだった。最初は、シンプルで閑散とした感じのサウンドにしたくて。そこからだんだん雲行きが怪しくなって、怒濤の展開に突入してゆく。バンド総動員で演奏している最後のパートは、実は閑散としたイントロ部分と全く同じコードを使っていて、単にシンプルか、フル・ヴァージョンかの違いなんだ。基本的なアイディアはそんなところ。シンプルに始まって、そこからガチャガチャした展開になって、もともとシンプルだったはずのものが最終的にはまったく別のかたちへと変容してゆく。いろいろと試しながら、このかたちに落ち着いた感じ。これはセクションごとに書いていて、何度か試行錯誤してるうちに正解にブチ当たった、そういう曲なんだ(笑)」
――あなたはDavid William Sims、Trevor Dunnといった強力なベーシストとプレイしてきましたが、それぞれに感じた特徴などを教えてください。
「結局、同じ人間は1人としていないし、相手によって自分の引き出しも変わってくる。Davidとはつかず離れず、それこそ80年代から一緒にプレイしている仲で、お互いのことを知り尽くしているし、今でも定期的に話したり連絡を取り合ったりする友人だ。近い将来、2人でまた何かしら一緒にやるかもしれないし……というか、俺としてはそうなることを祈ってるよ。だから、すごく気さくな関係というか、気軽にいろいろやりとりできる。Trevorに関しては、Davidほど長い付き合いじゃないから、まだそこまで深くは知らないけど、こいつは本物のプロだな、って毎回思わされるよ。なにしろ飲み込みが早くて、いちいち説明に時間を割く必要がないんだ。ちょっと楽譜を書いて渡しただけで、すべて理解してくれるしね。こっちが不安になって“念のため2人で事前に一度音合わせしとく?”とか言っても、“いや、必要ないっしょ”みたいな(笑)。実際その通り、打ち合わせなしでも見事な演奏を披露してくれるんだ。それぞれのバンドで、全く違うタイプの優秀なベーシストと組めたこと、はミュージシャンとしてはこの上なく恵まれているよね」
――なるほど。
「それはドラマーにも当てはまることで、TOMAHAWKで一緒にやっているJohn Stanierにしろ、THE JESUS LIZARD時代のMac McNeillyにしろ、演奏スタイルからして全く違って……その違いを具体的に表現するのは難しいんだけど、どちらも優秀なプレイヤーなのは間違いない。ヴォーカリストにしても、David Yowも、Mike Pattonも、あるいは20年前に今俺が住んでるナッシュヴィルで共演したHank Williams IIIにしても、みんな唯一無二の歌い手だ。俺は恵まれてるって心の底から思うよ。ただ、たしかに運がいいってこともあるけれど、それは自分が共演したいと思えるような才能あるミュージシャンにアンテナを張ってきたからでもあるんだよね。優秀なミュージシャンと一緒に演奏すると、自分の演奏も一段上のレベルにまで引き上げられるから、自分より才能あるミュージシャンと演奏するのが大好きなんだ。共演することで成長していけるしね。ギタリストにありがちな間違いとして、自分がフロントマンとしてやたら前に出たがる奴が多いっていうのがある。要するに、ステージ上で一番注目されるのが自分じゃなきゃ気が済まないわけ。少なくとも俺はそういうタイプじゃないし、むしろ観客の目を楽しませてくれるシンガーなり、フロントマンが前面に立って、その陰でギターをコツコツ弾いているのが性に合ってるんだ。たまにはこっちの演奏にも注目してほしいと思うこともあるけど、四六時中、俺ばかり見てもらいたいわけじゃない。もともと目立ちたがりやでもないしさ。そうやって、いろんなタイプの人間が集まって一緒にやっているのがバンドなわけだ」
――John Stanierに関しては、かつて彼が在籍していたHELMETと現在やっているBATTLESでかなり音楽性が違いますが、John自身、TOMAHAWKで、こういうプレイができることを喜んでいるのではないでしょうか?
「そうだと思うよ。BATTLESの音楽はすごくおもしろいけど、巧みなぶん技術を必要とされるというか、エレクトロニックな音やサンプルを駆使して、常にドラム・マシーンやクリックガイドと合わせて演奏したり、ループを意識しなくちゃならなかったりする。だから、何も考えずにドラム・セットの前に座って、ただ自分の衝動の赴くままにドラムを鳴らすロックンロール的なプレイができるのは、ものすごい解放感だろうと思うよ。俺の中ではロックンロールって、どんなスタイルやアプローチであれ、とりあえず楽しくなきゃ、っていうのがあるんだ。聴いている人が楽しくて興奮してこないと、演奏する側としても、自分自身が弾いていて楽しくないし、そそられもしない。それで聴いている人を楽しませようとしたところで、難しいだろう。だからジョンが、ただひたすらドラムを演奏する機会を思いっきり楽しんでくれてるといいな。サンプルやトリガーを一切気にすることなく、思い切りドラムにぶつかってね」
――あなたは、非常に個性的で強力なロック・ギタリストながら、他のプロジェクトでは、ジャズ、カントリー、ロカビリーなど様々なスタイルでプレイしています。そもそも最初にギターを始めた時はクラシックから学んだそうですが、あなた自身はどのジャンルが自分のコアにあると感じているのですか?
「たしかに大学ではクラシック・ギターを専攻していたし、他にもいろいろなものに手を出してはいる。ただ、TOMAHAWKにしろTHE JESUS LIZARDにしろ、いわゆるロックンロールの立場からギターに向き合っているときは、こちらの意識としても、聴いている側としても、俺のギターからクラシックの影響はそんなに感じられないんじゃないかな。俺のギターの根本はふたつあって、ひとつはUKのポストパンク、PiL、MAGAZINE、GANG OF FOUR、KILLING JOKEとか。もうひとつは、その後に来たアメリカのノイズ・ロック、BIG BLACK、SONIC YOUTH、BUTTHOLE SURFFERS、SCRACTH ACIDなんかだ。そのふたつを掛け合わせて、自分なりに咀嚼したのが、俺が今やっているギターの基本になってると思う。そこにクラシック・ギターやロカビリーや、いろんな味付けがされている感じかな」
――そんなあなたにとって、TOMAHAWKというバンドはどういう位置付けになるのでしょう?
「このバンドを始めて20年くらいになるのかな?で、最初の3年間に2枚のアルバムを出して、さんざんツアーしまくっていたから、その頃だったら間違いなくTOMAHAWKが自分にとってメインのバンドだった。そこから少しペースを落として、今回の5枚目は10年ぶりくらいの新作になる。その時々でやっているプロジェクトが自分にとってメインのバンドっていうことになるだろうから、そういう意味で、現時点では間違いなくTOMAHAWKがメインだな。こうして新作がリリースされるし、それを作っていた期間も含めてね。このアルバムの制作を始めてからもTHE JESUS LIZARDでライヴをやったりして、そのときはそっちに切り替えたけど、それでもアルバムを作っている最中は、他の活動より今作の曲作りを優先して、他のメンバーがそれぞれの活動を終えて、このプロジェクトを最優先にしてくれるタイミングを待っていたわけ」

――ちなみに、さっきUKポストパンクの話が出ましたが、THE JESUS LIZARDとしての最後のアルバム『Blue』は、先日亡くなったAndy Gill(GANG OF FOUR)がプロデュースしていましたね。彼と仕事したときの思い出を聞かせてください。
「俺たちがAndy Gillと一緒に仕事をしたのは、THE JESUS LIZARDとしてすでに何作もアルバムを出した後で、しかも最後の作品だったから、そこまで直接的な影響っていうのはなかったように思うけど、ギター全般に対するアプローチがとにかく独特だったよ。時々わざと歪な展開というか、普通だったらこうしないよな?って思うような要素を挟んできたりするんだ。一般的にギタリストって、すべてつつがなく自然に流れてゆくような演奏に寄りがちなんだけど、彼の場合、そこにあえて難解なトリックや展開をちょいちょい挟んむことで、全体的にどこか歪な印象を作るというか……そういうマニアックな技みたいなのものに長けてたね。例えば、ひたすらノイズとフィードバックだけのギターをまるまるレコーディングしておいて、そこから取り出したギターの部分だけをコードに置き換えて曲にして、ギターを全く弾かず、ただのフィードバックだけで引っ張っていくうちに、徐々に積み重なって最終的には倍音が広がる、みたいな展開とか。SONIC YOUTHもけっこうそういう技を使っていたよね。そんなことが勉強になったかな」
――ギターのスタイルとしては、TOMAHAWKに最も近いのはTHE JESUS LIZARDだと感じます。逆に、TOMAHAWKとTHE JESUS LIZARDで最も違っているのはどこになるでしょう。
「まあ、いくつか違いはあるけど、最も大きな違いはヴォーカルだよね。David YowとMike Pattonは明らかに毛色が違う。Davidはノイズと相性がいいんだよ……歌詞もすごくいいし。Mikeは、もっとトラディショナルな歌い手に近い。ものすごく巧く歌えるっていうのが前提にあって、その上でノイズだったりスクリームもこなせる。だからメロディを聴かせられるタイプのヴォーカルというか……あくまでもDavidとの比較においてね。そこがまず大きな違い。あと、Mikeのほうがサンプル、キーボードとか、エレクトロニックな音に関して積極的っていう点もあるかな。俺も少しだけキーボードをかじってはいるから、THE JESUS LIZARDよりもTOMAHAWKのほうがエレクトロニックな音が多く入っていたりする。そうなると必然的に、他の音も変化していくわけ」

――ちなみに、もうTHE JESUS LIZARDとして新しいアルバムはあり得ないのですか?
「そうだねえ……とりあえず、今すぐってことはないだろうな。正直、こればかりは俺にもさっぱりわからないよ。まあ、できないこともない、とだけ言っておこうか(笑)。THE JESUS LIZARDの新作が今後絶対にないとは言い切れない。ところで、大昔のことだけど、THE JESUS LIZARDは日本でもライヴやったんだよ」
――はい、観に行きました。インタビューもさせてもらいましたが、「Steve Albiniがエンジニアリングに関してあまりにも頑固なので、さすがに困っている」という話をされていたのが印象に残っています。
「アハハハハハハ、そりゃいいね!全く記憶にないけど(笑)!」
――「イグアナラマ」というイベントに出演したんですよね。
「1994年とかだったな。HELMETやHOUSE OF PAINも出てた。今もうちのどこかにポスターがあるはずだよ。またぜひとも日本でライヴをやってみたいね。頼むよ、また日本に呼んでくれよ(笑)。マジでお願いだから。コロナが落ち着いたら、日本、オーストラリア、ニュージーランドと回ってやる!どうか実現できますように!」

――私もできる限りの応援はします!では、あなたのキャリア全般についても幾つか質問させてください。東ミシガン大学でクラシック・ギターを始めたそうですが、当時は主にどんな音楽を聴いていましたか?
「大学でクラシック・ギターを専攻する前にも、ロック・バンドで活動してはいたんだ。パンクやメタルに夢中だったからね。大学に入った頃は、たまたま現代音楽に興味があった時期で、ドイツのHans Werner Henzeとか、日本の武満 徹とか……彼もギター音楽を作曲していて、そういう作品もすごく好きだったんだよ。ただ俺がクラシックから何を学んだかというと、音楽的なスタイルよりむしろ、日々鍛錬して自分に練習を課す生活態度みたいなところだね。どんなに忙しくても練習のために時間を割いて、日々のスケジュールを組むようにするところとか。学校に行ったり、仕事に行ったり、学校と仕事を掛け持ちしてるときなんかは、それこそ限られた時間をやりくりして練習時間を捻出しなくちゃならない。しかも、その時間を最大限に有効活用できるように、練習時間中は自分の決めたルールに従って集中するわけ。例えば俺のルーティンとしては、とりあえず45分の基礎練習をやって、そのあと実際に曲や課題を使って応用練習を45分、さらにその曲を基に即興の時間を45分、計2時間15分を練習に割いてた。クラシックでは、毎日の練習を怠らないように日々のスケジュールに練習時間をきっちり習慣づけるんだ。いまだにそれは継続しているし、例えばジャズ関連の本でサックスのパートを読んでメロディを研究してみたり、バイオリンの本を読んで、そこから新しいことを試してみたり、自分が作っている最中の曲をそれ風に弾いてみたりとか。だから大学でクラシックを学んだ一番の成果は、スケジュール管理が徹底的に身についたこと。ただ個人的には、“クラシックから影響を受けました”って言うギタリストには基本ロクなのがいないと思ってる。Yngwie Malmsteenとかアホらしくて!ああいう、やたらと大袈裟で、これ見よがしのネオ・クラシカルみたいなのは大嫌いなんだ。悪趣味だし、ただただバカげてるし、この21世紀に、いつの時代の話だよ?今それをやる価値があるのか?って思う。博物館や美術館に飾る音楽としてならアリなのかもしれないけど(笑)」

――ちなみに、子供の頃はどんな音楽環境で育ったのですか?
「俺の育った街には、いたるところで音楽が溢れ返ってた。ミシガン州デトロイトの郊外にあるアナーバーっていうところの出身なんだけど、THE STOOGESの出身地でもある。近くにはMC5もいたし、Motownもあって、Bob Seger、Ted Nugent、最近ではJack Whiteがいて、優れた音楽やミュージシャンの宝庫みたいな土地柄なんだ。うちの両親も素人ながら音楽をやっていてね。いわゆるアマチュア・ミュージシャンで、母親がクラシック・ピアノを弾いていたから、うちにピアノもあった。父親は若い頃、大所帯バンドみたいなところでシンガーをやっていて、耳から音程をとって歌ったり、ピアノを弾いたりできたんだ。親たちの世代が若い頃は、家にテレビなんてないし、ピアノを弾いたり歌ったりするのが娯楽の一部だったんだな」
――ところで、あなたは司書でもあるそうですが、どのようにしてその職に就いたのでしょう?書物や読書体験が音楽的な創作に結びつく体験などがあれば、具対的な例を話していただけますか?
「そうそう、大学生のときも、音楽の勉強をしながら図書館で働いてた。司書の仕事は好きだったよ。音楽の次に、今までやった仕事の中で唯一楽しいと思えたのは図書館での仕事だけだ。小さい頃から図書館に行くのが大好きだったから。全然ロックじゃないって思われるかもしれないね(笑)。バイクや車を乗り廻したり、崖から飛び降りたり、天井からぶら下がったり、芝居をやったり、ジャクソン・ポロック風の絵を描いてみたりするのがロックンローラーのイメージなんだろうけど(笑)。ただ、Keith Richardsも図書館に入り浸っていたっていう話だし、他にも図書館好きの奴はけっこういるよ。図書館て、知識と情報の宝庫みたいなところで、本も雑誌もあるし、楽譜から音楽からアートブックまで、アルバム作りに必要な材料はすべて図書館に詰まってる。歌詞の素材として文学があるし、アートワークの参考としてアートブックが使えるし、CDを聴いてそこから何かしらインスピレーションを得たっていい。まさにアイディアの宝箱だ。何年か前の一時期、音楽活動をスローダウンしていた頃……俺も歳を取ってツアーがしんどくなってきてさ。その間に何か仕事しようってことで……ミュージシャンを続けつつ、1年中フル稼働するのは控えて……もう何10年もフルタイムのミュージシャンをやってきてたからね。それで今住んでいるテネシー州ナッシュヴィルにある図書館で働くようになったんだ。すごくいい感じだよ。同僚もみんな良い人たちばかりで、ライヴやレコーディングの仕事が入ったら休暇を取らせてくれたり、俺的にはけっこういいバランスなんだ。もともと仕事とは関係なく図書館に入り浸っていたし、常に読みたい本が出てくるし、そこからまた自分の頭の中でアイディアを膨らませていったりするのが楽しい。作家も新しい人たちがどんどん登場してくるから、いつだって新しい発見がある。今は、アプリで月15枚まで無料でアルバムを借りられるんだ。それこそ室内楽、オーケストラからサウンドトラックまで、延々といろんな音楽に触れられる。図書館アプリで午前中に武満 徹の作品を聴いて、午後にはアイドルの曲を聴いて、みたいな。しかもBluetooth対応だ。最近の図書館の進化には目を見張るものがあるよ。行ったことはないけど、日本の図書館もきっといいんだろうな」
――TOMAHAWKのサード・アルバム『Anonymous』は、あなたのネイティヴ・アメリカン音楽に対する研究が反映された内容で、興味深かったです。ああいう音楽に興味を持ち、TOMAHAWKとしての表現に反映させようと考えたきっかけはどんなものだったのですか?今でもまだ研究は続けているのでしょうか?
「昔ほどじゃないけど、今でも聴いているよ。ハマったきっかけは、20数年くらい前、ナッシュヴィルに越してきたばかりの頃、Hank Williams IIIといわゆるオルタナティヴ・カントリー・パンクと呼ばれる音楽をやっていたところからなんだ。彼といろんなところで演奏していたんだけど、アメリカのカントリー・グループって、ネイティヴ・アメリカンの居住地に建てられたカジノなんかに呼ばれる機会が多くてね。俺もそこで彼らの音楽に触れる機会に恵まれたんだ。それまで存在すら知らなかった新たな音楽世界が開けたみたいで、とにかく新鮮だった。この音楽についてもっと深く知りたいと思うようになって……さっきからオタクなエピソードばかりで申し訳ないけど、実際にそうだから仕方ない。“若い頃、アメ車を運転していたら……”とか言えたら、もっとロックンロールっぽいんだろうけどさ(笑)。その後、本屋でナタリー・カーティスっていう民族音楽研究者の女性が、ネイティヴ・アメリカンの歌やメロディやリズムを集めた本を見つけたんだ。19世紀後半から20世紀初期にアメリカ中を巡って、彼らが実際に歌って、パフォーマンスする様子を記録して書き留めた本だよ。その本を読んで得た知識を基にいろいろ試しながら、自宅で作ったデモをMike Pattonに渡したんだ。そしたらMikeがものすごい興奮して、“うわ何これ最高じゃん、やろうやろう”って言ってさ。それで実際にバンドでも試してみた。もちろん、ネイティヴ・アメリカンのカルチャーには敬意を払ったよ。素材をそのまま使うんじゃなくて、自分たちなりにアレンジしたり、要素を足したり。そもそもエレクトリック・ギターとドラムとキーボードを使って表現したわけだしね。以前ネイティヴ・アメリカンの新聞から取材を受けたことがあって、そのときの記者もすごくよかったってって言ってくれた。彼の周囲にいるネイティヴ・アメリカンの友達もみんな気に入ってるって。ただ、今あれをやるのはどうなんだろう……またああいうことをやろうとしても、あの頃とは風向きが違うというか、他民族のカルチャーに他所者が手を出すべきではない、みたいな風潮があるじゃない?それは一種の文化的搾取や冒涜にあたるんじゃないか?って。そういう意見も理解できるし、それを尊重してあげたいと思う。だから今はもう……いや、この件に関しては複雑な想いを抱いていてね。文化を尊重したい気持ちはある一方で、俺は今も彼らの音楽が好きだし、人種にかかわらず誰もが楽しんでいいものだとも感じるんだ。ソースがどこにあるのか正直に明示してあるぶんにはね。それでも、この時代にあれをやろうとすると、色々な議論が巻き起こるだろうし、その都度いちいち自分なりの見解を説明しなくちゃならなくなるから、ちょっと割に合わないって感じてる」
 ■ 2021年2月26日(金)発売
■ 2021年2月26日(金)発売
TOMAHAWK
『Tonic Immobility』
国内流通仕様CD IPC235CDJ 2,300円 + 税
[収録曲]
01. SHHH!
02. Valentine Shine
03. Predators and Scavengers
04. Doomsday Fatigue
05. Business Casual
06. Tattoo Zero
07. Fatback
08. Howlie
09. Eureka
10. Sidewinder
11. Recoil
12. Dog Eat Dog