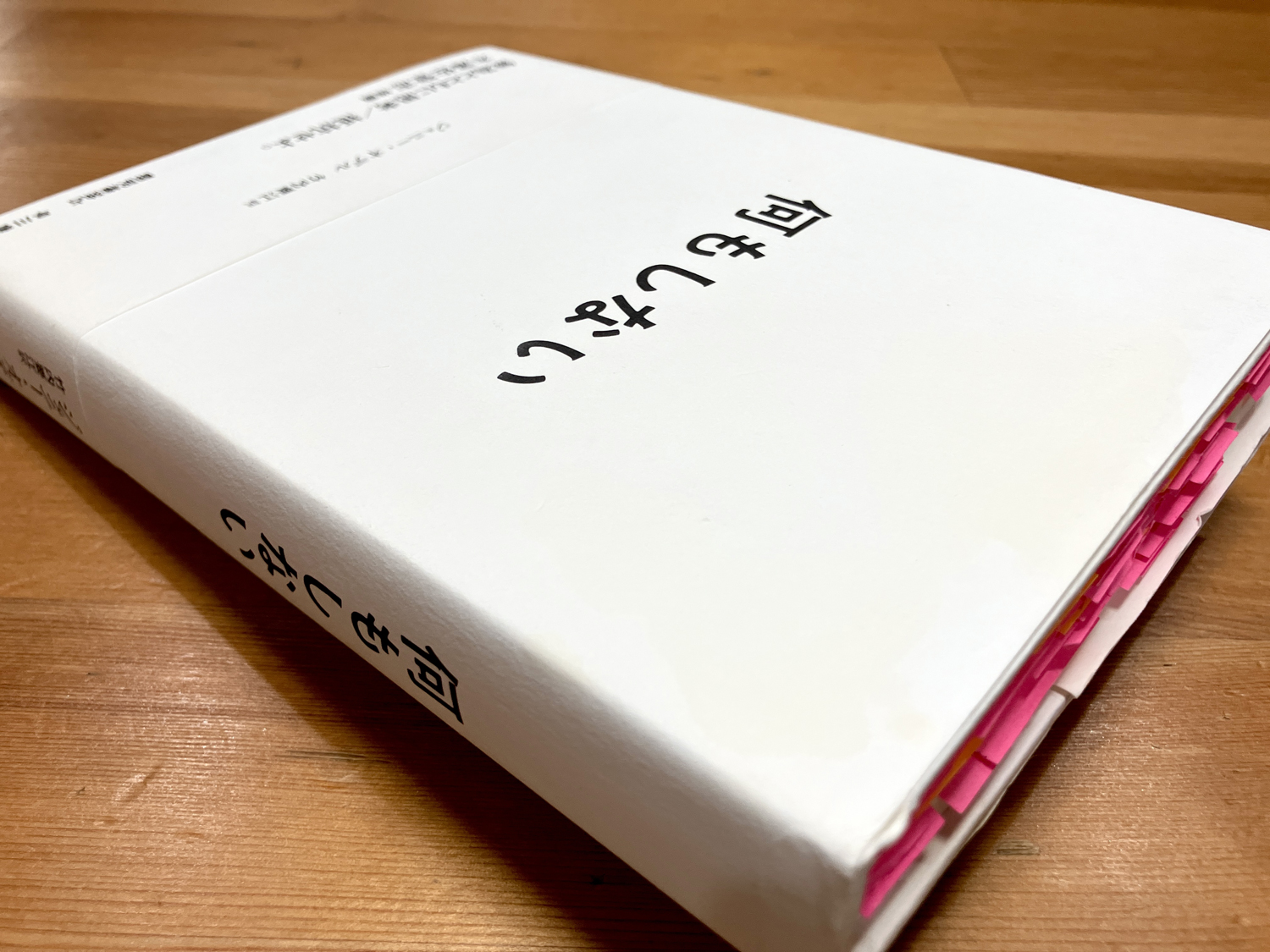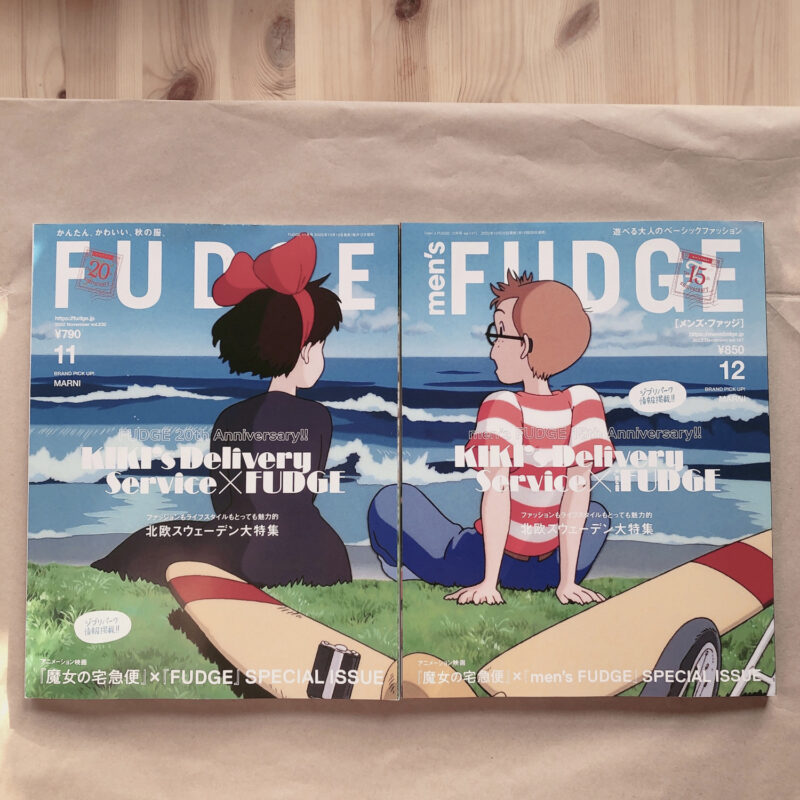文・写真 | コバヤシトシマサ
ジェニー・オデル 『何もしない』(2021, 早川書房)。気になりすぎるこの書名を目にしたら、手に取らずにはいられない。そうか、きっとあれだな。少し前に「寝そべり族」とかいう言葉が話題になった。たしか中国での話題だったか。生き馬の目を抜くような競争社会を成す中国で、あえて何もせず、ただ寝そべって過ごす若者たちのトレンドとして紹介されていた。さらに最近だと「静かな退職」なんていう言葉もある。これは日本の若者の最近の動向のひとつらしい。職場において意欲もやる気も見せず、ただ指示どおりの作業を淡々とこなす。そんな出世とも自己実現とも無縁な彼らの傾向を示す言葉だそうな。本書のタイトル「何もしない」も、きっとそういう類のものに違いない。そんな推測のもと本書を読み進める。
予想は半分は当たり、半分は外れたと言っていい。本書が掲げる「何もしない」とのスローガンは、端的にいえば現在のソーシャル・メディアが展開する“注意経済”(アテンション・エコノミーを本書はこう翻訳している)からの離脱を意味する。スマートフォンのアプリケーション上でフラットに並んだ数々の話題。国際情勢、凄惨な事件、社会問題、ゴシップ、ネットミーム、思わずツッこみたくなるあれやこれや。それらを眺めるとき、人はそれらについて考え、理解し、意見の表明を求められる。著者はそうした事態に警鐘を鳴らし、それが引き起こす弊害について警告する。以下は、著者が引いているフランスの哲学者ジル・ドゥルーズの言葉だ。
押さえつけようとする力は、人びとが考えを述べるのをさまたげるのではなく、逆に考えを述べることを強要する。今求められているのは、言うべきことがなにもないという喜び、そして何も言わせずにすませる権利なのだ。これこそ、少しは述べるに値する、もともと稀な、あるいは稀になったものが形成されるための条件なのだから。
――ジェニー・オデル 『何もしない』2021, 早川書房 p29
弊害はそれだけにとどまらない。現在の経済活動が地球の生態系に及ぼす影響と、ソーシャル・メディアが私たちに及ぼす影響との間には、類似性が認められると著者は指摘する。そして注意経済によって人は集中力を失ったり、注意散漫になるだけではない。望み通りの人生が送れなくなる可能性すらあるというのだ。
短期的には、気が散ることで私たちは自分のしたいことができなくなる。だが、長期的にみると、そのような経験が蓄積して、私たちは望みどおりの人生が送れなくなるか、さらに悪いことには、内省や自主規制の能力を骨抜きにされて、ハリー・フランクフルトがいう「私たちが欲しいと思うものを欲しがること」がより困難になる。
――ジェニー・オデル 『何もしない』2021, 早川書房 p184
だからこそソーシャル・メディアから離れ、何もしないでいるべきなのだと。
本書によるなら、ソーシャル・メディアが注意経済を促進するのは、それがそのメディアのエンゲージを高め、資本価値を生み出すからだ。そこでふと思う。ユーザーの側が注意経済に支配されるのにも、似たような理由が関係していないだろうか。SNSによってなんらかの注意を喚起されたユーザーは、それについて何かリアクションしたり、コメントしたりする。そうするのは、それに生産的な価値があると考えるからではないか。つまり人はそもそも何もしないではいられず、何かを生産しようとする気質がある。突拍子もない話に聞こえるだろうか?例えば本書にはピルヴィ・タカラというアーティストによる「研修生」と題されたパフォーマンス・アートの紹介がある。その作品でタカラは、自らの正体を明かさないまま、ある企業の研修生としてオフィスに通う。そこでただデスクに座って空を見つめたり、上がり下がりするエレベーターの中でただ立ち尽くしたりして過ごす。するとどうだろう。だんだんオフィス内には動揺が広がっていき、彼女に関するEメールがそこら中でやり取りされることになる。「ぼんやり窓の外を眺めているだけの社員がいます……」「彼女、午前10時半には何も置いてないデスクに座って、それからランチに出かけて……」ここで露わになっているのは、わたしたちは思っている以上に生産性というイデオロギーに浸っているということ。注意経済はそうした人の気質を巧みに利用しているのかもしれない。
ではそれでも注意経済を抜け出したいなら、どうすればいいのか。著者のオデルは自身の経験を例として挙げる。自分の注意をどう扱い、それをどこへ向けるのかに意識的になるのを推奨した上で、彼女は自分の身のまわりに耳を傾け、見つめようとする。動物や植物、気候、地形、その土地の歴史。そうしたものへ注意を向けることで、それまで平坦だった現実は大きく変化する。たまたま見かけた鳥や草木の名前を調べたり、その土地の来歴を知ったりするうち、現実はさまざまに複雑なコンテクストを持つようになる。彼女はいう。スマートフォンの画面に並んだ情報にはコンテクストがない。つまり背景や文脈がないのだ。それこそが問題の核心であり、だからこそコンテクスト崩壊状態から、ふたたびコンテクストを取り戻す必要があると。そのための鍵として、彼女は“時間”と“空間”の必要性を論じるのだが、詳細については本書を参照されたい。ここでひとつだけ言っておくと、著者が掲げる“何もしない”とは、何もしないことではない。それは注意経済から離れ、別のフレームワークで他の活動に従事すること
(p272)なのである。
以上の議論は、やもすると“仮想世界から現実に戻ろう”とのありきたりなメッセージに見えるかもしれない。しかし重要なのは、そのメッセージがどのようなコンテクストから生まれたか、だ。本書の醍醐味はそこにこそある。だから議論の全体について、ぜひ本書を読んでみてほしい。キャッチーな見出しだけで、あたかもそれを見知ったかのように誤解するのをこそ、本書は問題視しているのだから。
著者のオデルは、この本は何かを教えるものではなく、散歩でもしましょうとの誘いなのだという。音楽家のポーリン・オリヴェロス(ディープ・リスニング!)や、画家のデヴィッド・ホックニー、あるいは自宅のベランダにやってくる親子のカラスなどから着想し、そこから自由に論を展開している。何かを知ることは、それを知った当人が、自分の精神と周りの世界とを作り出すことなのだとし、それゆえ彼女はどう生きるかについて、ひとつの指針を提案したくなる誘惑をはねのける
(p298)。彼女の声からなにを聞き取り、自らの注意をどこへと向けるのかは、読み手に委ねられている。何もしないでいるためには、何をしたらいいのだろう。
■ 2021年10月5日(火)発売
ジェニー・オデル 著
『何もしない』
竹内要江 訳
早川書房 | 2,300円 + 税
四六判 | 336頁
ISBN 978-4-15-210054-2
テック企業が注意関心を貨幣のように取引する現代社会への最大の抵抗、それは「何もしないこと」だ。スタンフォードで教える現代アーティストが、哲学者、芸術家、活動家、そして野鳥たちの世界を自由に渡り歩く、「抵抗する人々」のためのフィールド・ガイド