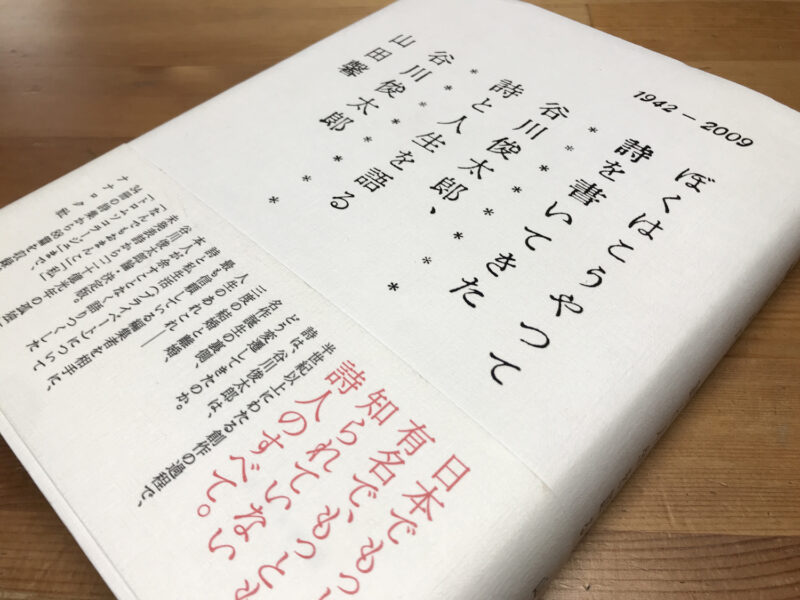文・写真 | コバヤシトシマサ
2023年の愛聴盤を紹介したい。といってもこれは今年リリースされたものではないし、しかもベスト盤なので、収録された曲の年代もバラバラ。自分が繰り返し聴いたという以外には、2023年とは全く関係がない。
Arto Lindsayの『Encyclopedia of Arto』。“アートの百科事典”と題された本作。その名の通り、Arto Lindsayのこれまでのキャリアを総覧した内容になっている。選曲も文句なし。自分は主にCDで愛聴したけれども、各種サブスクリプション・サービスでも配信されているようなので、誰でもアクセスしやすいと思う。
そもそもArto Lindsayは自分にとってはアイドルのひとりで、ただの音楽家ではない。“推し”というやつだろうか。英語やポルトガル語で囁かれる彼のヴォーカル・スタイルや、ブラジル音楽からノン・イディオムなギター奏法に至る音楽性はもちろんのこと、眼鏡の奥の神経質そうな眼や、そのファッション・センスまで、まるまる全部が好みなのだ。ジャケットのアートワークはどれも素晴らしいし、トレードマークであるDanelectroの青い12弦ギターも最高にかっこいい。
Arto Lindsayの音楽はどれも詩のようなものだ。そうした彼の持ち味を最初に意識したのは坂本龍一の「War & Peace」が最初だったろうか。坂本の2004年のアルバム『Chasm』に収録されたこの曲で、Arto Lindsayは作詞を担当している。Is war as old as gravity ?(戦争は重力と同じくらい古くからありますか?)
との印象的なフレーズから始まるそのテキストは、おそらく2001年に起きた9.11とその後のイラク戦争に端を発した言葉だと思うのだけれども、現在もその意義を失っていない。ここで全文は引用しないが、ぜひ参照されたい。
キャリアを一望できるベスト盤である『Encyclopedia of Arto』はCDでは2枚組なのだけれど、その2枚目がライヴ盤になっており、彼が自身の楽曲を“弾き語り”した模様が収録されている。“弾き語り”とわざわざ強調するのは、ファンには知られるとおり、Arto Lindsayは普通のギター演奏は絶対にしないから。ましてや通常の歌の伴奏などしない。これは“しない”のではなく、“できない”のだそうだ。彼はいわゆる“ノン・ミュージシャン”として知られている。ノン・ミュージシャンとは、音楽理論の知識やその技術がないことを指した用語。Arto Lindsayは音楽理論も、楽器の演奏技術も、全く持ち合わせていないらしい。ギタリストとしても長いキャリアを持つ彼は、ギターのコードをひとつも知らないという。本当だろうか。
これは自分にとって長らく真相の解けないミステリーとなっている。実際のところ、彼のギターの演奏からは一切のメロディも和音も排されている。聴いてもらえれば早いのだけれども、あえて説明するなら、フリーキーなノイズを使ったリズミックな演奏といったところだろうか。ともかく彼は普通にはギターを演奏しない。もともと彼は1970年代の後半にDNAというバンド――“ノーウェイヴ”ムーヴメントを代表するグループと言われている――から音楽のキャリアをスタートしているけれども、その頃から現在に至るまでギターの演奏に関しては一貫している。それはその通りなのだが、ではそのような人物がCaetano Velosoの作品をプロデュースできるものなのだろううか。ブラジル音楽界の偉人と言っていいCaetano Velosoは度々Arto Lindsayと共演しており、彼のアルバム『Estrangeiro』(1989)と『Circuladô』(1991)でArto Lindsayはプロデューサーを務めている。無論、プロデューサーの役割は譜面上のアレンジや演奏に関することだけではないのだろうけれども。まあ、あのBrian Enoもノン・ミュージシャンだと言われているし、そういったこともあるのだろうか。ともかくArto Lindsayは当初のパンク的な方法論を維持したうえで、音楽界の偉人と呼ばれる多くのアーティストたち――Caetano Veloso、Marc Ribot、Naná Vasconcelos、三宅 純、坂本龍一などなど――とコラボレートしている。
ところで“普通のギター演奏をしない”というと、どうしてもDerek Baileyと比較したくなってしまう。最近Paul Motianとのデュオ音源が発掘リリースされて一部で話題になっているけれども、Derek Baileyもまた“絶対に普通の演奏をしない”ことで一貫したギター・プレイヤーだった。聴いたことのない人に説明するのは難しいのだけれども、鉄の意志のごとき彼の“非”演奏は、聴いているうちに少々肩が凝ってしまうくらいに徹底したものだ。ギターの弦を弾いて(はじいて)演奏する場合、演奏に馴れた人でも、そうでない人でも、どうしてもギターに特徴的なある種の音が鳴ってしまう。ギターであれば当然鳴ってしまうそうした響きを、Derek Baileyは執拗に回避してみせる。そうした演奏を時に数十分に渡って展開したわけで、これはちょっと恐るべきことだ。彼の演奏はフリー・インプロヴィゼーション(自由即興)と呼ばれることもあるけれども、そうした観点から言うなら、Derek Baileyの音楽は単なる“自由”とは全く異なるように自分には聴こえる。
余談ついでに。Gavin Bryarsは1975年に発表した楽曲「Jesus' Blood Never Failed Me Yet」で、盟友であるDerek Baileyをギタリストとしてフィーチャーしている。(アルバム『The Sinking Of The Titanic(タイタニック号の沈没)』に収録。)そこでDerek Baileyがオーケストラと一緒に普通のギター・コードをポロロンと弾いているのを聴いたときは、思わず感動(?)してしまったものだ。
話を戻そう。Arto Lindsayの音楽にはそうした肩苦しさはまったくない。鉄の意志というよりはもっとしなやかで、もっと詩に近い。本アルバムの後半、彼がギターで弾き語っているライヴ録音に耳を傾けてみてほしい。鼻歌のようなささやきに、青い12弦ギターを叩いて鉱物のようなノイズを載せる。鼻歌と鉱物。音楽と音楽以前。それらが抱擁し合い、衝突し合う。ああ、このような芸術があって、本当によかった。
One sky is orange
Some skies are grey
Or a deep dark blue that gave blue its name
――Arto Lindsay "4 skies"