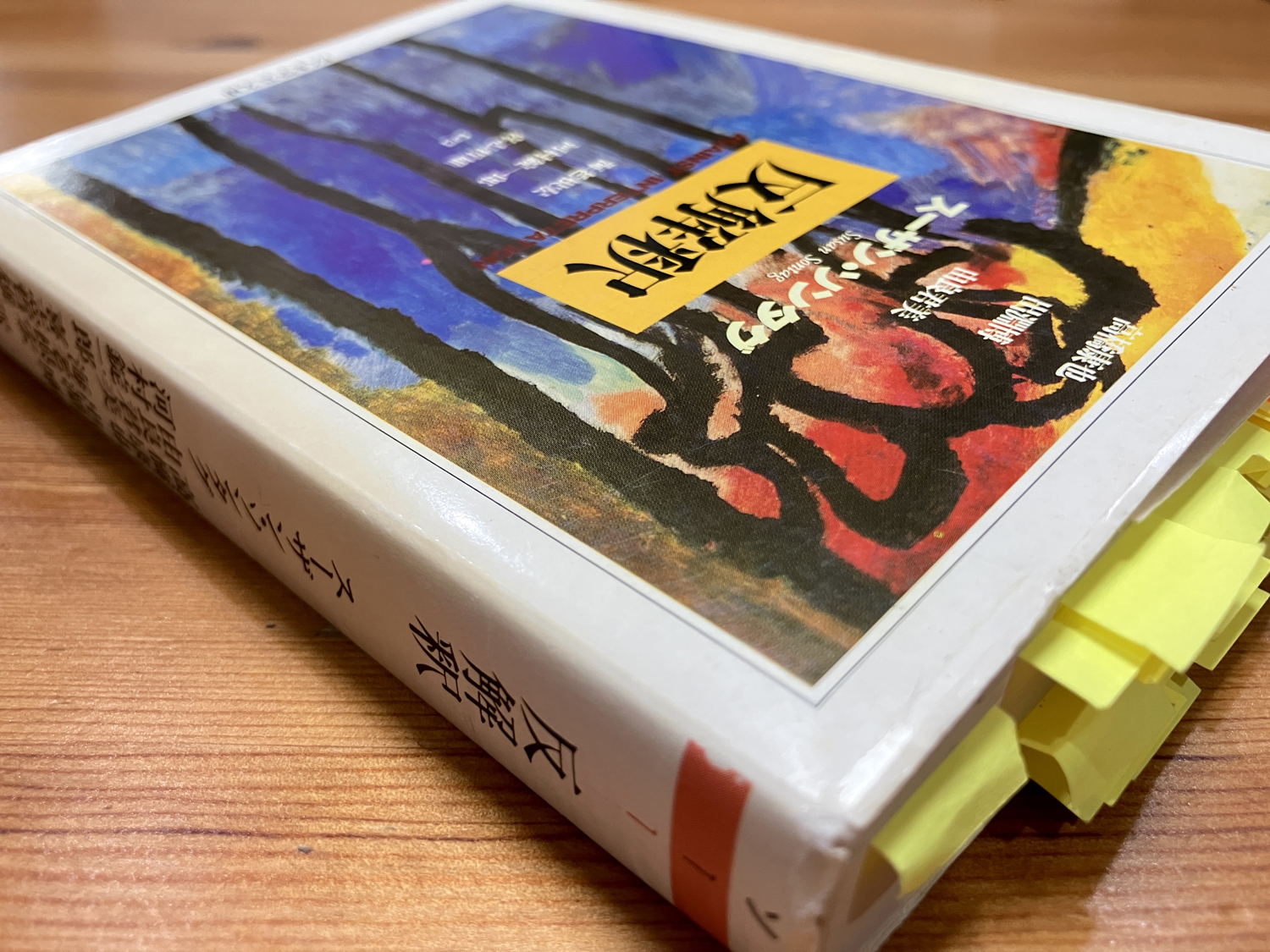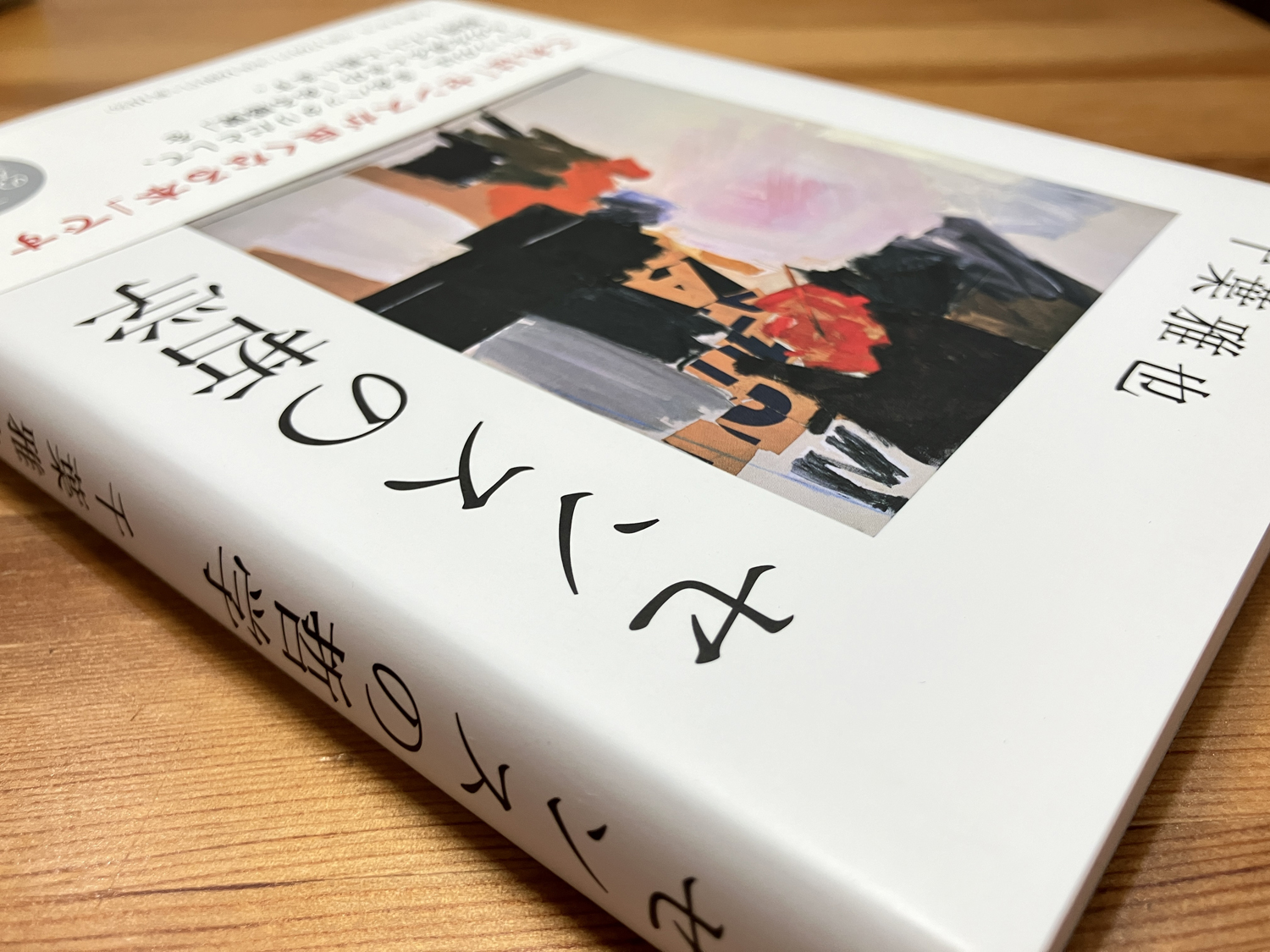文・写真 | コバヤシトシマサ
文芸批評や美術批評など、カルチャーを扱う批評は、その耐用年数が短いのが常だと思う。そもそもカルチャー自体、トレンドに左右される移ろいやすい現象であり、だから批評の寿命はその対象となる作品の寿命に依存する部分が大きい。例えば日本にもアニメや音楽などのサブカルチャーを扱った批評が存在するけれども、そうしたもののうち、50年後にも読まれるものがどれくらいあるだろう。もちろん批評とは時評であって、つまりその時その場での論評であるなら、十分にその意義はあるわけだけれども。
『反解釈』(1996, ちくま学芸文庫)は、スーザン・ソンタグによる批評を集めた論集で、1966年に刊行されたもの。収録された論文には、個別の文芸作品や美術作品を論じたものもあれば、そうした芸術一般における意義や問題を論じたものもある。なにより驚くのは、50年以上前に書かれたこれらの批評が、今なお刺激的に読めてしまうこと。前述したとおり、これはかなり稀なことだと思う。とはいえソンタグが扱っているのは、アルベール・カミュやフランツ・カフカ、あるいはジャン=リュック・ゴダールといった、その筋のビッグネームたちが多く、そうしたチョイスも長らえる要因のひとつではあるだろうけれども。ちなみにソンタグは個別の作家や作品については、躊躇なしにはっきりその良し悪しを断定している。たとえばアルベール・カミュのことはこっぴどく貶しているし、批評家のヴァルター・ベンヤミンにダメ出しをしたりもする。そうした彼女の痛快な口ぶりは、はっきりいってかなりおもしろい。
本書のタイトル「反解釈」は、冒頭に収録された短い論文のタイトルからとられている。反解釈とは読んで字の如く「解釈に抗う」ということ。ソンタグによるなら、現代においては解釈を逃れるかたちの芸術が一般的になっている。そしてそれは歓迎すべきことだと。
解釈からの逃亡は、とりわけ現代絵画に著しい。抽象絵画は通常の意味におけるどんな内容をももつまいとする試みである。内容がない以上、解釈はありえない。
――スーザン・ソンタグ『反解釈』1996, ちくま学芸文庫 p27
ソンタグは芸術表現における“内容”と“様式”というふたつの側面に注目し、優れた芸術はその“様式”によって意義をあらわすとしている。一方、あまりに“内容”にばかり拘泥する態度については、不満を隠さない。この“内容”と“様式”という対立軸は、本書に一貫するソンタグの問題意識となっている。
様式は芸術作品を決定する原理、芸術家の意志の署名である。
――スーザン・ソンタグ『反解釈』1996, ちくま学芸文庫 p62
ソンタグのいう“内容”と“様式”について、少し具体的に見てみよう。それは小説で言うなら「物語」と「文体」と言い換えてもいいだろうし、映画なら「ストーリー」と「画面構成」と言えるだろう。絵画については、「なにが描かれているか」と「色や形がどのように配置されているか」という異なるふたつの見方にも通ずる。小説にしろ映画にしろ美術にしろ、いわゆるエンタメ的ではない実験的な作品ほど、後者に重点が置かれることになる。ソンタグも抽象絵画を例に挙げ、それを「解釈からの逃亡」と評していた。
ここで思い出すのは、千葉雅也『センスの哲学』(2024, 文芸春秋)だ。この本で千葉はロバート・ラウシェンバーグの絵画作品について、まさに「色や形がどのように配置されているか」との観点から論じていた。それはソンタグの議論とも共振する内容で、おそらくソンタグの『反解釈』は、『センスの哲学』に遠く霊感を与えているのだろう。『センスの哲学』を大いに興奮しつつ読んだ者として率直に言うと、実はソンタグの議論より千葉のそれのほうが緻密かつ射程も長い。千葉はあの本で、センスが良くなるための懇切丁寧なガイドをしつつ、最終的にはアンチ・センス = 「センスがない」地平にまで到達してしまう。入門編のガイドを装いつつ、読者をかなりの深淵まで連れて行ってしまうあの本は、千葉雅也の真骨頂といったところだろうか。
“内容”と“様式”の話に戻ろう。ごく一般的にいって、小説はその“内容”によって評価されるのが通例だと思う。物語やそこに含まれる情感、翻ってそれらが指し示す教訓を読み取ること。読書とはそういうものだと考えられていないだろうか。そうではない読書、たとえばウィリアム・バロウズやジェイムズ・ジョイスの実験的な文体を楽しむような読み手は、おそらく少数派だろう。では映画はどうか。ここのところ、映画の“考察”なるものが流行っているそうだ。それは映画の解説を軸としたコンテンツで、多くがネット上で展開されている。そこでは特定の作品について、そのストーリーや背景を深く考察することで、作品が持つ真の意味を読み解くことが目的とされる。「この作品は、つまりこういう意味なのだ」というわけだ。これはまさに“内容”に重きを置いた評論であり、やはり映画においても物語消費が一般的だということになるだろうか。蛇足ついでに付け加えるなら、宇多丸や町山智浩らによる“内容”重視の映画批評に対して、蓮實重彦に代表される(シネフィル的な)“様式”重視の映画批評があるとも言える。だとすると、さしあたり“様式派”は頭数の上ではいくらか分が悪いと言えそうだ。
『反解釈』は1966年に刊行されている。当時はラウシェンバーグらによって抽象表現主義がポップアートへと変遷していった時代であり、ソンタグは小津安二郎やロベール・ブレッソンらを引き合いにしつつ、芸術が持つ様式的な意義について説いた。千葉雅也『センスの哲学』では、ラウシェンバーグの絵画作品の見方が示され、それにより芸術一般を様式的な観点から捉える手ほどきが展開されている。これだけを取り出したなら、ソンタグの50年以上前の議論は現在も引き継がれいるように見える。だとすると“様式”は、今なお芸術の原理たりえているのだろうか。それとも“様式的な芸術”は、小津やブレッソンやラウシェンバーグがそうであるように、かつての時代を反映した古典のようなものに過ぎないのだろうか。