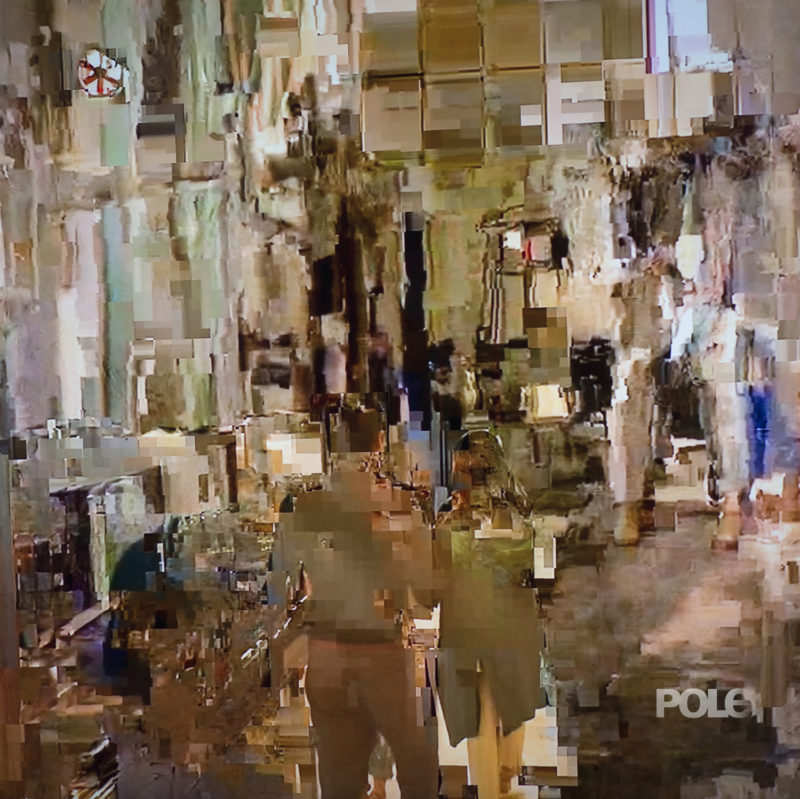失うものが一切ない状態で自分が何をしたいか
どのような経緯でスウェーデン語に辿り着いたのか、翻訳について、ライフスタイル、そして学生時代のことなど、いろいろなことを聞いてきた。
取材・文・写真 | SAI (Ms.Machine) | 2023年1月
――自己紹介をお願いします。
「久山葉子です。スウェーデン語の翻訳家で、エッセイストでもあります」
――スウェーデン語を学ぼうと思ったきっかけは?
「高校生の頃、英語以外も学びたいと思ったので、世界中のいろんな国と交換留学をするAFSという団体でスウェーデンを選んで、すごく田舎の街にホームステイすることになりました。それが本当のスウェーデンというか。妹もAFSで留学したんですけど、全然違って。行ったのは南米・ベネズエラだったんです」
――南米!久山さんの著書『スウェーデンの保育園に待機児童はいない』に妹さんが「治安の悪い国に長く暮らしていた」と書いてありましたが、南米だったんですね!
「そうそう(笑)」
――どこなんだろう、って読みながら思っていました。
「無事に帰ってきたんですけど、大人になってからもメキシコに留学したり。私とは正反対の地域に行ってました。今は、日本に長いこといますね。私がスウェーデンを選んだのは、SAIさんだから言うんですけど、高校の頃に、スウェーデンのロックバンドが流行っていて。特に、髪の毛の長いお兄ちゃんたちのバンドが好きで(笑)」
――ええ!そうだったんですね!
「EUROPEっていうバンドがいて、ヴォーカルの人がカッコいいと思っていて。留学したら道で会えるかも、みたいな(笑)」
――あはは(笑)。かわいい理由ですね。
「スウェーデン語を勉強したら話せるかな~、みたいな。日本では英語を通じて紹介されているヴォーカルのJoey Tempestっていう人は、Joakim(ヨアキム)っていう本名で。だからスウェーデンではJocke(ヨッケ)っていうあだ名で呼ばれているんですよね(笑)」
――その時代は、どういった音楽が流行っていましたか?
「あとはROXETTEとか、THE CARDIGANSとか」
――ABBAも流行っていましたか?
「ABBAは、うちの両親の時代ですね~。去年再結成していましたね」
――ちなみに、高校生のころは何部だったんですか?
「音楽がすごく好きで、ピアノを習っていました。本当はオーケストラとかやってみたかったんですけど、学校はコーラス部かギター部しかない感じだったので、ギター部に入って」
――そこから紐解くと、久山さんは文系なんですね。
「めっちゃ文系です。子供の頃から本が好きで。昔はスマホもiPadもなくて、友達と遊ぶより本を読んでいたほうが楽しいくらいの感じ。インターネットもなかったし、つまんないじゃん(笑)。中学受験をさせたがった親が、モチベーションとして“『パディントン』とか翻訳した松岡享子さんというかたが卒業生の大学に行けるよ”ってそそのかすくらい(笑)、本読むのが昔から好きでした。小学校のときに塾に行って勉強して、幸いその中学に入れたので、そこからはあまり勉強もしていなくて(笑)。大学受験もなかったので、代わりに留学するというコースを選びました。そのときから、日本に帰ってきたら大学は英文科に進むつもりでした」
――久山さんのご両親はどんなかたなんでしょう?
「うちの親は、ちょっと変わっていて……。母はあの世代にしては珍しく、大学でアメリカに留学していて。私が小さい頃は“アメリカはすごい”みたいなことをよく言っていたかな。まあ、今はもう言いませんけど(笑)。父(久山 敦)は植物関係の仕事をしていて」
――だからお名前が“葉子”さん、なんですか!
「そうそう(笑)。大阪にある、『咲くやこの花館』という植物園で働いていました。植物オタクなんだよね。『趣味の園芸』っていう、NHKの雑誌や番組にもよく出てますし、関西の『探偵!ナイトスクープ』っていう番組では、植物関係の質問のときは父が呼ばれて解説する、みたいな。その番組はみんな観てるから、“昨日お父さん出てたね”って学校で言われたり(笑)」
――研究熱心なのは、ご両親譲りなんですね。
「その2人が結婚してすぐ、イギリスのキュー植物園(Kew Gardens | 王立植物園)で実習生として1年働いていて、帰りにドイツでレトロなキャンピングカーを買って日本に帰ってきたみたい。1年かけてヨーロッパをぐるっと回ってから、下のほう……今は危なくて通れないような、イランとかイラクを通って」
――素敵です……!ご両親は冒険家なタイプでもあるんですね。
「そう。でも、あの時代って、けっこうそういう若者が多かったんですよ」
――ご両親は、おいくつくらいか、お伺いしてもよろしいですか?
「今76歳……SAIさんの知り合いにはあまりいない世代かな(笑)。あの頃は、海外に行った若者が多かったと思う。北欧に何十年も住んでいて、帰ってきて日本でレストランをやっている人とか」
――そうなんですね!全然知らなかったです。
「そうそう。そういう時代だったんだよね。そんな両親です(笑)。お父さんから、今年ヨーロッパに行くからよろしくって連絡があって。2ヶ月行くからって。ちょうど50年前の旅を再現したいんだって。だけど2ヶ月って(笑)。めちゃ心配で。レンタカーを借りて、ギリシャから始めて北欧まで上がるんだって。心配だからついていったほうがいいのかな、老人を2人で行かせるのは危険すぎる、って思って。私の想像を超えてる(笑)」
――めちゃくちゃ元気ですね!素敵です。そういえば、久山さんのパートナーのご両親はローマで育ったと著書に書いてありましたね。
「そうそう、その2人も同世代なんです。東京で大学院生だったときに、お父さんがイタリアで映画監督になるって言ってイタリアに行っちゃったり。やっぱり、そういう人が多かったんですよ。その時代。映画監督には全然なれなかったんだけど、その後、日本は景気が良くて、お金持ちがいっぱいローマに観光に来るから、ガイドの仕事がたくさんあったみたいです。お母さんもすぐ追いかけてきて、2人で問題なく暮らしていて。お姉さんと夫がうまれて、育って。今に至ります」
――久山さんがスウェーデンに移住されたきっかけは?
「夫がイタリア育ちで、子供ができたときに日本での子育てに違和感を感じていたようなんです。その頃、夫が東京にあるスウェーデンの会社で働いていたので、本社のほうに行きたいと言ったら、すぐにOKしてもらえて。あっという間に決まってしまいましたね(笑)」
――久山さんの著書からも、急展開でいろいろなことが決まったのだと感じました。
「そうなんですよ。まさか実現するとは思っていなくて。適当に“うんうん”とか言っていたんですけど(笑)、えっ、まじで行くの?みたいな」
――あはは(笑)。人生の転機という感じですよね。
「大反対とかはしていなかったんですよ、移住なんて絶対無理だろうと思っていたので(笑)。だけど後に引けなくなってしまって、もう。最初は不安でいっぱいでした。日本での仕事を辞めて来ているので、失業者になっちゃうし、友達も誰もいないし、本当にゼロからの再出発っていう感じで。だけど、逆にゼロから出発している人のほうが好きなことができるのかな、って思ったりして。東京にいたら、仕事を辞めてまで翻訳をやろうとは思わなかったと思うんですよ。本当に失うものが一切ない状態で自分が何をしたいか考えたときに、本と語学が好きだったので、翻訳とかをやってみたいな、って」
――キャリアが一旦まっさらになったり、環境が変わるのって、変化を自ら求めたり、パートナーが変化を厭わない人ではない限り、なかなかないですよね。
「そうですよね」
――同じような境遇のかたとお会いしたことってありますか?
「日本人はスウェーデンにたくさん住んでいるのですが、ほとんどスウェーデン人と結婚して来ているっていう感じです。スウェーデンに興味があってきた人もいますし、全然興味なかったけど、たまたまスウェーデン人と結婚して、しかたなくっていう人もたくさんいます。2組だけ、夫婦共にスウェーデンに住みたくて、えいやっと来た人は知っています」
――吉澤智哉さんですかね?
「そうそう、彼はスウェーデンで会社勤めをしていて、奥さんは保育園に勤めていらっしゃいます。彼女は、スウェーデンの保育について発信していて。お2人ともは、リアルで会ったことはないけど、SNSではいろいろやりとりしていますね」
――2017年頃から、スウェーデンについていろいろ調べているんですけど、日本人ご夫婦で移住されたかたってなかなかいなくて。久山さんのシチュエーションはレアなんだなあ、って改めて思っていました。
「珍しいですよね。やっぱり、移住したいっていう希望を持っている人はいると思いますが、家族で来ようってなると、正社員の労働ビザがないとスウェーデンに移住できません。かといって日本で働いている人がスウェーデンの会社で雇用されるのは難しいので。吉澤さんは専門的な技術力があったから転職できたのではないでしょうか。なかなかできる人はいないですよね」
――久山さんはこれまでどんなお仕事を経験されているのですか?
「大学を出た後、スウェーデンに関連のある仕事をしたくて、最初は北欧に行くツアーの旅行会社に勤めていました。それから東京に来て、スウェーデン大使館の商務部という、ビジネス・コンサルティングをする部署で働いて」
――留学後も北欧に縁のあるお仕事をされていたのですね。翻訳のお仕事として、大学で学んだ英語ではなく、スウェーデン語を選ばれたのは?
「スウェーデン語のほうが翻訳している人が少ないっていうのが、ひとつのメリットでした。要はライバルが少ない。ニッチなものは仕事量もそんなに多くないけど、ライバルも少ないので、自分ひとりぶんくらいの仕事はある。逆に英語とかだと、できる人がたくさんいるし、すごい競争率で。なかなか本を1冊自分で訳すチャンスっていうのは、巡って来ないと思うので。そういう意味では、ニッチな、あまり人がやっていないことをやるのもひとつの手段ですね。スウェーデン語は、高校の留学で基礎はやったんですけど、その後に東京でスウェーデン語学校にも行っていたんです」
――そうだったんですね!六本木にある学校ですよね。
「そうそう。東京スウェーデン語学校の速水 望先生が、大使館の広報部にもずっと勤めている人で、とてもお世話になりました。望先生には足を向けて寝られないです」
――スウェーデン語を学ぶっていうのは、めちゃくちゃニッチですよね。
「ニッチですね~(笑)」
――そうですよね(笑)。実は、スウェーデン語学校のクリスマス・パーティに行ったことがあるのですが、そのときに、スウェーデン語にキュンとくる心をこんなにわかってくれる人がいるんだ!って感動しました。
「新旧合わせると、生徒さんがけっこういますよね。私は、たまたま東京に引っ越したときにその学校が開校して。一期生だったんです。それから5年くらい勉強して。仲間がいるのって大事ですよね。留学から帰ってきたときより、もうちょっとできるようになっていた。日本だから、特に読み書きができるようになったかな。新聞記事とかを読んだりしていました。その状態でスウェーデンに移住して。私の運が良かったのは、その頃『ミレニアム』(スティーグ・ラーソン著)っていうミステリーのシリーズが、全世界ですっごい流行っていたときで。『ミレニアム』は日本でも訳されていたんですけど、それ以外のミステリーもどんどんスウェーデンから出てきて、日本の出版社も出したがっていたから、ちょうどすごく仕事があるときで、軌道に乗って、という感じでした」
映画『ドラゴン・タトゥーの女』(2011, デヴィッド・フィンチャー監督)は、『ミレニアム1』が原作。
――『ミレニアム』は、翻訳家のヘレンハルメ美穂さんも翻訳されているのでしょうか?
「そうそう、あれはちょっと複雑で……。なるべく早く出したいというのがあって、必ず2人で訳していました。5作目と6作目は私が下訳でざっと訳したものの全体を、ヘレンハルメさんが揃えてくださるという手法を取りました。そういうことは、よっぽど売れる作品じゃないとあまりないけどね」
――スウェーデン語から英語に訳して、そこから日本語に訳すのでしょうか?
「スウェーデン語から直接訳せる人たちが仕事が詰まっていてお断りすると、英語やドイツ語の訳者さんが英語やドイツ語に訳されたものから重訳することもあります。すごくきっちりした出版社だったら、原語と突き合わせてくださいっていう仕事もある。英語経由で訳しているから、できあがった日本語とスウェーデン語の間がかけ離れちゃっていないか、っていう」
――なるほど。そういうお仕事もあるんですね。
「あとは、人の名前とか地名とかって、英語の訳者さんは読めないじゃない。スウェーデン語独特の発音なので。そういった固有名詞だけリストで送られてきて、カタカナに直すっていう仕事もあるんですよ」
――スウェーデン語の地名って読みにくいですよね。
「英語読みするとだいぶ違っちゃう」
――“ヨーテボリ(Göteborg)”も“G”から始まりますしね。
「そうそうそう。“ヨー”なんだよね。英語圏で、“なんとかバーグ”さんっていう名前の人がけっこういるけど、スウェーデン語では“なんとかベリー”って読むから。それが“バーグ”になってたら間違いというか。思い切りアメリカ英語みたいに聞こえる(笑)」
――翻訳家のかたは、コミュニティといいますか、繋がりはあるんでしょうか?
「いろいろだと思う。英語はけっこう、偉い先生たちのお弟子さんみたいな感じで、グループとか横の繋がりがあって。イベントとかも多いから、そういうところでも繋がると思うんだけど。北欧語はそれが全然なかったんですけど、枇谷(玲子)さんっていう、ノルウェー語とデンマーク語の翻訳をしている翻訳者さんがみんなに声かけてくれて。北欧書籍翻訳家の会という形で何回かイベントをやったりしました。普段はゆるく繋がって、ブログを2週間に一度書いているっていう感じかな。それを見て、他の言語のコミュニティのかたからは羨ましがられたりします。“〇〇語もそういうのがあったらいいのに!”みたいな。みんな普段はひとりでやってる感じだから、北欧語はすごい!って言われるんだけど、それは全部枇谷さんのおかげ」
――スウェーデンで生活していて、良かったこと、大変なことを教えてください。
「みんなが家族優先で生きているから、普通に仕事しながら家族も大切にできるっていうのが楽でした。大変なことは……暗い。冬が暗い(笑)」
――今、ちょうどすごく暗いですよね。
「そうそう。12月、1月は一番暗いですね。それは、年末年始に日本に帰省することでなんとか乗り切っています」
――ビタミンEとか飲んでないと、って言いますもんね。
「あっ、Dだね(笑)」
――あ、ビタミンDですね(笑)。
「それはサプリで冬はみんな飲んでるんじゃないかな、太陽があまり出ないから。SAIさんがスウェーデンに行ったときは冬でしたか?」
――はい。夏に行ったことがなくて。12月、1月に行きました。しかも、キルナという場所で。
「あんなところに!すごい!北極圏だ」
――すごかったですね。日が暮れるのが早い!みたいな。
「ほぼ真っ暗な時期もあるよね。あそこまでいくと。旅行会社時代にアイスホテルを扱っていたことがあるけれど、すごく人気がありますよね。結婚式でも人気があるし。ハネムーンで行って、オーロラが見える、みたいな。夏は夏で別世界だよね」
――コロナ禍はどうでしたか?
「パンデミックの間に日本に来られなかったのはすごく大変だったかな。ちょっと予測していなかった展開っていうか。お金さえ出せば帰れるって思っていたから、そうでなくなった日が来たっていうのにびっくりして」
――海外との隔たりみたいなのをコロナ禍ですごく感じましたね。
「しかも日本は、最後までいろいろ規制とかがあって、大変だったよね。それを経験したから、やりたいことがあったらすぐやらなきゃって、けっこうみんな思うようになったんじゃないかな。会社を辞める人とかも増えた気がする。今しかできないこと。“いつか、いつか”って思って、またこんなことになったら、チャンスを逃しますからね。そういう意味では、優先順位がわかりやすくなった」
――そうですよね。それでは最後に、今年の抱負を教えてください。
「今年の抱負は親孝行で、どこまでも望みを叶えてあげたい」
――親孝行、大事ですよね。私もそう思います。
「ね。元気なうちにやっておきたいことって、いっぱいあるし。あと、なんとなく自分の人生って12年周期で来ている気がして。今の生活になってちょうど12年だから、今年から次の12年は全然違う方向に変えようかな、と思っていて。まだどうなるかわからないし、決まってないんだけど(笑)。そのためにちょっと動き出そうかな、っていう感じですかね。SAIさんの今年の抱負とか、予定とかはありますか?」
――今年、念願の夏のスウェーデンに行く予定があります。
「ついに夏の北欧!」
――海外でライヴするために、ソロ・プロジェクトを進めてきたので、がんばろうと思います。
「素敵。スウェーデンは、ストックホルムに行く予定ですか?」
――はい。あと、夏至祭の時期とちょうどかぶるので、ダーラナ地方も行けたらと思っています。
「いいね~。けっこう日本人で住んでるかたがいますね。大学があって、日本語学科が大きいから。来るとき、ぜひ教えてください。私がギリシャとかにいなければ会いましょう(笑)」
――もちろんです!楽しみにしています。
 ■ 2019年6月20日(木)発売
■ 2019年6月20日(木)発売
久山葉子 著・文
『スウェーデンの保育園に待機児童はいない 移住して分かった子育てに優しい社会の暮らし』
東京創元社 | 1,500円 + 税
B6判 | 272頁
ISBN 978-4-488-02799-5
1歳の娘の理想の子育て環境を求めて、9年前、家族3人で東京からスウェーデンへ移住した著者。スウェーデンの保育園に持っていくものは? 育児休暇は何日とれて、その間のお給料は?スウェーデンのママたちに教わった手抜きメニューって?実際に日本から移住した著者だから書ける、スウェーデンで暮らして良かったところ、悪かったところ。無理なく共働きで子育てできるとされる国での移住・子育て・日常生活を綴った、楽しく気軽に読めるエッセイ。