蓋を開けてみたら、意外と平気
取材・文 | 鈴木喜之 | 2020年10月
通訳 | 竹澤彩子
――あなたは、1969年、ニュージャージーの生まれだそうですね。子供時代は、どういう音楽環境に育ったのですか?
「最初に好きになったのはTHE MONKEESで、5歳くらいだったかな。その後8歳くらいのときに友達の影響でTHE BEATLESが好きになって……両親は別にロック好きってわけじゃなかったけど、一応THE BEATLESのレコードくらいは持ってたから、それを友達と一緒に聴いたり、あとはCHEAP TRICK、KISS、VAN HALENとかがお気に入りだった。自分でもギターをやりたいな、って思い始めたのは10歳くらいだね。それで両親にエレキギターをねだったら、父が誕生日に買ってきてくれたのはギターじゃなくてベースだった。そのほうが競争率低いだろうからって(笑)。そうして友達とバンドを始め、自分はベース担当で、CHEAP TRICKだとか、さっき名前を挙げたバンドなんかの曲をやってたんだ。ベースの弾きかたなんてロクに知らないくせに、どうやってCHEAP TRICKの曲をカヴァーしていたのか、今となっては謎なんだけど、本人たちはけっこうその気になってたんだよね(笑)。初心者のガキの分際で、なぜかLED ZEPPELINの曲に挑戦してみたり(笑)。中学時代はRUSHにも相当ハマってたなあ。その後14歳ぐらいからスケートボードに熱中し始めて、専門誌『Thrasher Magazine』を愛読するようになったんだけど、その周辺からBUTTHOLE SURFERSと出会って、脳味噌がブッ飛ぶくらい衝撃を受けたんだ。BUTTHOLE SURFERSを聴いて、それまでの価値観が一気にひっくり返り、そこからはもうRUSHなんか聴いてられるかよって(笑)。その頃からベースじゃなくて、ギターを弾くようになった。まあ、それくらいの年頃なら普通に音楽やバンドに夢中になるんだろうけど、自分はその中でも相当ハマってたほうだね。やっぱりBUTTHOLE SURFERSですべてが変わった」
――当時のあなたにとってBUTTHOLE SURFERSの何がそんなに特別だったんですか?
「いや、わかんない、ていうか全部だよね。曲の伝えかたにしろ、楽しみかたにしろ、影響力とか、何もかもが自分がそれまで知ってるバンドとは違っていて、ワイルドで、まさに目からウロコ。BUTTHOLE SURFERSもそうだけど、R.E.M.の曲と出会ったときなんかも、まだ10代前半の自分にとっては、ああ、こんな世界もあるのかって感じで新鮮だった。RUSHみたいな派手でわかりやすいロックよりも、魅力的に映ったんだ。今は一周してRUSHも全部ひっくるめて好きだけど(笑)。思春期にありがちなパターンで、新しいものに出会って衝撃を受け、それまで自分の好きだったものを全否定して、次に新しいものに出会って衝撃を受けて、またそれまでのものを否定して、っていうのを繰り返すうちに、ぐるっと廻って振り出しに戻る(笑)。中学の頃RUSHにハマり、その後RUSHなんてダサいってなって、散々いろんなバンドに夢中になっては否定して、やがて17、8歳の頃には、知られているバンドは一通り網羅したんじゃないかな。1980年代後半の10代のロック、それもインディ好きの御多分に漏れず、自分もHÜSKER DÜとか、MINUTEMENとか、SONIC YOUTHを崇拝してた。そして高校のとき友達とSKUNKっていうバンドを組んで、高校生の分際でSONIC YOUTHの前座をやらせてもらったり」
――SKUNKが所属したTwin/Tone Records、USインディペンデント・ロックの黎明期を担った重要レーベルで、THE REPLACEMENTSや SOUL ASYLUMなどをリリースしていました。当時あなたの周辺にあったシーンはどんな様子だったのか聞かせてください。
「良い質問だね。自分はTHE REPLACEMENTSの大ファンだったし、Twin/Toneと契約できるっていうんでマックス盛り上がってたんだけど、他のメンバーはわりとアッサリしてて(笑)。ただ、やっぱり興奮したよなあ……Twin/Toneって、もともとはミネアポリス出身バンド限定で扱ってたんだけど、他の地域のバンドも扱うようになった時期に、運良く自分たちにも声がかかったんだ。ちょうど同時期にWEENなんかも契約が決まって。実は、SKUNKに興味を持ったTwin/ToneのスタッフがSKUNKのライヴを観に来てくれることになったんだけど、それがWEENの前座でね。WEENの前知識ゼロだったTwin/Toneスタッフが彼らを初めて観て、SKUNKそっちのけで契約をその場で即決してた(笑)。恨み節とかじゃ全然なくて、俺が当時の担当者でも、SKUNKよりWEENを取るよ(笑)。そんな感じで、WEEN、SKUNK、BABES IN TOYLAND、JAYHAWKSの作品が同時期にTwin/Toneから出てるんだから、雑多もいいところ(笑)……今思い出したけど、THE COUP DE GRACEっていうメタル・バンドも同期だし、あれもいいバンドだったな。とりあえず今挙げたバンドとは、ジャンルもスタイルもバラバラなのに全部対バンしてる(笑)。ある意味かなりおもしろい実験期間ではあったよ。SKUNKに関しては、確実に光るものもあったはずなのに、なかなかそれに見合うだけの評価をされなかった(笑)。まだガキだったこともあって、試行錯誤しながらも演奏自体は悪くなかったし、エネルギーが半端なかったんだけどね」
――SKUNKでは、IRON MAIDENの「Wrathchild」をカヴァーしていましたが、ブリティッシュ・ヘヴィメタルとかも聴いていたのでしょうか?
「そうそうそう。普通にIRON MAIDENの大ファンだった。ただ、当時はIRON MAIDENなんてダサいっていう空気だったんで、“いや、俺たちはIRON MAIDENいいと思うぜ?”みたいなスタンスをあえて採る自己主張をしてた(笑)。いや、実際、IRON MAIDENが好きだったし、いまだにファンだしさ。SKUNKが残した最大の功績は、もしかするとあのIRON MAIDENカヴァーかもしれない(笑)。当時のあの空気感で、IRON MAIDENのカヴァーをやるなんて正気か?って感じだったからね(笑)。とあるパーティで、友達が持参したIRON MAIDENのカセットテープをかけたら、ホストが強制的に止めたんで、取っ組み合いの喧嘩が始まって、通りにまで出る大騒ぎに発展してさ。たかがパーティでIRON MAIDENの曲をかけようとしたヤツがいたってだけで(笑)」
――その後、1993年にニューヨークに移ってCHAVEZを結成することになった経緯を教えてください。
「もともと母方の実家がニューヨークなんで、子供の頃から頻繁に行き来はしていて、15歳になる頃にはCBGBにライヴを観に行ったりしてたんだけど、93年にひとりで移住することに決めたんだ。自分はニューヨークで暮らすもんだと思ってたし、行かない理由が見当たらなかった(笑)。大学を中退してニュージャージーに戻り、しばらく悶々とした日々を送ってたときに、CMJで仕事を手伝ってくれないか?って誘われてニューヨークに移ったんだよね。当時CMJのライターだったデブラっていう人が、SKUNK時代からよくしてくれていて、俺が大学を中退して職探しをしてるのを人づてで聞いたらしくて。彼女の紹介でCMJで働かせてもらえることになったんだ。最初は友達とかデブラのところに居候させてもらいながら職場に通って……当時の友達とは今でも付き合いが続いてるから、改めて考えると貴重なご縁だよな。まあ、そういうわけでイースト・ヴィレッジで働き出して、わりとすぐ自活できるまでにはなったんだ。ニューヨークに越してからは、ライヴに通ったり、常に音楽に囲まれた生活ではあったけど、自分で音楽をやることに関しては、半ば諦めかけてた時期ではあった……SKUNKの一件で心が折れてたし、ニューヨークで新しく知り合った人間は、俺が音楽をやっていることも知らなかったりして、自分が本当は何をしたいのかわからなくなってたんだよね。そしたらDavid Reidに“俺のバンドでベースを弾かない?”って誘われて、おもしろそうだったから手伝うことにして、それがまた新たな気持ちで音楽を始めるきっかけになったんだ。まだ21歳とか22歳くらいだったけど、SKUNKが終わると同時に、自分も終わった気がしてたから。誘われたそのバンドがWIDERとなり、カセットテープで発表した曲が話題を集めて、ライヴにもちょくちょく呼ばれるようになった。そこで後にCHAVEZを結成することになるJames Loと出会ったんだ」
――CHAVEZが残した2枚のアルバム『Gone Glimmering』と『Ride the Fader』は、現在も高く評価され続けています。Bob Weston、Bryce Goggin、John Agnelloといった人たちによって共同プロデュースされていますが、彼らとの仕事はいかがでしたか?
「今言ったプロデューサーもそうなんだけど、CHAVEZに関しては、いろんなラッキーが重なってね。そもそもJames Loと出会えたことからしてそうだし。彼のことはSWANSやLIVE SKULL繋がりで昔から知っていて、自分の中ではニューヨークのロック界の重鎮みたいな畏れ多い存在というか、実際、おっかなかった(笑)。Clay Tarverについてもそう。俺はもともと、ClayがCHAVEZの前にやっていたBULLET LAVOLTAっていうバンドのローディだったんだ。だから、憧れの先輩みたいな人たちに声をかけてもらっただけでも有頂天で(笑)、こっちも気合い十分で臨んだよ。ただ、JamesにしろClayにしろ、当時の自分より遥かにレコーディングの経験が豊富だったから、とりあえず先輩に従うって感じだった。彼らの好みや、目指している方向性は自分なりに熟知してたつもりだし(笑)、2人とも自分なりのポリシーがハッキリしてた人なんでね(笑)。自分はまだ青二才だったから、喜んで2人の後についていった。例えばライヴをやるにしても、それをやるだけの意義なり理由なりが必要で、気に入らない曲は一切やらないし、1曲1音が勝負っていう、見事な徹底ぶりだったよ。とにかく、やりたいことが常に明確でね。かつてClayは“一筋縄ではいかないバンドをやりたいんだ”って言っててさ。当時は何を言ってるのかさっぱりわからなかったけど、なんかカッコいいなあって(笑)。CHAVEZとしてアルバムを作る段階になったとき、誰が言い出したのかは忘れたけど、片っ端からいろんなスタジオを転々として、それぞれのスタジオ付きの優秀なエンジニアに協力してもらおう、ということになったんだ。予算が降りるし、せっかくだからってことで。James Loは色んなアイディアを持っている人で、しかも適応力があるというか、スタジオやエンジニアが変わっても、それぞれのやりかたにスーッと馴染んでいけるんだ。状況的に、ひとつのスタジオに長く留まって時間をかけて作る余裕もなかったから、複数のスタジオに分けて録るほうが効率的だったし、限られた時間の中で全部を出さざるを得ない状況なのもかえってよかった。しかも、今言ったような最高のプロデューサーと仕事する機会に恵まれて……Bob Westonとは昔からの友達だけど、彼と一緒に仕事できたのもよかったね。彼らとアルバムを作れたことは自分にとって素晴らしい財産だ。当時はまだレコーディングについての知識もほとんどなかったから、絶対ヘマしちゃいけないっていうプレッシャーがあったけど、そこに外部の人が入ることで、レコーディングが何倍も楽しくなったよ。良い思い出だし、不平不満は一切ないし、多くのことを学ばせてもらった」
――CHAVEZが契約したMatador Recordsもまた、最重要USインディ・レーベルのひとつです。かつてはCat Power、最近ではStephen Malkmusの作品に参加していることなどからもわかる通り、このレーベルとはずっと縁の深い関係になっているようですが、Matadorとの関係性や、彼らの業績をどのように評価しているかについて話してもらえますか。
「昔からものすごく評価してるよ。レーベルとしての存在意義だとか、確固たるヴィジョンの下に運営している姿勢にも感銘を受けた。90年代にMatadorと繋がってるということは、世界中のクールな情報にアクセスできるようになったっていうこと。スタッフもみんな、レコード・コレクターだったり、自分でも作品を発表してたり、筋金入りの音楽ファンばかりだったからね。Matador周辺の人たちと普通に接しているだけで、アートやカルチャーに関する知識が一気に広がったよ。アート部門のMark Oとか……彼はCHAVEZの“Break Up Your Band”のMVにもバンドを紹介する役で登場してくれてるけど、知識とセンスの塊みたいな人でさ。CHAVEZのアートワークも担当してもらったんだけど、最高だしね。プロダクト・マネージャーのエスターも、一見気難し屋なんだけど、まさに目利きの中の目利きって感じだ。Matadorで、その時代に一番キてるアーティストだけじゃなく、古今東西の最高にクールなアートや音楽を知ることができたし、どれだけたくさんの新しい映画なり音楽なり文学に開眼したかわかららないよ。紹介してくれるもの全部がツボすぎた(笑)。レコードの売り上げ枚数だけで言ったら、メジャーの足元にも及ばないかもしれないけど、Matadorが音楽ファンやカルチャーに与えてきた影響は計りしれないよね。しかも、いまだに名門レーベルとして存続して、広く認知されてるんだから、どれだけものすごいことか。今でも彼らと仕事をしてるって、考えてみたらすごいことだよな……いや、マジで貴重なご縁だよ。Matadorって、メインストリームでは見落とされがちなアーティストを次世代にまで繋いでくれるし……例えばPRETTY THINGSみたいな。つい最近ヴォーカルが亡くなったから、ここのところPRETTY THINGSのことをよく考えてるんだ。CHAVEZ全員がPRETTY THINGSの大ファンで、あんなふうに10年後、20年後に“うわ、マジでこんなすごいバンドがこの世に存在してたのか”って発掘してもらえたらいいね、って話してたんだよ」
――まさに、そうなったと思います。さて、2003年にはBilly CorganのZWANに参加しますが、もしかして、あのバンドにはあまり良い思い出はなかったりしますか?
「あー……まあ、そこはご想像にお任せしますってことで!」
――(笑)。ちなみに、現PIXIESのPaz Lenchantinにインタビューしたときは「ZWANの解散については新聞で知って驚いたけど、兄弟の急死でそれどころじゃなかった」と言っていました。あなたにとっては、どんな終わり方だったのでしょう?もし仮に、また一緒にやりたいと言われたらどうします?
「それもご想像にお任せします!」
――えーっと(笑)、他に何かあれば……。
「ん?今何か言った?」
――想像にお任せということで(笑)。その頃から、他者のプロジェクトにコラボレーター的な立場で参加してゆくキャリアを歩んでいるように思えますが、これは、バンドで活動するよりも、そういう形態の方が自分には向いていると意識するようになったからなのでしょうか?
「言われてみれば、そうなのかもね。そもそも自分はプロのミュージシャンになるつもりはなかったのに、気がつけば30代(笑)。ちょうどその頃、あちこちから声をかけてもらえるようになって……まあ、その一件の後、また振り出しに戻ったような心境で、この先どうしたらいいのかわからない状態のときに、友人のWill Oldhamが一緒にライヴをやらないかって声をかけてくれたんだ。そこからまた少しずつ道が開けて……しかも、最初に声をかけてくれたときは、Willが自腹を切ってライヴを企画してくれてね。ロンドンで、自分たち2人の共演っていう特別なかたちにして、それ用に曲を作ろうって言ってくれてさ。最終的には共作アルバム(『Superwolf』2005, Domino | Drag City)まで出すことになった。そこからRick Rubinと繋がりができて、そのうち、まさか共演することになるとは思ってもなかった面々も含め、いろんな人たちからレコーディングに呼ばるようになり、この先もなんとかやっていけるんじゃないかと希望が持てるようになったんだよ」
――なるほど。
「振り返ってみると毎回そのパターンだね。SKUNKがポシャって、しばらくしてバンド活動を再開したときにも、“ベースをやらないか?”って言われたから、“ああ、いいよ”って感じだったな(笑)。ただ、WillやRickとの仕事を通じて、自分は意外にこういうことが得意なんじゃないかっていうことに気づいて……実際、自分でもやっていて楽しかったし、手応えみたいなものを感じてた。とくに即興に関しては、ものすごいプレッシャーがかかる状況にも強いというか、普通だったら自分からわざわざキツい場面に飛び込んでいこうなんて思わないだろうけど、蓋を開けてみたら案外と平気なもんでね。実際、いろんな人の作品に呼ばれるようになって、毎回そういう状況で演奏してるな、って後から気づいたんだ。どんなに難しい現場だろうが、その場で臨機応変に対処して最大限の結果を出すって、セッション・ミュージシャンに求められる必須能力だよ。実際、前日に初めて聴かされた曲に合わせて演奏するなんて、ほぼ毎度のことだし。俺は楽譜が読めないから、普通だったら物怖じするところなんだろうけど、意外と平気。むしろそういう状況を楽しんじゃってたりするんだよ(笑)。そこは自分でも気がつかなかった才能で、気づけただけでもラッキーだった。Will Oldhamとの共演や、Rick Rubinに仕事を任せてもらったことで、業界での信用度も上がったしね。人の作品に参加するときは、常にギヴ & テイクの関係、単なる雇われじゃなくて、俺の意志やスタイルを理解、尊重してもらった上でやるから、こっちも演奏していて楽しいわけ。もともと人に会うのが好きで、誰かと一緒にプレイしたり、アイディアを形にする手助けをするのが好きなんだろうね」
――Dave GrohlのPROBOTも印象深い作品でした。あのプロジェクトには、どのようなかたちで関わったのでしょうか。
「彼とはNIRVANA時代からの知り合いで、お互いの作品をずっとフォローしてたんだよね。当時DaveはFOO FIGHTERSで行き詰まっていて、何か違うことを計画してた。それで“こういうことを考えてるんだけど……”って相談してくれて、自分もそのアイディアに乗ったんだ。アイディア自体が最高だし、めちゃくちゃ楽しかったよ。これまたいつものパターンで、自分から提案したわけじゃないけど、人に誘われてやってみたら、なんだかよくわからないけど、おもしろい展開になったよ(笑)。このプロジェクトでの俺の役割としては、ウィッシュリストに挙がっている候補者のコンタクト先を探して、協力してもらうよう頼むことだった。これに関しては、すべて友人のKevin Sharp(BRUTAL TRUTH)のおかげなんだ。彼はアンダーグラウンド・メタル・シーンの顔役みたいな存在だから、VENOMのCronosだの、King Diamondといったメタル界の伝説的な人物と一発で繋がることができた。俺の仕事は、ただ電話口で“音源を送るから、それに合わせてヴォーカルをつけてくれれば、こっちで完成させますんで”とかなんとか、プロジェクトの主旨について説明するだけでよかったんだ。いやあ、あれは最高だったね。めちゃくちゃ楽しかったよ。夢のような人たちと共演できて、ただひたすら興奮しまくって、しかも楽勝だった……あれから何年経つんだけ?たしか2000年とか、それくらいだったかな。ちょうど30代に差し掛かろうってときに、そんなお遊びをやってた(笑)」
――それから、QUEENS OF THE STONE AGEがMatadorに移籍したことも大きいのだと思いますが、このところJosh Homme関連の仕事も多くなってきた印象を受けます。
「彼のことはKYUSS時代から知っていて、あいつがまだ19歳くらいのときかな。その頃からずっとファンだったよ」
――昨年リリースされたDESERT SESSIONS『Vols. 11 & 12』では、他の参加メンバーとは少し違って、単なるゲスト・プレイヤー以上の、言うなれば共同プロデューサー的な役割を果たしているような印象を受けました。あのアルバムでは、どのような役割を果たしたのか教えてください。
「そんな大層なもんじゃなくて、ただ現場に行ってガーッと演奏して帰ってきただけだよ(笑)。あれもめちゃくちゃ楽しかったし、大満足してる。限られた時間の中で、気のいい連中に囲まれて、気持ちよく演奏させてもらったって感じ。2日間で6曲作って、しかも録音して完成させるところまでやるっていう、クレイジーなスケジュールだったけど(笑)、おかげで滅多にできないような貴重な体験をさせてもらった。この手のぶっ飛んだアイディアには、心意気だけでも、諸手を挙げて大賛成ってタイプだからね。とりあえずやるだけやって、失敗したら全部ボツにして1からやり直せばいいんだから」
――その『Vols. 11 & 12』や、Iggy Popの「Post Pop Depression Tour」に参加したときの経験を踏まえて、Josh Hommeという人物についての評価をお願いします。
「とりあえず、強烈なキャラだよね、いちいち笑かしてくれるんだ。常にパワー全開で、その瞬間その瞬間を全力で生きてるような奴だから、一緒に演奏してるとこっちまでテンション上がってくる。あれはもう天性の才能だよな……全力で周囲のみんなを楽しませる才能だよね。とくに歌う姿はマジで最高で、隣で演奏していて思わずニヤけてくる。マジで愛すべき輩だね」
――あなたはセッション・プレイヤーだけでなく、プロデューサーとしても、SONGHOY BLUESのニュー・アルバム『Optimisme』などの作品を手がけていますが、プロデューサーとして関わるときと、プレイヤーとして関わるときとで、意識の持ちかたに何か違いはありますか?
「よくわからないけど、ただ普通にプレイヤーとしてレコーディングに参加するときとは確実に違うよね。プロデューサーって、少なくとも俺にとっては、やっぱり大変。やらなくちゃいけないことが山積みで、プロジェクト毎に目的も状況も違うから、常に目標を明確にしておかなくちゃいけないし。単純に楽しいかどうかというレベルで言えば、普通にミュージシャンとしてスタジオに入ってパパっと演奏するほうがよっぽど気持ちが楽だ。自分のプレイだけに集中すればいいし、ある程度流れができている中に入って演奏するのと、1から10まで自分たちで作り上げなくちゃいけないのとでは全然違う。現場にいる全員が常に指示や意見を待ってる状態というのも、プロデューサーに求められる役割のひとつだから。それでも、大変だけど、とてもやり甲斐があることなのは確かだよ。俺の場合、プロデューサーとして明確なヴィジョンがあるというよりは、おもしろそうなプロジェクトに期間限定の助っ人としてレコーディングを手伝うようなスタンスでやらせてもらってる。逆に言うと、ゼロから企画を作るとか、すでにある程度出来上がっているものを、自分の閃きで180度逆のものに転換させるとかは、得意分野じゃないね(笑)。むしろ現場の盛り上げ役というか、グループの輪の中に入っていって、アイディアを実現の手助けするのが得意なんだ。まあ、現場や作品によって違うから、何とも言えないところもあるけどね。最近はDaniel Schlettとよく組んでるんだけど、すごく腕のいいエンジニアで、しかも彼の持っているStrange Weather Studiosがまたいいんだよ。俺は機材周りに関して素人同然で、Pro Toolsの使い方すら知らないから、エンジニアの存在が本当に重要なんだ。だからこそ、Danielみたいなエンジニアと出会えたことは、これ以上ないくらい幸福なことで、ここ1年から1年半くらい相当な数の仕事を一緒にこなしてる。彼のスタジオでレコーディングしたCOUNTRY WESTERNSの新作も出たばかりだよ」
――あなたの最近の仕事のひとつであるStephen Malkmusの『Traditional Techniques』も非常に良かったです。スタジオにあった様々なアコースティック楽器にインスパイアされて作られたというこのアルバムでも、多大な貢献を果たしているようですが、ここでは具体的にどういう役目を務めたのでしょうか。
「ライヴ録音って、自分にはいつものことで、特別なことでもないんだ(笑)。即席のバンドみたいにパッと集まって、サッとレコーディングする。Stephenから生楽器をメインにアルバムを作ってみようという案を聞いたとき、それまでの彼にはなかった路線だし、おもしろそうだと思って。そこから始まったんだ。これもまた作っていて楽しかったな。事前に送られてきたデモを何回か聴いただけで、リハーサルもしなかったし、デモも事前準備のためというより、あまりに曲が良いもんだからつい聴き返しちゃった感じで。とりあえずみんなで一緒に集まって演奏してみたらどんな音が出るのか試してみようっていう、それがあのアルバムの基本コンセプトだった。ちなみに完全非公表でレコーディングしてる。Stephenが自腹で制作したから、完成するまで誰もアルバムを作ってることを知らない。そこがまたいいんだよ。個人的には一番良いアルバム作りの方法だという気がする。誰も知らない状況の中で作品を作ったほうが、気兼ねしないぶん、かえっておもしろいものができるんだ。他人に話すと、どうしても聴かせろっていう展開になって、つい反応を意識してしまうからね。それより、とりあえず最後まで作ってから反応を知るほうが、作り手にとって健康的な気がする。俺がここ何年か関わっているプロジェクトって、わりとそんな感じで作っているものが多いし、実際そのほうが楽しいんだ。事前の準備だの、計画だのはすっ飛ばして、とりあえず現場に行って作品を完成させちゃう。Stephenの作品はまさにそんな感じで、個人的には最高に楽しかったよ」
――RUN THE JEWELSの作品にもよく参加していますが、異ジャンルであるヒップホップの作品に参加する場合でも、いつもと同じようにプレイを提供できるのでしょうか?
「俺がここまで何とかやってこられた理由を考えてみると、結局、ただ自分にできることをやってきただけなんだ(笑)。ただし、あくまでも自分なりのスタイルを貫いた上でね。これが意外と応用が利くらしくて、けっこう、いろんな場面で使えるんだよ。とりあえず、どんなプロジェクトであれ、何かしら自分の爪痕は残しているつもりだし、それが自分なりのカラーってことになるんだろうね。あと、Jaime Meline(El-P)と一緒にやっていて楽しいのは、向こうも俺のスタイルをわかってくれてるからだね。ヒップホップっぽくとか注文されることは一切ないし、基本“お前が必要だと思った音を付け足してくれよ”って感じでやらせてもらってる。あとは現場の雰囲気やノリ、その場で話していて感じたことを、自分なりに解釈して音にしているだけで、スタイルがどうこうってことじゃないんだ。Jaimeは、とにかく頭の回転も反応も速い人間だから、何かのアイディアに対して、自分がおもしろい球を返したら、そこからまた思いもよらない方向にどんどん転がしてくれる。あれはまさしく天性の才能だよ。一緒にやっていて楽しくて仕方ないね」
――El-P関連で、Zack de La Rochaのソロ・シングル『Digging For Windows』にも参加してましたよね?
「ああ、Jaimeを通してZackと知り合ったんだ。2人はこれまでにいろんなプロジェクトで共演してるから、そこに俺も軽いノリで参加した感じ。たまたま別件で話しているときに“今ちょうどJaimeの家にいるんだよ”っていう話になって、ついでに手伝うことになったんだ。本当に軽いノリ。あの曲に参加できてよかったよ。Zackとはここ何年かの付き合いになるかな……すごくいい奴だ」
――そのほか、AdeleからCURRENT 93、 Andrew W.K.からTINARIWENまで、本当にヴァラエティ豊かすぎるアーティストたちに関わってきたわけですが、特に楽しかった思い出、逆に大変だった経験などを教えてください。
「いや、それを答えるのは難しいよ。今言った全員、思い出すと自然にほっこりした気持ちになるもんなあ……どれも俺にとっては良い思い出だし、ひとつひとつが違っていて、そこがまたいいし……あー、参ったな(笑)。どこから始めようか……みんなマジで俺には大切だから。Andrew W.K.とか、プロデューサーとしても最高だと思うしね。2人ともCURRENT 93の大ファンだったから、その作品に2人で参加できて、嬉しくて興奮しっぱなしだった。俺とAndrewのニューヨーク人脈の中で、ブッちぎりでおっかなくて激しいバンドがCURRENT 93だったんだから、そりゃ興奮するに決まってる(笑)。Adeleのレコーディングも楽しかったよ。ちょうどRick RubinがマリブのShangri-Laスタジオを使い出した時期で、Adeleはまだ今みたいにビッグになる前だったんだけど、すごくいい子でさ。さんざん音楽について語り合ったよ。Dionの“New York City Song”っていう曲を2人で一緒にカヴァーしようって盛り上がって……あれ、マジでやっときゃよかったな。もし、あの曲を知らない人がいたら、とりあえず聴いてみて。それでAdeleがあの曲を歌ってる姿を想像してごらんよ、マジで鳥肌立つから!! そんな感じで、どれも本当に良い思い出だし、つくづく自分はレコード作りを愛しているんだなあ。20代には自分なんかにレコードを作る資格があるのかどうか、自信が持てない時期もあったけど、今では心から楽しいって言えるよ。我ながらよくここまでやってきたと思う……途中で諦めずに続けてきた自分に感謝だ(笑)」
――ところで、Alec Empire vs. Merzbowの『Live CBGB’s NYC 1998』という作品のライナーノーツを執筆していますが、これはどうして書くことになったのですか?
「Alecとも昔からの知り合いなんだ。最初に会ったのはベルリンで、自分が20歳前後の頃だったかな。当時Alecのやっているレーベル・Digital Hardcore Recordingsと、BEASTIE BOYSのレーベル・Grand Royalとの契約の橋渡し役を俺が担当していて、その頃からの付き合いだよ。90年代はDHR周辺とか、ドイツのシーンがめちゃくちゃ盛り上がっていて、自分も相当ハマってた。Alecのキャラがまた最高なんだよ。ちょうどCHAVEZを始めた時期とカブっていて、昼間はDHRのアメリカ進出を手伝う仕事をしてたんだ」
――本当にいろいろやってますねえ。さて、最も影響を受けたギタリストといったら誰になるでしょうか?
「いやあ……何しろ数が多すぎるから…………フィンガー・ピッキング・スタイルのギタリストは誰でも好きだけど…………ただ、強いて言うならPaul Learyかな。ギターの弾きかたにしろ、音楽の聴きかたにしろ、すべて何もかも変わったからね。あとはJohn FaheyとかEstil C. Ball……Ball版の“Pretty Polly”っていう曲があるんだけど、それがめちゃくちゃ衝撃で。どうやったらあんな音になるのか必死になって解明しようとしていた時期があるよ。あとはイギリス人のRichard Thompsonからも、ものすごい影響を受けてる。とりあえず、少ない動きでこんな演奏ができるんだ、って思った人は全員……それでいうなら、R.L. Burnsideなんか初めて生演奏を観たときの衝撃ったらもう。まるで何もしていないような、それこそ指なんかほとんど動かしていないように見えるのに、素晴らしい音が次から次へと紡ぎ出されていくんだから、一体どうやったらあんな離れ業ができるのか不思議でたまらなくて。まだ25歳とかで、わからないことだらけだったから、余計に衝撃だった。今ここで思い浮かんだところでは、ザッとそんな感じ。まあ、ほんの触りに過ぎなくて、他にも山ほどいろんなギタリストから影響を受けてるよ」
――最後に、今なお世界はかなり大変な状況ではありますが、これからの計画や現在やっていることなどについて教えてください。
「Willと一緒にやってるSUPERWOLFでまたアルバムを作っていて、そのミックスをどうするかっていうのが、目下最大のプロジェクトだね。マジで楽しみにしてる。ただ、プロモーションだのライヴだのをどうするかっていうことに関しては……いやあ、わっかんないねえ……まあ、考えたって仕方ないからね(笑)。これまで俺は宅録に馴染みがなかったけど、今はステイホームで作業するしかない。でもまあ、案外いけそうな気もしてる。ある意味、今まで通りなのかもしれない(笑)」
――いずれ日本でまた、あなたのステージを見られる日が来ることを待ちたいと思います。今日はどうもありがとうございました。
「こちらこそ。東京にお気に入りの場所がたくさんあるんだ。最後に、東京のお気に入りスポットを全力でおすすめしたい!残念ながら今の状態では、自分で行けないからさ……俺はTEENGENERATEの大ファンなんだけど、そのメンバーがやっているバーが東京にあって、あれ何て名前だったっけ?(後ろにいる奥さん?に)Fifiのやってるバーの名前なんつったっけ?そうそう、Poor Cow(東京・下北沢)だ。もう地上の楽園みたいなところで、東京にいるなら絶対行くべき。あとSUPERIORITY BURGER。友達とこっちで経営しているんだけど、東京に支店をオープンしたんだよ。それに、偉大なるGAUZEのライヴも観たい!」
SUPERIORITY BURGER JAPAN Facebook | https://www.facebook.com/Superiority-Burger-JAPAN-100181821454502/
 ■ 2020年10月23日(金)発売
■ 2020年10月23日(金)発売
CHAVEZ
『Gone Glimmering』Expanded
Vinyl 2LP OLE1620LP 3,500円 + 税
[Side A]
01. Nailed To The Blank Spot
02. Break Up Your Band
03. Laugh Track
04. The Ghost By The Sea
[Side B]
01. Pentagram Ring
02. Peeled Out Too Late
03. The Flaming Gong
04. Wakeman’s Air
05. Relaxed Fit
[Side C]
01. The Nerve
02. You Faded
[Side D]
01. Hack The Sides Away
02. Repeat The Ending
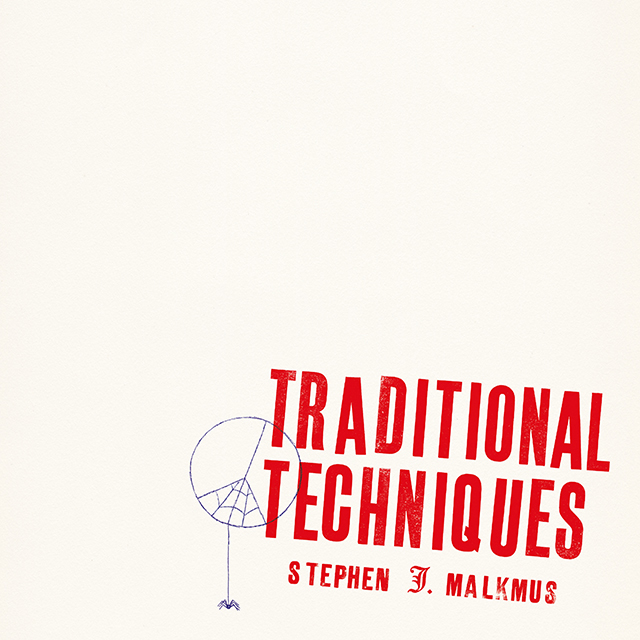 ■ 2020年3月6日(金)発売
■ 2020年3月6日(金)発売
Stephen Malkmus
『Traditional Techiniques』
国内盤CD OLE1513CDJP 2,200円 + 税
[収録曲]
01. ACC Kirtan
02. Xian Man
03. The Greatest Own In Legal History
04. Cash Up
05. Shadowbanned
06. What Kind Of Person
07. Flowin’ Robes
08. Brainwashed
09. Signal Western
10. Amberjack
11. Juliefuckingette *
* Bonus Track for Japan
 ■ 2019年10月25日(金)発売
■ 2019年10月25日(金)発売
DESERT SESSIONS
『Vols. 11 & 12』
国内盤CD OLE1488CDJP 2,200円 + 税
[収録曲]
01. Move Together
02. Noses in Roses, Forever
03. Far East For the Trees
04. If You Run
05. Crucifire
06. Chic Tweetz
07. Something You Can’t See
08. Easier Said Than Done







