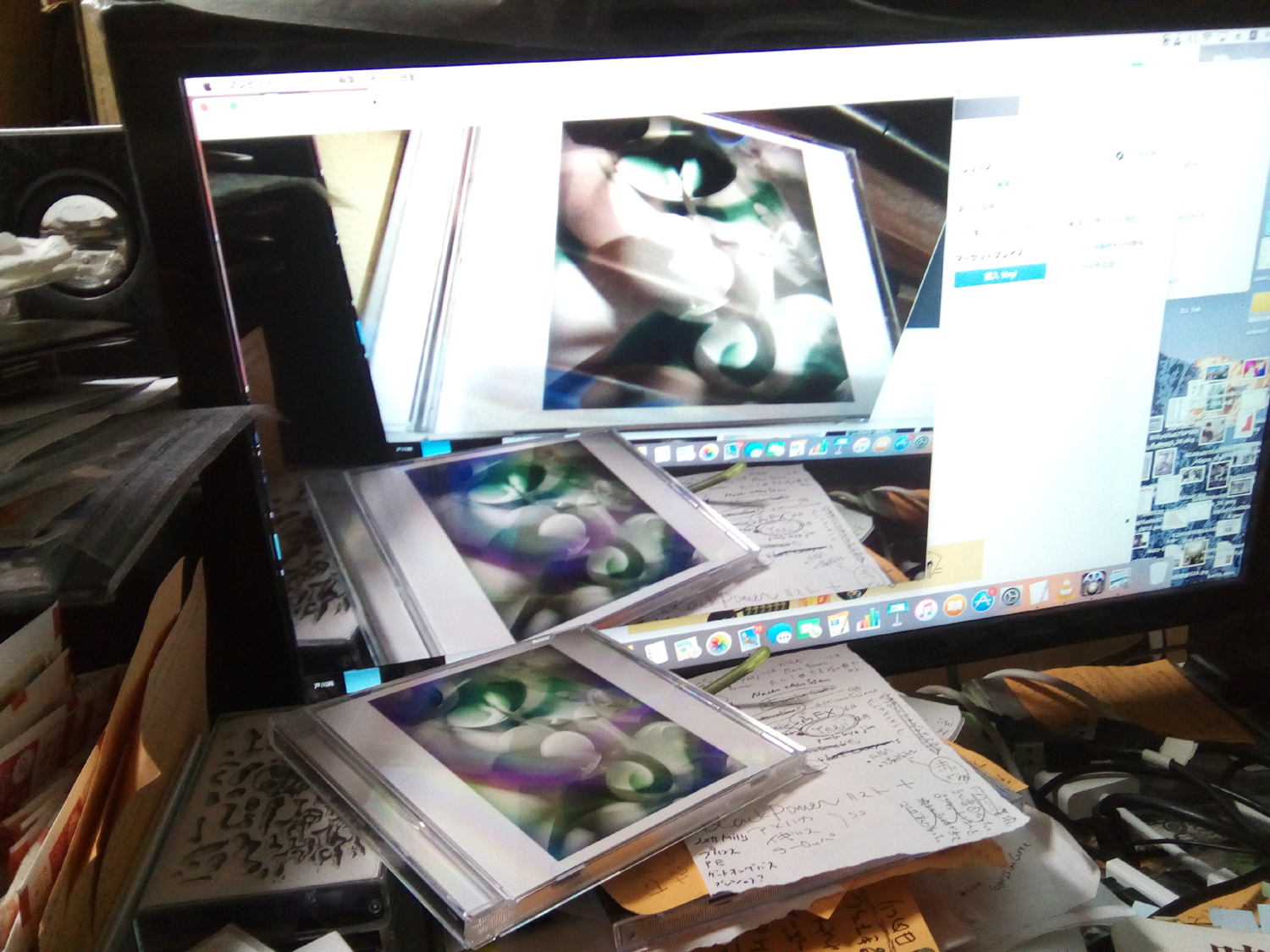文・撮影 | 三田 格
ハウス・ミュージックに大量のパーカッションを持ち込み、いわばトライバル・ハウスの先駆をなしたのはマイアミのMURK BOYS(俗称。正式にはMURK)だとされている。そのポテンシャルを最大限に引き出したのがプエルト・リコにルーツを持つMASTERS AT WORKの2人で、ベネルクス・スクールと称された「Touché」や「Global Cuts」といったヨーロッパのレーベルがその後の大きな受け皿となっていく。トライバル・ハウスにおける初期の名作はNo Smoke『Koro-Koro』(1989)やA Guy Called Gerald『Emotion Electric』(1989)、あるいはTEARS FOR FEARSをサンプリングしたE-CULTURE『Tribal Confusion』(1990)やBobby Kondersの諸作といったあたりになるだろうか。C + C MUSIC FACTORYによるMichael Jackson『Black Or White』(1991)のリミックス・シングルはメジャー展開の素早い例となり、Madonnaが『Bedtime Story』『Ray Of Light』『Don’t Tell Me』と、以後もこの路線を強く受け継ぐことになる(『Erotica』のリミックスはMASTERS AT WORKの2人)。後にアフリカン・ミュージックに強い執着を見せるLEFTFIELDの別名義Djum Djum『Difference』(1990)やエレクトロニック・パーカッションを叩きまくった808 STATEはハウスとテクノを横断するような作風で強烈な印象を残し、テクノであれ、ハウスであれ、いわゆる流行りのサウンドとしてトライバルが感染爆発を起こしたのは1992年に入ってから。BANDULU『Guidance』(1992)やPSYCHICK WARRIORS OV GAIAの諸作、さらにはFabio ParasやTeknotikaなどが立役者となり、Jaydee『Plastic Dreams』(1992)がトライバル路線のみならずダンス・ミュージック全体でも最大の売り上げを誇った曲となる。以後はこういったものの常で、手法はマンネリ化し、THE GRID『Figure Of Eight』(1992)のようにチャート・バスターズが現れては消え、Danny TenagliaやCevin Fisherといったプロデューサーが巨大産業の代表格となっていく。
クリシェ化するということは俗流のイメージから抜け出せないということであり、それもまたポップ・ミュージックのいいところではあるけれども、一方で研究熱心な音楽家たちはディープにアフリカのリズムを探り始める。クラブ・カルチャーでは散発的な試みはあったものの、ロンドンで「Mo’ Wax」などのレコード・デザインを手掛けてきたWill Bankheadが「The Trilogy Tapes」というレーベルを立ち上げ、自ら『Folkways I』 というカセット・テープを2008年にリリースしたところから、それは本格的に始まった。『Folkways I』に収められていたのはアメリカの「Folkways Records」から彼が恣意的にチョイスした音源で、Bankheadはそれらをサンフランシスコのレコード屋にあった“100円コーナー”から収集してきたという。「Folkways Records」は1948年にニュー・ヨークで設立されたレーベルで、膨大な量の民族音楽だけでなく、工場やオフィスの音など多種多様なフィールド・レコーディングを採集したことでも知られている(現在はスミソニアン博物館に収蔵された音源を部分的にネットで試聴することができる)。これの第2弾となる『Folkways II』を5年後の2013年にリリースしたのがBeatrice Dillonだった(それまで彼女がなにをやっていたのかぜんぜんわからない)。「Folkways Records」のアーカイヴから好きなドラム・サウンドだけを集めたという『Folkways II』と同時に、彼女は「Blowing Up The Workshop」からミックステープもリリースしていて、やはり「Folkways Records」に多数の作品を残したTony Schwartzやサウンド・エンジニアのRupert Clervauxとの共作を何曲か収録することで、キャリア初期からワールド・ミュージックと親和性の高い実験音楽に方向性を定めていたことを窺わせる。Will Bankheadが『Folkways I』をリリースした年はBOREDOMSが77人のドラマーを共演させた『77 Boa Drum』をリリースした年であり、『Folkways II』と同じ年には元BASIC CHANNELのMark Ernestusがセネガルのパーカッション・チームと組んだJERI-JERI『800% Ndagga』もリリースされるなど、明らかにパーカッシヴな音楽への興味は高まっており、同ミックステープにはJERI-JERI「Sama Yaye Version」もフィーチャー。2つの『Folkways』の中間地点となる2011年にはノイズ・ミュージックのオーソリティ、WHITEHOUSEのWilliam BennettがJohn Streicherと組んだCUT HANDS名義でアフリカン・ドラムを収集した『FACT Mix 283』を配信したり、BLURのDamon Albarnがダブステップのプロデューサーたちを大挙してコンゴに引き連れ、現地のミュージシャンたちとDRC MUSIC『Kinshasa One Two』を短期間に録音するなど、アフリカのリズムに着目したダンス・ミュージックのクォリティも一気に上がっていった時期でもある。Damon AlbarnやBaaba Maalに加えてAdrian SherwoodやBrian Enoが参加したAFRICA EXPRESSが始動したのも2009年。イギリスとアフリカの混合メンバーでつくられたAFRICA EXPRESSは『Terry Riley’s In C Mali』(2015)など現在までに5枚のアルバムをリリースしている。

Beatrice Dillonが『Folkways II』からデビュー・アルバムとなる『Workaround』を完成させるまでには、そして、7年かかっている。この間に彼女はミニマル・テクノの習作をつくり重ね、ポリリズミックの強度をじょじょに上げていく。SPACE AFRIKAやN1Lをリリースしてきた「Where To Now?」からのデビュー・カセット『Blues Dances』(2013)ではダンス・ミュージックと実験音楽はまだ別々に捉えられているという印象でどこか掴み所がなく、同レーベルからの12″シングル『Face A/B』(2015)ではサックスをフィーチャーしたミニマル・テクノやRicardo Villalobos風のファンキー・ビートを試みるなど、ようやくダンスフロアの入り口に立ったという印象。2015年と16年にはRupert Clervauxと組んだアルバム『Studies I-XVII For Samplers And Percussion』と『Two Changes』を「Snow Dog Records」と「Paralaxe Editions」から続けてリリースし、実験的なミニマル・サウンドを多種多様に追求していく。時にそれはダイナミズムを欠いたSteve Reichやアフリカン・ドラムを無機質にループさせたサウンド・インスタレーションに聞こえるも、『Workaround』の土台作りはこの過程でしっかりと整えられていく。Beatrice Dillonが主導したと思わしき『Two Changes』は長めのコンポジションが2曲と、全体的に予想外にアカデミックな仕上がりで、ミュジーク・コンクレートがリヴァイヴァルした2010年代の雰囲気を強く感じさせるものでもある。2016年にはさらに、ディストリビューターの強みを生かして新しい才能に弾みをつけさせるのが上手い「Boomkat Editions」から『Can I Change My Mind?』をリリース。Villalobosを思わせるミニマル・テクノの模倣はこれで打ち止めとなる。この間にDJとしても注目を集めるようになり、Ben UFOとの『43:44 / 44:32』(2016, Wichelroede)や未発表音源を含む「Rvng Intl.」の全音源を使った『RVNG Intl. At 15: Selects / Dissect』(2018)はかなり耳を引くミックス内容で、一方で、Laurel Haloと共にデトロイト・テクノの研究家として知られるKaren Gwyerとのスプリット・シングル(2016, Alien Jams)や2017年にはドイツのKassem Mosseと組んだDILLON WENDELとしてかつてなくアブストラクトな『Pulse / High』(2017)をWill Bankheadの「The Trilogy Tapes」から、さらにはCall Superと組んだ『Inkjet / Fluo』(2017)を「Hessle Audio」からリリースと、多方面とのコラボレーションも止むことを知らなかった。『Workaround』にもこの頃にはすでに着手していたそうで、充実という言葉を使わずに、どうやってこの時期を表せばいいのかという感じ。
1950年代には「Folkways Records」によって幅広くフィールド・レコーディングされ、60年代から70年代にかけてはコンテンポラリーなドラム・ミュージシャンがアフリカ各地から出現するようになったアフリカン・ドラム・サウンドは、SANTANAやTALKING HEADSを経て欧米のロック・サウンドと融合し、Malcolm McLarenがヒップホップと親和性を持たせた後、テクノやダンス・カルチャーというフロンティアでも大きな飛躍を伴うこととなった。「リズムに取り憑かれた」と形容されるビアトリス・ディロンが練りに練り上げ、最終的にシンプルな落とし所を得た『Workaround』はその中でも絶品の部類に入り、グライムから発展したウエイトレスとも接点を持つことで彼女自身の過去作とも連続性を見失うほどの完成度である(以前の作品をどうしても確認したいという人には『Workaround』とは唯一、直線的な線で結ばれている『Studies I-XVII For Samplers And Percussion』をオススメ)。ブリティッシュ・バングラのパイオニアとされるKuljit Bhamraのタブラをはじめ、Lucy RailtonによるチェロやJonny Lamのペダル・スティール・ギターなどアコースティック楽器の演奏やFM音源をサンプリングし、「Workaround Two」ではLaurel Haloが珍しく金属的なヴォーカルもちらりと聞かせている。エレクトリック・ギターに「Hessle Audio」のオーナーUntold、ハイハットにBatu、バウロンというアイルランドのフレーム・ドラムに(ハウスとクラウトロックを融合させた)Morgan Buckleyという布陣も恐れ入る。Dillon自身もドラム・プログラミングやモデュラー・シンセのほかにベースやパーカッションなどを演奏。プロデュースももちろん彼女が単独で行い、トリートメントの妙なのか、シンコペーションを多用したアフリカン・リズムの核だけが再現され、いわゆるワールド・ミュージックに特有の猥雑さがないところも新鮮。無菌室に放り込まれたアフリカというのか、催眠的で時空が歪んだような音響空間として再現されたアフリカン・ミニマルは映画『ブラック・パンサー』でも描かれなかったような未来を想起させ、すべての曲がアフリカ音楽に特有のBPM150に統一されているところがまた心憎い。新しいものはもう出てこないと悟ったように言う人もいるけれど、やってしまう人はやってしまうものです。
 三田 格 Itaru Mita
三田 格 Itaru Mita
1961年LA生まれ。共著に粉川哲夫と『無縁のメディア』、野田努と『テクノ・ディフィニティヴ』、編書に『アンビエント・ディフィニティヴ』、『ゲゲゲの娘 レレレの娘 らららの娘』、『忌野清志郎画報 生卵』、戸川 純『疾風怒濤ときどき晴れ』など。
 ■ 2020年7月31日(金)発売
■ 2020年7月31日(金)発売
Beatrice Dillon
『Workaround』
Pan | 国内盤CD PCD-24960 2,400円 + 税
[収録曲]
01. Workaround One
02. Workaround Two
03. Workaround Three
04. Workaround Four
05. Workaround Five
06. Clouds Strum
07. Workaround Six
08. Workaround Seven
09. Workaround Eight
10. Workaround Nine
11. Square Fifths
12. Workaround Bass
13. Pause
14. Workaround Ten
15. Extrait *
* Bonus Track