文・画 | 江永 泉
| 長歌風に
音波は身を包む。体は音を浴びる。時折、耳から音が流し込まれもする。音楽は香水のように働いている。青山 新が「FUEGUIA 1833」に触れながら述べた香りと音の相似性、その裏返しだ(note記事「香りとテキストにまつわるフレイバーテキスト」参照)。それゆえQRコードがプリントされたTシャツは香を焚き染めた服のように扱いうるし、これはUCGMによる『Ode to the Angels embryo』のフレイバー・テキストということになる。これを強いてジャンプスケア的に捉えた上で肯定しようとしている。この曲への没入を二重化するために。
聴取過程を一部、記してみる。2017年10月末、アメリカ航空宇宙局(NASA)はハロウィンに合わせてか、プレイリスト『太陽系内のおどろおどろしい音声 Spooky Sounds from Across the Solar System』を音声ファイル共有サービスSoundCloud上で公開した。冒頭を飾る「太陽の可聴化」では太陽を観測して得られたデータに処理が加えられ、くぐもり不安定に揺らめきつつ途切れない汽笛またはハミング(鼻歌)のような音が続いていく。『Ode to the Angels embryo』の6分43秒のうち、トンネルでのロードノイズめいた唸りが風切り音めいたザラつきとともに強まっていく冒頭17秒間が与える感触は、この可聴化された宇宙からの振動の手応えと通じていた。それで17秒から18秒にかけて突沸のように挟まる息漏れ声は電子的に増幅されたシンバルの体鳴のように感じられ、それが人体からの呼気であり発話だと確かに判じえたのは30秒時点になって詰まった喉奥からの呻きが入ってからであった。――この短いスパンで傾聴の姿勢は誘導される。ノイズ音楽を聴く耳、脳へとである。40秒台の呻きや囁きを経て、1分前後からの列車通過時のような轟音とカットアップされた叫びの照応を捉え、繰り返されるメロディを辿ることになる。そうしていると、引き延ばされ刻まれて意味を解体された声のなかに、さながら挽肉のなかに混じる指のように元の発話が聴き取られる瞬間が折々に挿入される。空耳(モンデグリーン)かもしれないが、もっともはっきり聴き取れたのは、3分6秒からの「ヤメロ」。こうして意味ある発話と響きある叫びのあわいで宙づりにされた声と音に貫かれ、基調となる旋律の歪みや割れを意図された雰囲気として聴く構えから、修正すべき荒れや崩れとして聴く構えへと、身体が引き戻される。まるで聴取者がノイズ音楽というフィールドに安住することを曲がゆるさないかのようである。しかし、そもそもこう語られてもいた。ノイズ音楽は音楽でありながらもノイズとしての異化効果を発揮できる非 / 反 / 脱音楽の位置を保ち続けねばならないという、アンビバレンツな性格にその特徴と存在意義がある
(小倉利丸『アシッド・キャピタリズム』110頁)。とすればこれこそがノイズ的アンビバレントなのだろうか。
異化とは知覚する際の手癖からの脱却に向かうことであり、そのためこうした音楽文化では何か常軌を逸したものの圧倒感が言祝がれがちだった。そしておそらく、太陽系内で得た音を“おどろおどろしい”とタグ付けしてハロウィンに合わせて流す所作はこうした異化効果論によって制作と享受が価値づけられるノイズが市場経済へと包摂されてある状況と地続きである。例えばインターネットはALI PROJECTから戸川 純を聴くようになった耳と脳をBiS階段「好き好き大好き」そしてVIVINOS「Suki Suki Daisuki♡」へと誘導していく。ジャンプスケア的なホラー感と異化作用を帯びたノイズとがカワイイ意匠またサイバーゴス的装飾で糊付けされる肉体がある。そこでの『Ode to the Angels embryo』の聴こえ具合はこのようであった。
振り返れば、ノイズの力は例えば次のように熱心に語られてきた。ノイズやインダストリアル・ミュージックが普通いわれる音楽と本質的に異なるのは、音楽という領域と生活のなかで経験する「音」の壁を取り払ったということである
(小倉前掲102頁)。このようなノイズに日常生活への批判意識を認める小倉は、同時代――1990年代初頭――の重厚長大から軽薄短小への時代の転換のなかで、最も大衆的な支持を得た
(同106頁)音楽としてのヘヴィメタルのなかにノイズ的要素が流れ込んでいく様子を肯定している(とはいえヘヴィメタルは多分に子供騙しの歌詞や、顰蹙を買いそうなセックスや悪魔の歌、安手のヒロイズム、男性優位、白人中心
(同106-107頁)といった要素がしばしば確認されてきたとも指摘している)。ここにはバタイユやクリステヴァを想起させるような倒錯と侵犯の美学の影響が認められるだろう。そしてそうした美学の浸透は社会批判性を帯びたノイズが文字通りの「騒音」や「雑音」としてのノイズという拒絶の方法からさらに、オルタナティブな快楽の戦略へとその戦線を拡張してきたともいえるし、後退させてきたともいえる
(同101頁)状況と表裏一体だったことも小倉の記述からうかがえる。言ってみれば、ここにおいても椹木野衣がクロソウスキー『バフォメット』を参照しつつまとめていた1980~90年代のシミュレーショニズム美学の気風が共有されていたのだ。そこには自己も、内面も、起源も、唯一の神も不在です。ただ全方位に加速する恐るべき欲望の運動の持続だけがあるのです
(椹木野衣『増補 シュミレーショニズム』110頁)。つまりは境界攪乱や暴力性の肯定である。とはいえ小倉はそれの無節操な称揚などしておらず、例えば自律性を奪い産業に都合のいい中毒的サイクルへと追いやる搾取的ノイズ
と、やはり中毒的ではあれ、そうした搾取に敵対するがゆえに暴力的要素を含むサブバーシブなノイズ
とにノイズの使用を腑分けする程度には、注意深い(小倉前掲93頁)。快楽を供給する産業に埋没せず、しかし禁欲的にもならずに、自律した欲望の道を探る小倉は、言ってみれば内向的な解放性を音楽に見出しもする。階級や党といった抽象的なカテゴリーへの同一化ではなく「私」にこだわる人々が「私」を越える連帯を獲得できたのも自律的な個人の意志にこだわったからである
(同31頁)。自己の境遇から離脱させる音楽の力を言祝いだマーク・フィッシャーを連想しもする(もっともフィッシャーが実際にヒスノイズやクラックルノイズを論ずる際には今日のような情報社会化が進む以前の音楽文化を追懐するよすがとしてそれを扱っていたが)。もちろん上述の諸論に通底しているように映る、過剰さに満ちた質感の理想視、それを批判したのがトリスタン・ガルシア『激しい生 近代の強迫観念』であって、ガルシアの手にかかるとロマン主義者の末裔にロックンローラーが据えられ、生成変化的成長志向も加速主義的イノベーション憧憬もノスタルジックな初体験信仰も所詮はニヒリズムへの道として一蹴され、最後には中庸が打ち出されることになる。だが、実のところ『激しい生』の論調は、マーケティングから自律したジャンキーになることを訴える『アシッド・キャピタリズム』と共鳴しもする。このアシッドな資本主義の中では快楽による抑圧に押しつぶされないジャンキーの身体管理が必要なのだ
(小倉前掲291頁)。おそらくフィッシャーはこうした快楽を活用するための自己への配慮を思弁として記したところで個々人の草の根的活動に寄せる拍手喝采に留まってしまうものと感じられたがゆえに、それを越えるものとしてコミュニズムを志向したのだろうが、別の道もあるはずだ。例えば、悲劇的なものと喜劇的なものの反転可能性に焦点を当て、中庸や追懐(ノスタルジー)の実践に代えて、間の抜けた宙づり、サスペンションへの滞留を試みること。あたかも灰野敬二と音割れポッターのあいだで、『太陽系内のおどろおどろしい音声』とともに『Ode to the Angels embryo』を聴取するかのように?
喜劇が悲劇よりも悲劇的な質感をもたらす契機がある。若杉公徳の漫画『デトロイト・メタル・シティ』はデスメタルの多分に子供騙しの歌詞や、顰蹙を買いそうなセックスや悪魔の歌、安手のヒロイズム、男性優位
などを表層的に過剰に盛ることで戯画化し、ジャンルこそ異なるものの、格闘漫画として読まれると同時にカットアップされてギャグ化される板垣恵介や猿渡哲也の作品にも通ずる印象をもたらしている(この漫画のキッチュな暴力性はメイヘムを扱う映画『ロード・オブ・カオス』(2019, ジョナス・アカーランド)よりはむしろ曽山一寿の漫画『絶体絶命でんぢゃらすじーさん』のそれと並べられるべきものだろう)。しかし、それだけではない。滑稽ゆえにただ深刻であるよりいっそう残酷化する場面をも、それは描き出している。例えば第七巻、刑務所に服役し労苦する過去の姿を背景に浮かばせるヨハネ・クラウザーI世(北原元気)のパフォーマンスを、市井で小馬鹿にされた過去の姿を背後に浮かべるだけのヨハネ・クラウザーII世(根岸崇一)のパフォーマンスが上回ってしまう場面。まるで犯罪者になった者が背負う苦悩より小市民の抱く憤懣のほうにこそ、圧倒的な演奏が伴ってあるかのようだ。これは根性論を茶化す笑い事と映るだけではなく、物語世界において、現にそのようであることの無情さを汲み取りうる場景とも思える。それは支配的な見方とは別の見方が取りうるという(メジャーに思えていた)権威から(オルタナに思えている)権威への横断を、つまり脱権威化と再権威化をもたらすだけではなく、意図とその体現の間に結ばれていた決して壊れないはずの紐帯を破断させもする(いじましい苦労も切実な思いや願いも表現の成功を保証しはしない無情)。そして別様の関係を結ぶ余地があったと気づかせもする(異化効果)。身も蓋もない、そのようでしかなさへの滞留。必然性の偶然性を思い知らされること。同じ文字を見続けるうちにそれが無意味な線の連なりに感じられてくるように(字形の、そのようでしかなさ)。異化に誘うような無情な綻びを、詩人はさながら家屋の用途も目的も知らず眺める未開人のように天空や大洋を眺めるのだと記すカント『判断力批判』のまなざしから引き出し、そこから身体の有機的統一を前提とせずに身体像を捉える物質的
な地平を展開するのがポール・ド・マンであるが(「カントにおける現象性と物質性」参照)、そこでド・マンはカントの文の説得力の一部が散文的な物質性
に、例えば適合 Angemessen
と不適合 Unangemessen
が入り乱れて登場するうちに正反対の両者が混同されて感じられるという字面上の紛らわしさに求められるのだと論じもする。ド・マンのこのカント読解はふたりのヨハネ・クラウザーがつくる場景のように悲喜劇性を帯びていよう。これに倣えば、声が意味ある発話とも無意味な叫びとも定められず飛び交うなかで物質的
な地平に誘われ極めてなにか生命に対する侮辱
(宮崎 駿)に類する聴こえをもたらしたとも『Ode to the Angels embryo』について言えそうだ。こうして6分43秒間の締め、かすれて途切れるにいたる喉声の、ホラー的な耳心地へと触れるに至る。再びフィッシャーを呼ぶ。
フィッシャーは「怪奇なものとぞっとするもの」のなかで、怪奇やぞっとする質感を強いてフロイトのいう不気味なものから分けようとする(引用は『早稲田文学』2021年秋号から。大岩雄典訳・解説)。そうして精神分析の家族主義的色彩(恐怖的モチーフを去勢不安のような家族物語の反映として処理してしまうこと)を一旦は斥けた上でフィッシャーはむしろ家族についての一般的概念を奇妙としてしまう
(大岩訳90頁)手がかりとして精神分析を捉えなおし、ぞっとする愛の可能性を素描するに至るのだが、その道中でこう述べている。鳥の鳴き声に、単なる動物的反応や生理的メカニズムを越えた(あるいは向こう側の)何かがあると感じられるとき――そこで働いている何らかの種類の意図、私たちがふだん鳥とは結び付けない意図の形式があると感じられるとき、その鳴き声は〈ぞっとする〉ものとなる。これと、すでに述べた〈怪奇なもの〉の「属しえぬ」感覚とには、明らかに共通するものがある
(同95頁)。つまり怪物的なものの出現への驚きによる世界観の変容としての恐怖体験が論じられる。これに対し、怪奇なものではなく、ぞっとするものに固有の恐怖体験としてフィッシャーは不在に直面し沈思黙考する瞬間を論じており、メアリー・セレスト号やストーン・ヘンジ、イースター島のモアイ像、そして映画『猿の惑星』(1968, フランクリン・J・シャフナー)のラストに登場する彫像などが例示される。――使い古された(ラヴクラフト贔屓の)図式で言えばダーレス的モンスター・パニックに対するラヴクラフト的コズミック・ホラー、いまだそれ自体が明らかになっていない存在に、わたしたちはいまも見られているのではないか
(同97頁)と知らしめる、ぞっとする遺構群の質感。――このフィッシャーによる恐怖論がまさしく謎めいた過去を仄めかす痕跡の散らばるフィールドをひとりで探索し続けては時折フラッシュバック的ジャンプスケア演出に驚かされるような探索ホラー・ゲーム(例えば『ゆめにっき』(2004, ききやま)や『P.T.』(2014, 小島秀夫)、そしてその後続の作品群のような)の骨組みを素描するかのように映る点は興味深い。――だが、まずもってここで確認したいのはフィッシャーの恐怖論で取りこぼされている笑劇性だ。サイコロジカル・ホラーは緊張と弛緩を交互に繰り返すが、その反覆の蓄積はこのサイクル自体を子供騙しとして穿ち見るシニシズムも培う(そうすると今後に向けた希望と不安とで人を駆り立てるという意味で、未来なる観念すらを子供騙しとして拒否する境地も見えてくる)。化物の正体見たり枯れ尾花、王の裸体を飾っていた服は消え去る。謎めいた雰囲気への穿ち見が起こる。曖昧な痕跡の背後には、そもそも明快な設定の用意がないかもしれない。閑散とした光景や孤独感を催す静寂は、省エネのゆえなのだろうか。舞台が閉鎖されたりループしたりするのは、限られた場所や空間を使い回すためだったのではないか……。実際、こうしたホラーは低予算や少人数での制作、インディーズと相性が良い。一面では深淵でいわくありげな痕跡と映るものが、他面で見すぼらしい鰯の頭に過ぎないという無情。しかしながら、まさに現代的な恐怖は、この生が、リッチに作り込まれた悲劇よりはむしろ、キッチュな低予算ゲームにこそ似ているという漠然とした予感と共にこそ看取されるものではないか。いわば世界から雑に扱われているという笑うに笑えない質感。リソースがあれば解消されるはずの困難に取り囲まれた、貧しい生のどうしようもなさ。ありふれたグダグダのなかの安っぽい惨めさは、英雄的な崇高視に値しないがゆえにいっそう、宿命的な悲惨さよりもおそるべき質感をもたらすのではないか。かくして『Ode to the Angels embryo』の結び、氾濫する轟音が退いていくなか残る呻きは、二重化されて響く。一方ではモノとヒトの境域でのタナトス的な怪奇の発露として。そしてもう一方では、まもなく絶唱めいた叫びへの没入を終え、どうしようもない日々の生活への引き戻しに直面する者がなお抱く一抹の未練の、ぞっとする残滓として。
| 主な引用・参考文献
| 青山 新「香りとテキストにまつわるフレイバーテキスト」 | 『OKOPEOPLE編集室』2022年3月26日
| 小倉利丸『アシッド・キャピタリズム』 | 1992, 青弓社
| 椹木野衣『増補 シミュレーショニズム』 | 2001, 筑摩書房
| トリスタン・ガルシア『激しい生 近代の強迫観念』栗脇永翔 訳 | 2021, 人文書院
| マーク・フィッシャー「怪奇なものとぞっとするもの」大岩雄典 訳・解説 | 『早稲田文学』2021年秋号所収 早稲田文学会
| ポール・ド・マン「カントにおける現象性と物質性」上野成利 訳 | 『美学イデオロギー』所収 2005, 平凡社
| 若杉公徳『デトロイト・メタル・シティ』第7巻 | 2009, 白泉社
| 反歌風に
無の充満。プラズマ波。沈黙が唸る。裂孔。息吹。呻き。デスボイス。叫び、喃語、のストロボ化。ストリングス。Marcia alla turca(アテネの廃虚より)。快速電車が通過します(中澤 系)。今際の洩れ、の声(自分だけの暗い部屋、また黒洞々たるデッドスペース、そこで独りで傾聴のこと)。
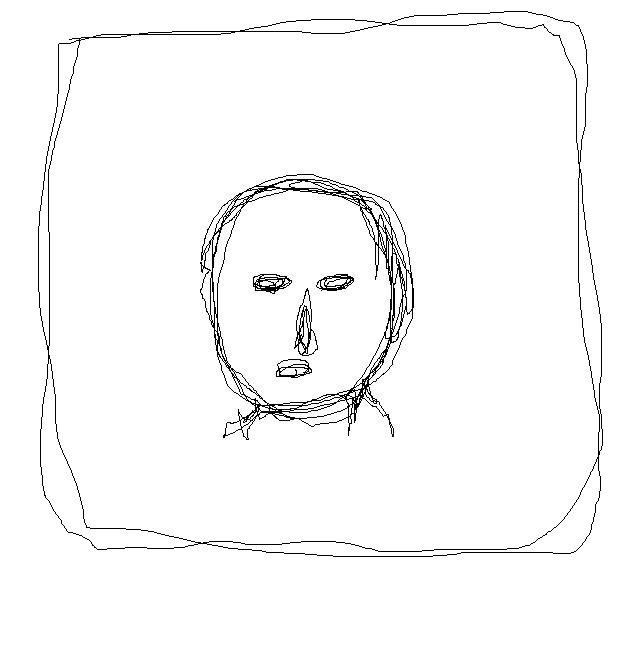 江永 泉 Izumi Enaga
江永 泉 Izumi Enaga闇の自己啓発会。『闇の自己啓発』早川書房.2021(木澤佐登志・ひでシス・役所暁と共著)、「闇のブックガイド ミステリー編」(『このミステリーがすごい!2022年版』所収。木澤佐登志と共著)、「ナタの時代、あるいはデスゲーム的リアリズム」(『S-Fマガジン』2022年2月号所収)など。
書いたもの (2022.01~06): 「思い出の話」(星野いのり編『青空と黄の麦畑』所収)、「ON BEAUTIFUL LIFE (美しい生活について) Ver.2.0」50首(玉野勇希編『ユーフォリクスver.1.5』所収)、「なぜだかわからないけど加速する」(『文藝』2022年夏季号所収)など。
やったこと (2022.01~06): ケンジ・シラトリとのコラボレーション『ウェイバックマシン』を公開(桜井夕也編『PIED PIPER WEB』掲載)。お布団CCS/SC 1st Expansion『夜を治める者《ナイトドミナント》』(作・演 得地弘基)に演出助手として参加。花形槙『still human』に実践協力として参加(Stilllive2022, KUMA EXHIBITION 2022 ほか)。長谷川愛・青山新との座談会「未来の友達」を公開(『anon press』掲載)など。







