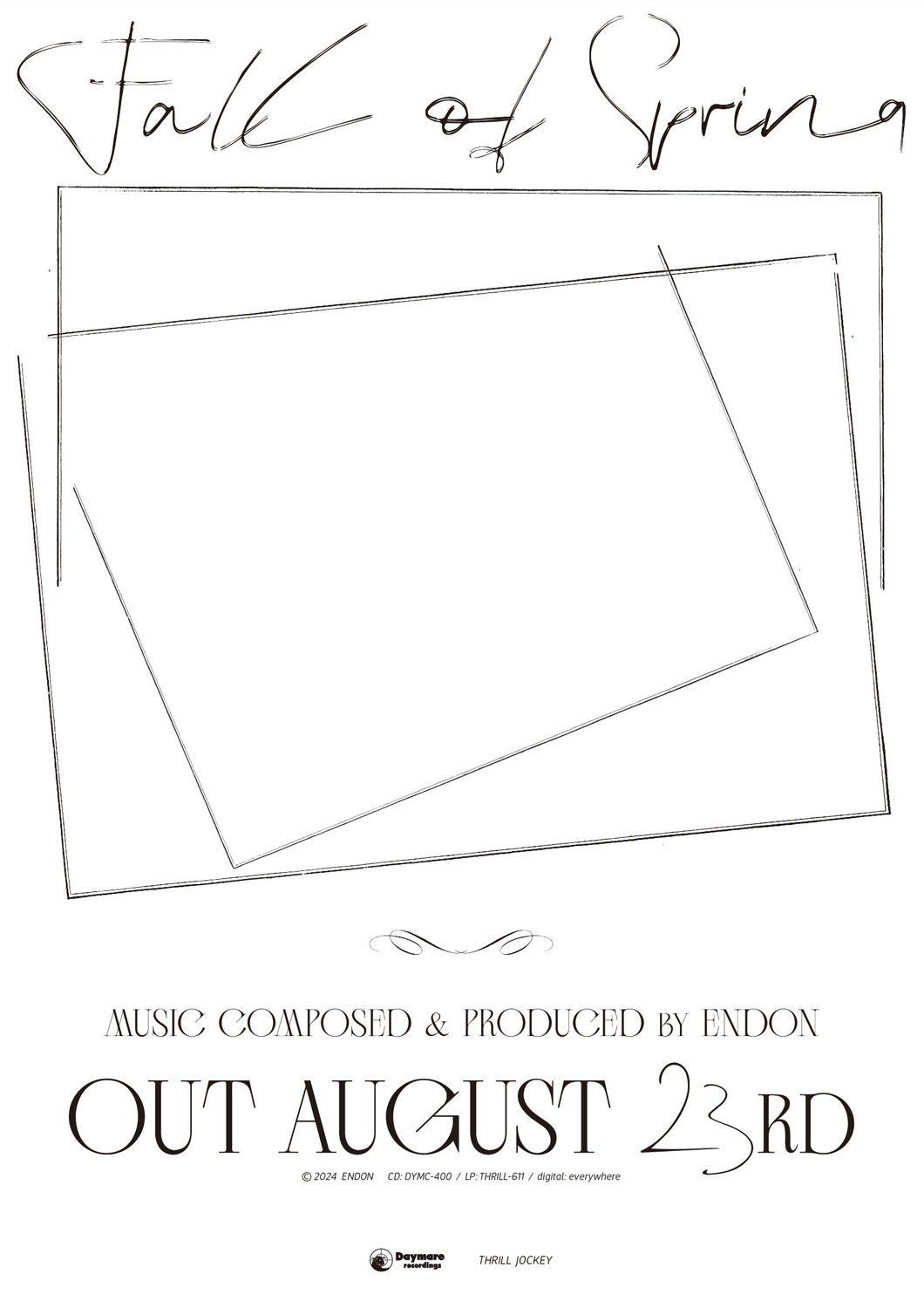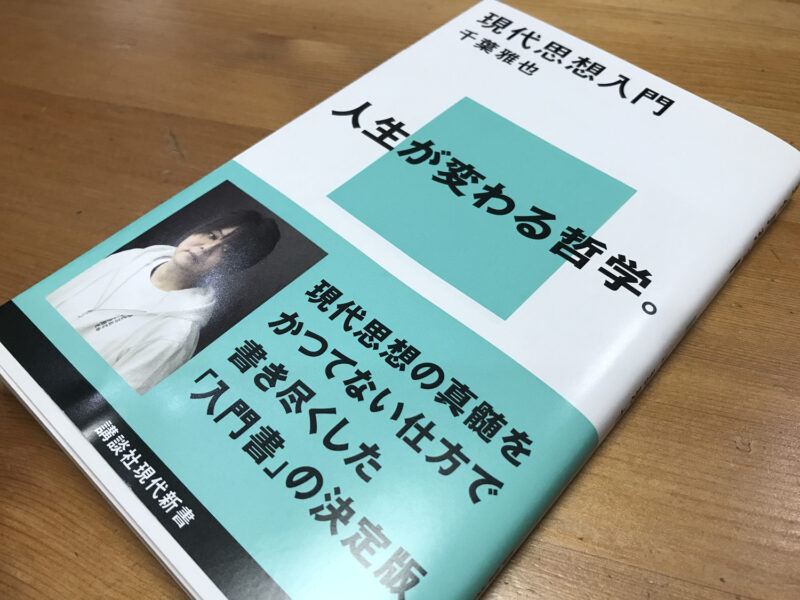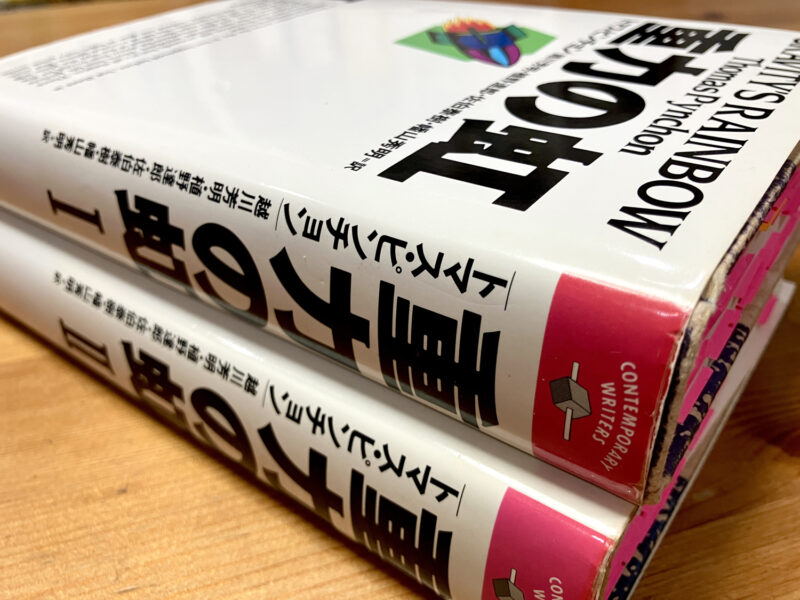文 | 清澄薫香馨
私が「evil spa 7」にてENDONを「目撃」し、衝撃と共に具現化への焦燥を抱いたあの瞬間の私を絶対的に信じた末に誕生した拙稿(「ノイズ・崇高・耽美――ENDON論」2024, 『新紀要 第二号』)がENDON本人にまで届いたのは、全く刹那の出来事であり、未だにあの「目撃」と共に実感が湧かない。ENDONのニュー・アルバムへのレビュー寄稿のお話をいただいたときはなおさらである。
前述の拙稿は、正直言ってENDONに対する感受の方向性を狭めてしまうのではないか、という危惧があった。「目撃」には多大なバイアスが漂っているものであり、「雑考」という語を用いてある程度の謙遜を表出してしまったが、文章において全体的には私の解釈の普遍化が伴う代物となっていて、実践することによって批評の功罪を自ら思い知ることとなった。だがそれでも、「目撃」にバイアス覚悟での信頼を置くことについては何ら疑念を抱くことなく、というか自らを騙してでも普遍化の一途を辿ること、その思いを堂々巡りの騙しに付随させて上昇させていくことである種の止揚へ達成できるのではないか、そのような粋がりをここでもさせていただこうと思う。
那倉氏はUNCIVILIZED GIRLS MEMORYに宛てて執筆した論考(「神の国」はどこにあるか――UNCIVILIZED GIRLS MEMORY『HEAVEN』リリースに寄せて)において、樋口恭介氏が執筆したKazuma Kubotaへの論考を引用し、ノイズ批評における形容句の「有意味性」「肯定性」への変容について述べた。「物語」や「人間讃歌」という語句を用いた、ノイズ・ミュージックにとっては目新しい方法での批評に対して、那倉氏はこれはノイズ・ミュージックが纏っていた否定神学的な色気の失効を示すにとどまる出来事、もしくは証拠を差し出しているのに過ぎないのではないか?
。要するにノイズ・ミュージックが単なる音楽の仲間入りを果たしたと言うことなのではないか」と疑問を呈した。たしかに、否定の特質を帯びたノイズ・ミュージックに肯定性を当てはめる行為はなかなか異質に思える。騒音によって構成されることがノイズ・ミュージックの必要条件である以上、否定の特質まで否定することとなり、裏の裏で表となってしまう。それならばその音楽は「単なる音楽」に対する評価条件と一致し、ノイズ・ミュージックがノイズ・ミュージックではなくなってしまうことも危惧される。
そうであるならば、ここで述べられた「単なる音楽」とは一体どのようなものであるか、という問いについて紐解かなければならない。というのも、ここではノイズ・ミュージックの否定性を強調することに留まっていて、那倉氏は前記の論考において最終的にはUCGMに対して「神の国」という語を用いて評しているが、否定性の喪失――つまり、ノイズ・ミュージックの存在意義が消失してしまうことが「単なる音楽」化であるとここでは読むことができる。
だが、果たして本当にそうなのであろうか。ノイズ・ミュージックにおいて肯定性を主張することは、その背後にはこのような転回を可能とする何か大きな作用が存在し、それによってノイズの実在がある意味克服というかたちで再興されたと言っても良いのではないか。このような疑問提出の形式を借りた意志の下、論を進めていきたい。
ノイズ・ミュージックの肯定性の背後に存在するものとは何か。それを探るために、少々唐突ではあるが、その存在を“中心”として捉えた議論を援用したい。
パスカルやシュレーゲルといった哲学者・美学者に影響を受けた二〇世紀ドイツの美学者・ゼードルマイヤーは、人間にはもともと“中心”が存在し、それが失われることによって人間や芸術作品に「中心の喪失」が発生した、と述べた。“中心”とは、いち個人としての人間や社会を周縁に据えた場合の、神であったり総合的人間像(個人的には「絶対精神」としても良いだろう)であったりする。人間がその中心に向かって働きかけ、芸術において“中心”を神とした場合、神に対して作品を捧げ、作品の美性・崇高性は神に由来するものだとし、作品自体も神のためのものだとした。もともと“中心”に神が存在し、その周りを取り囲むように人間が存在したのであり、人間が神を信仰し、働きかけ、神もそれに対応するかたちで人間に救済を与えた、このような図式で理解してもらえたら良いだろう。だが近代に、アドルノの語を借りれば「新しさ das Neue」を追い求めたモダニズムの動向によって神が失われ(もしくは死亡宣告を下し)、自らの源泉であり目的である“中心”が喪失する現象が発生する。この状態をゼードルマイヤーは、権威の喪失という意味で「美的アナキズム」と表現した。モダニズム以降の抽象芸術は神に依らない芸術として、視点を神から歴史へ移し「過去の芸術とどのように差別化を図るか」と内容や表現の自律性や純粋性を追い求めた結果として「抽象」となるが、それは神をはっきりと外部の存在だと規定し、外部でありながら自らの内部にも浸透するという全能性に基づいた、「神即自然」という語で表される神が万物に宿るような、ある意味でスピノザ的な汎神論的な神を退けた。それにより、人間の“中心”は失われドーナツ状となり、“中心”へ向かうという実質的に人間の本能となっていた行動のみがそこには残留し、存在しない“中心”へ彷徨い続けるのである。
これはもちろん音楽の世界にも発生したことである。教会音楽や王権神授説に基づいた王族や貴族へ捧げられた器楽曲、時代が少し進んでも、革命的機運に乗せ絶対精神への理想を主題とした楽曲であるような、“中心”の希求を旨とした所謂クラシック音楽の時代から、近代においては実存的主題の楽曲や、音楽理論実験としての十二音技法等が登場した。そもそも音楽理論自体も、数的調和性によって宇宙を説明しようとしたピタゴラスから始まったものであるし、理論からの離脱自体が背神行為であるとも言える。
では、ノイズ・ミュージックにおいては「中心の喪失」が発生しているのか。もちろん、全音楽史の中であったら明らかに喪失の対象であり、美的アナキズム状態にあると言える。ただ、現代におけるノイズ・ミュージックそれのみで捉えた場合、あまりにも美的アナキズム性が強いあまり、言ってしまえば初めから“中心”なんてなかったと言える。たしかにこれは暴言かもしれない。ノイズ・ミュージックは歴史的産物であり、その始祖であるルイージ・ルッソロは、産業革命以後社会に溢れた工業機械による騒音をテクノロジーの賞賛による意識の拡張という未来派芸術の名目の下音楽として認定したが、これは人間の物理的活動や生産様式としての下部構造が上部構造を規定するマルクス主義的唯物史観に基づくものだと言える。後に未来派はファシズムの成立に影響を及ぼすが、ファシズム自体もマルクス主義の理論を全面的に否定したわけではないのは事実であるし、唯物「史」観と言うほどであるからノイズといえども歴史には抗えないものである、と言える。だが、現代においてはどうであろうか。現代のノイズ・シーンは那倉氏も指摘する通りそのほとんどがハーシュ・ノイズとなっている。ノイズ・ミュージックの攻撃的精神性を純化させた結果だと言えるが、そのような危うい音楽の危うさの所以は、ハーシュ・ノイズの外縁に存在する音楽全体との比較によって成立しているし、ノイズの純化である故にその純粋性をある意味でおもしろがり、外縁の音楽とも「コラボ」している例が多数存在する。このような視点に立てば、現代においてもその異様さは音楽全体に関わる構造や歴史によるものだと言えるが、その否定の性質やノイズへの美的判断の特異性に目を向ければ、ノイズ・ミュージックをそれとして扱うことも容易に可能である。私はノイズ・ミュージックの作品に対して崇高の念を抱くことがあるが、そのとき、その崇高を感じる上での背後には「対象」が存在していないことが多い、このように思い返してしまう。また、普遍妥当的存在とは言えないような、ある種自分勝手な「対象」を想定してしまう。美的快感とはまた別種の精神の高揚――それは相対化不可能なほど大きなものを感じるからであり、神の観念をそこに感じる、と言っても良いだろう。ただ、私がノイズ・ミュージックの音源を聴取し、ライヴを鑑賞する際に感じる崇高には、そのような神は存在しない。代わりに感じるのは、大きなものではあるが、尊大ではない。そしてカントの『判断力批判』(1790)によれば、そのような背後の対象は間主観的普遍妥当性によって一者性を担保されなければならないものであるが、聴衆一人一人に全く別の格を持つ対象が各々に存在しているように感じる。私個人にとっては一者であるが、その一者性の普遍性を、容認とまでは言わずとも他者に対して要請しようとは到底思えない。この要請こそが美や崇高の判断を下す上で必須の条件となるが、ノイズに対する崇高はあくまで私の心の中にのみ表出した観念であり、一般的に崇高の観念を抱く際に必須となる一者性の他者への要請すら烏滸がましく、傲慢性を帯びてしまう。その対象とは相対的には存在するものと言えるかもしれないが、聴衆全体の観念を俯瞰して見れば、あまりにもその対象がぐらぐらと不安定でいて、そもそも存在を認められない「無対象の崇高」とも呼べるかもしれない。正直言ってしまえば、ノイズ・ミュージックなんて全て同じように聴こえてしまうし、そのようなものを個別に批評することは非常に困難を極める行為である。
ただ私がENDONを「目撃」し、此度のアルバムを聴取したとき、私はその背後に絶対性を帯びた何かを感じてしまった。それはその「目撃」がバイアスを通過したものだと知っていながら絶対的な信頼を置く行為と重なっていた。絶対的に尊大であり、自分勝手に抱いた観念であっても他者への同意の要請を行いたく、ある種純粋にカントの美的理論に沿ったような崇高への手順を踏んでしまったのである。前述の歴史的分析に戻って紐づけてみれば、現代のノイズ・ミュージックの「無対象の崇高」は伝統的な崇高論から脱却した新しい理論の下遂行されたものであると言え、ENDONに対する崇高は、反動的なものとなる。たしかにゼードルマイヤーはモダニズム時代の抽象芸術を美的アナキズム状態にあると述べ、「中心の喪失」は「中心の回復」を想定した上での句であるから、このことからゼードルマイヤーが意図していたのは保守革命であった、という分析もある。歴史的にみればこの崇高は保守革命の思想が背後に存在する観念と捉えることもできるが、現代のノイズについて語る上では歴史的分析は適当ではなく、ノイズそれ自体の超越性に視点を絞ることもまた重要であることは前述した。となると、ノイズ・ミュージックが初めから“中心”なんて存在しない音楽で、ENDONに対する崇高は、実はENDONがノイズ・ミュージックで初めて“中心”を持った存在である、ということとなり、これは保守革命でも何でもなく、わかりやすく「革命」と呼称することができるのである。
ただ、これは形式のみが革命の様相を呈しているだけであり、内実を覗くとかなり危険な状況となる。もともとが美的アナキズムの状態であったノイズ・ミュージックが初めて“中心”を獲得するという革命をENDONが成功した、ということであるが、これはもともとの体制を崩壊させ、抜本的改革を行なったということのみの説明であり、何から何へ変わったのか、どのような事柄に視点が当てられた結果として革命が発生したのか、ここが問題である。
結論を先取りすると、この革命にはファシズムへの転化の危険性がある。そもそももともとのノイズ・ミュージックが美的アナキズム状態であると述べたが、この語は権威性の否定という意味で用いられている。だがアナキズムというのは、バクーニン的解釈に基づけば総破壊の理念の下否定が行われる。この破壊行為をノイズの特質としての否定と読み替えることも可能であるし、そもそもルイージ・ルッソロがその潮流の中にあった、未来派を創始した詩人のマリネッティの思想では、総破壊と結びつけて戦争賛美が述べられていて、これが後にファシズムを形成するひとつの影響となる。ここでファシズムの厄介な点として、様々な思想の評価できる部分を取捨選択して噴火後の火山に激烈に堆積するマグマのように大きく積み上がってきた点が挙げられる。ファシストによる否定として「反自由主義」「反共産主義」「反保守主義」があるが、そのどれも理論的には完全否定しているわけでなく、思想を形成する上で都合の良いように解釈して、野望へとムクムクとうねり昇ったのである。バクーニンの総破壊の思想の、美的アナキズム状態にあるノイズ・ミュージックへの影響については述べたが、権威に対しても破壊が作用するならば、民族主義の神話という権威の下人民が団結することも不可能なのではないか。だが、ファシズムはそのまま遂行され、生き残った。この一見都合の良いように見えるファシズムの取捨選択は、思想家全体を容認せずその一部を否定する行為なのか、それは止揚と呼べるものなのか。ただ、ノイズ・ミュージックにおける逃れられないパンク性によって、ENDONにも否定性・破壊性が存在する、ということは補足しておきたい。
そして、私自身も個人的な体験としてENDONのファシズム性を感じてしまったことがあるし、このことは論を進める中で決して葬り去れない体験であろう。私は前稿で、ENDONと我々の間には断絶が存在しそれによって崇高となっていて、本当にENDONの崇高を感受できるのならば、ライヴでは観客は拳を突き上げてモッシュなんかせずにその場に立ち尽くして口をあっけらかんと開けながら観るはずだ、というようなことを述べた。だがここで、ステージ上のENDONと呼応するかたちで拳を突き上げる現象には演者と観客の平等性が表れていて、断絶が由来の崇高を感じながら棒立ちで鑑賞することは、権威性に基づいた全体主義の現れである、と解釈することもできる。
ファシズムになり得るかもしれないという危うさ――これと関連した指摘は仲山ひふみ氏がINCAPACITANTSのライヴ・レポートにて家父長制的でナショナリズム的なファナティシズムへと容易に反転しかねないその危ういポテンシャル
と述べ、これは那倉氏の論考でも引用された。ここで注目しておきたい点としては、前述のような指摘は、まさに観客が演者と呼応して拳を突き上げてモッシュする様に対しての指摘である。私の先ほどの論理とは全く逆のことのように見える。仲山氏の指摘において直接は述べられてはいないが、拳を突き上げることと対立して置かれるのは棒立ちしてただただ演者を見つめることであろう。ただ、私の「棒立ち」と仲山氏のそれは内実に差異が存在する。仲山氏はノイズ・ライヴにおける拳を突き上げる行為を「フーリガン的」「筋肉性」優位であるとした。ホモソーシャリティに基づく強固な結束力の下行われ、反対に棒立ちについては、ある意味ソーシャル・ディスタンスをとった、実存に深く自問する態度であろう。それに対し前述の私における拳を突き上げる行為は“観客”と“演者”という関係性に絞って「平等」であり、棒立ちは二者を断絶し一方的な信仰心を抱かせる態度である。同じ行為でも内実は全くの逆に各々対応しているが、私における拳を突き上げる行為の平等性は、ライヴ会場やノイズ愛好家の界隈内のみで有効化するものであり、ある程度の排外的性格についてはこれを認めざるを得ないため、これも偏向がかったものである。
ENDONは“中心”を持ったノイズ・ミュージックである――このようなテーゼの下ここまで論を進めてきたわけであるが、本当にENDONが「新たに」得たものは果たして中心なのであろうか。ENDONの背後に存在するものは、ENDONが“中心”として希求するものなのだろうか。仮に“中心”を神とすると、神を希求するという芸術行為は、その芸術が神のために存在するものであり、手段ではなく目的として神が存在する。神を利用して作品の自立性を担保しようとするのならば、それは背神行為である。ファシズムにおいては“中心”として民族主義を掲げ、民族主義の権威主義的国家の形成を目的としたが、これはまさに“中心”を目的としている。ENDONではどうか。私は、民族主義や神といった固有名詞はその“中心”から観測することができない。そこにあるのは、まさしく自己なのではないだろうか。「中心の喪失」により美的アナキズム状態にあった芸術において、神等の他者概念に委託することなく“中心”に自己を置くことで、周縁と自己との境を無くし、そもそも“中心”という概念を超克する――これはそのままニーチェの超人思想に置き換えることができる。ルサンチマンの虚構性による神の死によって人間はニヒリズムに陥るが、寧ろニヒリズムを徹底させ没落も辞さず強烈に生を肯定することは、“中心”のない世界で自己が自己であるための実存を目的化させるという意味で、ENDONもその背後にあるのはENDONそのものであり、そもそも「背後」という言い方をせずに、そこにはENDONしかない。ステージ上にはENDONただそれだけが存立し、ENDON自身の“力”によって我々は崇高を感じるのである。ただややこしいことに、ニーチェ的な超人思想がENDONに現れているとしても、ファシズムの軛からは逃れることはできないだろう。ファシズムの取捨選択にはニーチェもその対象となっていて、弱者は天国に行くことができるとか革命を信仰して精神的に復讐を果たすこととかではなく、自立した意志によって強く生きることを説くニーチェの思想を政治化させたものがファシズムであるとも言える。
以上の事柄から、一応ENDONの超人的自立性というひとつの結論へ至ることができたと思うが、それ以上にファシズムの性質が露呈したものとなった。私は本稿を進めていくうちに段々と、全てを飲み込んでいき必要のないものは軽々と排泄してしまうファシズムの鬱陶しさに私自身も飲み込まれていきそうな感覚に陥った。だが、今ここで文章を進めていくことができているのも、その危うい綱の上で三半規管を必死に働かせているからであり、この危うさについては前述の仲山氏の記事にも表出されていく事柄である。ノイズ・ミュージックというエクストリームの最端において、ファシズムを始めとした様々な排外的事象に容易に反転が考えられることは、表現方法としてエクストリームを選択しようとも、深淵が飲み込まれようものならば、明らかにメタ的に見ることができない表象化が発生し、それは看過できない問題となる。ただ、ノイズ・ミュージックが実証的にエクストリームであって、ENDONに崇高を感じる以上、そのことを直視した上で自らの実存に語りかける必要がある。少なくとも私は、『Fall of Spring』を『Fall of Spring』として受け取るほかないだろう。
既に存在し得ない“中心”から漂う“妖気”は、ノイズによって超人としての実存を“亡霊”へと歪ませる。自己の格を疑いながら聴衆を嘲笑い、ノイズに乗せた妖気が我々を通り抜け、こう囁く。“This is a punishment, Time does not heal”。
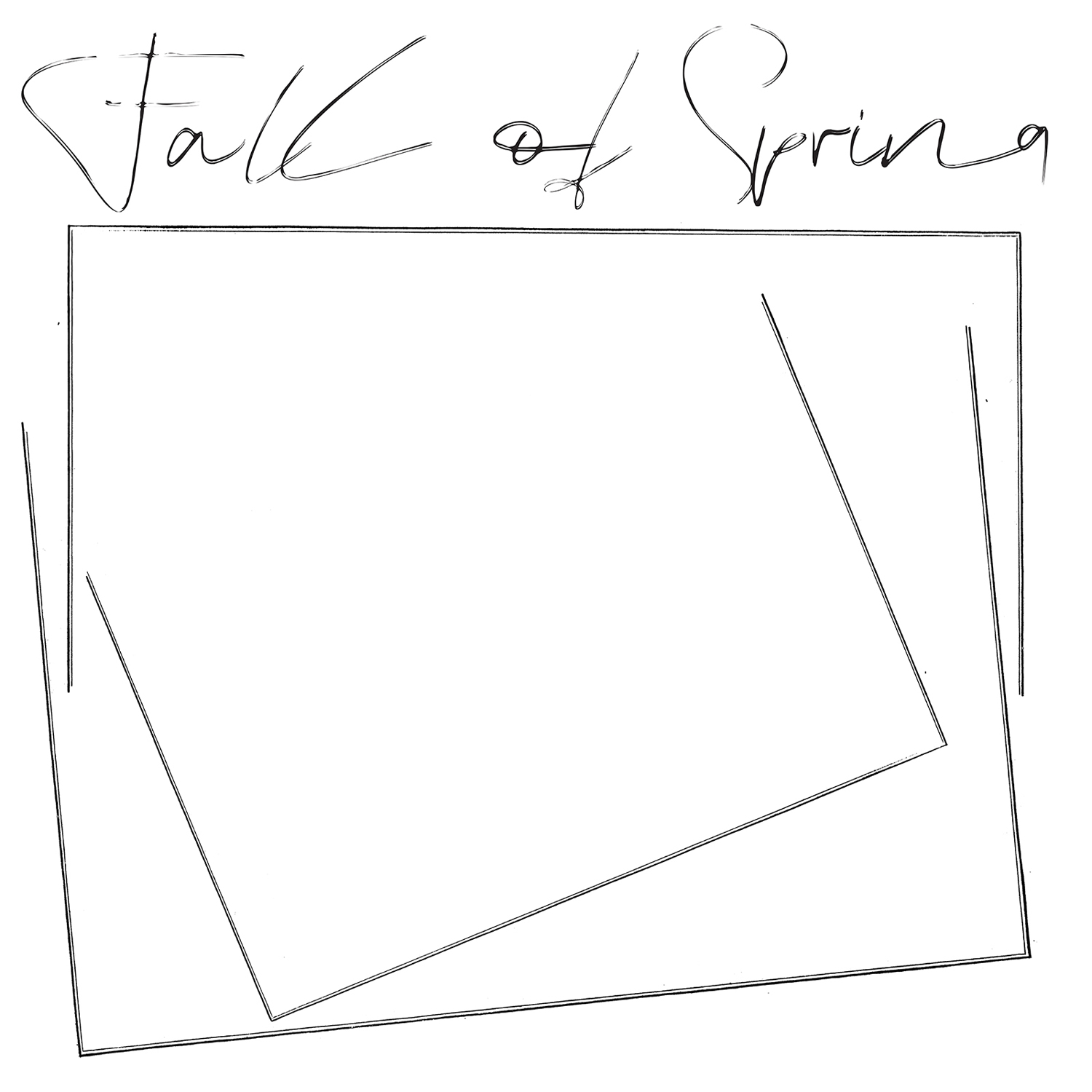 ■ 2024年8月21日(水)発売
■ 2024年8月21日(水)発売
ENDON
『Fall of Spring』
CD Daymare Recordings DYMC-400 2,500円 + 税
[収録曲]
01. Prelude For the Hollow
02. Hit Me
03. Time Does Not Heal
04. Escalation
05. Cross on My Fire *
* an extra track on CD edition only
[Vinyl]
8月23日(金)発売
Thrill Jockey Thrill-611
https://thrilljockey.com/products/fall-of-spring