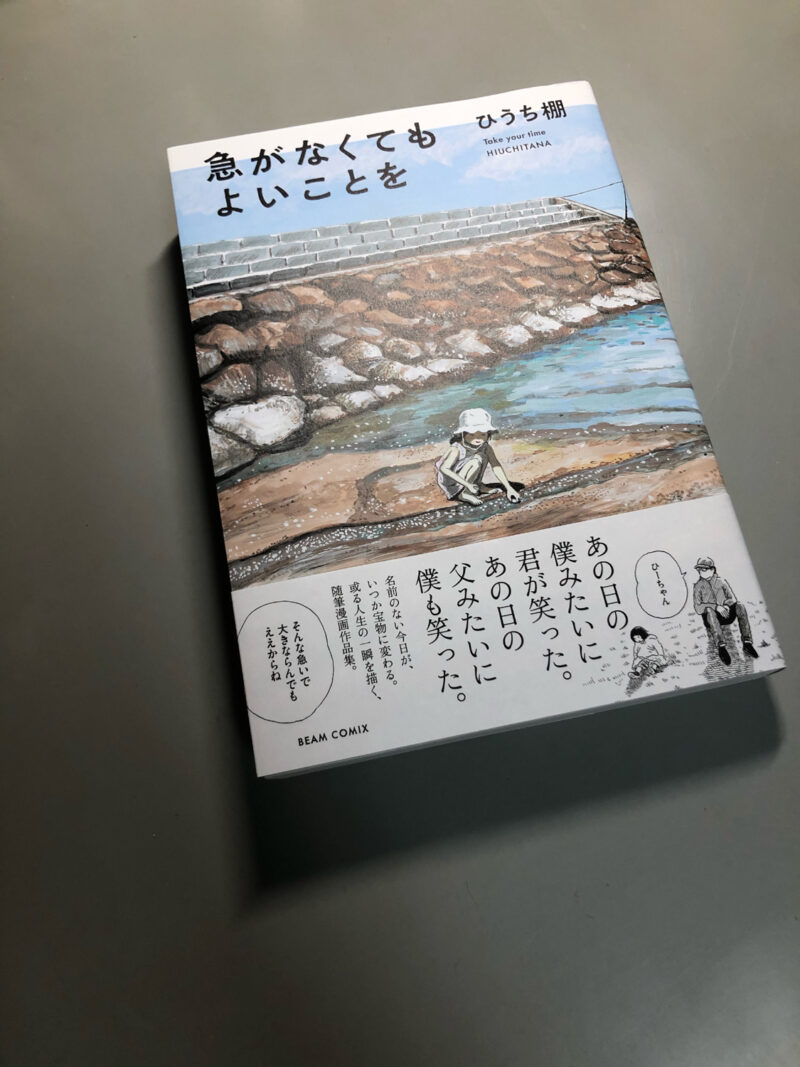文・撮影 | ミリ (Barbican Estate)
2021年の数少ない祭典が始まる。11月5日(金)より、東京・渋谷 Bunkamura ル・シネマにてヴィム・ヴェンダース監督の回顧上映、「ヴィム・ヴェンダース レトロスペクティブ ROAD MOVIES / 夢の涯てまでも」が始まるのだ。私は関係者でも何でもないが、ヴェンダースのしがないファンとして、この特集上映の成功を心から願うと同時に、今回上映される10作品のうち9作がヴェンダース自身の監修によるレストア版であるというから、あわよくば全作品を新たにソフト化していただきたく、可能な限り何度でも通って盛り上げたい!

なんといっても今回の目玉は、日本では長らくアクセスが困難な『夢の涯てまでも』(1991)のラインナップだが、そのことはまた別の機会に書くとして、まず私が個人的にプッシュしたいのは“ロードムービー3部作”と呼ばれる、『都会のアリス』(1974)、『まわり道』(1975)、『さすらい』(1976)である。「カンヌ国際映画祭」でパルムドールを受賞した『パリ・テキサス』(1984)や、同じくヴェンダースの代表作『ベルリン・天使の詩』(1987)は言うまでもなく至上の映画だが、それでも私はヴェンダースを映画作家として存在させる強さは“ロードムービー3部作”にあると思う。今回のレストア版特集上映の中では最も初期のこれらを初めて観るかた、すでに観たことがあるかたにもさらにおもしろさを感じていただけるよう、レビューを書いていく。

『都会のアリス』(1974) アメリカに嫌気がさした青年と、生意気でませた少女アリスがアメリカ・ニューヨークからオランダ・アムステルダムを経てドイツの町々をめぐる旅を描く『都会のアリス』。以降ヴェンダースの作品ではアリスの視線、アリスのキャラクター像そのものは反復される。『パリ・テキサス』の主人公の息子ハンターは姿形、服装に至るまでアリスにそっくりな少年だ。
興行的にも、ヴェンダース本人的にも失敗作だった前作『緋文字』(1973)で、彼はイェラ・ロットレンダーという子役と出会った。彼女から着想を得て、ジャーナリストの男がぶっきらぼうな9歳の少女アリスと、ひょんなことから彼女の記憶を頼りに祖母の家を探す旅に出るという『都会のアリス』の脚本を書き上げた。実は『都会のアリス』の完成は奇跡だ。ヴェンダースが脚本を書き上げようとしていた1973年の夏、彼はピーター・ボグダノヴィッチの新作『ペーパー・ムーン』(1973)を観て、すっかり打ちのめされてしまった。『ペーパー・ムーン』の脚本は『都会のアリス』のそれとあまりに酷似していて、そして素晴らしかったからだ。ヴェンダースは企画の中止を考えたが、サミュエル・フラーの説得、助言によって脚本は書き変えられた。実際、テーマやラストの展開までふたつの映画は似た点も非常に多いが、私は最も大きな違いにそのカメラがあると思う。
『ペーパー・ムーン』に限らず、それまでのロードムービーではしばしば車に乗る人物は真正面、もしくは真後ろから映されることが多かった。車は移動していてもカメラは固定で、密室での会話に重点が置かれる。対照的に『都会のアリス』では車に乗るふたりはいつも真横から捉えられる。さらに助手席で退屈そうにしているアリスの主観ショットにより、流れゆく風景が随時挿入され、観客は同乗者と同じ自由な視点を得る。男がアリスに何かを尋ねても、アリスは空返事をし、答えないこともある。逆にアリスが男に何かを言っても、彼も同じようにする、車内はむしろ常にディスコミュニケーションの状態だ。ヴェンダースは古典ロードムービーの会話劇を否定し、“移動”そのものを観客に感じ取らせることに成功している。
『まわり道』(1975) ナスターシャ・キンスキーの初登場シーン。彼女は最初こそ子供っぽいが『まわり道』の修行の旅を経て映画のラストでは信じられないほど大人びている。共演するファスビンダー・ファミリーの俳優、ハンナ・シグラに引けを取らない貫禄だ。
“教養小説”、あるいは“発展小説”と呼ばれるジャンルの小説、ゲーテの『ヴィルヘルム・マイスターの修行時代』を基に、ヴェンダースとは度々タッグを組んでいる作家ペーター・ハントケが大胆に脚色した現代劇が『まわり道』だ。作家を志す主人公の青年は、旅に出ることで小説を書き上げようとする。旅では大道芸人や恋仲になる女優、口を利かない少女、詩人など様々な人を道連れにし、戦後ドイツの責任や人々の孤独感、男女とそして家族の在り方について、ヴェンダースの後年の作品と比べても『まわり道』は最も直接的な語りと、問題定義がなされている。1975年という東西ドイツ分断の真っ只中に政治と家族に関するストーリー・テリングと、失われた風景への哀愁とが文学作品を通じて融合したのだ。
『まわり道』で無口な少女ミニョンを演じるのは、これが映画デビューとなったナスターシャ・キンスキーだ。ヴェンダースはロック・クラブで踊る彼女を見かけて、ドイツの怪優クラウス・キンスキーの娘と知らずにスカウトした(初めは18歳だと聞かされていたが、いざ契約の段になるとナスターシャは14歳だった)。近頃毎年日本のカルチャー誌ではピンクのモヘアニットを着た『パリ・テキサス』のナスターシャが表紙になっており、同作はおしゃれ映画の代名詞のようになっているが、その出発点である無骨な『まわり道』を観て、ぜひ彼らと一緒にドイツの地方都市を発見してほしい。
『さすらい』(1976) 『まわり道』の撮影中、ドイツの田舎にたくさんの魅力的な場所を発見したヴェンダースは、ついに脚本の全くない行き当たりばったりの映画を作りたいと役者も含むスタッフ5人で『さすらい』の旅に出た。実際はどうにも撮影が立ち行かなくなり道中である程度のシナリオを書いたが、『さすらい』が究極のロードムービーであることに変わりはない。
愚問だが「いちばん好きな映画は何ですか」と聞かれた時、私はいつも『さすらい』だと答える。地方の映画館を巡業する映写機修理技師の男と、人生に絶望した謎の男のふたりが、映画のフィルムとレコード・プレーヤーを積んだ大型トラックで廃館寸前の映画館を転々としながら国境沿いの西ドイツを淡々と移動してゆく、176分の怠惰でコラージュ的とも言える大作だ。原題の『Im Lauf der Zeit』(= 時の流れるままに)の通り、この“時間”に上手く乗ることができなければ、それはもう本当に退屈な映画かもしれない。ただし逆にこの“時間”にフッと乗ってしまうと映画が永遠と続いてほしい、終わらないでほしいと渇望してしまう。
そのトラックでは当然寝泊りすることもでき、完全に守られた小宇宙なのだが、ふたりの男は女や家族のいる世界への憧れも捨てることができない。守られた空間にも徐々に苛立ちを募らせてゆき、ふたりの男は別れてはまた合流を繰り返す。このふたりの関係性はヴェンダースにとってのドイツとアメリカの関係なのだと私は思う。ドイツ・デュッセルドルフ生まれのヴェンダースは15歳の頃にアメリカのロック・ミュージックに出会って以降、それが彼の一番の友人になった。21歳でパリのシネマテーク・フランセーズに通い詰め、黄金期ハリウッドと、またドイツ人映画監督フリッツ・ラングとF.W.ムルナウのアメリカ時代の作品に出会った。ヴェンダースのアメリカへ想像は異様なまでに膨らんでいたが、いざ憧れの地アメリカと現実的遭遇を果たした1971年は時すでに遅く、ハリウッドの官能性は消え去っていた。商業的かつ画一的な映画やテレビに耐えかねたヴェンダースは、半ば逃げ帰ってくるようにドイツに戻った。
しかし彼が完全にアメリカを意識しなくなったということは決してなく、『イージーライダー』(1969)や『断絶』(1971)など彼の映画作りの手本にもなっている“アメリカン・ニューシネマ”のムーヴメント、それ産んだアメリカに属せなかったということは、以後彼の多大なコンプレックスになっており、それが“ロードムービー3部作”、とりわけ『さすらい』を形成している。トラックの荷台にはフリッツ・ラングの写真がある。かつてラングやムルナウはハリウッド以上に大作を作っていたことでハリウッドに迎えられたが、『さすらい』で登場するドイツの田舎の映画館では、今やポルノ映画ばかりが上映され、ロマンティックなハリウッドのフィルムがかかることはない。ムルナウやラングら故郷の映画の父をアメリカに奪われ、そしてハリウッドから拒絶された陸の孤島の絶望を、ムルナウの恐怖映画さながらのシャープなモノクロ映像で紡いでいく。
“ロードムービー3部作”は作家個人の劣等感や、ドイツの土地が持つ暗い歴史が浮き彫りになるが、しかしどれも暗い映画ではない。むしろ登場人物たちはいつもBob Dylanなり、CANNED HEATなり、アメリカのロックを口ずさんで非常に楽観的であり、可笑しく、最後には必ず変化や発展がある。以後の『アメリカの友人』、そして『パリ・テキサス』でヴェンダースのアメリカへの私的な愛憎、葛藤はついに収支決算が済まされるが、それは“ロードムービー3部作”の修行時代なくしてはあり得なかっただろう。実際『さすらい』のラスト・シーンほどに美しい映画に私は未だ出会えていない。どうか最後まで寝ないで、いや寝てしまったとしても画面に映る移動そのものに身を任せて“ロードムービー3部作”を堪能してほしい。

■ 2021年11月5日(金)-12月16日(木)
『ヴィム・ヴェンダース レトロスペクティブ ROAD MOVIES / 夢の涯てまでも』
東京・渋谷 Bunkamura ル・シネマ(全国順次開催)
http://wenders-retrospective2021.com/
[上映作品]
『都会のアリス 2Kレストア版』『まわり道 4Kレストア版』『さすらい 4Kレストア版』『アメリカの友人 4Kレストア版』『パリ、テキサス 2Kレストア版』『東京画 2K レストア版』『ベルリン・天使の詩 4Kレストア版』『都市とモードのビデオノート 4Kレストア版』『夢の涯てまでも ディレクターズカット 4Kレストア版』『ブエナ・ビスタ・ソシアル・クラブ』
[上映スケジュール]
https://www.bunkamura.co.jp/cinema/lineup/21_wim_wenders.html
Instagram | Twitter
 東京を拠点に活動するエクスペリメンタル / サイケデリック / ノーウェイヴ・バンドBarbican Estateのベース / ヴォーカル。ロック・パーティ「SUPERFUZZ」などでのDJ活動を経て2019年にバンドを結成。2020年3月、1st EP『Barbican Estate』を「Rhyming Slang」よりリリース。9月にはヒロ杉山率いるアート・ユニット「Enlightenment」とのコラボレーションによるMV「Gravity of the Sun」で注目を浴びる。同年10月からシングル3部作『White Jazz』『Obsessed』『The Innocent One』を3ヶ月連続リリース。今年3月にLana Del Reyのカヴァー「Venice Bitch」をYouTubeとIGTVで公開。4月9日に「The Innocent One」のMVを公開。9ヶ月ぶりのシングル『The Divine Image』を9月22日にリリース。
東京を拠点に活動するエクスペリメンタル / サイケデリック / ノーウェイヴ・バンドBarbican Estateのベース / ヴォーカル。ロック・パーティ「SUPERFUZZ」などでのDJ活動を経て2019年にバンドを結成。2020年3月、1st EP『Barbican Estate』を「Rhyming Slang」よりリリース。9月にはヒロ杉山率いるアート・ユニット「Enlightenment」とのコラボレーションによるMV「Gravity of the Sun」で注目を浴びる。同年10月からシングル3部作『White Jazz』『Obsessed』『The Innocent One』を3ヶ月連続リリース。今年3月にLana Del Reyのカヴァー「Venice Bitch」をYouTubeとIGTVで公開。4月9日に「The Innocent One」のMVを公開。9ヶ月ぶりのシングル『The Divine Image』を9月22日にリリース。
明治学院大学芸術学科卒。主にヨーロッパ映画を研究。好きな作家はヴィム・ヴェンダース。