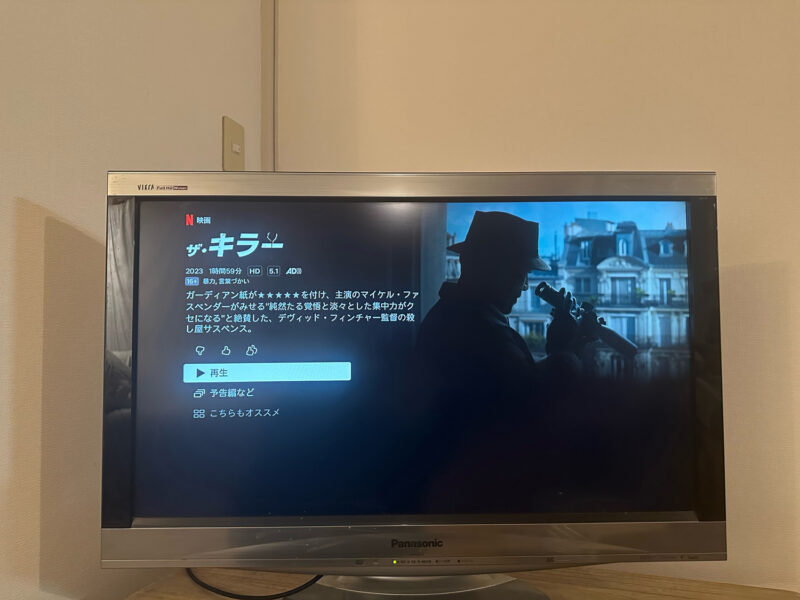「ボウイって永遠の中二病だよね」
2017年、東京。自身の誕生日である1月8日から4ヶ月に亘って開催された、David Bowieの世界観やキャリアを総括した大回顧展「DAVID BOWIE is」を一緒に回りながら、知人はぽつりとそう漏らした。豪華な衣装やレアな機材は勿論のこと、ファンからの手紙、読んだ本、創作時に使ったペンやメモの切れ端のみならず、少しの間住んでいたベルリンのアパートの鍵、果てはコカインを吸い込むときのスプーン(実に中二的グッズ)まで展示され……いやその前に、こんな些細なものまで何十年も保管し、自分の意志で御開帳して「展覧会」をする人物、一体どんな自意識(エゴ)の持ち主なんだよ、とファンでないかたは若干引いてしまうだろうか。もしくは、やっぱりそのくらいナルシストじゃないと世界のロック・スターは勤まらんよなあ、としみじみしてしまうだろうか。説明不要かもしれないが、“中二病”とは思春期に特徴的な、過剰な自意識やそれに基づくふるまいを揶揄する俗語。具体的には、不自然に大人びた言動や、自分が特別な存在であるという根拠のない思い込み、またはコンプレックスなどを指す。名称は、その年代の子供が抱きがちな心理状態であることから、一過性の病気に見立てたもの
(『デジタル大辞泉』より)である。ボウイは中二病。私は噴き出しつつ「そうですね」と同意した。同意したけれど、一過性の
と切り捨ててしまいがちな、子供の頃のナイーヴな時期や心を、私たちファンはボウイと共に肯定してきたはずだ。きみのその気持ちはずっと大切に持ったまま大人になってもいいんだよ、と澄ましたロックスターの仮面の隙間から、人懐こい笑顔で頷いてくれるような。きっとボウイを好きになった誰もが、そういうイメージを持っているのではないかと思う。

ブレット・モーゲン監督『デヴィッド・ボウイ ムーンエイジ・デイドリーム』は、この「DAVID BOWIE is」の延長線上にある映像作品と位置付けられるだろう。所謂アーティストのキャリアを紹介するドキュメンタリーではない。第三者のナレーションや関係者の証言などは一切なく、「デヴィッド・ボウイ財団」が保有する膨大なフッテージ (音楽のデモ・テープのような、ダンスやパフォーマンスの個人的な映像もたくさん残っているようだった)、生前にボウイ自身が残した音声のみで構成されている。そのため、やはりファン以外の人々には少々とっつきにくい内容であろう。ロックのレジェンドを取り扱ったものとしては格別のヒットを飛ばした、ブライアン・シンガー監督によるQUEENの伝記的娯楽映画『ボヘミアン・ラプソディ』(2018)のような楽しみかたは期待できない。ボウイの内省的な言葉や音楽に耳を傾け、彼の人生のコアな部分を追体験するような作品だ。映像には様々なエフェクトがかけられ、編集され、ボウイの多くのアルバムのプロデューサーとして関わってきたTony Viscontiが手掛けた劇伴も手伝って、翻訳された歌詞とボウイのコメントを脳内で繋ぎ合わせつつ、自分自身とボウイの対峙一本勝負!!! といった感覚に、私は再び陥った。
……どうだろうか。ますます、ファン以外の足は遠のいてしまっただろうか?違うんだ!!! 待ってくれ!!! ユーアーノットアローン!!!(「ロックンロールの自殺者 Rock 'N' Roll Suicide」より)
だいたい、これを書いている私自身、“アーティスト”ボウイに支えられ、リアル“中二”時代から細々と創作活動を続けているタイプの人間であって、“すばらしいアーティストの姿勢や思想を追体験する”ことは意味があり、必要なことだろうが、それ以外の観客にとっては『ボヘミアン・ラプソディ』のような物語を、このハードな現実を束の間忘れ愉しむことに魅力を感じるだろう。そういった考えを否定したくはない。ボウイは以前から、そのポップな存在感とは裏腹に、(ちょっと先輩格ではあるが)THE BEATLESやTHE ROLLING STONESが持っているようなトレードマーク的にすぐ思い浮かぶ曲がないと言われてきた。こと日本では、David Bowieと言われて真っ先に思い浮かぶのは大島 渚監督『戦場のメリークリスマス』(1983)で演じたジャック・セリアス大佐としての姿で、なんなら坂本龍一作の例のピアノによるテーマ曲をボウイの曲だと思っている人すら少なくないようだ。ボウイは“シリアス・ミュージックの王様”だと英国では揶揄されている側面もあると先日小耳に挟んだのだが、これも“永遠の中二病”評価と似ている。シリアス、つまり歌詞も曲も難解でいかにも深刻そうで、謎解きを撒かれたファンはそれらを解釈するのに夢中になるオタク気質が多いよね(笑)、というのだ。本国でもそんな感じなのだから、一発でドアを開けられなければどこから入ればいいのかと立ち往生してしまうことは想像に易い。そういった評価が間違っているとも、ドア一発開きだった私の口からは決して言えないが、果たしてボウイ自身が“内向き”……インナースペースを彷徨い続ける宇宙飛行士だったのかというと、そういうわけでもないということに、このすさまじく“内向き”な映画を観て改めて至った次第である。
ボウイは言う。大切なのは 何をするかで 時間のあるなしや 望みなんか関係ない
16歳の時から 誰にもできない大冒険をしようと決めていた
(予告編より)……生まれてから69年間、癌を患っても本当に最後の最後まで、創作へ捧げた人生だった。音楽を中心に据えつつ、ファッションで衆目を集めたり、舞台に立ったり作ったり、勿論映画にも多数出演した(その映画のほとんどがB級作品というのだからおもしろい、というか愛おしい)。もう少し細かく辿ろう。Ziggy Stardustというキャラクターを作り出し、渇望した成功をやっと手にしても思い切り良く捨ててドラッグにもハマり(ケルアックやバロウズを尊敬していた身としてジャンキーの暮らしを体験をしてみたいという……、なんならわざとなんじゃないかとすら思う)、回復の後にあっけらかんと小綺麗な英国紳士としてお茶の間に向けてスマッシュ・ヒットを発射し(『Let's Dance』!さあアイドルとして翻弄されてみよう、浮ついた80年代の空気への挑戦だ。この時期はボウイ・ファンにこそ人気がなく、モーゲン監督自身も見返すのは苦痛、とまでコメントしている笑)、反動からかソロを解体してバンドの一員になり(普通は逆なのだが……)、迎えた病める90年代という時代を若いミュージシャンや新しい音楽と戯れ、その名も「ボウイ債」と呼ばれる資産担保証券を発行してエンターテイメント産業の資金調達の新しいかたちを示し(そのヒントから音楽ギョーカイは何か考えたのだろうか?)、インターネットにいち早く飛びつき、健康的な“ロックおじさん”になった。“家族”という小さな共同体の中で父というポジションに着地してから、2010年代前後から亡くなるまではインタビューに応えることは一切やめ、つまり、沈黙したのだ(“沈黙”も“行動”である)。植民地主義帝国出身、金髪碧眼イケメンの白人男性という強者の立場をあえて切符のように利用して、ボウイは世界中を飛び回った。定住することに魅力を感じない、と日本にも住んでいたこともある(ベルリン時代のような泥臭い生活をしていたわけでもなさそうだが)。……これだけ並べるとどこも“内向き”な感じはなく、非常にアクティヴな足取りである。しかし、まさに自身が“孤独”をれっきと堅持しているからこそ、これだけの旅ができたのだろう。世界の広大さと同じだけ広い世界を、様々な出会いを通して自身の“孤独”の中に作り上げたのだ。ボウイ終焉の地は結果ニューヨークであったが、トランプ政権とコロナ禍を、彼は体験はしなかった。特にCOVID-19は世界同時多発的に駆け巡り、この目に見えないウイルス自体が存在しないと息巻いている人々と、それ以外の人々(恐れかたも実に様々である)との間に、家庭内やパートナー、友人間であっても容赦なく分断を生み、誰しもが持っているはずの“孤独”とうまく対峙できない個人の弱さを炙り出したとは言えまいか。繊細で、不安で、それ故にカルト宗教や根のないスピリチュアリティ、インチキ医療などに飛びつく。付け込んでいた側もだんだんと自らがそれに飲まれていく事態は、テレビをつけてもネットを開いても、もちろん身近なところでも、今いくらでも転がっている。それを冷めた目で観察しながらどこか馬鹿にし切れず、空恐ろしさを感じる人もまた、多いのではないだろうか。あからさまになった全人類が考えるべき問題に惑わされ、身動きが取れなくならないために、David Bowieの生きることへのポジティヴな情熱から学ぶことは大いにあると思われる。この映画には、大切なコードがたくさん書き込まれている。国語の教科書でおなじみの、星 新一『おみやげ』のように。……あれ、まだ載っているのかな??

ボウイは世間一般的にグラム・ロックの象徴とされているところも大きいためか、トッド・ヘインズ監督『ヴェルヴェット・ゴールドマイン』(1998)や、最近ではガブリエル・レンジ監督『スターダスト』(2020)など、完全に同人二次創作のような作品も作られており、これらについて私個人としては微笑ましい、やれるならやっちゃうよね~!以上の感想はないのであるが、ボウイ本人やボウイの遺族はこういった動きを好ましく思っていなかった。あくまで自分の作品は自分の手の内の中で完結させたいというアーティストとしての意志が働いているのだろうし、それは全く尊重されるべきだ。そんな中、今回の『デヴィッド・ボウイ ムーンエイジ・デイドリーム』に関しては、「デヴィッド・ボウイ財団」公認の初めての映画作品、というのは当然目玉である。ボウイは生前、「DAVID BOWIE is」の映像版もイメージにあったようで、モーゲン監督とちょっとしたミーティングの機会も持っていたらしい。監督自身、制作の初期に心臓発作を起こして一週間昏睡状態になり、ボウイの“すべての瞬間を成長に利用する”生きかたがより迫ってきたとのこと。いやあ、完全にボウイに憑りつかれている感がある、安心するなあ(←もしかしたら最低のことを言っている)!本当に良かった、ご無事で。そして、今回の作品の中で、ようやくその美しい姿が大々的にスクリーンに現れた。彼女とゆっくり過ごしたいからスロウペースな活動に切り替えたいと本編でも語られる、ボウイの最後にして最愛の伴侶、イマン・モハメド・アブドゥルマジドである。主にジギー時代の妻であり、成り上がるときの相方でもあったアンジェラ・ボウイは、ボウイ伝説の中でよくよく登場していたわけだが、イマンに関してはあまりフォーカスされてこなかった。注目していただきたいので、彼女のことを書く。
イマンは1955年生まれ(ちなみにボウイは1947年生まれなので、歳下とはいえわずか8歳差、男性スター界隈では珍しいパターンであろう。イマンのほうが離婚歴が多いことも)。16歳のときに、祖国ソマリアからケニアへ家族と共に逃げてきた、つまり難民である。NGO団体に保護され、大学では政治学を学び、1976年にその抜群のスタイルと美貌(小さな頭、細く長い首に手足、アーモンド型の瞳に真珠のような歯並び、輝く黒い肌。しかしイマンはケニア人としては平均的な容姿だと言っているそうだ。これは謙遜ではなく、単なる彼女にとっての事実として述べているだけだと思う。なんと美しい、と溜息を吐きつつ、ハテ、美しい人間、とは……?)、5ヶ国語を駆使する頭脳明晰さを買われてモデル・デビュー。ナオミ・キャンベルらと共に80年代から90年代にかけて“黒人の女性スーパーモデル”として活躍した。白人モデルとの賃金の差に抗議して労働環境改善を促したり、やがて有色人種向けの化粧品会社を立ち上げ、そちらでも成功。それについてイマンは、“肌が黒い = 肌が強い”という偏見があるし、自身がモデルを始めた時代には黒い肌のファンデーションやスキンケア用品というものは存在すらしていなかった。難民問題も美容やファッションも、全て政治と深く関係している。あらゆる分野において平等と多様性が一番大切だと、自分のブランドを通じて伝えたい、という旨の発言をしている。3度の結婚を経ても、本名をそのままキープした。現在は途上国を中心に貧困撲滅のため尽力する団体「CARE」、HIVで親を亡くした子どもたちの支援団体「Keep a Child Alive」や、ダイヤモンドやレアメタルといったアフリカにおける紛争の火種となる鉱物を巡る虐殺や汚職等の終焉を目指すNPO団体「Enough Project」など、様々な慈善事業に関わっている。ボウイは彼女がデビューした1976年、アメリカの黒人音楽専門番組「Soul Train」に登場した。白人アーティストがこういったテレビ番組に出演することはまだ相当なレアケースであった。モーガン・ネヴィル監督のドキュメンタリー『バックコーラスの歌姫たち』(2013)でも、そのときの様子を垣間見ることができる。素晴らしい作品だったので、ぜひチェックしてほしい。当時ドラッグの問題を抱えていたせいでガリガリのボウイは、それでもブラックのミュージシャンたちと楽しそうに打ち合わせをしていて、80年代に入って登場したMTVでもブラック・ミュージックが流れる機会が少なすぎる、と珍しく険しい顔つきでインタビュアーに苦言を呈している映像もYouTubeなどで観ることができる。私は1984年生まれで、幼い頃はMichael JacksonやWhitney Houstonに夢中になった。テレビの向こう側で煌びやかに唄って踊る彼 / 彼女らを見て、黒人差別だなんてバカバカしいものはまったく過去の遺物だと勘違いしていた。しかし2023年になっても、黒人に限らず人種差別問題解決の目処はつかず、事態は最悪最低なままだ。スターがキラキラしていれば魔法のように偏見が解ける、そんな簡単な構造ではないことを痛感する日々である。イマンとボウイの間にも子供がいる。黒人スーパーモデルと白人ロックスターを親に持ったとしても、肌の色のせいで様々な困難に直面するだろうことを2人が考えなかったわけがない。ボウイの最後の作品である『★』は、自分と同じ誕生日であったElvis Presleyが、ネイティヴ・アメリカンと白人のアイデンティティの間で揺れ動く主人公を演じたドン・シーゲル監督『燃える平原児』(1960 | すごい邦題)の主題歌、「Flaming Star」からインスパイアをされているのではないかという有名な説がある。この曲はそもそも「Black Star」というタイトルであり、1960年の映画作品ということを鑑みると変更の理由も様々あるのだろうが、どちらのヴァージョンもエルヴィスの歌唱でレコーディングされている。アルバムのタイトルを呼ぶときは“black star”と発声しなければならないが、記号の“★”の表記であることは、歌詞やタイトルで言葉遊びを多様したボウイ最後の謎かけとして、死後7年経った今も考え、なんなら愉しめてしまうのだ。舌触りの良い感想など全て吸い込まれ、思わず足がすくむような、ダークで重苦しい、それでいて希望も感じさせる、歴然とカッコいいロックな遺作である。さらに、そのプレスリーの娘Lisa Marie Presley(先日訃報を聞いたばかりだ)と結婚したこともあるMichael Jacksonは「Remember The Time」(1991 | 『Dangerous』収録)という曲のMV(1992)でイマンと共演している。僕と恋に落ちたことを覚えてる?
と繰り返し唱えられるその曲では、エジプトの女王役の彼女と煽情的なキスシーンも堂々披露し、子供じゃないもん!とブレイクスルーしようとしたマイケルの葛藤の痕跡を見ることができる。ボウイがイマンと結婚した(1993)ことに関して、白人男性が黒人女性を妻にすることで“意識高い系”なアピールになる、イマンほどの女性ですら一種のトロフィ・ワイフでしかない、というゴシップ(?)に対し、そのちょうど逆位置にいたと言えるマイケルの、何かメッセージのようなものを個人的には感じているのだが……。金も地位も持ち得た特権的な立場から行う様々なことを、セレブレティの慈善事業だ、結局は偽善だよね、と常に斜めから見上げられていたストレスを、イマン、ボウイ、そしてマイケルも、自分のラッキーを常に自己批判しつつ、それでもと諸問題に何かアプローチしていたはずだと思う。特別なセレブでなくとも、自分の立っている位置から見て、できる範囲で誰かを援助をしたり、マイノリティへの想いを馳せること。白昼夢のなかで足掻いた経験こそ、現実を少しでも変えようと動くことに繋げるべきだと、私は強く思う。……おっと。またボウイのラビリンス(魔王の迷宮)に迷い込んでしまったようだ。出来の悪い陰謀論よりも、こっちの“おもちゃ”のほうが楽しいよ!と伝えたいのだが……、どうですか?!?!

まずはこの映画の表題曲「Moonage Daydream」を部屋でひとり、もしくは誰かを誘って?寝転んで聴きながら、歌詞を読み、それからぜひ、劇場に足を運んでほしい。わざわざレコードやCDを買わなくても、これが読めているあなたには、簡単にできるはずだ。この世にはもういない、けれどボウイは起き上がらせてくれる。背中を押してくれる。彼は、何かしたい、生きたいと願う人々を現実に向かわせるためにこそ、ロックンロールを使ったスターだった。ささやかながら、同じことを私もなぞってみよう。
"Moonage Daydream"
I'm an alligator,
I'm a mama-papa coming for you
I'm the space invader,
I'll be a rock 'n' rollin' bitch for youKeep your mouth shut,
you're squawking like a pink monkey bird
And I’m busting up my brains for the wordsKeep your 'lectric eye on me babe
Put your ray gun to my head
Press your space face close to mine, loveFreak out in a moonage daydream oh yeah!
Don't fake it baby, lay the real thing on me
The church of man, love
Is such a holy place to be
Make me baby, make me know you really care
Make me jump into the airKeep your 'lectric eye on me babe
Put your ray gun to my head
Press your space face close to mine, love
Freak out in a moonage daydream oh yeah!
♬ジャーッジャジャン♬
はあい、ワニでーす✌︎
同時にきみの母であり、父。
それでいて宇宙を侵略する異星人。
ロックンロール・ビッチ!つまり両性具有だ。
きみのためにこそやってきた。
静かにしな!
ごちゃごちゃ言うんじゃないよ!
こっちの脳みそまで変になっちゃうじゃんか
だけど、
ごまかさなくてもだいじょうぶ。
本心を俺に投影してくれていい。
俺を聖堂にして使い込んでくれ。
もっとへんなことを考えていい。
もっと俺を、まるでないものみたいに、
宙に放り投げてくれていい。
どうぞ視線を注いで、
ただし、視点は沢山もつんだよ。
しょせんは中二病の白昼夢、と他人からは言われちまうんだから。
気持ちはわかる、でも気にしすぎるなよ、
それよりいっしょにあそぼう。
妄想しまくろう、
フリーク・アウトしよう、
よっしゃ 出ようぜ!!!
 ■ 2023年3月24日(金)全国公開
■ 2023年3月24日(金)全国公開
『デヴィッド・ボウイ ムーンエイジ・デイドリーム』
IMAX® & Dolby Atmos® 同時公開
https://dbmd.jp/ | Twitter | Instagram
[監督・脚本・編集・製作]
ブレット・モーゲン(『くたばれ!ハリウッド』『COBAIN モンタージュ・オブ・ヘック』)
[音楽]
トニー・ヴィスコンティ(David Bowie, T.REX, THE YELLOW MONKEY etc.)
[音響]
ポール・マッセイ(『ボヘミアン・ラプソディ』『007 ノータイム・トゥ・ダイ』)
[出演]
デヴィッド・ボウイ
字幕: 石田泰子
字幕監修: 大鷹俊一
配給: パルコ ユニバーサル映画
宣伝: スキップ
配給: ハピネットファントム・スタジオ
2022年 | ドイツ・アメリカ | カラー | 135分 | スコープサイズ | 英語 | 原題: MOONAGE DAYDREAM
©2022 STARMAN PRODUCTIONS, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

Official Site | Instagram | Twitter
広島県出身。2005年東京にてHOMMヨ結成、ギター / ヴォーカル担当。2020年よりソロ活動開始。2021年末1stソロ・アルバム『The Parallax View』発売。弾き語りライヴを中心にトークやエッセイ執筆、作詞、ジン製作など、闇雲に動いている。
| 『The Parallax View』特設サイト
https://www.trash-up.com/niimariko1/