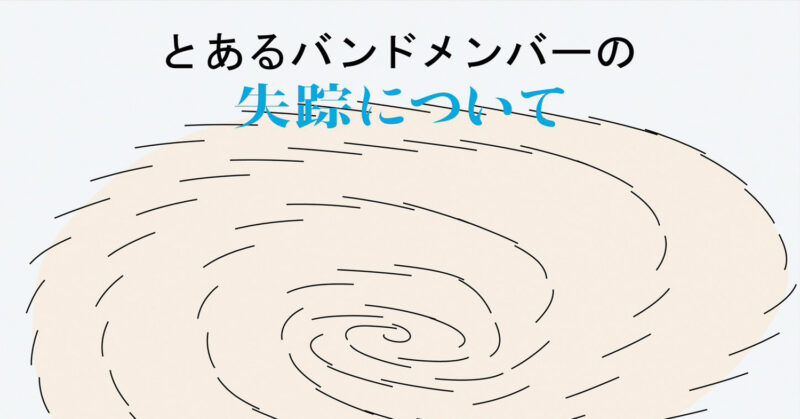自分たちが何を重要視しているか
ギターの牧野琢磨、コントラバスの服部将典が本作のレコーディングのスタートと認めている日付が2020年2月14日。その翌月には日本中で多くのライブやイベントが中止 / 延期となっていったことを思い出す。そこから2年強を経て、バンドとしては異例となるリモートでの音源制作も交えながら完成した『こもん』は、文字通り“コロナ禍という非日常の記録”と言える作品だ。
だが、そうした性質を否応なく帯びたアルバムでありながら、ここにはコロナ禍以前どころか、彼らが結成以来15年を貫く、淡々とした自覚のようなものもしっかりと続いている。
それはNRQの1stアルバム『Old Ghost Town』(2010)から変わらないと言えば変わらない。ひとことで言えば、その匂いは、“異”。じつのところ彼らは、2000年代後半から東京のインディ・アクトたちと個々に交錯し助力もする重要プレイヤーたちであったし、2010年代に大きく浮上してゆくceroや片想い、ホライズン山下宅配便、VIDEOTAPEMUSICらともNRQは平然と同じ場所にいた。朱に交わって紅くなるというより、NRQはNRQのまま。突出した違和感を周囲に振りまくようなわけではなく、むしろその逆で、彼らの音楽や演奏はアート性というより日々に根差す。日常のなかでふと気づく懐かしい気配のように香り、そして、彼らが“異”のままであることはピリッと走る静電気のような緊張感とともに、いつでもぼくにNRQを新しく発見させた。
新作『こもん』には、いろんな意味でそんな彼らの本質がもっともあらわになっている感覚がある。インタビューに答えてくれた牧野(以下 M)と服部(以下 H)は、奇しくもこのアルバムの制作の始点に居合わせた2人でもある。両者の言葉を楽曲ごとに聞くなど、今回のリリース元であるSweet Dreams Pressの福田教雄(以下 F)を交え、ついつい話は2時間近くに及んだ。
取材・文 | 松永良平 | 2022年5月
写真 | 山口こすも
――Sweet Dreams Pressのサイトで『こもん』についてパンスさんが書いた文章(『こもん』に寄せて)を読みました。
M 「あの文章を書くにあたってパンスくんが“会いたい”と言ってくれて、新宿でちょっとおしゃべりしたんです。実は初対面だったんですよ」
――それは意外。お客さんとしてはNRQを観ていたそうだけど。
M 「僕も彼の読者だったんです。TVODの本(『政治家失言クロニクル』2021, ele-king books)も買ってた。歳も近いし、問題意識も通じるところが多い」
――パンスくんが初めて観たNRQのライヴがストラーダとの対バンだったというのもすごい。
M 「そういうことは知らずにお願いしましたね」
――今回はSweet Dreams Pressからのリリースという新しい環境でもあります。
M 「僕らからお願いしたんです。前のレーベル(P-Vine)が不満とかではなく、なんとなくいつも他者(のまなざし)は必要だし、それがあったほうがおもしろいというのが確信としてあって。自分たちだけで作って出すこともできるんだけど、制作のシチュエーションというか、座組みみたいなものを毎回変えていくことで、慣れた手つきにしないということがすごく重要だという気持ちがある。今回そのために必要な“他者”は誰だろうと考えたときに、福田さんだったらすごくいいな、という意見がバンド内でも一致したんです」
F 「去年、WWW(東京・渋谷)でやったGOFISHのワンマン(2021年7月4日)に牧野くんが来てくれたんだよね。話したいことがありそうな感じがあったし、僕も何となくピンときた。そこからですね」
M 「結局、バンドでマスタリングまでの費用は受け持つので、マスターを納品してから後は福田さんにお願いします、という方式にしました。原盤権は僕らが持ち、レーベルはライセンス料を払うというかたち」
――アートワークとか、パッケージのスタッフィングはSweet Dreams?
F 「そうするのかな?と思ってたんだけど、違います。牧野くんには、山口こすもさんの写真で、デザインは加瀬 透さんにお願いしたい、というかたちが最初からあったみたい。じゃあ、それでやりましょうと」
M 「福田さんにそう言ってもらえてよかったです。本当に感謝してます。何となく毎回、“あの人とこの人はどうだろう?”みたいな組み合わせについては妙な確信があるんですよね。こすもさんはInstagramの写真がすごく好きだったので前から撮ってもらいたいと思っていた。加瀬さんとはとある雑誌を一緒に作っていた。最近いろいろなところで名前をお見かけするので、来年このアルバムを作ってたら頼めなかったかも」
――ブックレットが、24ページのフルカラーですよね。ぜいたくな作り。
M 「今回は、制作がリモートありスタジオありで、クレジットがちょっと入り組んじゃってるので、1曲1見開きにしたんです。ベーシックにNRQの4人がいることは共通しているんだけど、ゲストが加わってるとか、誰がエンジニアとして録ってるかが違ってる。それに、宅録とスタジオの二項対立じゃなく、アルバムを通していろいろな全てがグラデーションのようになっている状態。でも、まさしくそれがコロナ禍の現実を反映したようで、結果としてはよかったと思っています。制作メモを読み返してみたら、最初の頃に“リモートで録った曲はリモートっぽく、スタジオで録った曲は生々しさを活かす”みたいなことを自分で書いていたんだけど、全然そんなことにはならなかった。聴いた人は、どれが一緒にやってて、どれがリモートなのか、すぐにはわからないと思うんですよ。いかにも一緒にやってそうな曲が、全員バラバラの録音だったりするので。デジタル技術もいろいろ駆使してそうなってるあたりがすごくおもしろいし、現代的でもある」
――山口さんの写真1枚に1曲のクレジットの組み合わせでブックレットの見開きが構成されているでしょ。めくっていくと、カレンダーというか、歳時記みたいに感じます。
M 「まさに。このアルバムはそのままコロナ禍の記録という感じです」
――“今回は1曲1曲作ったんだな”と。もちろん、アルバムって1曲ずつ作るものだけど。
M 「そうそう。でも、まさにこの2年間は、1曲ずつ作っていたっていう感じがする。アルバム1枚をいっぺんに録ったっていう感じではなく」
――ミックスを牧野くんが自分でやることにして、すごく苦労してるようなツイートをしてたでしょ?確かに、いつもより音の配置とか独自な感じがしました。あまりないバランスだと思う瞬間がいくつもあって。
M 「いわゆるミックスで行われる当たり前の作業はあまりやっていないんです。(自分のミックスは)なるべく録ったまま、の気持ちなんですよ。シラちゃん(MC.sirafu)ともよく話すことなんだけど、専業のエンジニアじゃない人がミックスするとき苦労するのって、ドラムじゃないかな。ドラムが空間を占める割合が大きすぎて、その処理にはかなり技術を要するから、自分ではやりたくなかった。だけど、今回はこれまで気になってたことに向き合う実践編だと思って、やりました」
H 「今回のアルバムがこれまでと違うと自分的に感じたのは、スタジオで録音する前にライヴをあまりしていなかったこと。前は、ステージ上で曲を叩き上げるスタイルで来ていたから。だから、牧野くんがミックスをするときも、叩き上げていた部分の補助を自分の感覚でやっている感じ。アルバム全体も牧野くんの曲が多いし、音が“牧野”なんですよ」
M 「まずいな、それは(笑)。でも、服部さんは“今回のミックス、俺はすごく気に入ってる。全部の音が良く聴こえる。だから、最終的なマスタリングでも音をビルドアップしない方向で元のミックスを活かす方向がいい”と言ってくれて、僕はすごく感動しました」
H 「おもしろいと思っていたので。最終的なミックスでも“牧野”のかたちになってる感じが好きだったんです」
――全曲ではないとはいえ、牧野くんが自分のミックスにこだわったのは、今服部くんが言ったように、ライヴで叩き上げられなかったぶんだけ、ミックスという工程がもうひとつ必要だった、と思ったから?
M 「(その思いは)たしかにありました。サードの『ワズ ヒア』(2015年)や4枚目の『レトロニム』(2018年)を聴くと、演奏がすごく巧いんですよ。ライヴでやってきた曲を録っているから、BPM的な意味でなく、4人の呼吸がすごく揃ってる。今回は本当にライヴができなかったし、結局ミックスをしながら潜在的に曲に宿っているエッジを“けがいてあげる”みたいな、そういう作業が一段必要だった。曲がすでに持っている要素をブーストするのではなく、曲が密かに持ってる可能性みたいなものを露わにするということ。それは、演奏している自分たちじゃないとできなかったことかもしれません」
――それと関係あるかどうかうまく言えないけど、『こもん』を人混みの中とかで聴いていると不思議な感覚に襲われるんですよ。ひとつところにまとまったバンドの演奏というより、あっちからもこっちからも楽器の音が予期せぬ感じで聴こえてくる。“誰かいる!”みたいにドキッともするし、その逆で、人間の出す音が周囲を行き交ってることで安心感を得たりもする。
H 「えんちゃん(遠藤里美)が参加した“ポヤイスの春”はそんな感じかもしれない。あれを録ったときは、もうコロナ禍に入ってたっけ?」
M 「2020年の2月14日。まだ誰もマスクしてなかった。“何なんだろうね、あのウィルスは?”みたいな話をしながら、僕と服部さんとえんちゃんの3人で井草地域区民センター(東京・杉並)の一室で録りました」
H 「そうか。だけど、完成したのは、それから1年以上経って、吉田くんと中尾さんがリモートで録った音を重ねてからだった」
M 「今回の『こもん』の制作の始まりは、あの2月14日だった。もともとあの曲は、夏目(知幸)くんが監修したSINCERITA(東京・阿佐ヶ谷 | ジェラテリア)のオープン10周年コンピレーション(『Music For Gelateria』)用に録ったんです。そのコンピにはソロ名義で提供したんだけど、それを1年後にNRQで音を重ねて、ミックスし直した。今回は他にも、劇団ロロのために作ったり、Rojiのコンピレーション用に作った曲を録り直した曲もある」
――そういう制作過程も含めて、たしかに記録っぽい。集まって一気に固める感覚とはちょっと違う。
M 「ミックスにちょっと悩んでいたときに、oono yuuki bandとの2マンがあって、新間(功人)くんと楽屋で話していたら、自分の家にドイツのムジーク(musikelectronic geithain)っていう高級オーディオを揃えたからそれで聴いてチェックしようと言ってくれて、ミックス途中の音源を持って行ったんですよ。そうしたら新間くんが的確なアドヴァイスをくれて。たとえば、“アサカ・ン・ムード”は曲の緩急によってベースの音量をもっと上げ下げしたほうが際立ってよいのでは?みたいな、めちゃくちゃ具体的な助言。夏目くんにも制作中に少し意見を聞いたし、そういうふうに自分ともメンバーとも全く違う方向から意見を聞いて、それを反映していくのは今までにはないことでした」
H 「そういう過程がちゃんと反映されて結果が出ている感じですかね。リモートとスタジオのハーフ & ハーフじゃないし、コロナ前から録っている曲も、別の目的で作った曲もあるし。それを普段はエンジニアじゃない牧野くんがミックスしていることで、絶妙な距離感、バランス感が出ておもしろい」
――そういえば今回、服部楽曲がなかったですね。
H 「別に意味はないんです。曲ができなかったので(笑)」
M 「滑り込みアウトで、間に合わなかったんです。だから今度7”を出そうと福田さんと話してるんだけど、それは服部さんの曲でやります。Henry Cowellのような」
――今回、『こもん』をもっと深掘りしていくにあたって、服部さんにオブザーバー的な俯瞰で曲ごとにコメントをもらえるといいかな、と思ったんです。
M 「それはいいですね!」
――まずはM01「あの丘のむこうがわへ」。アルバム中唯一の中尾さん楽曲です。
H 「中尾さんって、タイトルの付けかたがいいな、と思うんです。今回は譜面にタイトルがもう書いてあったんだっけ。牧野くんが“あの丘のむこうがわ”って言うと、中尾さんが“あの丘のむこうがわへ”です、ってちゃんと訂正されるんですよ(笑)」
M 「曲名を間違えているわけじゃなくて、曲決めのときに略して言うことがあるじゃないですか。そういうときに必ず訂正が入ります。漢字をひらく / ひらかないにもこだわりをすごく感じさせる。この曲も“丘”だけ漢字で、あとは全部ひらがなという指定でした」
H 「これを1曲目に決めたのは中尾さんなんですよ。それもいいな、と思いました」
M 「いつもアルバムの曲順は中尾さんに決めてもらっています」
――自分の演奏としてはどうですか?
H 「これは2021年の10月15日にスタジオで撮ったんですよ。10月1日にタバコが値上がりしたので、そこから禁煙しようと思って、けっこう本気で2週間くらいやっていたのでボーッとしていて。だからあんまり覚えていないです(笑)」
M 「この曲は、アルバム制作の中で一番最後に中尾さんが持ってきてくれたんですよ。最後にできた曲なんだけど、構成やアレンジでも各々の役割が最初からはっきり決まっていて、かたちになるのは早かった」
――M02「SOTESU」。これは“ソテツ(植物)”?それとも“ソウテツ(相鉄)”?
H 「吉田くんは読みかたは“ソテツ”にすると言ってました。だけど、本当は相鉄線のことらしい。これはライヴでもけっこうやってました」
M 「僕のミックスを最初に吉田さんに確認してもらったら、“4人が平等に聴こえるからもうこれで大丈夫です”って返事だった。実は、コントラバスは針が赤く触れるギリギリくらいまで上げたので、セオリーからしたら相当デカい。そこが聴きどころです。後半、中尾さんのドラムが入ってきてからはドラムロールが主役かもしれない」
H 「あれはコンポステラの“淵”という曲のパターンなんですよ。吉田くんが中尾さんにあの感じでとリクエストしていました」
M 「後ろ髪引っ張られるようなリズムで、独特な合いかたですよね」
――M03「六道の辻」。
M 「実はこれが一番古い曲です。録音はコロナ前。よくできた曲ですね。ハコが違うと必ずこの曲をやります。6/8のリズムに薪をくべ続けるようなイメージがあるし、ライヴでその日のバンドの調子を測るのに一番いい」
H 「ああ、そうですね」
M 「作ったときは、Dollar Brandの“Tintinyana”みたいなイメージでした。この曲は馬場ちゃん(馬場友美)のミックス。この曲もやっぱりコントラバスが聴きどころですね」
H 「このコントラバスは、前に使っていた楽器だよね。ちょっと硬めの音がする」
M 「それで音が元気なのか。この曲、自分でミックスし直そうと思ったけど、元の馬場ちゃんミックスよりいい感じにはできなかった。コントラバスの音がサヴェージな感じなんですよ、バイーン!って感じで、荒っぽい」
――馬場友美ミックスで録っていたということはいつ頃?
M 「ディスクユニオンで『HIT』っていうLPを出したときだから、最初は2015年。あのLPに新曲を1曲入れようということになって録ったんです。後に、ライヴでもよくやっている曲だから、CDにも入れておきたいと思って、金野さん(金野 篤 | MY BEST! RECORD)に連絡して、馬場ちゃんにマルチをもう一回ミックスしてもらって収録しました」
H 「この曲までくると安心しますよね」
M 「そうだね(笑)。非常に安心感がある」
――M04「雨 Rain」。この曲は鈴木常吉さんへの提供曲で、実際に本人のレパートリーになった。
M 「この曲の何がよかったって、服部さんにストリングスを重ねてもらうとき、服部さんが“常さんが書いた歌詞を送ってくれ”って僕に言ったことです。それに感動しちゃって、だったらブックレットにも歌詞を載せようと思いついた。NRQでやるにあたってちょっと構成を作り替えたんで、そのままの歌詞では歌えないんだけど、こうやって載せるのは意味がないことじゃない。服部さんに言われたことがきっかけでそう気が付いたんです」
H 「実務的な話で、そんな感動的な話ではないんですけど、歌詞があったほうがストリングスを重ねるためのとっかかりになるんですよ。せっかく歌詞があるんだし、それを演奏に使わない手はない。いい曲ですよ。常吉さんにはNRQとしてそれぞれに関わりがあったので、これを収録できてよかった」
M 「“NRQと演奏するといつもうまくいきすぎるからイヤだ”って常吉さんはよく言ってました(笑)」
――録音のクレジットが、吉田、服部、牧野に分かれてるのは、リモートだったから?
M 「それぞれの楽器をそれぞれが録音しました。こういう情報を省略しないで全部載せることで、制作方法の仔細がわかったらおもしろいと思って」
――さっきもちょっと話題には出ましたが、M05「ポヤイスの春」。
H 「最初のベーシック録音から時間も経っちゃって、僕の弾きかたもライヴをするうちにだいぶ変わったんですよ。だから、最初はコントラバスの音を差し替えたいと思ったんです」
M 「でも、ベーシックでは、えんちゃんにマイクを立ててもらって“せーの”で僕と服部さんいっぺんに録ったから、音が被ってて差し替えができなかった」
H 「その“せーの”でやったときは、あまり演奏を固めずに録った。だから差し替えたいと思ったんですけど、ちゃんと聴き直したらこれはこれでおもしろいと思えて」
M 「このときえんちゃんが録ってくれた僕と服部さんの音がすごくよかったので、それを使わない手はないと思って、今回改めてリビルドしました」
H 「後から被せてくれる人たちも、元の演奏ありきで被せてくれるから、どんどん説得力が出てきて。おもしろかったですね」
M 「別々に録ったのに、えんちゃんのアコーディオンと中尾さんのサックスがセクションみたいになっていて。さすがだな、と思いました」
H 「コンピ版では、桜井(芳樹)さんもいたよね」
M 「桜井さんはたまたま隣の部屋でリハーサルをしていて。僕らの部屋を覗きに来てくれたので、無理なお願いをして、曲の後半にエレキギターを弾いてもらったんですよ。そのヴァージョンはSINCERITAのコンピで聴けます」
――ここまでがアルバムがLPレコードで両面5曲ずつだと仮定すると、A面ラストが「ポヤイスの春」、B面ラストが「ポヤイスの冬」。
M 「中尾さんは、A面B面の意識で曲順を考えているふしがあるから、案外そうしたかったのかもしれない」
――“ポヤイス”は“架空の国”という意味合いがありますが。
M 「これはピアソラ“ブエノスアイレスの四季”のパロディですね。暗喩みたいなヴェールはあまりなく、その都度の興味で名付けをしているんです。意味は、醸しだされるならば朧気に、くらいで」
――M06「SEIBU TRAIN」は、吉田さんのソロ『ROAM』(2017, MY BEST! RECORD)に収録されていた曲のNRQ版。オリジナルもすごいメタリックだけど、さらに大変なことになってる。
M 「もともと僕はあの曲がすごく好きで、NRQでもやろうと提案したんです。それで、今回ギターで参加してくれた杉山さん(杉山明宏)のバンド・DOIMOIと名古屋で対バンしたときに、DOIMOIはマジでメタルのバンドだし、“SEIBU TRAIN”を彼と一緒にやったらすごくおもしろかった。なので、今回のアルバムにも杉山さんに入ってもらおうと提案したんです。エレキギターはすでに僕がいるけど、こういう試みはバンドの可能性を拡げることになるから」
H 「(牧野とは)ギターのタイプが全然違うからおもしろいよね。僕はこういうメタルっぽい曲調で弓を使ってみたいという気持ちがあったので、楽しかったですね」
M 「コントラバスに弓だもんね。エレクトリックベースじゃない」
H 「あと、吉田くんはやっぱり息子を溺愛しているんだと思いました。(息子が)鉄道好きなんですよ」
M 「あ、そういうこと?“相鉄”に“西武線”?息子くん、鉄オタだもんね。言われてみれば急に電車の曲名が増えたね」
――M07「minato」。
M 「吉田さん曲」
H 「これはいい曲ですね。シンプルで」
M 「この曲のコントラバスは低音のマイキングがちょっと遠かった?マスタリングのときに低音がちょっとぼやけてるから締めてほしい、みたいなことを服部さんが言ったじゃない?」
H 「そうだった」
M 「この曲もBandcampで先行販売したんですよ。今回、Bandcampで先行販売した曲はすべてミックスし直しています。だから初出とは違うものになっている。中尾さんは、たぶんこの曲のことを言っているんだと思うんですが、“吉田さんの主メロ(二胡)に対してクラリネットはカウンターを吹いてるんだけど、牧野くんがミックスで僕の音を上げすぎちゃうから、拮抗しててあまり効果的じゃない”って言ってた。中尾さんはちっちゃく吹いてるんだけど、僕はいつでもそれを大きく聴きたいし、人にも聴かせたくてついフェーダーを上げてしまう。特に今回、自分でマイクを立てて録音した中尾さんの管楽器は下げられなかった。思い入れが強すぎて(笑)」
H 「中尾さんと吉田くんの音の絡みはいつも良くて。主メロに対しての中尾さんの佇まいが素敵なので、ついフェーダー上げちゃう気持ちも半分わかります(笑)」
――「minato」という曲名で、とってつけたように言いますけど、服部さんは最近、“浮と港”という新バンドをやっているじゃないですか。
H 「はい。お誘いをいただいて」
F 「浮(BUOY)は、米山ミサさんという女性シンガー・ソングライターのソロ・プロジェクト名なんですけど、彼女がGOFISHのバンドセットにコーラスで参加するようになった流れもあったりして、Sweet Dreams Pressで彼女のアルバムを出すことになったんです。それで米山さんがGOFISHバンドのドラマー・藤巻(鉄郎)くんに声をかけて、“誰かベースでいい人いませんか?”と聞いたら、服部くんの名前が挙がった。僕も、服部くんはいいんじゃないかと思ったので誘いました」
M 「結成はいつなんですか?」
H 「ライヴは去年の8月が最初ですね」
――けっこう、あちこちでもライヴしてますよね。
H 「昨日まで浮と港で、名古屋と松本に井手くん(井手健介)と行っていました。それで、ツアー用に4人がそれぞれのソロ音源を入れたCD-Rを作ったんですよ。自分は米山さんの曲を弾き語りしたんです。それを井手くんが車の中で聴いて、“服部さんってやっぱりNRQの4分の1を占めてるんですね”って言ってた(笑)。無自覚ながらNRQが滲み出ちゃってたみたいです」
M 「車の中で自分の音源を聴くとは胆力あるね(笑)。どうですか新しいバンドは?」
H 「楽しいですよ。楽しくやってます」
M 「生まれたばかりのバンドって、そのときにしかない楽しさがあるよね」
――そうですね。そこはNRQとは違う感覚でしょ。
M 「NRQは結果的にもう15年もやってしまった(笑)。驚くべきことなんですが!」
H 「でも、演奏がだんだん良くなってきてるのかはわかるし、その都度ベストを尽くそうと思ってやっているけど、やっぱり(納得できるまでは)時間はかかるとも思いました。浮と港のように、自分が最年長のバンドにいたこともこれまであまりなくて、多少意識しちゃうところがある。フォローできるところはできたらいいな、と思いますしね。ちょっとMCの合いの手を入れたり、コーラスが増えていったり」
M 「バンドによって臨む姿勢が違うのは自然なことだと思う」
H 「それで言うと、こないだ穂高亜希子さんの誕生日ライヴをやっていて、吉田くんと一緒に出てきたんです。穂高さんと吉田くんと自分の3人で一緒にやっていた時期があって、その3人で一緒にやるのは9年ぶりだったんです。本番前にちょっと合わせただけで、ほとんどリハもせずに演奏したんだけど、それがけっこう楽しかったんですよね。こっちも楽しかったし、観た人もよかったと言ってくれて、感慨深いというか、なかなかこういうのは続けていないと経験出来ないことだと思いました。」
M 「服部さんは“蓋を開けてみないと物事わかんない”っていうほうが絶対好きだよね。ツアーでも“1日目と2日目が同じ曲順だと飽きちゃう”って前に言っていたから」
H 「飽きちゃうというか、1日目のライヴで出来がよかった曲は、2日目にやると自分がそれを再現しようとしちゃう。それでだいたい失敗するんです。うまくいかなかった曲をまた次やるのはいいんだけど」
M 「僕なんかは安定するものがあったほうが拠りどころになるかな、と思う。一応、僕らがやっていることも芸事なので、大阪でうまくいったら名古屋でも同じクォリティのものをお客さんに見せたいと思うから、セットリストは固めちゃいたい。でも服部さんの言うこともなるほどな、と思います」
――ちょっと話が脱線しましたが、M08「アサカ・ン・ムード」。
M 「この曲は、Roji(東京・阿佐ヶ谷)のコンピ(『crowd』, 2020 | 牧野琢磨“レクイエム・フォー・2020 ~ アサカン・ムード”)で一回やってるじゃない?Rojiのコンピのときは完全にリモートで、僕が弾いたラインを服部さんに差し替えてもらった。服部さん、アルバム用にそれをもう一回やることにけっこう戸惑ってたよね」
H 「ベースとストリングスのフルセクションを録ったのがけっこう気に入ってたから、もう一回録り直すことへの戸惑いがけっこうあったんだと思う」
M 「すごく感じたよ、その戸惑いを」
H 「ライヴでもあの曲はやってたけど、それはそれで音源とは別物と思っていたから」
M 「音源で作り込んだフルセクションと、バンドのライヴでやっていた感じの折衷案を求められて戸惑ったという感じだよね」
H 「単純に、イメージがパッとできなかった。音を重ねていくことで何となくこうすればいいのかな?というイメージができて、それでやれたんですけど」
M 「一応言っておくけど、Rojiコンピはデモ音源集なので、あのときのテイクは、あくまでデモなの」
H 「あ、あれはデモなの?」
M 「そう!今回が本ちゃん。服部さん、今気が付いたね(笑)。あくまであれはデモだって言っておけば、同じことをもう一回やるのに躊躇なかったよね」
H 「そうなんだ。みんなデモだったんだ?」
M 「デモ音源集って銘打たれてたよ。僕らだけデモのつもりじゃなく作って出しちゃった、っていうことだね。今日、服部さんの疑問が氷解してよかったです(笑)」
――M09「第四間教室」は、劇団ロロの“『いつだって可笑しいほど誰もが誰かに愛し愛されて第三小学校』教室のテーマ・改題”っていうサブタイトルが付いています。
M 「ロロからお芝居のための音楽をお願いしたいというオファーをもらって作った曲です。舞台が教室に切り替わったシーンの音楽だった。同じお芝居の中で、服部さんも曲を書いているんですよ。同じお芝居の曲なんだけど、音楽は作家性の違いが出ました。服部さんのほうはHans Zimmerっぽいというか」
――ズズーン、みたいな(笑)。
M 「そうそう!僕はDanny Elfmanみたいに、固まったメロディのモチーフがあるような曲」
H 「これはわりとシンプルだけど、なんか変な曲ですよね」
M 「それは、ロロの台詞回しを意識したからかも。ロロって台詞の体感がすごく速い。だから曲調的にもそれと同じニュアンスで、お尻が切れてるような感じにしました。“学校の感じ”とか“せつない感じ”とか、先方からのイメージを共有しながら。服部さんもイメージを共有しながら作業していたよね」
H 「自分の担当シーンはけっこう込み入っていたから、音楽はバックにあるイメージで作った」
M 「それがアブストラクトで効果的で、僕のやっていることとはまた方向が違って素晴らしかった。そして、舞台を見に行った中尾さんは、服部さんの音楽をすごく褒めてました」
――まあ、何よりも同じバンドにHans ZimmerとDanny Elfmanがいるのはすごいことだと思います(笑)。では、最後のM10「ポヤイスの冬」。
M 「これはおもしろかったね」
H 「シラフさんのシンセね。手拍子も効いてる」
M 「よかったよね」
H 「最初にリハに入ったときからけっこう試行錯誤して変わった感がある」
M 「リズムが独特だからだよね。なんでこんなガッタンガッタンしたリズムになったのか考えてみたんだけど、Motownのドキュメンタリー映画(『メイキング・オブ・モータウン』2019, ベンジャミン + ゲイブ・ターナー監督)を観ていたら、はたと気がついた。あ!THE TEMPTATIONSの“Get Ready”のパターンなんだな、と。それとDavid Bowie問題。いわゆる、“最近の映画にDavid Bowie使われすぎ問題”があるじゃないですか(笑)。映画『スウィング・キッズ』(2018, カン・ヒョンチョル監督)を観ていたら、カラックスの『汚れた血』(1986)の異化シーンにオマージュを捧げるかたちで“Modern Love”が使われていた。そのシーンで号泣してしまって(笑)。無理をして何回もカラックスを観ていた過去の自分が報われたような気がした。だからここはいっちょボウイみたいな曲を作りたいと思って、シラちゃんに“ボウイみたいなシンセ”ってリクエストしたら、GOBLINみたいなシンセが入って返ってきちゃった(笑)」
――『サスペリア』(1977, ダリオ・アルジェント監督)の(笑)。
M 「そう。けれど僕もシラちゃんもロメロが大好きで、『ゾンビ』(1978)のエンディング曲を一緒に演奏したこともあったので、2人共通の原体験が反映できたな、と(笑)。この曲、コントラバスのリフがずっと聴こえてる。コントラバスって境界がぼやけちゃう性質があるから、エレクトリックベースみたいにシークエンスで聴かせるのがあまり有効じゃない。だけど、この曲ではシンセと音域を分けて聴こえるようなミックスができたと思っています」
H 「コントラバスとしてはこういうリフものはあまりないので、ひたすら弾いていて楽しかったです」
M 「あと、これはアルバム全体通して言えるけど、今回は二胡にリヴァーブがほとんどかかっていないし、全くかかっていない曲もある。歴史上残された音源の中で、一番リヴァーブがかかっていない二胡だと思う(笑)。前提としてリヴァーブがあるセオリーを外したかったし、ライヴで吉田さんがチューニングを下げて鳴らしている、あの音にしたかった。あのダーティな二胡の感覚がこの曲で一番顕著に出せたかな」
――この曲が最後に来たのも中尾さんの判断なんですよね。
M 「“手拍子がエンディングっぽい”って中尾さんは言ってました。“カーテンコールっぽい”って(笑)。毎回今まで何をやってないか、ってよく考えるんです。それで、手拍子も今までNRQでやってないことのひとつだと思って、家で録りました。K-POPの影響もあるかもしれない」
――アルバム・タイトルを『こもん』にしたのは?
M 「僕が考えました。これは、マルクスの言う“コモン(共有財産)”。斎藤幸平の著作群を読んで、やっと『資本論』の意味がわかったな、と思った影響もあるんです。NRQのアルバムとしては、今までになく直裁で素直な名付けだったと思う。『コモンセンス』でもいいかもしれないし、『コモン・コモン』でもよかったけど、マイク・ミルズの映画(『カモン カモン』)に被ってたかもしれなかったから危なかった(笑)。結果“コモン”をひらがなの『こもん』にしたら、それでNRQのタイトルになるんじゃないか?と思った。みんなにも“いいじゃないか”と言ってもらったので、これでいきましょうと」
H 「ちょうど自分も斎藤公平の本を読んでたんですよ。興味があって牧野くんとも話していて。で、その流れでタイトルの提案があったから、スムーズに同意しました」
――深読みする必要もなく、そのままの『こもん』。
M 「そうです。たとえば、今回は“わざわざ呼びました!”っていう感じのゲストもいない。大げさでなく、曲が要請する音を出してくれる人を要所要所でお願いしたというだけ。ブックレットの制作も、福田さんを中心にデザイナーの加瀬さん、写真のこすもさんとやりとりをしてもらい、各々の視点を加えていってもらう、という感じでした。新間くんにアドヴァイスをもらったり、夏目くんに意見を聞いてみたり、いろんなエンジニアの人に関わってもらったりしたこともそう。つまり、『こもん』は“自分たちが何を重要視しているか”みたいな思想を表しているし、アルバム自体を表す言葉にもなっていると思います」
――そういう共有感に加えて、遍在(あまねく在る)みたいな感覚の表現に近い気もしました。
M 「おっしゃる通りです」
――どこにでもあるけど気が付かなかったり、不意に目の前に出てきたりするものに出くわす感覚がNRQの音楽にあるという。
M 「円環は見えたり見えなかったり。だからやっぱり、あまり大げさな表現じゃないんですよ。そこがけっこう重要です」
――そこは、周りのバンドが解散したり、形態が変わったりしても、コロナ禍になっても、NRQがこの15年いつもやってるという事実にもつながる気がします。
M 「アルバムも平均して3年に1枚出してるし、働き者ですね(笑)」
――ジャズ・ミュージシャンが毎晩セッションする相手を変えて演奏を続ける、みたいなこととも違うわけだし。いい意味での緊張感があるんでしょうね。
M 「僕らは昔から友だちだったわけじゃない。バンドをやろうと思って集まった人間たち。だからというか……尊重し合っているし、尊敬しています。あと、今思ったのですが、NRQにはバンドとしての欲望がないんだな。“ミックスをうまくやりたい”とか、“今夜うまく演奏したい”とか、各個人の欲望はもちろんあるとは思いますが」
H 「各々よい距離感というか……欲望が個人に起因しているのが、良いところかもしれない」
――中尾さんが「あの丘のむこうがわへ」の“へ”や表記にこだわるのも、そういう欲望なのかな。
M 「そうそう。だから中尾さんもインスタライヴをNRQでやると言えば来てくれるし、曲順をお願いしたら考えてきてくれる。中尾さんが決めた曲順はある種、彼の中でもう答えが出ているから、そこに譲歩の余地はない。けれど、つまりそれは、中尾さんが自分の意志をこのバンドに持ち寄ってくれているということ。吉田さんも意志を持ち寄っているし、服部さんも僕もそう。だからそういう意味で、本当に“バンド”なんですね」
――そういうバンドのありかたを、制作過程と音像の両方で示してる作品と言えるのでは。
M 「毎回、アルバムを作り終えるたびに服部さんに、“もう無理、そもそも自分には才能も何にもない、振っても絞ってももう何にも出てこない、だからバンドやめる”っていう話を聞いてもらっているんですが(笑)、今回は終わってみたら、むしろ“またバンドを延命、長生きさせてしまった……”っていう感じだった。けれどそれは前向きな意味で。この方法で録れるんだったら、もうちょっと突き詰めて何かできるのかもしれない」
H 「コロナ禍という状況がきっかけではあるけれど……」
M 「それこそ今、Sweet Dreams Pressで新曲を7”で出そうかっていう話をしているけど、服部さんが作ったコントラバスのラインにみんながリモートで被せてみよう、と『こもん』をふまえた上でのアイディアが出ていて。この状況下で制作方法が拡張されたので……それはやっと人並みに現代的になっただけとも言えますが(笑)。果たしてそれが、バンドにとっていいことなのかどうか」
H 「それは、これからわかってくると思う!」
服部将典 Twitter | https://twitter.com/hattomas
牧野琢磨 Twitter | https://twitter.com/_N_R_Q
吉田悠樹 Twitter | https://twitter.com/yoshida__y
Sweet Dreams Press Official Site | https://sweetdreamspress.com/
 ■ 2022年5月25日(水)発売
■ 2022年5月25日(水)発売
NRQ
『こもん』
CD SDCD-054 2,400円 + 税
Bandcamp | Minna Kikeru
[収録曲]
01. あの丘のむこうがわへ
02. sotetsu
03. 六道の辻
04. 雨 Rain
05. ポヤイスの春
06. SEIBU TRAIN
07. minato
08. アサカ・ン・ムード
09. 第四間教室
10. ポヤイスの冬
 ■ LEMONS
■ LEMONS
Mai Mishio with Goodfellas 7ep Single Release LIVE
2022年6月8日(水)
東京 代官山 晴れたら空に豆まいて
開場 18:00 / 開演 19:00
予約 3,500円 / 当日 4,000円(税込 / 別途ドリンク代)
予約
[出演]
Mai Mishio With Goodfellas / NRQ
2022年7月3日(日)
東京 国立 地球屋
開場 / 開演 18:00
2,000円(税込 / 別途ドリンク代)
予約
[出演]
微炭酸 / ニューグリフィンズ / NRQ
トーク: 森 元斎 + 荒内 佑 (cero)
■ Tales
2022年7月9日(土)
東京 小岩 BUSHBASH
開場 / 開演 18:00
予約 3,000円 / 当日 3,500円(税込 / 別途ドリンク代)
予約
[出演]
空間現代 / NRQ / オシリペンペンズ