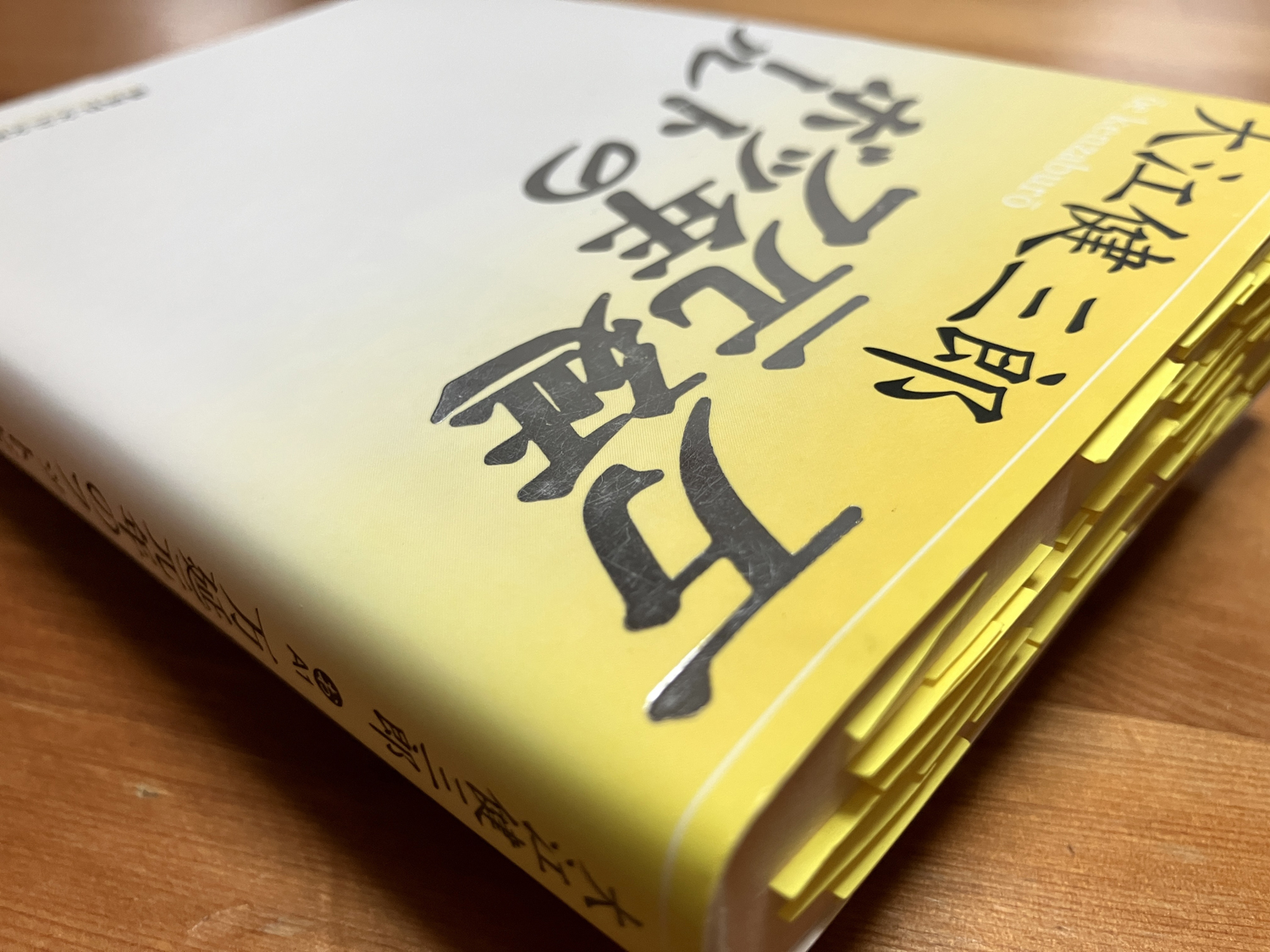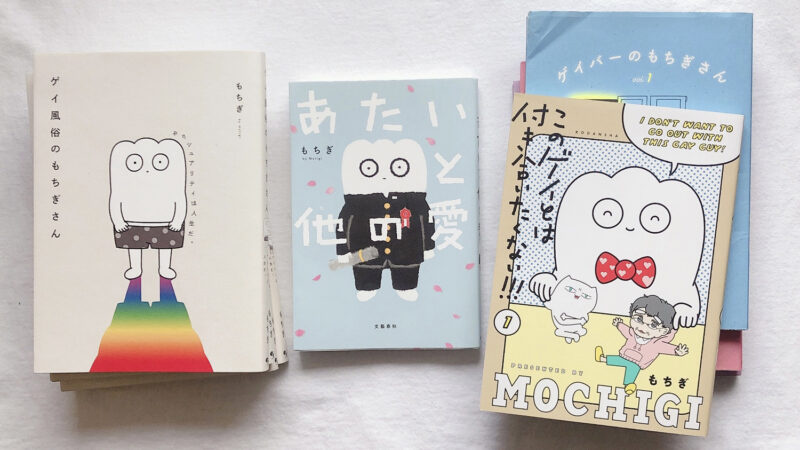文・写真 | コバヤシトシマサ
わりと知られた大江健三郎の小説を手に入れたので、読んでみた。『万延元年のフットボール』(1967)。ノーベル文学賞も受賞している大江の、これは代表作と言っていい。村上春樹の『1973年のピンボール』(1980)は、本作からそのタイトルを借りているそうな。よし、ここはひとつ真面目に文学と向き合ってみるか、との思いで読み始めた。ところがである。その意気込みは冒頭でいきなり脱臼を余儀なくされる。
この夏の終りに僕の友人は朱色の塗料で頭と顔をぬりつぶし、素裸で肛門に胡瓜をさしこみ、縊死したのである。
――大江健三郎『万延元年のフットボール』1988, 講談社文芸文庫 p11
死が必ずしもシリアスでないのは、文学作品等では間々あること。そしてシリアスなものだけがシリアスなわけでもない。とはいえ、肛門に胡瓜か……。冒頭で告げられるこの死が、本作全体を支配する禍々しい空気への案内状になっている。友人の死は作中で何度も反芻されることになるが、安易な解釈を許さない異様な出来事は、この死以外にも次から次へと起こる。そうしたディテールを丹念に書き連ねていく大江の筆致には、たまげてしまった。いったい何を読まされているのだろう?と読み手が自問してしまうような展開が続きつつ、しかしこうした人を食ったような話を綿々と書くのが文学の仕事なんだな、と大江の筆に導かれるまま妙に納得してしまった。
言葉の使いかたもかなり凝っている。定型的な語彙の使用が極力避けられているような印象を受けた。他の作品を読んでいないので、本作が大江作品に一般的な文体なのか判断がつかないのだけれども。凍害によって傷んでしまった観葉植物が犬の濡れた口の臭いに似たなまなましく強い臭気
(p148)を放ち、黒ずんだ斑を露にしたそれらの植物たちが立ったまま死につつある大男のようだ
(p148)と。これは比喩や形容に限った話ではない。小説全体がそのような独自の語彙で書かれており、本作を読み辛いとする向きもあるらしい。しかし定型文をことごとく排し、ゼロから語彙を組み立てたかのようなやり方で、この長い物語は書かれている。その徹底には素朴に驚いてしまう。
一方でほとんどギャグのような展開も多い。ウケ狙いの冗談のように書かれたエピソードがわりと頻繁に出てくる。人物たちの繊細な機微が、その繊細さゆえに途切れ、その結果として冗談のような展開を見せる。“破滅的ギャグ”とでも呼ぶべきそうした挿話が随所にあって、感触としては北野 武の映画に近い。冒頭の胡瓜しかり。端的にいうと下ネタが多く、そのあられもないバカバカしさが、人間の愚鈍さを露呈させる。思わず失笑しつつも、しかし紙面の奥から生真面目にこちらをみつめる大江の視線がそこにはあるのだ。ひとつ例をあげよう。「楽便器」のエピソード。主人公の妻が、世話になるジンという女に「楽便器」なるものを贈る。「楽便器」とは底の無い椅子のごときもの
(p149)で、普通の便器の上に載せれば、使用者は洋式便器をもちいるのと同じ姿勢で、膝に負担をかけず排泄することができる
(p149)のだ。ジンには過食の気があり、体重が130kgを超えている。そんなジンのため、通信販売のカタログで見かけた「楽便器」が贈られるわけだ。このような贈り物にジンは気分を害さないだろうか。主人公とその妻は気を揉む。そうした経緯を大江は事細かに綴っており、例によって読み手は、いったい何を読まされているのか?と自問しつつも、この不可解な便器の向こうには、こちらを見つめる大江の視線があるのだ。
主人公の名が蜜三郎で、その蜜三郎の子が障害を持って生まれたとの内容もあり、本作は大江による私小説との趣向もある。しかし単なる私小説というよりは、“未熟な日本の私”を描いた作品としたほうがしっくりくる。穴ぐらに篭って思弁に耽る蜜三郎。社会に向き合おうとしない彼は、まさに未成熟であり、彼自身、そのことに自覚的でもある。そして物語が進むにつれ、それが戦後の日本そのものなのだということが明らかになる。蜜三郎の弟、鷹四はかつて学生運動に入れ込んだのだった。彼はそののち、四国の山村で村人たちを巻き込んでの一揆を計画し、決行する。“革命を志すも百姓一揆になってしまう”という状況は、西洋近代が日本という場所にどのように導入されたかを踏まえてのものだろう。思えば「楽便器」も、いびつな西洋化のカリカチュアだった。先の敗戦を自ら総括することができず、看板だけすげ替えて“近代”の“民主国家”となった日本。成熟のプロセスを踏まえないままの場所で、蜜三郎と鷹四はそれぞれにその克服を試みる。
一揆は念仏踊りと共に遂行される。念仏踊りとは、死者の魂を呼び込む盆踊りのようなもの。実は100年前にこの村で実際に一揆が起こっており、念仏踊りはその魂を現代に蘇らせるものでもある。そして現代の一揆の目的は、“スーパー・マーケットの天皇”の打倒だ。村の谷間にあるスーパー・マーケットの経営者を失墜させること。ここに並ぶ「念仏踊り」「一揆」「スーパー・マーケット」「天皇」との語群。“近代化した村社会としての日本”をそのままトレースしたかのようなこれらの語群は、大江の言語感覚の真骨頂と言っていい。言語感覚が爆発したかのようなこうした大江のセンスは、ちょっと他に類例を思いつかない。端的にキャッチーなだけでなく、この才覚こそが、大江文学が大江文学であるための条件のようになっている。
この傑作を最後まで読み終えて思うこと。本作はたしかにあるやりかたで日本という場所を書いている。それは戦後の日本であり、“戦後”というパースペクティヴを通してこそ、この小説はその効果を最大にする。だとすると2025年の現在、もはや戦後ではなく戦前なのだとの物言いがしたたかに語られるに至った今、本作のアクチュアリティは若干目減りしたともいえる。作中に登場する“スーパー・マーケットの天皇”なる人物。彼は朝鮮人でもあるわけだけれど、“スーパー・マーケット”と“天皇”の並記は、それだけである種の批評性を持つ。発表当時であればなおさらだろう。翻って現在、その批評性は弱まったとも思う。小説が時代を映すものである以上、それは宿痾でもあるし、その事実は作品の価値を棄損するものではないけれども。ひとつ言えるとするなら、本作で大江が問うた課題は、スキップされたまま現在に至ったということ。
最終部で蜜三郎は、我が子でない子も、我が子として育てることを決意する。原則と手続きとを誤ったとしても、なおそれを引き受けて生きることを彼は決断している。敗戦の22年後、1967年にその決断は書かれた。