文・撮影 | 波田野州平
映画の中の食事
以前友人と話していて、印象的だった映画の中の食事の場面は?という話題になったことがある。そのとき咄嗟に思い出したのが『燃ゆる女の肖像』(2019/フランス/セリーヌ・シアマ)の、画家マリアンヌが派遣された孤島の家で真夜中にひとり起き出し、誰もいない台所を半裸姿でがさごそと荒らした果てに見つけたハード系のパンを一心不乱に貪る場面だった。その食いっぷりから、食べるということが正当な欲望のひとつだということがありありと感じられる場面だった。
それとは打って変わって、『パルプ・フィクション』(1994/アメリカ/クエンティン・タランティーノ)でオーヴァードーズしたユマ・サーマンが運び込まれた家のプッシャーが、足をテーブルの上に投げ出して浅い皿に盛られたシャバシャバの豆をスプーンで食べる場面はどうだろう。テレビに夢中で食べ物には目もくれず、でも慣れた手つきで器用に犬の餌のようなまずそうな豆を食べるその姿は、食事とは所詮消費であると体現しているようで、これがアメリカのTVディナーってやつ?(『ストレンジャー・ザン・パラダイス』1984/アメリカ/ジム・ジャームッシュ)と、これも印象的な場面だった。
犬の餌といえば、『好人好日』(1961/日本/渋谷 実)で交際している彼女の実家にひとり挨拶にやってきた男が、彼女の父親に手土産の高級羊羹を渡すが、数学者の父親は数式に夢中で、上の空で受け取るとそのまま男の目の前でその高級羊羹を飼い犬の餌にくれてしまうという場面には思わず笑ってしまった。父親役の笠 智衆のいつも通りのとぼけた怪演がここでも効いていた。
食べ物ではなく、食べる場所が印象的だったのは『非情城市』(1989/台湾/ホウ・シャオシェン)だろうか。四角い食卓を壁にくっつけて、つまり四角い食卓の一辺を殺してしまい、そこで向かい合って食事する様子が新鮮だったのを覚えている。そして皆とにかくよくお茶を飲む。やくざまでも「茶にしよう、茶にしよう」と食卓を囲んでお茶を飲みながら話しているのが新鮮で、アメリカがTVディナーなら、これが台湾茶の在りかたなのかと納得した。
茶で思い出すのは、『幕末太陽傳』(1957/日本/川島雄三)でフランキー堺が遊郭の女の部屋で晩飯を食べた後、その飯碗に茶を注いで飲み干すと、布巾でくるっと飯碗をぬぐっただけでまた戸棚に仕舞ってしまう場面だ。フランキー堺の相変わらずの流れるような仕草もお見事で目を奪われたのだが、それと共にかつては食器を洗剤で洗わなくても茶で流して拭けばおしまいだったのかと、その簡潔さになぜか胸のすく思いになったのだった。
飲み物というとやはり、『駅 STATION』(1981/日本/降旗康男)のビールだろうか。刑期を終えた高倉 健が訪れた呑み屋で出所後初めて口にするシャバの飲み物、それがコップ一杯のビール。まじまじと感慨深そうにビールを見つめ、ゆっくりとコップの端に口をつける高倉 健。今観るとこんなベタな演出よくやったなと思わずにはいられないが、健さんの生真面目一辺倒の演技が「ばかやろう若造、それが映画だ」と、清も濁もベタすらもビールと一緒に飲み干すようで忘れられないものがある。いや、高倉 健が出所後にビールを飲み干す映画は『幸福の黄色いハンカチ』(1977/日本/山田洋次)だった。山田洋次ならこのベタさ加減も頷ける。てっきり雪の降る凍えた夜にさびれた呑み屋でビールをすすったものだと、その薄暗い画面まではっきり甦っていたのだが、それは存在しない映画の場面、つまり記憶の捏造だった。こうした勘違いが映画を語る際にはよく起こるが、その間違えかたにその人がどう映画を見ているのかが如実に表れて、大変好ましいことだと思う。
そういえばミニシアター隆盛の90年代から2000年代にかけて、映画のパンフレットの最後のほうに料理を紹介するページがあった。どこかのお店のシェフが映画にちなんだ一品を創作して紹介するページで、一体これを誰が望んでいるんだろう?という疑問に満ち溢れたページだったが、今となってはいわゆるタイアップ広告のページにお金をかける意味がミニシアター系映画の界隈にもあったのかと、これはこれで味わい深い一品だったのかと今になると思うのであった。
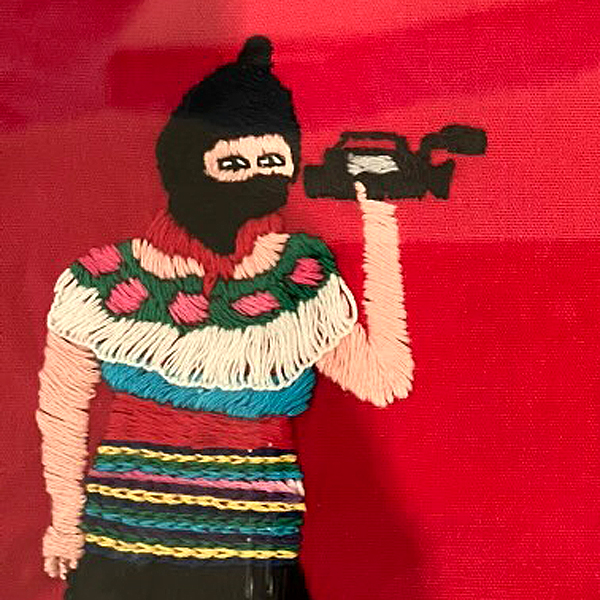 波田野州平 Shuhei Hatano
波田野州平 Shuhei HatanoOfficial Site | Instagram
1980年鳥取生まれ、東京在住。
カメラを携え、各地で出会った未知の歓びを記録し、映画を作っています。
近作に『私はおぼえている』(2021)、『それはとにかくまぶしい』(2023)がある。





