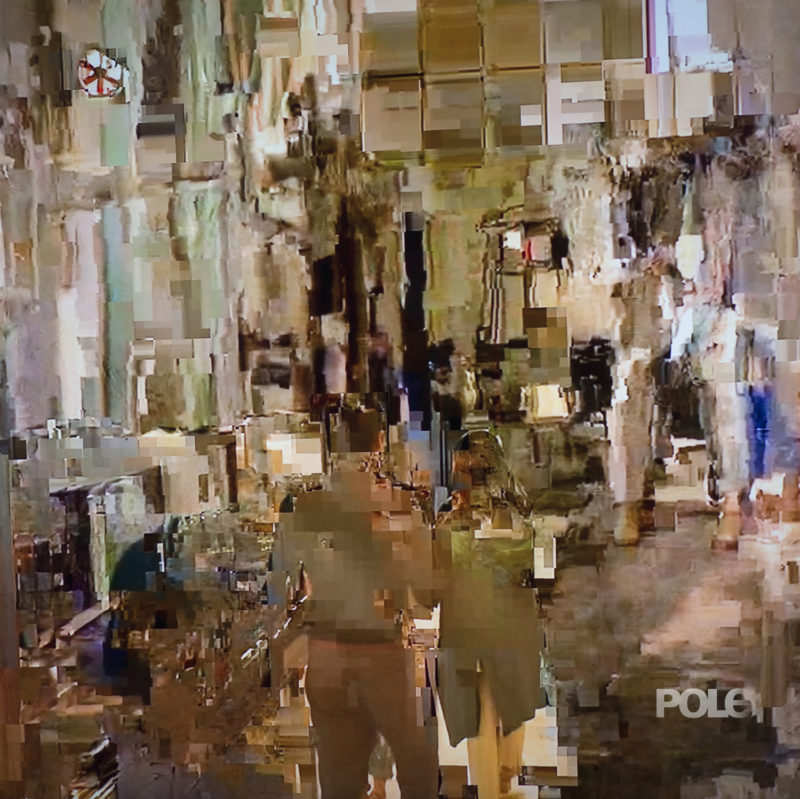最後までやらないと攻略にならない
取材 | 南波一海 | 2024年7月
序文・撮影 | 久保田千史
――バンド名義の話から聞きたいのですが、“小日向由衣 with 組織”だったのが、いつしか“組織-kohinatayui band-”になりましたよね。それは意識的に変えたのでしょうか。
「意識的にやってます。よく気付きましたね!」
――それはやっぱり小日向さんの単なるバック・バンドとしてではなく、もっとメンバーと並列でいたいというような思いがあるからなのかなと。
「私、根本的にはバンドをやりたかったんですよ。バンドを組めるなら組みたかったという思いがずっとあって、それができなくて地下アイドルの世界に紛れ込んだ何年間、なんですよ。私にお客さんがつけば一緒にバンドやりたいという人たちを集められると思い込んで、モデル歩きのレッスンをさせられる変な事務所にまで行ったくらいなので。でも、当時の私には無理だったし、組めたとしてもうまくいかなくてまたすぐ解散とかになっちゃうかもしれない。だからスタンスとしては今のこの感じが気に入っているんですけど、あくまでバンドとしてやりたいなと思ってはいたんです」
――出発点がバンドだったから、ある意味で原点回帰なんですね。
「昔、コピー・バンドをやろうということで組んだことがあって、私とギターが職場の友人で、あとはmixiみたいなので集まったんですよね。同じ音楽が好きで集まったメンバーではなくて、活動の地域がこのあたりなので練習に来られる人、ドラムができる人、ベースができる人ということで募集したんです。だから、みんなでイチから知らない曲を聴いて、わざわざコピーするくらいだったらオリジナルを作ったほうが早くない?ということになって、自分で作ってみたら、作れたんですよね。子供の頃から歌を作って遊んだりしていたので、その延長で、メロディにコードをつけてもらえば作品にできるんだとわかったし、それが自分のやりたいことだと気付いた。それが出発点だったので、今、そのかたちでやれているのが嬉しいし、やっぱりバンドは楽しいんですよね」
――地下アイドルの世界で活動を続けてきた結果、ちゃんと小日向さんのやりたいことを汲み取ってくれるメンバーと出会うことができて、組織の結成に至り、いつしか“with 組織”が“組織”に変わっていった。
「“with 組織”というほど私がバンドに対して細かく指示できるわけでもないし、何か言うとしても、もうちょっと弾ませてほしいとか、落としたいとか、静かな始まりにするのはどうかな、みたいな感じなんです。それで、変化をつけたいなら2番から静かにしたほうがいいんじゃないかなとメンバーに言われて、実際にやってみてそれでいこうとなることも多いから、みんなでやっているという感覚が大きいんです。とはいえ“with 組織”名義だと、組織というバンドがいて、そのバンドと一緒にやっているんですか?と言われたこともあったんです」
――ああ、コラボみたいな。
「もしくは私のバック・バンドの名前だと思われたりとか。小日向由衣と組織が分けて捉えられちゃってた。それは自分の中では違うんです。みんな同じなので。初見でもわかるようにするにはどうしたらいいんだろうと考えたときに、“組織-kohinatayui band-”にしようと思いつきました。本当は“組織”だけで伝わるようになったら“kohinatayui band”もいらないくらいです。だから組織だけの曲もあるといいんですよね。小日向由衣がソロでやっている曲をバンドで演奏してます、ということではなくて。バンド内で曲を作りたいという人が現れたら、また変わってくるかもしれない」
――ゆくゆくは椎名林檎と東京事変みたいなスタンスに、ということですよね。
「椎名林檎ほどの知名度だったら東京事変だけでもどんなバンドかわかりますけど、組織と言ったところで誰なんだっていう(笑)」
――検索ありきの時代ですしね。アレンジャーを“業者”と呼ぶ人のネーミング・センスだなとは思います。
「6年目に入ったんですけど、当初はまさかこんなに続くと思っていなかったので(笑)」
――最初は主催イベントの一夜限りの企画だったんですか?
「そうですね。みんなの反応がすごくよくて、なんならソロのときよりも感想が多かった。それで私もメンバーも、お客さんがこんなに喜んでくれるならまたやりたいねとなって、続けるようになりました。メンバーも優しいから続けられているんだと思います」
――きっと音楽的にもバンドでやるのが合っていたんでしょうね。
「私のやりたい音楽はDTMっぽいピコピコ音じゃなかったりするんですよ。キーボードよりもピアノの音が好きだし、キーボードは飾りで少し入っているくらいが好み。ソロのライヴをこれだけしょっちゅうやってるのに、パソコンからポンと音を出して、いい感じのギターが鳴り始めると不思議なんですよね。色気がないなと思っちゃう」
――いつも同じ音が同じタイム感で出るわけですもんね。アイドルに限らず、バンドでも同期ものがあると制限を感じることはあります。しかも、小日向さんのような行き当たりばったりな生き様を見せる人は、勢いとかハプニングも込みで取り込めるバンドのほうが合っているかもしれないなと今話していて思いました。
「リハで思い付いたことをすぐにやってもらえるのも楽しいんですよね」
――今回レコーディングしたものはバンドでやってきたアレンジなんですか?レコーディングの際に大きく変わったものはありますか。
「“夢見る羊ちゃん”はライヴでやった回数が少なかったんです。関(美彦)さんのイベントに組織で出るときに、関さんがアレンジしてくれた曲をやりたいということで、やることになって。結果的にはオケとは違う感じになったんだけど、これはこれでめっちゃいいねとなったんです。その後、各自がレコーディングまでに考えて持ってきたものを合わせたかたちです。それ以外の曲は、例えば“ドッペルゲンガー”はライヴを重ねるたびに試行錯誤してきて、同じだったことが一度もないくらい少しずつどこかが変わっていきました。そういう曲のほうが多いかもしれないですね」
――アレンジは各自で持ち寄って固まっていくんですね。
「そうですね。最初はコード譜もないまま音源を送って、ギターの稲葉(敬)先生がコードを起こしてはくれるんですけど、それも目安程度で。そこから、みんなでああだこうだしながら、諸田(英慈)さん(小日向作品のアレンジャーにして組織の鍵盤担当)が強い意志を通したり、そっちのほうがいいかもねと合わせたりしてますね」
――小日向さんのソロに関しては諸田さんがほとんどすべての編曲をやっているのに、コードを起こすのは稲葉さんなんですね。
「そうなんです(笑)。どうしてそうなったんですかね?諸田さんがいない時期とかもあったからかな」
――音数に関してはダビングも少なく、シンプルになりました。
「オケだと何秒か空白があると焦るんですよ。1人でライヴで歌うときは特に。でも、バンドだと静寂があっても焦らないんですよね。人がいる安心感なのかな。オケだと1、2、3、4という隙間があったら何か入れたくなるけど、バンドはただの隙間にはならなくて、なんかおもしろいんですよね。物足りないな、とはならないというか」
――オケでライヴすると余白がただのカウントになりがちだけど、バンドだとより音楽的な効果があげられるということですよね。Peace Musicの中村宗一郎さんによる録音も作品の強度に貢献しているのだと思います。
「中村さんはめっちゃ優しくて。たぶん、中村さんが重視しているのは楽しい空気で録音することだと思っていて。やっきになって何度もテイクを重ねるよりも、少しくらいミスがあっても勢いのある最初のほうのテイクが魅力的だっていう考えかたなので、肩の力を抜いて、気負わずにやりましょうという雰囲気を作ってくれるんです。今回、基本的にクリックなしで全員一緒に録ってるんです」
――一発録りなんですね。クリックなしも今ではかなり珍しい録りかただと思います。
「私も中村さんと同じ考えで、私は自分で弾いてないからかもしれないですけど、正確なテンポよりも表情があるほうが好みなんです。テンポが揃っているものは小日向由衣のソロでやれるから、組織でやるなら組織じゃないとできないことをやらないと作品を出す意味がないと思っていたので、最初に中村さんと打ち合わせしたときに、この人となら絶対にうまくやれるって勝手に親近感を持ちました(笑)」
――クリックに沿うよりも、その場でどう感じてどう表現するかを重視したわけですね。
「バンド・メンバーはそれまでクリックなしで録ったことがなかったらしくて怯えてたんですけど(笑)、終わったらみんなが楽しかったと言っていて。ライヴしているような感覚がレコーディングできたのは初めてだったなと話してました。特に稲葉先生が、こんなふうにやっていいんだって驚いてました。諸田さんが体調不良で来られなくて、鍵盤始まりだった曲が急遽ギター始まりになったりして、それこそまさにライヴ感が出たものもあります。私も仮歌ですけど、ガラス越しに一緒に歌いました」
――演奏と同時に歌も歌っていたんですね。
「仮歌だからがんばらなくていいんだけど、みんなの気持ちが乗るようにわかりやすく盛り上げたりして。中村さんからは、このあと本チャンのレコーディングがあるんだから頑張りすぎて喉潰さないでねって言われました(笑)」
――インフォメーションだけだと小日向由衣のレパートリーをバンドでやってます、ということしか受け取れない人もいると思うんですけど、そこには必然があるし、ミラクルなことが起きているというのは伝えたほうがいいのかもしれないですね。
「それだ!組織のライヴを追ってくれている人には伝わっていると思うけど、たしかにそうですよね。アイドルだけじゃなく、シンガー・ソングライターのかたでもバンド編成は生誕ライヴだけだったりするじゃないですか。でも、私はわりとコンスタントにバンドでもライヴをやってきたと思っていて。近い人はそれを知ってるから、組織でアルバムを出すことを、やっとだねって喜んでくれるんですけど、普通はただの小日向由衣のバンド再録盤みたいに思いますよね。そこに対する視点がなかったです。このインタビューが必要だ!」
――(笑)。2020年の『夢じゃないよ』以降、こうしてコンスタントにフル・アルバムを出し続けているわけですが、“できない”というラベリングをしてきた / されてきた小日向さんは今やもう“できる”人ですよね。例えばレーベルや事務所に所属していて、誰かに促されて、締切はここですと言われて作っているわけではないじゃないですか。それでも作ることができるモチベーションはなんだと思いますか?
「やりたいことしかできないという病気なんです(笑)。やれないことはできなさすぎるんですけど、私の中で曲を作るということは衣食住よりも大切なときがあるくらいなので、やれるんですよね。ゲームとかと同じで、ゲームは楽しくて止められないじゃないですか。曲も、ワンフレーズ出てきたら最後までやらないと攻略にならないから、そのままにしておくのが気持ち悪いんですよ。早く作りたいし、作ったら聴かせたい。だから物にして出したいんです。最初のアイディアが出たら、私を3日間閉じ込めてもらえれば必ず完成させます(笑)」
――そうして進んできて、振り返ったら5枚ものアルバムができていた。
「いや、でもグッズの入稿は追いついてません!今朝データを入れないとライヴ当日に間に合いませんというギリギリさだったので。みんなが普通にできることは人よりもすっごいがんばらないとできないんですよ。みんながちょっとめんどくさいなと思うようなことは、非常に、本っ当にめんどくさい。やらないといけないのはわかってる。これを甘えと言うなら甘えと言ってくれていい。でも、できない。最終的にどうにもできなくなって、泣きながらがんばることになるんです」
――そんな人がたくさんの人と出会い、バンドを組めたというのはすごいことですよね。
「バンドはめっちゃ大きいですね。私が曲を作りたいと思えるのも、そこに繋がることなのかもしれない。バンドの楽しさがあるから曲を作りたくなるわけで、すべてのモチベーションになっているかもしれないです」
――誰かと何かが作れるとは思えないような人が、業者②こと諸田さんと完成させられるようになり、今度はもっと多い人数と作業してバンド作品を完成させたというのは感動的だなと思います。
「でもまぁ、5、6年前にスタート地点に立つまでは10年くらい地底と呼ばれるところにいたので。今日のライヴに意味があったはずって自分に言い聞かせながらジタバタしてただけの期間が長かったんですよ。諸田さんに出会うことになる年、本当はワンマン・ライヴをやったらやめようとしていたくらいなので。『まとめ』(2017)というCDを作ったのもそうですし。100枚だけプレスしたら1枚あたりの原価がめっちゃ高くなっちゃって、4曲入りで2,000円で売ったらみんなから高い高い言われたんですけど(笑)。当時は地底のイベントで、最初の出番じゃなくてトリを目指していたんですど、それって一歩引いて冷静に考えたらめちゃめちゃ小さい話なんですよ。既存曲のカヴァーでその場を盛り上げることでトリになれたとて、ちょっと離れたみたら、そのトリに一体何の意味あるのかなっていう」
――だったらオリジナルをやっていくぞという思いを強くしていったわけですもんね。当時は、まわりがカヴァーの定番曲で盛り上がっていて、小日向さんのオリジナルは知らない曲だから盛り上がらないと言われていたのが、今はオリジナル曲でしっかり盛り上げているのだからすごい話です。今作の1曲目の「ネコみたいに」もまさに定番曲になってますよね。
「あの頃の私がかわいそう(笑)。“ネコみたいに”を作った当時は狙って作ったわけではなくて、ライヴでやっていくうちに盛り上がることがわかって、じゃあ定番にしようとなっていきました。育っていくのも楽しいですよね」
――もちろんバンド・サウンドならではの曲もたくさんあって、「世界が泣いてる」はまさにバンドこそが完成形ですよね。
「そうですね。このヴァージョンもブツっと終わるのは諸田さんのこだわりですけど(笑)。不安になるくらい突然のタイミングで切れる曲です」
――「別れの時」はとてもよい曲ですけど、これはどのアルバムにも収録されてこなかったですよね。シングルのみの曲で。
「CD-Rの『桜ひらひら恋心』に入っていたカップリング曲で、ライヴでもそんなにやる機会がなく、埋もれていたんです。もともと作っているときからバンド・サウンドに合うと思っていたから、組織のアルバムにちょうどいいな、今じゃないと輝かないぞと思って入れました。時が来たなという感じです。泣きそうになっちゃうくらいすごくよかったです」
――小日向さんのメロディはとてもJ-POP的なんだなと感じる曲です。
「そう!やっぱりこの界隈にいるとみんなおしゃれとかシティとか言いたがるけど、私は王道のJ-POPで勝負したいんですよね」
――それから、日々のライヴの賜物で、リリースを重ねるごとに歌がよくなってますよね。このバンド・サウンドにもしっかりハマっていると思います。
「よかった!私、歌がよければもっと輝かしい未来が待っていたかもしれないと思うんです(笑)。ライヴも、配信とかで見られるやつは全部見返してます。ここはいきむと外から聴くとこうだからダメだなとか、逆にここは気持ちが昂ったら多少ズレてもグッとくるなとか、少し昂るくらいはただ下手に見えるだけだなとか」
――自分を分析しているんですね。
「特に“サイダー”とか感情を込めたくなる曲ほど冷静に歌うほうがいいと思ってやってます。ライヴが後半に向かうにつれて、抑えきれない!ってなるんですけど(笑)。たぶん、それも興味があるからできるんですよね。歌うことには興味があるので。楽器ができないのは興味が持てないからなんだと思います。ピアノを7年間習っていたのに、結局今やってないのはそこまでの興味なんだろうなって」
――曲作りと歌に特化してきた結果が小日向さんの各作品に刻まれていると思います。アルバム最後に収録された「誓います」はどうしてボーナス・トラック扱いなんですか?
「ライヴの最後とかアンコールとかでやっている曲で。今回のアルバムにもっと入れたい曲もあったんですけど、予算とかスケジュールの兼ね合いで、削って削ってこの収録曲になってるんですよ。でも、どうしても“誓います”は入れたくて、レコーディングの最後にみんなに泣きついて入れてもらいました。泣いても笑っても1回だけ演奏して終わろうということで、それがそのまま収録されたかたちです。それで、その場の会話も入ってるんです」
――気持ちのよい終わりかたですよね。本作をリリースして、レコ発をやったら新たに見えてくるものもあると思いますが、今後もソロとバンド編成の両輪で進んでいく感じでしょうか。
「そうですね。バンドはレアな機会にしか観られないもので、それも音源がちょっと生音に代わったくらいのものにはしたくないと思ってます。私、ちょっと前までは組織と小日向由衣が同じになればいいなと強く思っていたんですけど、最近また組織とソロが違って存在したらいいなと思い始めていて。ソロにしかできない曲、バンドにしかできない曲があったり、もっとわかりやすく棲み分けができるといいなと思っています」
 ■ 2024年7月24日(水)発売
■ 2024年7月24日(水)発売
組織-kohinatayui band-
『プルコギ革命』
なりすレコード | こっこっこレコード
CD KOKKO-05 3,000円 + 税
[収録曲]
01. ネコみたいに
02. ドッペルゲンガー
03. 生春巻き
04. サイダー
05. 夢見る羊ちゃん
06. 世界が泣いてる
07. ハリボテの恋
08. 手と手
09. 水色
10. 別れの時
11. 誓います *
* Bonus Track