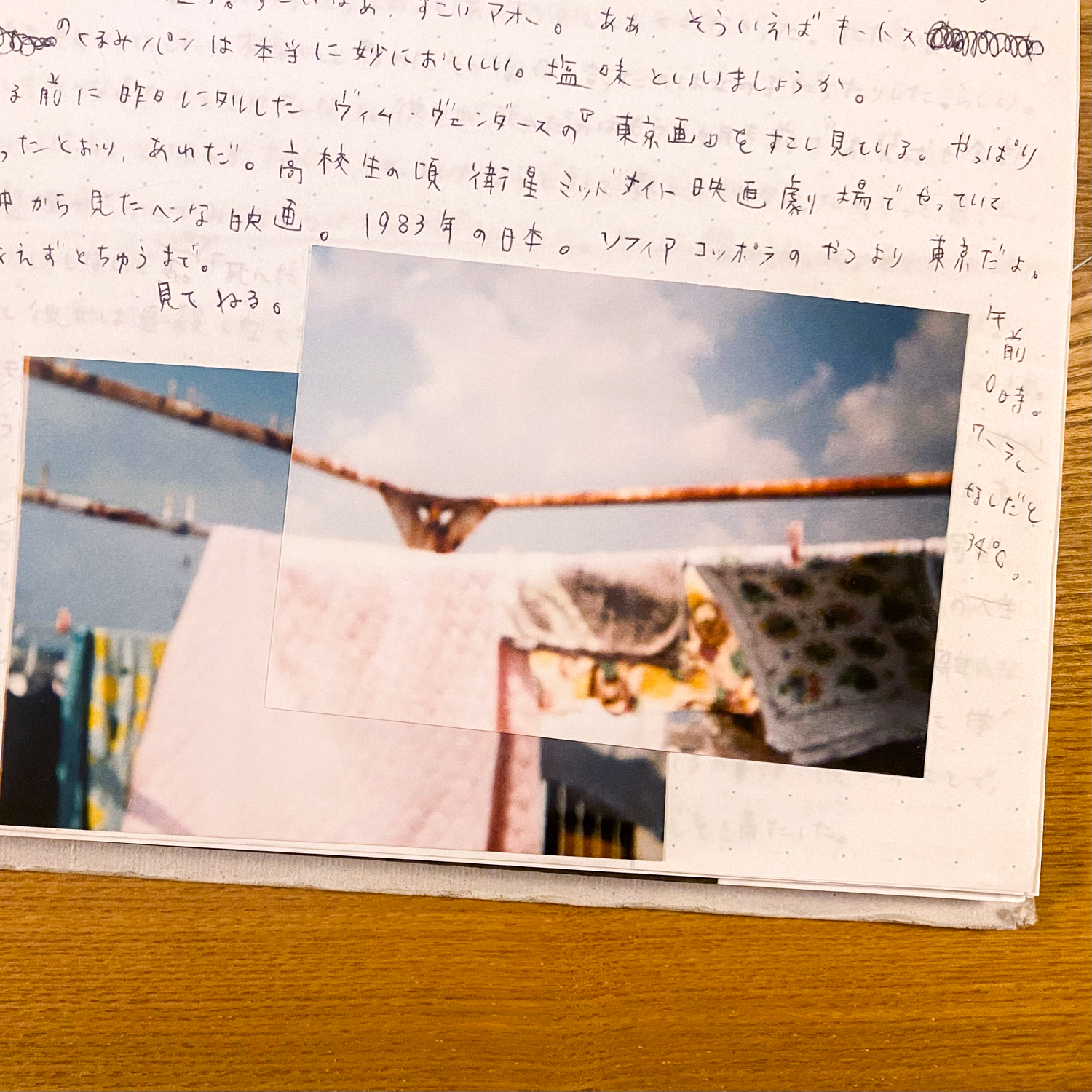文・撮影 | 梶谷いこ
長い、長い、まるで永遠に続くかのような百日紅の季節がついに終わったら、萩の花の季節が来て、萩の花の終わり頃には金木犀が香り始める。そんな花の順序の摂理を、あたかも息を吐くようにおしゃべりに織り交ぜることができる。
それが、幼かった私が思う“大人の条件”だった。花の順番だけではない。雲の形、雨や風の名前、洗濯に出されるコートの仕立て。私が子どもの頃を過ごした母の実家のクリーニング店では、一日中、私が思う“大人の話”が飛び交っていた。そしてその真ん中にはいつも、祖父の日記帳があるような気がしていた。個人商店のクリーニング屋の主人だった祖父は、夕方に自分の仕事を終えると工場の2階にある住まいに上がり、毎日決まって黒い日記帳に万年筆を走らせた。
天気、気温、アイロンを当てた「カッターシャツ」の枚数、増えてきた洗濯物の種類、道端に咲いていた花。祖父は白地に藍染の着流しの上に鶯色の羽織を羽織り、座卓に向かってその日のことを書き留めた。折りたたまれた脚は細く、骨っぽく、日記帳の文字はひどく震えていた。私は、蕎麦ぼうろなどを食べながら、その様子を黙って見ていた。はらり、はらりと落ち葉が1枚ずつ土の上に降り積もっていくように、祖父が日記帳を1ページ、1ページと重ねていく様子を、静かに、じっと見つめていた。
そのうち、自分が思う“大人の話”は、こうして1日1日と時間を積み重ねることで生まれるものなのだと、ある日気づいた。去年の今頃は大きな台風が来たとか、今年はまだ袷のオーバーコートを捌ききれていないとか、川べりにもう彼岸花が咲いていたとか、そういう、店の人たちが交わす話は、過去の出来事を参照して繰り出されるものらしい。私は次第にそう理解するようになった。そして憧れた。自分も早くそうなりたいと願った。だから目の前を通り過ぎる時間を、経験を、ひとつも取り逃したくないと思った。日々の記録を付けることは、私にとって、早く大人になるための手段だった。
「月光荘」のスケッチブックに出会ったのは、大学1回生のときだった。京都の一乗寺の恵文社の奥のギャラリーの隅。彫り装飾のついた木製の小さな棚の下半分に、月光荘のスケッチブックのコーナーがあった。店内は今のように明るくはなかった。薄暗い、踏むとギシギシ鳴る床にしゃがみこんで、私はスケッチブックを物色した。画用紙でできた「アツ」、ハガキほどの厚さの「特アツ」、裏が透けて見える「ウス」、「ウス」の紙に、罫線ではなく青い点が印刷されている「ウス点」、「ウス」の紙に色をのせた「イロブック」。用紙のバリエーションに迷ったが、とりあえず、一番小さいサイズのものを全種類買って帰った。幸いどれも300円ほどで、そこまでの出費にはならなかった。
値段の割にどれも活躍したが、なかでも「ウス点」は画期的だった。紙が薄いので、スケッチブックというよりトレーシングペーパーのようにして使うことができる。それに、目印に印刷された青い点は、コピーやスキャンをしても写ることがなく便利だった。また青い点の間隔が1cmというのも良かった。強い力で大きな字を書く私には、「コクヨ」のノートのA罫もB罫も細すぎて使いづらかった。その点、1cm間隔ならゆったりペンを走らせることができる。これだ、と思った。私は2Fのサイズのものを、スケッチブックではなくノートとして使うことにした。
大学3回生の夏休み、ゼミで「日記」の課題が出た。それも、2ヶ月弱の夏休みで見たものや聞いたものをひとつ残らずすべて記録すること。私は大真面目に取り組んだ。夜行バスで行った東京・ワタリウム美術館の「さよなら ナム・ジュン・パイク」展も、開業1年経って初めて行った「梅田シャングリラ」の天井から垂れたミラーボールも、当時出町柳の駅前にカレーの匂いを漂わせていた「カミ家珈琲」の三角屋根の上で回る風見鶏も、目に入るものすべてを2Fサイズの月光荘のスケッチブックに書き留めようとした。
私は、スケッチブックをいつでもどこでも持ち歩き、時間があればペンを取った。写真も撮った。彼氏がプレゼントしてくれた110フィルムのカメラで目に入るものをどんどん撮り、現像して糊で貼り付けた。そんなお金、あの頃の生活の一体どこにあったのだろうと今は思う。でもフィルム代や現像代に苦労した覚えはない。記録にかかるお金を、私は支出の優先順位第一位に据えた。あの夏、それほどまでに私は日記に燃えていた。
約2ヶ月間の自由時間をすべて記録するのに、スケッチブック1冊きりでは到底足りなかった。私は追加分を調達するためだけにひとり京都の市バスに乗り、一乗寺の恵文社まで行った。どうしても月光荘のスケッチブック、ウス点、2Fサイズでなければならなかった。
休み明けに、私は意気揚々と束になったスケッチブックをゼミの授業に持参した。しかし、律儀に課題をやってきたのはクラスで私ひとりだけだった。先生も、まさかこの課題をやってくる学生がいるなどと思わなかったのだろう。大感激し、猛烈に私を褒めた。教室の黒板の前でただひとり褒められながら、私は“誂”という文字を思い出していた。
中学の頃、国語の授業で“誂える”という漢字がテストに出た。私はそれをクラスでただひとり“あつらえる”と読んだ。正解だった。隣の席の男子には「なんでそんな漢字知ってるんだよ」と鼻で笑われた。祖父のクリーニング屋には、“誂”という字がそこかしこにあった。洗濯物の背広は、既製品の“吊し”とオーダーメイドの“誂え”で呼び名が分かれていたし、着物を包むたとう紙には「お誂え」と印刷されていた。
クラスでひとりだけ“誂える”という字が読めるとわかったとき、私は恥ずかしかった。“御里が知れる”とはこういうことだと思った。大学のゼミの先生に絶賛されながら、私はその時のことを思い出していた。それから、祖父の黒い日記帳や、店の人のおしゃべりを思い浮かべた。学校の勉強は好きだったし、未だにまた学校に通いたいくらいだ。でも今になって思う。サイン・コサイン・タンジェントとか、五言絶句とか、遺伝の法則とか。そんな学校の授業以上に、私に“世の中のこと”を教えてくれたのは、子ども時代を過ごした祖父の店だった。そして、そんな私の知っている“世の中のこと”は、少し古めかしくて、偏っている。

Instagram | Twitter | Official Site
1985年鳥取県米子市生まれ、京都市在住。文字組みへの興味が高じて、会社勤めの傍ら2015年頃より文筆活動を開始。2020年、誠光社より『恥ずかしい料理』(写真: 平野 愛)を刊行。雑誌『群像』(講談社)、『Meets Regional』(京阪神エルマガジン社)等にエッセイを寄稿。誠光社のオフィシャル・サイト「編集室」にて「和田夏十の言葉」を連載中。