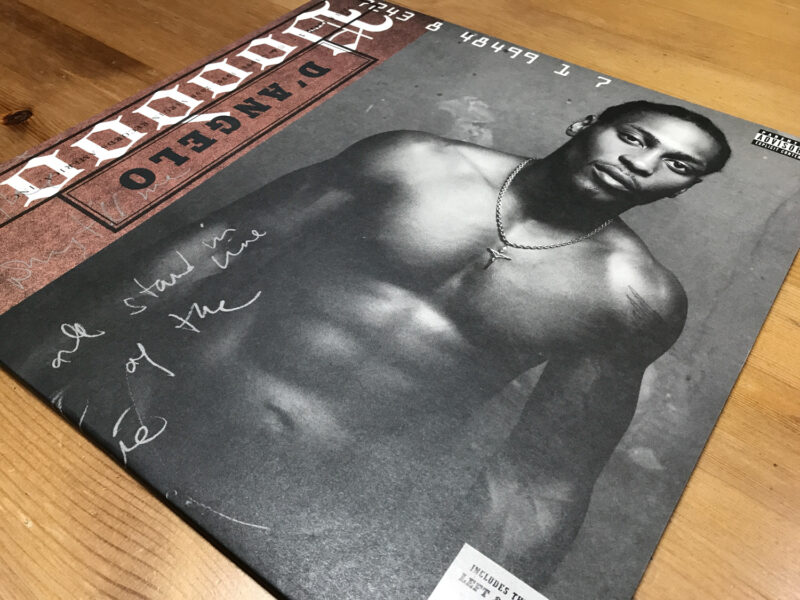文 | 那倉太一
UNCIVILIZED GIRLS MEMORYの初めてのフル・アルバムが「 [...]dotsmark」からリリースされると聞かされたときの高揚を今でも覚えています。
「 [...]dotsmark」はノイズ・ミュージックのレーベルと言って齟齬はありませんし、UCGMがノイズ・ミュージックとして括られる音源をリリースするということで間違いもないのであって、ZENOCIDEの玉野勇希とdotphobが結託してノイズ・ミュージックの音源を製作するとなると、これはもう当然一筋縄ではいかない、沈鬱で爽快感がなく、暴力と非力の綱渡りの情景が収められているであろうプロダクトの到来を心待ちにするほかないのであります。頼もしい人物達によるノイズ・ミュージックの新作を同時代に享受できると思うだけで高揚するほどには私はいまだにノイズ・ミュージックを愛しているわけです。
昨今、ノイズ・ミュージックにコンシャスな音楽を対象にした興味深い批評をSNSで見かける機会が増えたように思います。そんなものは、あなたのエコーチャンバーとフィルターバブルの賜物にすぎないと一蹴されてしまいそうですが、私の目を引いたのはその質的な変容でした。それは、私が最もそういった類いの音楽を対象とした批評に触れていたおよそ20年前から今日までの、それらにある程度目を見張ってきた期間に観察された言表ということになります。特筆すべきものとして2020年に『ele-king』誌上に掲載された樋口恭介氏によるKazuma Kubotaに関する論考が挙げられるかと思います。そこにはおよそノイズ・ミュージック批評としては場違いな「物語」や「人間賛歌」といった言葉が堂々と記されています。この有意味性、肯定性への傾きは何を意味するのでしょうか。この論考は旧来のノイズ・ミュージックとその批評に対するある種のアタックであったと思います。今月発刊された『新紀要』に掲載されている清澄薫香馨氏による「ノイズ・ミュージックにおける否定の系譜――ルッソロ・メルツバウ・ヴォミールを巡る円環」にもある通り、ノイズ・ミュージックへの批評には伝統的にその否定性が重要なファクターとして扱われてきました。そういった土壌のもとに樋口氏の論考に即座に差し込まれる疑問があるかと思います。「これはノイズ・ミュージックが纏っていた否定神学的な色気の失効を示すにとどまる出来事、もしくは証拠を差し出しているのに過ぎないのではないか?」。要するにノイズ・ミュージックが単なる音楽の仲間入りを果たしたと言うことなのではないか。または、「Kazuma Kubotaの固有のノイズ・ミュージックが飛躍なしに人間賛歌を物語る音楽なのではないか」、等々。私はこの論考の登場に近年のノイズ・ミュージック批評の潮目を感じました。樋口氏は今や相当にパフォーマティブな主体として知られている通り(顕著なものとして、現在テレビ東京で放映中の『SIX HACK』をご覧ください)、その言表行為の評価を字義通り受け取るには相当な注意が必要なのも事実であります。しかし、樋口氏が作品から滲み出る作家の実存の断片に焦点を合わせることが何らかの方略であったとしても、このテキストから伺えるある特定の集合的なノイズ・ミュージックに対する享楽と期待は氏にとっても、また、多くの聴者にとっても、安定した有意味性を持つ「エモ」に回収可能と言いきることはできないように思います。
では、ノイズ・ミュージックは、例えば欠如という現実
(ラカン)、純粋な差異
(ドゥルーズ)といった変容の起源とも言うべきものに果敢に関係を挑む営為と言えるのでしょうか。はたまた、ブラシエ的な「絶滅」のサウンド・トラックとしての強度を有しているのでしょうか。
随分と大仰な物言いとなってまいりましたが、私にとっては、UNCIVILIZED GIRLS MEMORYの『HEAVEN』はそういった問いを考えるにあたって格好の材料であると同時に、稀有な音楽表現であることは疑いようがありません。まず、その点を強調させていただきたいと思います。
それでは、外堀を埋めるように、それこそ否定神学的なお芝居を多分に含みながらUCGMの特権性について放逸なお喋りをさせていただこうと思います。
さて、現行のノイズ・ミュージックの情況とはいかなる様相を呈しているのでしょうか。広義には、どんな様式であれ非楽音の存在感にフォーカスしている作品はすべからく「ノイズ・ミュージック」と呼称可能であるというのが今日的な共通認識かと思います。この文化は、全ての録音物は音楽であるという認識と両輪を成すようにして多くの作品を産出してまいりました。また、商品としてパッケージされていなくてもノイズ・ミュージックは至るところに存在しております。都市生活者や労働者にとって親しいものでは、産業機械の唸り、孤独な部屋の中で耳につくトランス変調の雑音、ある出来事に際して生じる誰かの叫び声や爆笑、台風の日の微小な建具の隙間と侵襲する暴風が織りなす豊穣なフリーキー・トーン、自身の身体に引き寄せれば、鼓動、耳鳴り、喘息発作の摩擦音など。騒音主義的ではない、より穏やかな趣のものであれば、国木田独歩が感心した武蔵野の鳥のさえずり、どこかで実の落ちる音、時雨が葉にあたってささやくような音などもそう言えるでしょう。そうした、採取や模倣、再現への欲望を喚起するノイズは私たちの生活空間に満ち溢れています。小さく見積もってもそれらを録音してしまえば、すべからくノイズ・ミュージックと言うことができます。
このような話題が展開いたしますと、ひと昔前は決まって「排除されるべき対象」としての「ノイズ」を聴取するというトピックが頭をもたげるものでした。これは思弁的な言語の話題とも言えますし、私の手に余りますのでここでは控えさせて頂きます。John Cageが無響室で聴いたのは自身の身体の音と断言することも十分可能ですし、否定神学的な物言いに紙面を割くより、私たちは先を急がなくてはなりません。録音された作品が何らかの形で享受され語られる以上はそれが純粋な否定を表現しているなどと言うことはあり得ず、必ず何がしかに対する肯定性を有していると言えます。また、個人的な経験から申し上げましても、ある音響作品やその上演に会遇致しまして、その趣味の悪さによって不愉快だと感じたことはございますが、耳が音響的に攻撃されて不快な気分になったというような体験は私は持ち合わせておりません。その意味では、私は前衛としてのノイズ・ミュージックの現場に立ち会った経験などなく、あくまでも商業的な原理によって構築された大衆の趣味をある程度には裏切ることのない順応主義的なノイズ・ミュージックしか享受してこなかったのかもしれません。私にそれを恥じる気持ちは全くありません。その意味でも私は前述したような問題の語り手としては不適格かと思います。また、そのような聴取行動のせいもあり、私の耳は騒音性難聴をまんまと発症しておりますので、レシーバーとしての生物学的基盤ももはや定型とは言えず、繊細でもありません。ということは――そういうものが果たして存在するのかどうか存じ上げませんが、私は恐らく「正しい」音響の聴取において不具を抱える者であります。加えて申し上げますと、第一に私たちは環境依存的な存在であり、その最たる場である身体に宿る感性を容易には操作できません。そのような前提もあり「聴けないノイズを聴く」ことについての対話は実際的な聴取体験の場を想定して表現するノイジシャンにとっては、愚かな言説の堂々巡りを引き出してしまうが故に、前時代的な戯れとして憚られるように見受けられるのが私の印象です。その一方で、ノイズ・ミュージックというジャンルが登場した際に有していたであろう、逸脱性や不定形性、不可能性への志向が賦活する創造のエネルギーが潰えたとも私は考えておりませんし、そのような「力」に対して、たとえその対話の不可能性が高いとしても、少なくない作家の内にはある種の信仰が残っているのも確かなことであると感じています。そのせいか、ノイズ・ミュージックというタームはもはや当初の特権性を持たないものの、それを自身の作品や活動にあてがう場合には、いまだにどこか甘美な居心地の悪さを与えてくれる言葉であります。そのような性質からか――もはやその残滓と言うべきかもしれませんが――「ノイズ・ミュージックとはなんなのか」という問いが立ち上がること自体が、商品化されたノイズの魅力の一部であることを否定し尽くすこともいまだにできそうにはありません。冒頭でも申し上げた通り、昨今では、未来派やJohn Cageの紹介から導いてくれるような、ノイズ・ミュージックの発祥(発症)から、そのサブ・ジャンルの紹介や、そういった集合から逸脱するアーティストの固有性への言及に至るような、網羅的かつ現行ノイズ・ミュージックの動向をおさえた論考や批評がございますので、ぜひそういったテキストに触れて頂ければと思います。近年のそれはまた旧来の語らいとは違った要請のもとに発露されている印象を与えるものであり、私と致しましては、ある種のリヴァイバルの蠢動を感受せずにはいられません。無論、これは私自身が気持ち良くなるように都合よく状況を誤読している可能性を否定できるものではございません。
現代的状況において、ノイジシャンがノイズ・ミュージックの略称として「ノイズ」と何気なくその会話において使用する場合には、そのほとんどが「ハーシュ・ノイズ」を指しているように見受けられます。それ以外のジャンルについては比較的細かいサブジャンルの名称において呼称されております。インダストリアル・ノイズ、パワー・エレクトロニクス、グリッチ、コラージュ等々。上位概念といいますか、それぞれの演奏者の手つきや感性の下地や鳴らす場の状況設定やその形式として、ロック、現代音楽、フリージャズ、ニューウェイヴ、ポストパンクと呼称されるジャンルが先駆しております。無論全てを挙げられたわけではありませんが、上述したジャンルを想定した中で、論ずるかたがたがそれぞれの思う輪郭線をひいて「ノイズ・ミュージック」と総称しているのが現状かと思われます。
音楽作品に昇華できそうな非楽音的なマテリアルとしての「ノイズ」すなわち「雑音」は現行の音響派やDTMの作家にとってはありきたりに採取、製造され、加工、編集される対象――まさに「素材」として位置づけられています。2005年3月号のユリイカの特集『ポスト・ノイズ 越境するサウンド』におけるディスクガイドのラインナップの時点で、そのような「荒れ狂うノイズから素材としてのノイズへ」という志向は既に決定的に示されています。およそ20年前のこのような特集の存在も、本邦においてのノイズ・ミュージックのリヴァイバルが幾度かあったことの証左でもあります。
この素材としての「ノイズ」が、特定のジャンルにとって、その「発達の最近接領域」の先にある水準に到達するための協同的な役割を果たす「他者」として振る舞った場面を、私たちは度々目にしてきたかと思います。「発達の最近接領域」というのはロシアの発達心理学者ヴィゴツキーによる概念ですが、自分1人で達成できる課題の水準と、協同的な他者と共に取り組めば達成可能なより高次の課題の水準との差をあらわす概念です。例えば、一人遊びでは無理でも、親や兄弟や友人と一緒であれば達成できるパズルや積み木のような遊戯の場において顕現化するものです。このような「ノイズ」による、閉塞した特定ジャンルへの、いわば効能のような側面については「ノイズ」を概念と固有名詞の間で揺れ動く「擬似ジャンル」と定義づけする、レイ・ブラシエの論考『ジャンルは時代遅れである』(Genre is Obsolete | 2007, Multitudes)においても展開されているので参照されるとよいかと思います。
上述したような、他の特定ジャンル内で素材として並列に取り扱われず、懐柔されていない「ノイズ」を主役にみたてた音楽をノイジシャンは「ノイズ・ミュージック」と呼びたくなるものなのでしょう。繰り返しますが、現状の物言いでそれを基礎づけているのは「ハーシュ・ノイズ」だと言えます。しかし、「ハーシュ・ノイズ」はその音像イメージからか確かに純正ノイズ・ミュージックと呼ぶべきような印象を与える面を有することは容易く理解できますが、私の感覚からすると、これは反感を持つかたも多くいらっしゃるかと思いますが、「ハーシュ・ノイズ」はロックのマニエリスムであるというのが基本的な立場です。卓にペダル・エフェクターを並べて、ツマミを操作する「ハーシュ・ノイズ」のスタイルを「テーブル・コア」などと呼ぶ場合がございます(これはレイ・ブラシエが『ジャンルは時代遅れである』において特権的に扱ったRudolf Eb.erよる定型的な「ハーシュ・ノイズ」のスタイルに対して提出された否定的な呼称です)。このスタイルには、ペダル・エフェクターとアンプを使用するというある種のマナーと言いますか、機材依存的な側面がございます。ここでJohn Zornのものとされる新しい音楽というよりも、新しい機材しかない
という発言を引いてみますと「ハーシュ・ノイズ」はその成立過程において、電気楽器、その中でも特にエレクトリック・ギターの機材の新しい使用法の発見に端を発しているという歴史的事実を排するのがおおよそ不可能だということに気づかされます。このような「ハーシュ・ノイズ」の革新性をその消極的な面から先に語りますと、その擁護者と致しましては少々薄暗い気持ちとなってまいりますが、積極的な面から言い換えますと「ハーシュ・ノイズ」登場のインパクトの中核はエレキギターなどの電気楽器が占めていた発信源が楽典的な習熟から解き放たれ、それらしい自分好みの騒音が発信されるものであればなんでも使用可能になったということが大きいでしょう。そのことで、喧しい既存の音楽に新しい抽象芸術化の途が拓けたことが特筆すべき点です。このような電気とペダル・エフェクターの新しい関係 = 使用法から多くの作品が生みだされました。発信源が楽典的な習熟から解放されたことは、ロック史にお馴染みの反ロック的な形容詞としてまさしく「パンキッシュ」な印象を与えました。ですが、それも、パンクがそうだったようにそう賞味期限がそう長いわけではありませんでした。「テーブル・コア」的な「ハーシュ・ノイズ」は大体はロックのために製造されたペダル・エフェクターを演奏していることになりますので、演奏家として自然に習熟度を上げていきますと、ペダル・エフェクターが孕んでいる自然な性向としてのロック性が頭をもたげてまいります。無自覚に「テーブル・コア」に興じればただの「ロック」になるのです。それを周到に回避しパンキッシュなイメージを与えること――ロックのマンネリズムやフリージャズで言えばありがちな集団投射的なパワー・インプロの手癖から解放されること――はいつしかこのジャンルの伝統的な目標の一つとなりました。
ただ、その一方で、私が率直に申し上げたいのは、現行で最も気の利いたロック・ミュージックのスタイルのひとつとして「ハーシュ・ノイズ」の存在を無視できないという実感でもあります。
INCAPACITANTSのライヴを観賞中に、ロラン・バルトがそのプロレス批評『レッスルする世界』(Le monde où l'on catche | 1952, Esprit)において述べた何物も全面的にしか存在しない。いかなる象徴、いかなる比喩もなく、すべてが余すところなく与えられる。何物も影に残さず、身振りはすべての余分な意味を切り払い、観衆に対して儀式的に、自然と同じようにきっちりとした、純粋で充実した意味を提供
されたような気分に浸り「ロケンロー!」とその胸中で叫んだり、眼前に立ちはだかったMerzbowの音壁に対峙し「極度に抽象化された爆音の独りLED ZEPPELINだ」といった感想が浮上してくるのは至極当然の感性とも言えるのです。無論その二者の音楽性はそのような言表に収まるものではありません。
仲山ひふみ氏は、『ele-king』に掲載された東京・落合 soupでのAaron Dilloway来日公演のレビュー記事において、INCAPACITANTSのライヴにおける演者と観客の呼応関係を「フーリガン的」かつ「筋肉性」優位であるとし、そこに家父長制的でナショナリズム的なファナティシズムへと容易に反転しかねないその危ういポテンシャル
を嗅ぎ取り家苦痛と快楽の抗争のゲームをいかにして美学的に致命的であるのみならず政治的にも危険な帰結をもたらしかねないものとしてのクリシェ的な固定化から守るか
という問いをジャパノイズのアーティストとそのリスナーに差し向けています。私は多くの点でこの意見に同意いたします。ですが、その問いに対する実践をINCAPACITANTSに求めるのは、ジョン・フォードのフィルムに収められた女性や人種の表象を変更するほどに不可能かつ馬鹿げているとは言わないまでも、やはりそれは我々観客が担うべき問題だと考えます。仲山氏の発言はノイズ・ミュージックを聴取して狂ってしまうというある種の「症状」に対して、作品や演者の存在から導出可能なイメージとの垂直的な関係を特権化することの危険性を示唆するものであると捉えるべきでしょう。すなわち「偶像崇拝の禁止」です。ここには、私たちの、ノイズ・ミュージックの演奏とその聴取には「マイナーな欲望」を志向するというイメージを保持し続けて欲しいという願いが背景にあるのかもしれません。それはそうと、むしろ白痴的な、一見して水平的な連帯を阻止する為にも垂直的な幻想を排することが肝要です。垂直的な関係の特権化とは到来が待望される天上の「神々の国」を仰ぎ見てその実在を信じ込むような態度です。垂直的な関係の特権化は「父」「神」「理想」に接近し、自分を高みに持っていくことで主体化することと言い換えられます。対して水平方向に広がる関係を重要視することは、垂直方向の特権化に伴うような主体化を引き受けずに隣人との関係から個体化を目指すプロセスと言っていいでしょう。隣人とは仲間のことではありません。イエスが最も重要な掟として「隣人を自分のように愛しなさい」と言った隣人のことであり、それは当時のイスラエルにおける罪人である徴税人や売春婦、ひいては自分を迫害する敵をも含む社会的諸関係を超えて見い出される他者のことであります(多くの人間は貨幣や資本という物神の圧倒的な支配のもとに水平的な方向に目をやってもその視界には経済的合理性しか見つけられないというニヒリスティックな気分によって無力化されています)。このイエスの言葉に偶像崇拝の禁止についての実践的な想像力を見いだすことができます。柄谷行人は『力と交換様式』(2022, 岩波書店)において、モーセの率いた盟約共同体が農耕可能な「約束の地」に入ると、唯一神であるヤハウェ神を棄てて、農耕神バールを奉じて偶像崇拝に至った例を示して「偶像崇拝の禁止」を定住の禁止に集約されるとし、神を目に見える造形物として崇拝することだけが偶像崇拝なのではない。それは別のかたちでも生じる。たとえば、国家、民族、共同体を崇拝することである
と述べています。また、ヘブライ語聖書(キリスト教徒が指す旧約聖書)はユダヤ民族の栄光の歴史でも英雄譚でもなく、反対に、前述したような「偶像崇拝の禁止」を含む律法の実践に対して民族が繰り返しつまずき、失敗を重ねる様子を赤裸々に描いたものであり、紆余曲折の歴史の中に神の意図を見出そうとする信仰の格闘の記録であるとも述べています。この「偶像崇拝の禁止」という法を拡張致しますと、垂直関係の特権化も偶像崇拝に値するというのが私の考えであります。垂直方向を特権化するということは「父」「神」「理想」といった圧倒的な他者と1対1になるということです(余談ですがこのような志向と近年声高に語られる「ドルオタに成ること」や「推しの文化」を私は全く異なる機序に基づいていると考えています)。
ヴィンスワンガーというスイスの精神科医は、人間というのは往々にして自身の領分を越えて尊大にもそういった崇高なものと対峙して「問い」を解決できると「思い上がり」をしてしまうものだと考えました。このような崇高なものと人間の「思い上がり」との関係は勿論ノイズ・ミュージック特有のものではありません。むしろ音楽全般に周到に刷り込まれた罠と捉えることもできます。むしろ、ノイズ・ミュージックは本来的にはこのような崇高概念に常に挑戦すべきものとする向きもございます。非常な困難を伴いますが、ノイズ・ミュージックを聴取して享楽している私たちの体験からどこまで「崇高さ」に対する感情を差し引くことができるのかというトピックからこのジャンルの現在的な有り様へ迫ることも重要な視点であると考えます。
この「崇高」という美学カテゴリーには歴史的変遷がございますが、そのどこをとってもノイズ・ミュージックと容易に関連づけられることができます。この「崇高」という話題において必ずと言っていいほど召喚されるエドマンド・バーグのそれを引いてみましょう。バーグは『崇高と美の観念の起源』(A Philosophical Enquiry into the Origin of Our Ideas of the Sublime and Beautiful | 1757)において、「美」とは「小ささ」と「僅かさ」から生じる「繊細」という部分が互いに他といわば融合
することで成立し、なおかつ力強さの外見があらわでないこと
であり、これらを「もっともらしさ」と総称しています。「美」はこのような均斉調和に基づく快に基づいているとし、一方で「崇高」を苦や恐怖に基づくものとして対比させました。「崇高さ」を「曖昧」さがもたらす不安な印象と「欠如」と「闇のような力」がもたらす、驚愕や共感や敬意を喚起する感性の高揚と表現しました。こうも言っています。恐るべき対象と関わり合って恐怖に類似した仕方で作用するものは、何によらず崇高の源泉であり、それゆえに心が感じうる最も強力な情緒を生み出すものにほかならない
と。このあたりは私たちにとって馴染深いと言いますか、非常にこの書物の調子の良い部分であります。たしかに芸術鑑賞の際にこういった感覚の到来に喜んだ覚えのあるかたも多いかもしれません。特にエクストリームなカルチャーを愛する人間はこういった感覚、というより、こういった物言いに非常に弱い心性を有しているようにも思います。私も例外ではありません。しかし、バーグの提出した崇高概念には敬虔なキリスト教徒として18世紀のイギリスにおける信仰軽視と無神論の流行による道徳の退廃に抗って「裁く神」と「正義の神」の復活という意図が背景にあったことも知られています。『崇高と美の観念の起源』を読み進めますと、我々が苦と危険の観念をもっていても、実際にそのような状況に置かれていない時にはそれは歓喜となる。 …… この歓喜を引き起こすものは何であれ、私はそれを崇高と呼ぶ
というフロイトの快楽原則と神への宗教的帰依が一体となったような節に出くわします。また歓喜は自己保存に属する情念
、苦または危険の除去に伴う感情
であり歓喜する対象が崇高である
と述べています。第二版で追加された「力能」においては神が発揮し賜う正義、神が施し賜う慈悲の観念を持ってしても、何ものにも妨げられぬこの自然に生じる恐怖を完全に取り除くのは不可能である。我々は歓喜しつつも、同時に恐怖を感じる
とも述べます。この「崇高なもの」に触発された感情の両義的な性質が重要であり、カントやド・マン、リオタールに受け継がれるのですが、少し粘着的に足を止めてみます。バーグにおいては、苦や恐怖の除去による歓喜を引き起こすものを「崇高」と名指すことが明らかにされています。またそのような神の「力能」をもってしても自然に生じる恐怖を完全に取り除くのは不可能
であるのならば、恐怖の残滓が存在するわけです。バーグは恐怖の対象の説明も忌避し、驚愕や共感や敬意を喚起するメカニズムを説明しないまま、その両義性を半端に調停し、その享楽を可能にする神への信仰――「喜ばしい恐怖」を要求しているのです。このような審級はド・マンのいう「美学イデオロギー」と一致すると言えるでしょう。ド・マンの『美学イデオロギー』(Aesthetic Ideology | 1996, University of Minnesota Press)においてそれは偽の意識の審級であり、その真の機能は〔美感的判断の〕まやかしの安定性と権威を確保することにある
とされています。バーグ的な崇高体験における感性の限界としての両義性を抑圧しようとする身振りは、政治と倫理の美学化に容易に連結されるものであり、それが、美学の全体主義的イデオロギーへの融合という悲劇的な事態を招いてきたことは衆知のことであるかと思います。
ユダヤ律法における偶像崇拝の禁止を最も崇高なもののうちのひとつとしたカントは『判断力批判』(Critik der Urtheilskraft | 1790)において「崇高」を「表出不可能なもの」の「否定的表出」としました。感性的には表出不可能であるはずの超感性的な絶対的なもの(道徳的に善いもの)が表出不可能であるという事実によって「否定的に表出される」という事態がカントにおける「崇高」です。超感性的なものへの否定的な到達は絶対的な到達不可能性によって構造的に可能となるので、超感性的なものと感性的なもの、道徳的に善なるものと崇高なものの適切な関係性は決定不可能となり、美的カテゴリーの不安定性が保たれるとも言えます。しかし、カントが構想力は、たとえそれが頼りにできる感性的なものを超えてはなにも見いだせないとしても、それでもまさに自らの制限のこうした除去によって、限界づけられていないものを感じる
としたように、崇高において問題となっているのは構想力の限界を超えてある「彼方」ではなく、その限界であると言えます。ジャン=リュック・ナンシーが『崇高な捧げもの』(L'offrande sublime | "Du Sublime" 1988, Editions Belin)で限界の外には何もない、呈示可能なものもなければ、呈示不可能なものもない。 …… そうではなくて、ただ限界だけがある
と述べた通りです。より具体的な記述をド・マンの『カントにおける現象性と物質性』(Phenomenality and Materiality in Kant | In Gary Shapiro, Alan Sica "Hermeneutics: Questions and Prospects" 1984, University of Massachusetts Press)という論文のなかで引用したパスカルの『パンセ』(Pensées | 1669)にも見つけられます。われわれの感覚は、極端なものはなにも認めない。あまりに大きい音は、我々をつんぼにする。 …… 過度の性質は、われわれの敵であって、感知できないものである。われわれはもはや、それを感じることなく、その害を受けるのである。 …… すなわち極端な事物は、われわれにとっては、あたかもそれが存在していないのと同じであり、われわれもそれらに対しては存在していない
のです。これは「聴けないノイズを聴く」とか「エクストリーム・ミュージック」という呼称の持つ決定的な不全性や滑稽さを示しているとも言えます。カントの言うようにピラミッドの大きさから十分な感動を得るためにはあまり近寄りすぎてはならないし、同様にあまり遠ざかってはならない
のです。崇高が生じるのは唯一の特権的な視点、つまり行き過ぎた総括も行き過ぎた把捉も避けるような場所
であり、崇高を「無限」や「絶対」との――否定的であれ、消極的であれ――関係に還元してしまうやり方は再検討を余儀なくされるのです。崇高な「巨大なもの」とは「大きいもの」と「途方もないもの」とのあいだに位置する境界上の現象なのです。このような境界性とは体系的な思考に閉じ込められたままにはならず、むしろそういった境界画定から逸脱したものなのです。境界線上ののあちら側でもこちら側でもない場所で宙吊りにされるというダブルバインド状況における両義的な感情が「崇高なものの感情」なのです。私はUCGMのお2人はこのことを強く享受した経験があり、また、ここまでご紹介した崇高概念の理解の前提をもとに固有の限界のアレンジメントを記録しておられるのだと思います。ノイズ・ミュージックは美的カテゴリーの不安定性と美学イデオロギーの間で常に揺れ動いています。そのような「寸断された身体」と「全体性」――非力と暴力の綱渡り――の間にある、ダイナミクス自体がこの『HEAVEN』に強く記録されております。
さきほど「ハーシュ・ノイズ」は騒音主義的な音楽に新しい抽象芸術化の波をもたらしたと申し上げましたが、バーグとカントの影響を受けたリオタールはアメリカの抽象表現主義絵画の中でも、特にバーネット・ニューマンの絵画を、上述してきたような崇高概念に時間論的視座を導入して賞賛しました。時間という概念が導入されることで音楽にぐっと引き寄せるのが予期されます。『時間――四次元への眼差し』(L'Art et le temps: Regards sur la quatrième dimension | Palais des Beaux-Arts, 1984)という展覧会カタログに収録された「瞬間、ニューマン」(Newman: The instant)において、リオタールは時間とはタブローそれ自体である
と述べています。どういうことなのでしょうか。リオタールはカント的な「呈示不可能性」を継承しつつも美術批評においては別の脈路を見出します。リオタールに従えば、作品が「みずからを呈示」する「出現」そのものによって、観賞者の継起的な時間の綜合を行っていた構想力が機能しなくなる状態が崇高さに触れる契機としています。こうも言っています。「崇高」とは、そこにあるものの「出現」を「瞬間的」に感覚すること――すなわち「瞬間を感覚すること」であると。これは私の実感といたしましても素晴らしいノイズ・ミュージックに触れた折に出くわした覚えのあるものであり『HEAVEN』においても幾度か去来した感覚であります。
さて、ここまで論を進めたところで、ノイズの作品論など到底手に負えるものではないと直感していた私のもとに『HEAVEN』の音源データが届き、早速それを再生し、ある場面を描写した貧しいメモを見返してみます。
“侵襲的に悪い思い出が回帰した場面なのか、それとも、定位できない対象に対する、もはや能動性を妄信しているにすぎないと言えるほどに具合の悪い想起と抑圧の関係の場所そのもののスケッチなのか判別不能な症候的音楽である。過去には心地よいものとして享受したはずの西洋クラシック音楽――すなわちわれわれの記憶――「の・ようなもの」が加工されて奇怪な様子で現前化している。この楽音と非楽音の混濁した音塊を前にして「本質的に決定された聴取の形式など存在しない」と遥か昔に決着をつけたはずの問いが再活性化されてしまう。その問いを閉じた時にあてがった蓋が馴染みのない拍子で開閉し、その内部からも何か不吉な音が鳴っている。あくまで自身の経験からくる体系的な理解を基盤とした閉じられた身体において、たとえそれが偽装された主体性であったとしても自身の現在的な美的判断に依って趣味の良さと快楽性が一致する音楽を選ぶことができる――もしくは『そういった判断のもとにしか評価できないし、しないようにできている私』――という高慢な態度が、彼らの演奏における不愉快な中断と突発的な悪寒を感じさせる音響の生成によって触発され、自身が特定の貧しい集中の形式に逃げ込んでいた事実が暴露される。そこに誰もいないはずなのに誰かが鳴らしている、もしくは誰かがいるはずなのにひとりでに鳴っている。「本当にもう怖いものなんてないの?」と揺さぶりをかけてくる。どこでもないけれど、どこへでも通じる場所で。声は奇怪な音響と一体化し不安を喚起するほころびそのものであったり、ときより反応関係をみせ縫い合わせようと試みるような優しく演劇的な素振りを見せはするものの、いつ落ちるとも知れない枯葉のように――二度と同じメロディを歌うことをしなくなったパティ・ウォーターズのように――憂鬱に、しかし甘く揺れている。出口の見えない孤独な発声の揺らぎと、呪われた音響の不快感の激化に不快感を感じながらも、それを観察できたことに幾分か安心を感じた瞬間に、唐突に悪夢から目覚めさせられるかのように声のみによって決定的な最小限の音階が示され、曲が終わる。無論はなから承知のことではあったが「これは音楽である」と宣言され、それと同時に我々は拘束から解放された安堵と突き放されたような思いに至るのだ”
この限りではありませんが、多くの部分が上述してきた「崇高なもの」に触発された感情との一致を見出すことが可能かと思われます。この作品が美術史的にみておおいに「崇高さ」と関係したものであると、私は断言せざるを得ません。
さて、「テーブル・コア」的な「ハーシュ・ノイズ」が観賞者の構想力を宙吊りにする瞬間を容易にはアレンジできなくなって久しい90年代、ラップトップが楽器として登場することでノイズ・ミュージックは革新的な展開を迎えます。代表例としては、Pitaを筆頭にしたMego的なセンスの登場です。ジム・オルークが彼らの活動を“Brand New Punk Computer Music”と評した通り、その革新性はまさにロックの手癖をオールドウェイヴと切り捨てるかの様にパンキッシュでした。より厳密にラップトップによるハーシュ・ノイズの名手と言いますとPitaの本人名義にあたるPeter Rehbergや、Zbigniew Karkowski、Russell Hazwell、一時期のMerzbowが挙げられます。デザインにおいても切れ味においてもロックのマンネリズムからの解放を感じさせるそのインパクトはまさに音響パンクでした。楽器としての歴史の蓄積が浅く、演奏の手さばきがブラック・ボックスとなるラップトップから暴力的な音を発するその姿は、70年代のオリジナル・パンクが我々に抱かせたような、「楽器を弾けない奴らがそこら辺にあったチューニングが合ってるかどうかなど関係ないエレキギターで無茶苦茶なコードをかき鳴らす」といった「幻想」を再燃させるには十分にパンキッシュでした。UCGMのdotphobもそういったPCによるハーシュ・ノイズの奏者というアイデンティティを全体的ではないにせよ系譜的に有していると思います。しかし、dotphobのパンキッシュな印象は70年代のオリジナル・パンクが我々に抱かせたそれとは随分と趣きの異なるものです。彼はライヴにおいてはアクションじみた身振りなど微塵も見せずに、マスクを着けたままPCの前に屹立し、何か陰惨で病的な作業に没頭しています。彼の音色が持つ「痛み」への固執――被虐的とも加虐的とも形容しがたい代物――は一体どこから来るのでしょうか。
もうひとりのメンバーである玉野勇希も「パンク」というものとおよそ無縁とは言い難い人物です。それはZENOCIDEというハードコア・パンク・バンドのヴォーカリストであるということのみで説明のつくものではありません。
今一度申し上げますと「パンク」とはロック・ミュージックのマンネリズム的感性に対する反動的かつ革新的な姿勢や志向を指しました。いまやその廃墟と言ったほうがいいのかも知れません。その意味において、多分にロック的なハーシュ・ノイズ優位なノイズ・ミュージックの変遷における「革新」について「パンキッシュ」という形容詞を宛てがって論を進めてまいりました。旧来のスタイルの否定や反権威主義、ニヒリズムという失われた「パンク」の公約数をUCGMにおいてはハッキリと見て取れるかと思います。「パンク」には当初、その「公約数」として目された思想や態度の真偽のほどが試される次元が存在しました。ポーザーでないかどうかという視線にさらされるわけです。真正性、オーセンティシティの問題と言えます。もはや、パンクはロック・ミュージックの下位カテゴリーであるパンク・ロックへと成り果て、むしろファッションの意匠としての存在感が強固となり、前述した倫理的なオーセンティシティの次元は見えづらくなりました。ですが、自身の実存を切り売りするかの様な新しいパフォーマンスをする受難者として舞台に立つ演者には当初のパンクにおいて問題とされた「真正性を保持しているかどうか」という視線が注がれます。また「バンド」という表現形においての人前で発声するという行為、すなわちヴォーカルというのは非常に演劇的な営みであって、真正性の問題について頭を抱えざるを得ない構造を持っています(UCGMはバンドと言ってみても差し支えないでしょう)。その倫理基準の存在は、例えば「刺す」とバトルで口にしてしまったら実行しなくてはならないというMSCの掟や、悪魔のキッス「カスタムラブドール」のリリックにおける、彼女たちの美容整形手術の享楽を前提とした構えに見て取ることができます。現代的には、パンクにも由縁の深い「ハードコア」という言葉を使用する際にその真正性の問題が最も厳しく立ち上がると言えるのかもしれません。私はUCGMの表現からもこの真正性の高さを感受してしまいます。アルバムの表題と曲名しか明記されておらず発声に際して言語が伴っているかどうかも判然としていないにも関わらずです。私は、先ほど彼らの音色に触れた際に受け取った、被虐的とも加虐的とも形容しがたい「痛み」への固執を、この筋からも無視できません。むしろ、それは実在していて、その「痛み」そのものの真正性を、その感受性自体が支えているのではないかと考えてしまうほどです。
彼らが自身の似姿を攻撃するのは何故でしょうか。勿論、そんなことは知る由もありませんが、私はドゥルーズの『ザッヘル = マゾッホ紹介 冷淡なものと残酷なもの』(Présentation de Sacher-Masoch: Le Froid et le Cruel | 1967, Editions de Minuit)におけるあるくだりを思い出さずにはいられません。責め苦が主人公自身、息子や恋する男性、子どもを対象とする、叩かれているもの、放棄され供儀に供されるもの、儀式的に贖われるものとは、父との類似であり、父から受け継いだ性器的なセクシュアリティなのだと結論せねばなるまい
またこれこそが『《棄教》』なのだ
という箇所です。そして、ドゥルーズはマゾッホの全作品の最終目的はキリストであるとしています。しかし、それは「神の子」ではなく新しい《人間》
であり、父との類似の廃棄であり、性愛もなく、財産もなく、祖国もなく、口論もせず、労働もせず、十字架に架けられた《人間》
であると。何も私はUCGMのお2人が字義通りそのような人間になるべく日々を暮らしているであろうなどというようなオーセンティシティをキリストに比肩させようと試みているわけではありません。私が強調したいのは、彼らの強烈な「棄教」への意志――その実在性を疑わないのは他ならない「私」がこの『HEAVEN』と関係することでそう思うからです――と、その視線が示す先にあるものです。それは『HEAVEN』――すなわち「神の国」です。「棄教」によって目指される「神の国」とはヴィンスワンガーの治療論で取り上げた垂直方向の特権化という人間の「思い上がり」や空間的な高みを目指す崇高概念でもって接近できるような場所ではありません。UCGMはイカロスではないのです。誰もがこの作品から観察可能なポスト・インターネット以降の悲観主義が持つ絶望しながらもどこか軽妙洒脱な意匠を借用して彼らが呈示するのは、このような「高さ」ではなく、さまざまな「あいだ」に位置する限界なのです。
キリストは「神の国」の到来を待ち望む当時のユダヤ教ファリサイ派の人々から神の国はいつ来るのかと尋ねられ、「既に到来している」としたうえでこう答えました。
神の国は、見える形では来ない。『ここにある』『あそこにある』と言えるものでもない。実に、神の国はあなたがたの間にあるのだ
■ 2023年10月18日(水)発売
UNCIVILIZED GIRLS MEMORY
『HEAVEN』
CD OOO-50 2,000円 + 税
https://ultravybe.lnk.to/UCGM-HEAVEN
[収録曲]
01. Incubator
02. Ode to the angels embryo
03. エス
04. Raven
05. R0G0B255
06. Etude for heaven
07. Reserved death
08. Cadenza
09. Heaven
10. ex.Heaven