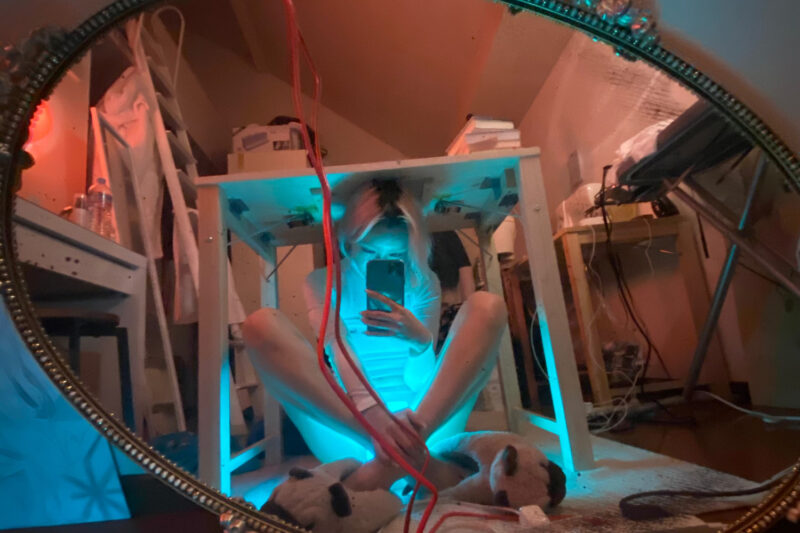文・撮影 | 波田野州平
In the Mood for Y2K
2026年の年明け、ひと回り以上歳下の若者たちに誘われて、歌舞伎町にある台湾料理屋「叙楽苑」を訪れた。新宿にはここに来るためか、映画を観るためか、レコード屋を回るためにしか訪れることはなく、都心から西に離れて暮らすようになってからはほとんど訪れる機会がなくなっていた。
私にとって新宿の入口といえばアルタではなく、その隣にある百果園だった。串に刺さったむき出しの桃やメロン、パイナップルなどのカットフルーツが陳列され、歌舞伎町へ向かう群衆が甘い果実の匂いと鼻を突く汚水の臭いをかき混ぜる。ここもアジアであるというムードを、東洋一の歓楽街へ向かいながら実感するにはうってつけの場所だった。店先で客を呼び込む、幼いようにも歳老いているようにも見える年齢不詳の男もそのムードを醸し出すのに一役買っていた。ドリアンなる奇怪な食べ物を初めて見たのもここだったように思う。
その先には幾度となく訪れたテアトル新宿があり、中でも『ユリイカ』(2000/日本/青山真治)を観たときのことが思い出される。学生だった私には「なんか押し付けがましい善意に溢れた映画だな」程度にしか感じることができず、その後再見する機会を逸したままだが、若造のお目当ては上映後の監督と東京に居を移したばかりのJim O'Rourkeのトークショウだったのかもしれない。ニコラス・ローグのことばかり話そうとする監督のシネフィルらしいムードにJim O'Rourkeは乗り気ではなさそうで、噛み合わない時間が流れていたが、私には彼がいつも音楽雑誌の写真で着ている若草色のカーディガンを見られただけでも満足な時間だった。
映画といえば思い出すのはコマ劇場隣のミラノ座で、封切り初日の初回に『シン・レッド・ライン』(1998/アメリカ/テレンス・マリック)を観たことだ。とは言っても、たまたま大久保の友人宅で夜を明かし、そのまま朝一で映画でも観てから帰ろうと思ったまでで、この映画について知っていたことは、伝説的監督の20年ぶりの新作ということだけだった。そのためか、ウディ・ハレルソンが戦場で手榴弾を投げる前に爆発させて下半身を失う場面以外は覚えていない。それよりもミラノ座の入口頭上に掲げられた、視界からはみ出るほどの巨大な看板を仰ぎ見ながら狂信的なファンの行列に並んだのを覚えている。そして映画を観終えてコマ劇広場に出ると、1,000円で1分間好きなだけ殴っていいですという商売を営む“殴られ屋”が、それじゃあと日頃の鬱憤を晴らすべく躍起になる男の拳を巧みにかわしていた。
コマ劇広場の隣にはLIQUIDROOMもあり、GODSPEED YOU! BLACK EMPERORの2度目の来日公演を観たのがここだった。初来日の原宿ASTRO HALLのときと同じく、その音の洪水にどう反応すればよいのか戸惑ったまま、呆然と2時間半立ち尽くして鼓膜と体を震わせていた。最後にメンバーが舞台から降りてワルツを奏でながら客席の中を練り歩く間、誰もいなくなった舞台の壁には16㎜フィルム・プロジェクター3台で投影された引っかき傷のような“HOPE”の文字が震えていた。終演後、ごった返す人たちとエレベーターのないビルの7階から階段を降りながら、1ヶ月前に起きた歌舞伎町ビル火災のことを思い出し、将棋倒しにならず無事コマ劇広場に帰還できたときには心底安堵した。
人混みに眩暈がすると、ひと息つくために訪れるのが花園神社だった。鳥居をくぐるとエアポケットに落ちたかのように突如としてひとけのなくなる境内で、私はしばし空を見上げて放心した。しかし酉の市が立つ時、ここは雑多な欲望が一堂に会する場所へと変貌した。たくさんのテントがひしめく中、ひときわ隅に押しやられたテントにすし詰めにされた人たちと肌を密着させて、私も欲望をつのらせていた。そして、蛇を引きちぎった挙句に食べてしまう白装束の老婆を前に、小さな劇場はその日一番の生臭い熱気で充満した。
全演目が終わり、見世物小屋から吐き出された私は、友人たちと課題制作の映画撮影をするために境内を歩いた。俯瞰ショットを欲した私は、ひとりで神社脇にある雑居ビルの階段から全景と、そこからズームアップした主演俳優の姿を撮影する。すると背後から「何撮ってんだ?」と声をかけられる。振り向くと40代くらいの男がこちらを睨み、また同じ言葉を繰り返す。「映画を」と答え終わる前に「見せろ、撮ったものを見せろ」と迫ってくる男の態度に私は憤慨し、「嫌です」と答える。すると「俺は疑うのが仕事なんだ」と意味不明な正当性を主張する男。しかし次に継がれた「探偵だからな」という言葉が耳に届いたとき、不覚にも私の憤慨は好奇心に転化し「え?探偵?」という言葉が口からよだれのように垂れていた。
私は態度だけは不服であることを示し、しかしその胸の内は自称探偵なる人物に好奇心を拭えぬまま、男とその雑居ビルにある自称探偵事務所に入る。小さな机に向かい合い、DVカメラの液晶パネルで撮影した映像を一緒に観ていると、そこに映る俳優の姿を見て「お前の女か?」と尋ねる自称探偵。「いや、映画の役者です」と答えるも、「女をこんなところに連れてくるんじゃねえ」とこちらの答えを一切無視したセリフのような忠告にますます探偵らしくなる自称探偵。「あーはい、気をつけます」とふてくされた態度でセリフのように返すと、その場は学生が課題で作ろうとしている映画よりも映画らしいムードになっていく。ひと通り映像を見終え、私が無害な存在だとわかると「すまんな、疑うのが仕事だから」と、自分だけが使うことを許されたセリフだと言わんばかりに決めゼリフを繰り返し、自称探偵は押収したDVカメラとminiDVテープを差し出す。私は荷物をまとめ、その場を去ろうと振り返ると、扉には漆黒のラブラドール・レトリバーと“探偵”という文字が並んだポスターが貼られている。当時、東京のいたるところで見かけて気になっていた謎めいたポスターの主を偶然にも突き止めた私は、男が本当に探偵だったという驚きの一方で、根城はここだったのかという、こちらのほうが真相を解明したような探偵的満足感を得て扉を開けたのを覚えている。
あれから26回目の年明けの歌舞伎町で、私は当時のムードを覚えているどころか物心ついていたかどうかわからない若者たちと食卓を囲み、〆のごま団子を食べている。そして熱々のあんこが上顎の皮をめくり取るのを感じながら、数年前、まだ物心つくかどうかわからない娘を連れてこの魔窟のような路地に迷い込み、ここで〆のごま団子を食べたのを思い出していた。そして会計を済ませ、夜も更けてまどろむ娘を抱えて店を出ると、階段の中腹で金髪のロシア人と思しき女が行く手を阻んでいる。黒光りするボンデージ・ファッションに身を包み、看板の赤い光線に照らされてポーズを決める女の尻は露わになっていた。私たち夫婦はうつむいてそそくさと通りすぎたのだが、さっきまでまどろんでいたはずの娘はいつの間にか覚醒し、ぱっちりお目々はむき出しの桃尻に串刺しになっている。階段を降りた先でバズーカ砲のようなカメラを女に向けた中年男を通り過ぎ、魔窟の出口を目指す間も、娘はその眼差しを一刻も逸らすことはなかった。
私はいつか大きくなった彼女がふとあの夜の階段を思い出すことがあるのだろうかと思いながら、今夜は阻むもののない階段を降り、若者たちと「新宿センター街思い出の抜け道」を後にし、駅を目指した。
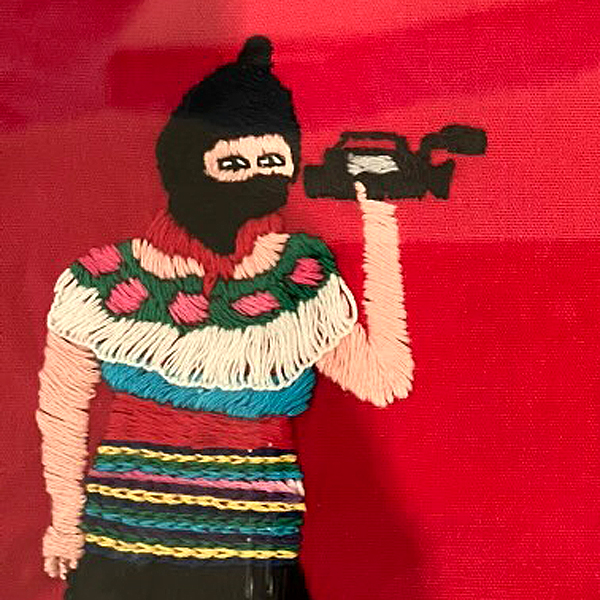 波田野州平 Shuhei Hatano
波田野州平 Shuhei HatanoOfficial Site | Instagram
1980年鳥取生まれ、東京在住。
カメラを携え、各地で出会った未知の歓びを記録し、映画を作っています。
近作に『私はおぼえている』(2021)、『それはとにかくまぶしい』(2023)がある。