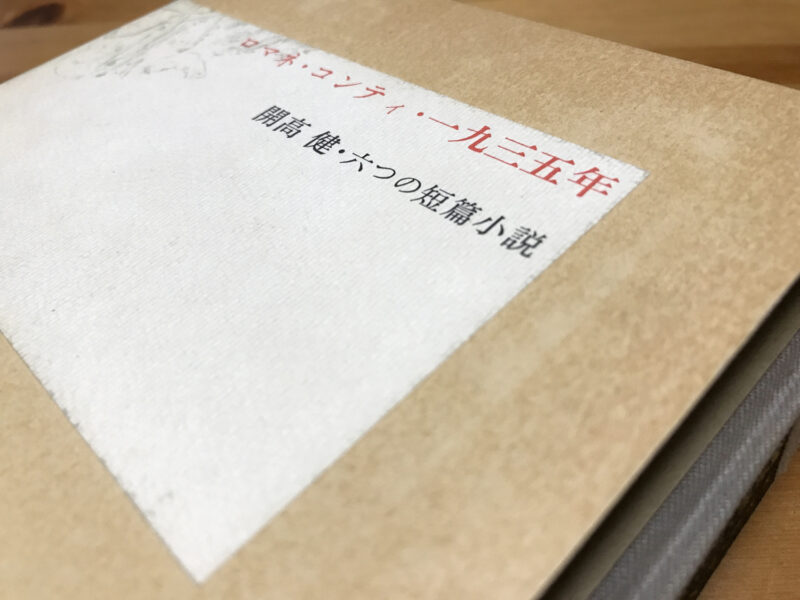文・撮影 | 後藤祐史
わたしは何か楽しいことがあったら笑ったり、悲しいことがあったら泣いたり、考えもしなかったことが起これば驚いたりします。ただ、わたしは人生でこれから何が起こるのかを予め予測することができません。予測することができない分、対処できない事態に遭遇することがあります。対処できない事態自体は普段の生活の延長線上にあることがほとんどで、超常現象とかでない限り、しようと思えば説明がつくことが多いでしょう。しかし状況説明ができても、その場の感情までには折り合いがつけられなかったりします。
2002年公開のイタリア映画『息子の部屋』は、死による家族の崩壊に直面し、悲しみにくれる様子を描いた作品です。
あらすじ
精神分析医ジョバンニは、事故で息子を失う。「あの日をやり直せたら。」残された彼、そして妻も娘も、悲しみを独りで抱え、どうすることもできない。そんなある日息子と付き合っていたらしい女の子から手紙が届く。妻の電話に応え、彼女が初めて家にやってきた。
この映画の前半では仲睦まじい家族の様子が描かれます。しかし、あらすじにも書かれているように、息子の死を境に、家族はそれぞれ嘆き悲しみ、バラバラになります。家族関係の崩壊です。というのも息子のアンドレアが死んでから、家族一緒にいるシーンはほとんどありません。皆がそれぞれ悲しんでいます。これまでどれだけ一緒にいたであろう、そしてこれからも続いていくであろう関係が、なんらかの原因で壊れてしまい、もう二度と元に戻らないと分かったとき、すくなくとも私は悲しいを通り越してとてもやるせなくなるのだろうと想像しました。
例えば非常に政治的な人間がいたとして、その人の政治的な選択の根元には必ず、その選択をするに至った感情があるはずだ、思っています。しかし、常日頃から自分や他者の本当の思いについて考えを巡らせているような時間はありません。これはお互いに言えることですが、人は人生の選択を重ねるうちに、自分の気持ちを思い出さなくなります。自分の気持ちは常に事細かに表現できるものではないからです。だから、シンプルに悲しい気持ちになったり、楽しい気持ちになったりしたときに、自分が感じている思いがどういうものか分からず、どんな行動をしたらいいか戸惑ってしまうかもしれません。
普通の家庭で育った人は大抵、家族という共同体の中で、社会の一端を知ることになります。生まれていきなり社会経済のど真ん中に放り込まれる人はいません。とりあえず、家族の中で全ての良い悪い嬉しい楽しいを知ることになります。そしてその年月が長く、濃厚になればなるほど、人の価値観の中心は、家族との時間の中で触れたものが礎となります。この映画では残された家族が、家族関係の場から離れた場所でどのように過ごしているか、というそれぞれのシーンを通じて、家族関係の崩壊を端的に示しています。これはどういうことかというと、家族というのは個人の集まりであると同時に、一人では生きていけない人達が集まって、家族、という共同体を演じている、ということを表しています。当の家族たちは、自分たちに起きた出来事を相対化して語ることはできません。ですから当然のように、関係が崩壊しているということまでに、思いは巡りません。
印象的なシーンとして、アンドレアが死んでから数日経ったある日、娘のイレーネが体育の時間に癇癪を起こし、授業を崩壊させるシーンがあります。兄の死の悲しみからくるフラストレーション、妹のイレーネがやり場のない気持ちをぶつけるシーンとして描かれます。しかし、本来の家族関係の中であれば、何故そんなことをしたのか、と両親がイレーネに話をするシーンがあってもおかしくないのかと思います。実際、アンドレアが生きていた頃に、彼が学校の教材を盗んだり、部活動で手を抜いたりしていて、両親がその本意を直接伺うシーンがあります。アンドレアはそんなことをするような子ではなく、素直ないい子だ、という両親の像があるからです。しかし、兄アンドレアが死んでからというものの、一般的な家族の像というものの中で生きていた人々は、家族の役割を果たせないのです。父は仕事、母は家事、子供は学校、というごくごく平凡な像です。
Brian Eno「By This River」 | 『息子の部屋』エンド・ソング
そうしたら、本質的な部分での家族関係は壊れてしまうのでしょうか。というとそうではなく、そのまま何も変わらないのです。そして何も変わっていないということはとても重要です。なぜ重要なのかというと、他の何よりも悲しく何も手につかない、という気持ちでつながっている、ということです。そして何も変わらないけれど、残された家族は辛い気持ちで生きるしかないし、それこそが悲しい。行き場のないやるせなさと付き合っていかなければいけない。そのことこそがこの映画で一番重要なことなのです。人はなんらかの物語に触れる時、その物語の面白さやいかに感動したかを、自分が触れたことのある感動や、経験したこと以上の言葉で表すことが難しいと思います。
終盤で息子と付き合っていた女の子、ちょっと名前は忘れちゃったんですけど、その子が家に来てアンドレアと文通をしていた際に送りあっていた写真を見せるシーンがあります。そこには笑顔のアンドレアが写っています。それを見て父のジョバンニは静かに俯きます。家族関係のヒエラルキーで見ても、生活の実質的な部分を担っているのは父のジョバンニです。息子のアンドレアと最後に会話したのもジョバンニであり、友達との約束があるから、と言って父の誘いを断って行ってしまった後に、アンドレアは死んでしまいます。アンドレアが死んだのは、自分が引き留めなかったからだ、と本気で思っています。
しかし、実際に誰のせいか、ということは本当に重要なのではなく、家族とはいえ、みんなそれぞれ色々な思いがあります。それはどうしたって揃えることができないのです。気持ちが通じていないのではないか、と思うのは親として当然の反応で、それを確かめることができなくなるのも当然の反応です。それでも起こってしまったことは、取り戻せるものではないのです。悲しさ・やるせなさとの向き合い方、を提示し、最終的な方向として、とりあえず、その悲しみを受け入れて、また日常になんとなく戻っていく、という結末は、非常に生々しく、説得力のあるものだと感じています。辛いことは変わらず、付き合っていくのだけど、死は生と対極なのではなく、生の中にあるものだからです。この映画では最終的に一旦は崩壊しかけた家族がやはり、共同体の中に帰属していく結末です。それはどうこうではなく、悲しみを受け入れ始めた人々が、自分たちの帰る場所はどこなのか、というのを自然に考えた結果である、ということです。
人は強く受けた印象を人生の中で何度も思い出すことはあっても、自身の生死に影響をさせることはありません。人は何があってもとりあえず自分の意思で人生を決めるしかないからです。他者と共生することが当たり前とされている中で、そこは個人に委ねられるのか、ということが私にとってはなんとも言えない状況のように感じます。『息子の部屋』はこれまで誰も予期していなかった、突然の別れ、喪失を通して、そこに晒された個人の感情を描写し、強固であるように見えて実は希薄な人間関係、そして、生活と個人の意思決定との密接な関係を表現した映画です。