文 | 久保田千史
Photo ©Katsuki Mitsuhashi
あらかじめお伝えしておきたいのは、本稿は彼を慕う人々の代表として記すものではなく、あくまで私的に書き残しておきたいものであるということです。筆者は決して、日々論議を交わしたり、旅程で寝食共にしたりという間柄ではありませんでしたから、ご家族をはじめ、近しいご友人たち、そして共に現場を作り上げてきた人々の心に感光した彼の像の尊さは計り知れません。しかしながら、正直に言えば文章を書き綴る行為が苦でしかない筆者でも、彼の逝去にあたっては筆を動かさざるを得ません。ご本人は与り知らない事柄かもしれませんが、3分先の未来予想ですら3分後に覆ってしまうような筆者にとって彼は、長期的な未来を妄想する楽しみを与えてくれる特別な存在でした。彼の死による喪失感が、楽しみの消滅に起因する利己的な感情なのかもしれないと考える度に、自分の浅はかさを痛感します。でも書くべきだとは思う。お名前での呼称は、どうしても表情が浮かんで言葉に詰まってしまうので、ジェンダーニュートラルでない三人称代名詞の使用もお許しください。
初めて彼の存在を知ったのは、ステージの上の人物としてでした。彼には太一さんというお兄さんいて、共にENDONという楽団を組み、お兄さんがヴォーカル、彼の担当はエレクトロニクス。お兄さんは喉の各種パラメータを自在に操り、Diamanda GalásやMaja Ratkjeなどに匹敵する稀なヴォイス使いだけれど、当時は喉に留まらずヴァイオレンスの針が閾値を超えていて、お兄さんがフロアに降りてくる度に恐怖を感じたものです(その方向性は徐々に異なる表現形態へと転化され、洗練を見たものの、決して角が取れたわけではありません)。彼も彼で、自作インストゥルメントの部品が弾け飛ぶようなパフォーマンスでしたし、ヴォーカルの弟さんだということもなんとなくは把握していたので、同様におっかない人間に違いないと勝手に想像していました。よって、筆者の積極的に人間関係を築く能力が皆無というスペックと相まって、ただただ観客としての立場を維持していたのです。ところが後の2014年、ENDONの『MAMA』という作品をパブリッシュすることになったDaymare Recordingsというレーベルの濱田 忠さんからインタビューのご依頼をいただき、暫し思案。濱田さんには、怖いな~、大丈夫ですかね?的なお返事をしたように思います。でも結局、迷ったらやってみる仕様なので、お話をお伺いすることに。取材にはお兄さんとギタリストの宮部幸宜さんで臨んでくださったのですが、まずクレバーな思考と熱意に舌を巻き、次いで音楽聴取や諸々の問題に対する視点が筆者と近しいことを知り、尊敬と親近感を同時に得る結果となりました。以来、公演会場ではお兄さんの計らいでメンバーのみなさんにご挨拶をするようになり、彼とも言葉少なながらも会話できるようになったのです。終演後に顔を合わせる彼は、ステージと違って、繊細な美青年という印象。もし自分のセクシャリティが違ったら、恋しちゃうかもな~、って思ったりしました。
ENDONは各々が様々な分野において突出した才能・技術を保持する特殊な集合体なのですが、秀でた文筆家としての彼を認識したのは、同年に発表されたZENOCIDEというバンドとCARREというエレクトロニック・デュオによるコラボレート作品『Veronica Puts On Silk』においてでした。そのリリース情報に添えられていた彼のテキストは、文字を読むという喜びを否応なしに再確認させられるもので、資料の添付としての範疇をはるかに超えたものだったのです。一見、イメージの異なる単語がばらまかれているようで、ノイズとの関連性からもバロウズ由来のカットアップを思わせながらも、総体では偶然性と相反するナラティヴが貫かれ、300頁の小説をシュレッドして1頁に繋ぎ合わせたようなスピード感、3時間級ノワールのフィルムを3分にタイムストレッチしたような強烈な視覚的表現には、驚嘆するほかありませんでした。グロテスクなイメージや下世話な単語を多用しながらも、厨二やエログロナンセンス的な饐えた趣きに陥らず、メインストリームでもおかしくないポップを醸し出しているのもおもしろかった。加えて、皮肉めいていたり、攻撃的だったりするラインから敵意や悪意が感じられず、かといって諦観で綴られているとも言えない読後感を不思議に思い、いっそう彼への興味が掻き立てられました。当時は商業誌に在籍し、中途半端な三流以下ながら、編集者という立場でもあった筆者にとって、いやらしい言いかたをすれば“見つけた”という感覚だったかもしれません。一流の編集者がどういう感覚で生きているのか知らんけど、ベストセラー誕生に至るまでにはきっと、そういう出会いがあるものなんでしょう。この人となら、すごい何かが作れるに違いない、という確信がありました。翌年、お兄さんの運営する「G.G.R.R.」というレーベルが、ANAL VOLCANO、CHAOS MONGERS、CARRE、FILTHY HATE、INCAPACITANTS、PREPARATION SET、ZENOCIDE、そしてENDONの佳曲を集めた間違いないコンピレーション・アルバム『TOKYODIONYSOS』を発表したのですが、そこに添えられていた彼のテキストも、真っ白なパッケージに画像素子を埋設するような筆致が素晴らしく、確信をさらに深めました。
そうこうするうちに、筆者の片想い念が伝播したのか、彼の単独インタビューを取る機会に恵まれたのです。赤い牛のシンボルでおなじみの清涼飲料水が所有するスタジオでのレコーディング・セッション企画で、“No-Input Mixing Board”奏者として名高い中村としまるさん、「MultipleTap」をはじめとする挑戦的な企画の主催でも知られる康 勝栄さん、そしてENDONのバンドメイトであり、ソロでもスプリット作品を発表した相手でもある愛甲太郎さん(M.A.S.F.)という、またとない面々とのセッションを録音後に、各々の単独取材という算段でした。録音は、スタジオの専属エンジニア・川島 隆さんのお人柄と手腕もあって無事終了。彼はほぼ全編ヘッドセットでのヴォイス・ドローン。そういったパフォーマンスはこれまで観たことがなかったので、音楽家としての引き出しの多さに感嘆したのでした。ところが、いざインタビューの段になってみると、彼は爆睡。みんなで代わる代わる声をかけても目を覚ますことはなく、結局は愛甲さんが“らしいよ”方式で答えてくださることに。ヴォイス・ドローンは想定していたセットではなく、寝かかっていただけだったのです。睡眠は決して彼の怠惰や不徳によるものではないので、笑ってはいけない気もするのだけれど、取材時にインタビュイーが寝てしまうという経験は初めてだったので、可笑しくて笑った笑った。みんなも笑った。ソファに沈み込むように眠る彼の姿には、昭和っぽい破天荒な芸術家というよりも、どこかエンジェルめいた魅力を感じていました。その日、彼はENDON『Acme. Apathy. Amok』(2011, […]dotsmark)リリース時のTシャツを着用していて、筆者もお気に入りでよく着ていることもあり、かっこいいですよね~、と声をかけたところ、「本当はもっとハイブランドっぽいTシャツにしたい」とおっしゃっていて、そのあたりの感覚はお兄さんがディレクションするブランド「SLAVEARTS®︎」に受け継がれているのかな?と今となっては思います。
翌2016年におけるENDONの活躍は目覚ましく、2度のUSツアー、米「Hydra Head Records」からの『MAMA』ヴァイナル・リリース、同レーベルのオーナー・Aaron Turnerが率いるSUMACのリミックスワークだけでも、雑に言えば夢叶えたように見えるけれど、ENDONはネクストレヴェルに向けてKurt Ballou(CONVERGE)のGodcity Recording Studioにて新作の録音も済ませていました。それが2017年のアルバム『Through The Mirror』なのですが、同作の発売に向けて、彼の連載小説をやらないか?というお兄さんからの打診を受けました。筆者が色めき立ったのは言う間でもありません。『Through The Mirror』のトラックリストに合わせた8週に亘る連載なので、8本も彼の短編が読めるのです。その打ち合わせと称してお兄さんを伴って国分寺で会った彼は、連載の開始を喜んでくださってはいたものの、どこか、心ここにあらずの瞬間もあって、繕いや虚言とは無縁の人だと感じていたから喜びが本物であるのは伝わったものの、その表情からは彼が嬉々として執筆を進めるタイプではなく、ある種の苦行を経て創作しているのだと窺え、こちらも半端にはできないという緊張感を得ました。しかし打ち合わせ自体は始終楽しかった。現代思想に精通した彼らしく、ガタリ、ドゥルーズやニーチェの話題で持ち切りだったり、ひとたび話が音楽に及ぶと「PANTERAが一番好きだな~」という一面も見せてくれたり。美術家の田巻裕一郎さんがあつらえた彼のジャケットにもPANTERAのロゴがあしらわれていましたよね。いつだったかは忘れてしまったけれど、BUSHBASHで観たある日のENDONが素晴らしかったので、Twtterで他人の感想もサーチしてみたことがありました。ヒットした結果のひとつに、「ENDON良かったが、こんなアンダーグラウンドでかっこいいパーティにPANTERAなんてメジャーなTシャツ着てきてる奴がいる、ダッサ~」的な、言っちゃえばマウンティングっぽいポストがあって、付けられていた盗撮写真を見たら彼だった、ということもありました。笑ったな~。しかも彼はガタリとPANTERAを同列の口調で語るんです。そこにポップの秘密を見た気もしました。話が逸れましたが、肝心の連載「鏡を抜けて」はと言えば、お兄さんの尽力でMAさん(Hidden Circus)による最高の挿画も得て、内容は素晴らしいものになったと思います。ただ、見せかたに関して筆者の技術不足は明白でした。原稿料も、字数では測れない“作品”の対価とは思えない額しかお支払いできず、今もずっと悔やんでいます。もし筆者ではなく、大手出版社の編集者の目に留まっていたら。でも連載終了後、FEVERだったかな、公演会場で会った彼は、変わらず控えめな微笑みで喜んでくださっていました。同年はBUSHBASHで開催された田巻さんの個展「リトミック」に彼が寄せたテキストも読めて、良い1年だったなあ。
2018年最初に読めた彼のテキストは、ANAGRAで開催されたMAさんの個展「SAPIENCE IN TOKYO IN 2018」の開催に宛てたものでした。同展では「鏡を抜けて」で使用させていただいたピースの原画が展示され、感慨もひとしお。MAさんの絵は実物の迫力がハンパないので、機会があったらみなさんにもぜひ観ていただきたいな。その年、筆者は子供がまだ小さかったり、収入が芳しくなかったりでほとんど公演に足を運べず、行けても終演後に会えなかったりで、彼とはあまり言葉を交わせなかったのですが、Black Smokerから発売され、後にかのThrill Jockeyからも世界発売されることになるENDON『Boy Meets Girl』の発売にあたって、「VICE」というウェブマガジンのためにお兄さんたっての希望でメンバー全員でのインタビューを取ることになりました。4年越しで彼の肉声をレコーダーに収められることになったというわけです。ドラムの横田 慎さんとちゃんとお話できたのも嬉しかったな。メンバー各々の意見も性格も違い過ぎるENDONだけに、その日の取材は賑やかになって楽しかった。街にぞろぞろ繰り出して、スタッフのかたに撮影していただいたり。その日に最も印象に残ったのは、ノイズの自由度と、社会的なダイヴァーシティを関連付ける意味で筆者が投げた質問に対する彼の回答でした。ENDONには間違いなくそういう要素がある。インタビュアーというのは、そういういやらしい質問をしがちなのですが、ダイヴァーシティを語りたいバンドだっているわけです。それはそれで素晴らしいことだと思うけれども、彼はさらっと「そんなのは大前提」と答えたのです。それは、ENDONや彼の活動にとてつもない希望を感じるに十分過ぎる一言でした。
その後、リストラを経て、素晴らしい職場に拾っていただいてからも公演になかなか行けない日々が続きましたが、幸いお兄さんとは頻繁に話す機会があり、その度に必ず彼は話題に上りました。創作活動の話ではなく、「新しい仕事が決まったよ」とか、「機材に『Temple Of The Morning Star』のステッカー貼ってるよね」といった話題ばかりでしたが、それでも、彼が元気にしていると知るだけで嬉しかった。
今年5月に入って、こんなこと言うのは不謹慎かもしれないけれど、鈍い虫の知らせというか、なぜか漠然とした嫌な予感がありました。それが何かはわからなかったけれども、連休中にお兄さんからの電話を受けた瞬間、良い話ではないことはすぐにわかった。最もショックを受けているであろうお兄さんが詳しく状況を説明してくれているにもかかわらず、情けないことに呆然と無言で答えるしかありませんでした。
ご兄弟のご実家を訪ねてお別れしてからもしばらく、目の周りがカサカサになっていましたが、今なお頻繁につまみ読みしていた「鏡を抜けて」を、まとめて再読することにしました。すると、一気に彼の文章に初めて触れたときのわくわくが蘇って、活き活きした気持ちも戻ってきたのです。彼の生気が間違いなくそこに宿っていて、テキストが先か、彼が先か、というカバラめいた感覚も楽しい。欲を言えば、小嶋アンナ登場作品をもう2篇くらい読みたかったな。いや、読めるんじゃないかな。だから、彼とあれをしたかった、これをしたかったと考えるのはやめました。再び彼と何かできる日までに、もっともっと楽しいことができるように、知恵や技術を身につけるしかない。時間かかるな~。がんばろ。それまで暫く休憩していてね、那倉悦生さん。





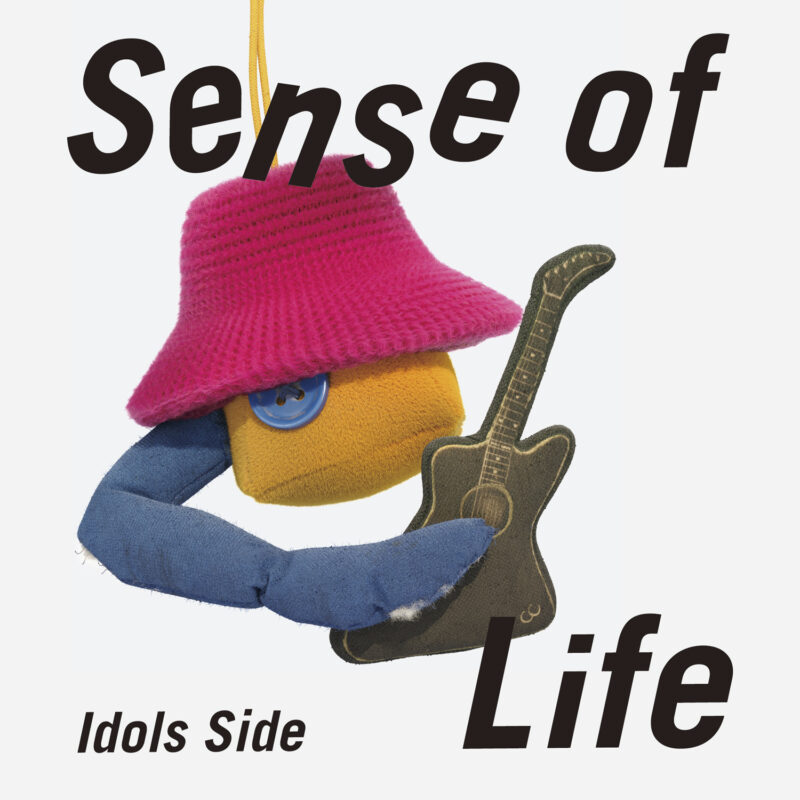



1 Comment
Add Yours →自分にとっての彼はいつも遠くから眺めてるだけで十分な人でした。例えば立ち姿だったり。演奏している時。生前は考えもしなかったけど、今こうして改めて考えると自分は彼の姿が好きだったんだと思います。また彼と久保田さんが何かをやる時を楽しみにしています。