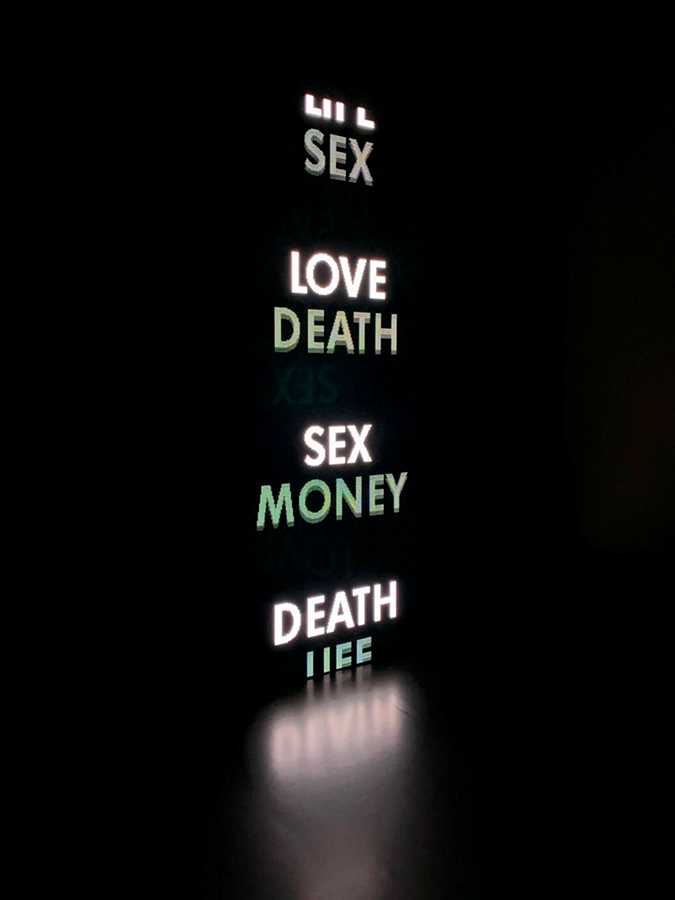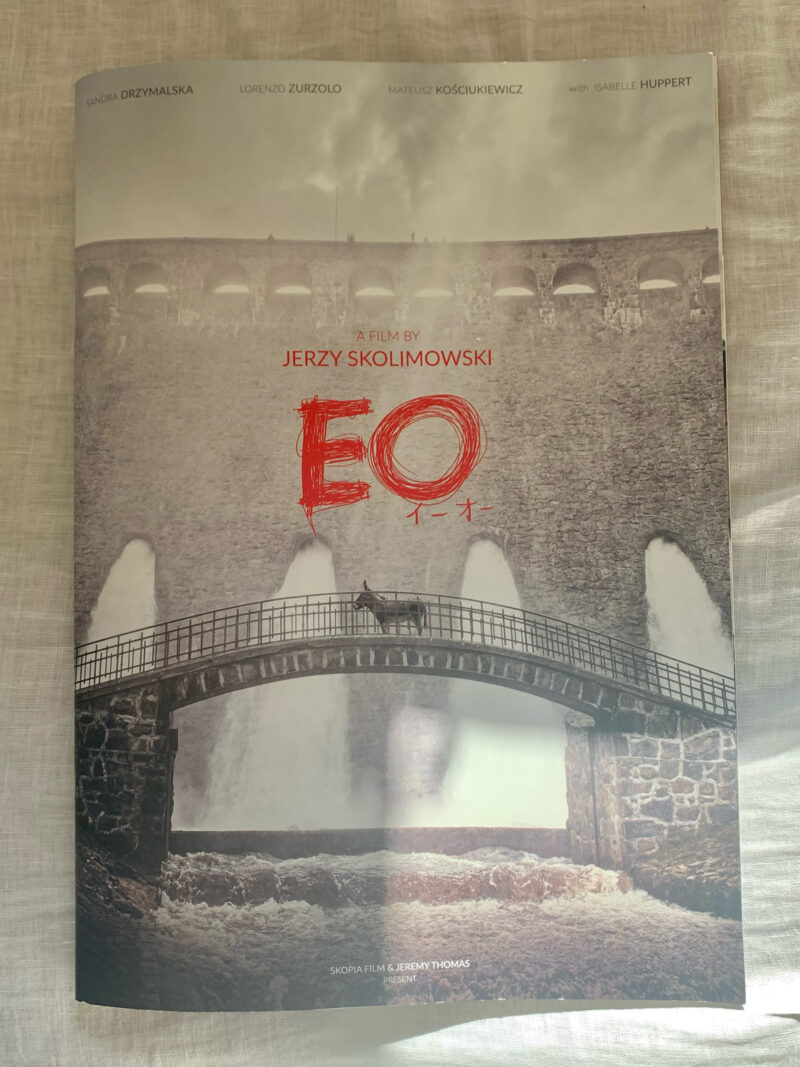文・撮影 | 梶谷いこ
私は物持ちが良い。しかも、異様に良い。
先日、ファンデーションを買いに百貨店に寄ると、いろいろあって3年前に買ったものを未だに使っていることがわかった。ボトルの中身はまだ半分以上残っているように見えたが、これ以上使い続けるのはさすがにまずいと思い、ばっさり捨てることにした。今使っている電子レンジを買ったのは、大学入学でひとり暮らしをはじめた時だったから、かれこれ18年前のことになる。本体には「National」と書いてある。30歳を過ぎた頃まで乗り回していた自転車は、親戚からプレゼントしてもらった中学入学のお祝いだ。故郷の鳥取から進学先の京都までわざわざ運んできて、就職先への通勤にも使った。小学校6年生のときに買ってもらったウールの靴下を、36歳の今も当たり前に履いている。何から何までどうしてこんなことになるのか、自分でもよくわからない。物の扱いが格別に丁寧かと言われると、それは違うと思う。現に通勤に使っていた自転車を指差さされ、「すごい自転車に乗ってる」と職場の先輩に笑われたことがある。新しい自転車を買うと、「やっとやん。おめでとう。前のはもうボロボロやったもんなあ」と言われた。
“良い”か“悪い”かでいうと、物持ちが“良い”なのだから“いいこと”のような気もするが、かといって自慢にはならないような気もしている。自分の“物持ちが良い”理由について、心当たりが3つある。まず、悲しいかな新しいものを買う金銭的余裕があまりないこと。それから、そもそも買い物という行為自体がそこまで好きではないこと。そして、古い物を捨てることを思うと面倒くさくて嫌気がさすこと。つまり積極的にそうしているのではなく、消去法で既に手元にある物を使い続けているだけということになる。単にずぼらなのだと思う。件の職場の先輩は、「できることなら毎日新品のものを使いたい」「いかに安く、常に新しいものを身につけるか、それが私の人生のテーマや」と豪語する。彼女は「ネットで見つけた」という一足3,000円のパンプスを、テレビドラマが1クール終わるごとに履き潰して買い替えているそうだ。お金の余裕がなくて買い物が苦手で使い古しを捨てるのも面倒な私からしたら、いくら安いとはいえ、半年も持たない靴を次から次に買って履いて捨てるなんて、考えただけでウンザリしてくる。しかし先輩は買い替えるたび誇らしげに報告してくれるので、これについて彼女の頭にはウンザリの「ウ」の字も浮かばないのだろう。ずいぶんマメな人だなあと素直に感心する。
いよいよ私の人生も2周目に入ったか。この春は折に触れ、そう思うことが多かった。世は2000年リバイバルブームだそうだ。ファッション・トレンドを伝えるニュースの見出しには、“Y2K”(= Year 2000)という文字が踊る。歳をとると、時代というものは単に10年区切りでぴしっとボーダーラインが引けるものではない、ということが身をもってわかってくる。すでに2000年前夜といったムードが時代に立ち込めていた1998年、私は13歳だった。中学1年生の私は、こたつ布団から上半身をにょっきり生やし、腹ばいで頬杖をついてファッション雑誌をめくっていた。それは初めて自分ひとりで本屋へ行き、自分のお小遣いで買った雑誌だった。表紙には「for INDEPENDENT GIRLS」と書いてあったと思う。すると、頭上から声が降ってきた。「昔ようこんなん着とったわ!」。私を上から見下ろす母の声だった。聞けば、あんなブラウスやそんなスカート、こんなカーディガンなど、目の前にある雑誌に載っているような服を、若い頃の母も着ていたのだという。さらに、もう捨ててしまったものもあるが、いくつかは確かまだ持っているはずだともいう。今すぐ雑誌に載っているようなおしゃれができるなら、と私は母に頼んでそれらを出してもらうことにした。しかし、嫁入り道具のタンスに頭を突っ込み、母が出してくる服はどれもイメージしたものとは違っていた。特徴だけ聞けば確かにそれっぽいのに、実物を見るとなぜかガッカリしてしまう。袖の感じが違っていたり、色合いが母の記憶と違っていたり、なんだかんだで少なからず昭和のにおいが漂ってくる。あれもだめ、これも気に入らないと次々に却下されるので、「難しいだなあ」と母は呆れていた。
ただそのなかでひとつ、私の御眼鏡にかなうものがあった。丸襟の白いブラウスだった。それは母がお茶汲みの会社勤めをしていたときに買ったものだそうだ。両胸元のポケットにはフラップがついている。丸襟の割りにはちょっとマニッシュな雰囲気がして、大人っぽかった。貝ボタンは高級なのだと母は得意気だった。以来、もう20年以上このブラウスを着続けていることになる。セーターの内側に着たり、1枚で着たり、それから、慣れないアイロンがけの練習台になってもらったりもした。
先日、恥ずかしながらプロフィール写真というものを撮ってもらった。そのときにもこのブラウスを引っ張り出して着た。母が買ったタイミングから考えると、“御老体”と言ってもいいかもしれない。撮影の前夜には、「長老、ここはひとつ……」と、これまでの労をねぎらう気持ちでアイロンをあてた。はたと気づけば、あの時の母とほとんど同じ年頃になっていた。最近、嫁入り箪笥からこのブラウスを引っ張り出してきた、当時の母の気持ちがよくわかる。私より10も20も年下の客で賑わう服売り場で、「こんなん昔あったなあ」と言いたいのを必死にこらえる自分がいる。

Instagram | Twitter | Official Site
1985年鳥取県米子市生まれ、京都市在住。文字組みへの興味が高じて、会社勤めの傍ら2015年頃より文筆活動を開始。2020年、誠光社より『恥ずかしい料理』(写真: 平野 愛)を刊行。雑誌『群像』(講談社)、『Meets Regional』(京阪神エルマガジン社)等にエッセイを寄稿。誠光社のオフィシャル・サイト「編集室」にて「和田夏十の言葉」を連載中。